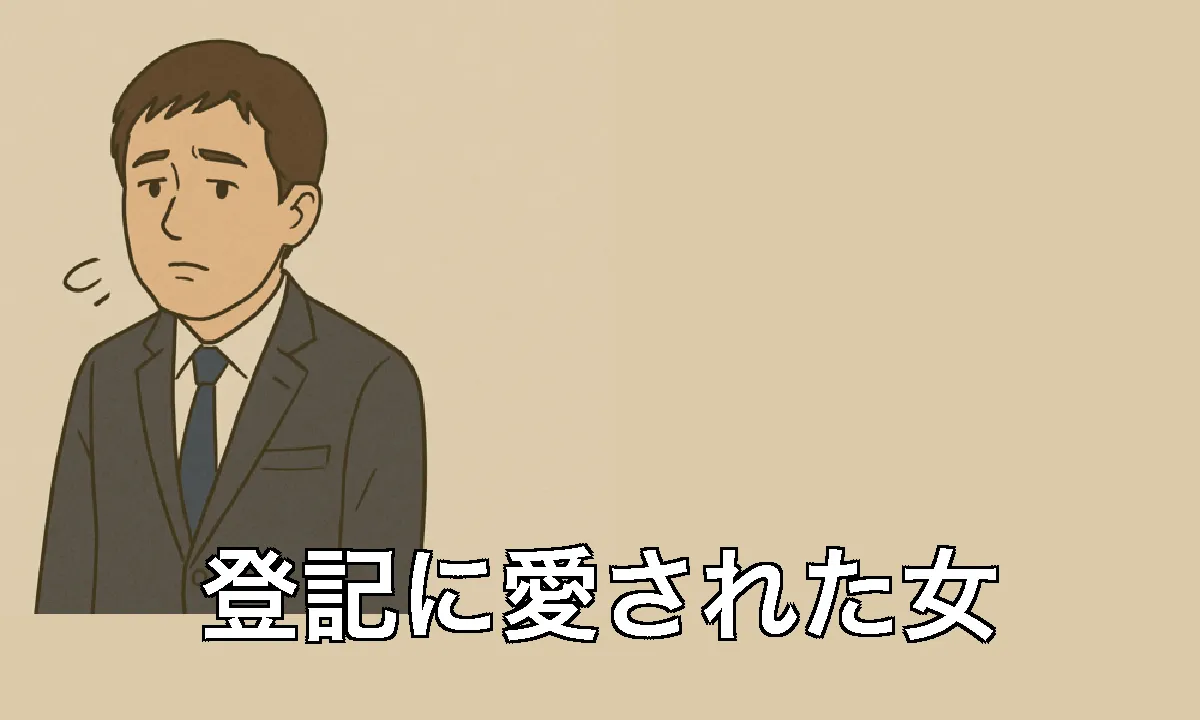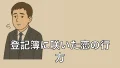旧家からの依頼
田舎町の旧家から舞い込んだ、妙に整いすぎた登記の調査依頼。
登記簿を眺めながら、俺はしばらく目を細めた。古い家の相続登記の依頼だったが、妙にスムーズすぎる。あまりにも綺麗すぎる書類の流れに、逆に違和感を覚えた。依頼人は「何も問題ないと思いますよ」と言っていたが、そんなときほど怪しいのが世の常だ。
遺言書のない相続
依頼人は「遺言はない」と言い張るが、状況には不自然な点が多い。
相続人は一人だけ。配偶者も子もいないという。だが、前所有者の交友関係を調べると、かつての婚約者の存在が浮かび上がった。しかもその女性は生涯独身で、十年前まで司法書士をやっていたという。偶然?――いや、偶然にしてはできすぎている。
土地の変遷を追え
昭和から続く土地の所有権移転の履歴に、不可解な空白が見つかる。
登記簿謄本を追っていくと、平成のはじめに所有権が一度空白になっている時期があった。その期間に何があったのか、書類からは読み取れない。だが、役所の古い記録には、抹消された仮登記の履歴が残っていた。「仮のまま抹消された登記」が意味するものとは?
女王と呼ばれた司法書士
10年前まで活躍していた伝説の司法書士の名が、登記簿の端に残されていた。
その名を見た瞬間、サトウさんが珍しく手を止めた。「この人、有名でしたよ。ミスが一つもなかったから“登記の女王”って呼ばれてた」。俺は新聞記事で読んだ記憶があったが、まさかこの案件に関係していたとは。いや、関係どころじゃない。彼女こそ、この物語の主役だ。
彼女が残した手口
複数の登記を照合することで浮かび上がる「ある法則」。
同じ筆界、同じ印鑑、同じ書式。だが署名欄だけが微妙に違う。彼女は相続人のいない土地に目をつけ、法の網の隙間をくぐり抜けて「正規の登記」として成立させていた。それはまるでキャッツアイのように、痕跡を残さない盗み。美しく、しかし確信犯だった。
忘れられた除籍謄本
見落とされていた除籍謄本が、真相への鍵となる。
町役場の保管室で埃をかぶった除籍謄本を発見した。そこには彼女が未婚のまま死んだこと、そして依頼人の祖父がかつてその女性と関係があったことが記されていた。血縁の有無よりも、感情が書類を動かすことがある。そう、彼女は最後まで自分の手で正しさを貫こうとしたのだ。
サトウさんの着眼点
無愛想な事務員が放った一言が、全体の構造を変える。
「この登記、提出日と押印の日付が逆です」――その指摘にハッとした。よく見れば、他の登記にも同じ傾向がある。形式美のなかに潜むわずかな“遊び”が、彼女の遺言だったのかもしれない。やれやれ、、、ほんと、冴えてるよなこの子は。
やれやれ僕の出番か
過去の記憶と現在をつなぐ、小さな違和感に気づいた。
登記とは事実の記録だが、感情は写らない。だが、女王はそこに自分の意志を埋め込んでいた。それに気づくには、同じ書類を千回見たうっかり司法書士の、直感だけが頼りだ。やれやれ、、、やっと見えてきたぜ、登記の本音が。
真の所有者は誰か
登記簿に記された名義人が、実は存在しない可能性が浮上する。
彼女が最後に書いた名義人は、既に亡くなった兄の名前だった。兄は戸籍上存在せず、彼女が作った「架空の所有者」だった。つまりこの土地は、登記上は誰のものでもない。だが、感情上は、彼女の「遺したかったもの」だった。
封印された登記申請書
保管庫の奥に残された一通の申請書が、すべての点と点をつなげた。
封筒の中には提出されなかった申請書とともに、一枚の手紙が入っていた。「私は登記が好きでした。最後に誰にも迷惑をかけず、私の仕事を終えたかった」――それは、法を愛した者の、静かな降板だった。
シンドウの推理
野球で鍛えた勘と事務所仕事で得た忍耐力が、最後の謎を解く。
彼女の目的は、相続放棄された土地を、無主物として国に戻すこと。だが登記を用い、あえて誰のものにもせず、空白のままにすることで「記録」だけを残した。それが“登記に愛された女”の、最後の表現だった。
真実の女王
「登記に愛された女」の本当の目的とは何だったのか。
俺にはわかる。彼女は、法が好きだったのだ。ただそれだけ。好きだからこそ、ルールの中で最も美しい一手を打ちたかった。そしてそれは、俺たちのような司法書士だけが気づく“作品”だったのだ。
依頼人の嘘と動機
すべてを仕組んだ人物の計略と、その代償。
依頼人は事実を知っていた。だが、財産を得るには女王の“仕掛け”を解くしかなかった。そして俺に依頼をした時点で、半分諦めていたのだろう。嘘は、登記簿には残らない。だが、真実を前にして沈黙することで、罪は記録された。
静かな結末といつもの日常
事件の余韻を残しつつ、また地味な書類仕事が始まる。
「さて、登記識別情報の再発行申請が3件です」と、サトウさんが机の上に書類を積む。俺は椅子にもたれて深く息を吐いた。「やれやれ、、、あの女王より、この事務員のほうがよっぽど恐ろしいよ」――静かな日常がまた始まった。