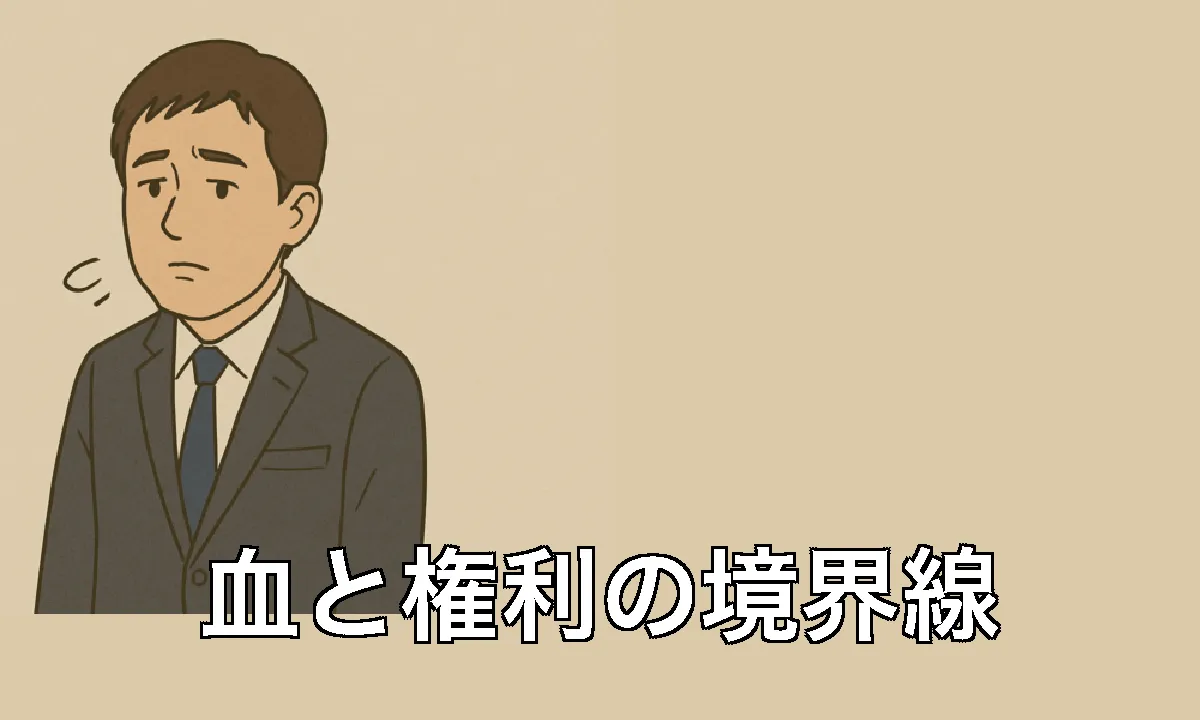はじまりは一本の電話
遠縁からの突然の相談
「シンドウ先生、ちょっと変な話なんですが……」
朝9時。いつもより少し早めに鳴った電話に、私はまだ眠気を引きずったまま応答した。
相手は、昔一度だけ仕事を手伝ったことのある不動産業者の男性で、彼の知人が遺産相続でもめているという話だった。
曖昧な血縁と登記の壁
「戸籍には長男と書いてありますが、DNA検査をしたら一致しなかったんです」
耳を疑うような話だった。長男が長男でなければ、相続登記はどうすればいいのか。
相続人の資格は血か、それとも戸籍か。法律と現実の狭間に私は立たされた。
遺産相続の闇
名義変更を拒む戸籍の空白
登記の申請書類を作るにあたって、戸籍を一通り洗い出す。
すると、被相続人が若い頃に一度、子の出生を届け出た形跡があるが、その後抹消されている。
一方で、今回「長男」と名乗っている人物の記録は、実はそれよりも後から追加されたものだった。
兄弟か赤の他人か
「昔のドラマでありましたよね、ほんとは他人だったってやつ」
そう言って苦笑いする相談者に、私は乾いた笑いで返すしかなかった。
法務局に提出する書類は、DNAではなく、戸籍に基づくことが原則だ。
DNA鑑定の提案
司法書士の業務範囲を超えて
「DNA鑑定書も添付したいんですが、意味ありますか?」
その質問に私は少し黙り込んだ。答えは「No」だが、「意味がない」と言い切るのも難しい。
登記手続きには関係なくても、争いを防ぐ材料にはなるかもしれないからだ。
塩対応の中にある鋭い観察
「先生、それ、誰が一番得するか考えてみたら?」
ぽつりとサトウさんが言った。今日も塩対応だが、視点は鋭い。
「戸籍があるけど血縁がない人」と「血縁はあるけど戸籍にない人」。結局、争ってるのはどっちが遺産を取れるか、それだけなのだ。
封じられた出生の記録
古い登記簿の記述に違和感
相談された土地の登記簿謄本を見ていると、ふと一つの異変に気づく。
昭和のある時期に、なぜか登記簿に抹消された所有者の名義がある。
しかもその所有者の名は、今回DNAで親子と証明された人物の旧姓と一致していた。
筆跡から読み取る真実
「この名義変更、手書きの訂正がされてますね……」
登記簿原本の筆跡を追うと、誰かがあとから加筆したような痕跡があった。
もしかすると、この抹消された所有者は、意図的に消された“本当の相続人”なのかもしれなかった。
鑑定結果とその波紋
血縁関係の否定がもたらす決断
鑑定結果が示したのは、今の戸籍上の「長男」は実子ではないという残酷な事実だった。
だが、戸籍を覆すことはできない。相続権は形式の上では、今の長男にある。
法の下では、それが「正解」だということになる。
登記は誰のためのものか
「法律って、誰の味方なんでしょうね」
サトウさんが言ったその言葉に、私は返す言葉がなかった。
登記は真実を記すものではなく、形式と手続きの産物でしかない。それでも誰かの人生に深く刻まれる記録なのだ。
やれやれの解決
真実よりも大切なもの
「結局、形式を重んじて登記しました。納得はしてもらえませんでしたが……」
裁判にしなかっただけマシだろう、と自分に言い聞かせる。
やれやれ、、、また誰も幸せにならない相続登記が一つ、終わった。
それでも書類は片付けなきゃならない
夕方、机の上に山積みの書類を片付けていると、どこかの誰かが笑っているような幻聴が聞こえた。
「まるでサザエさんの最終回みたいですね」とサトウさん。
私は苦笑いして答えた。「うちには波平もカツオもいないけどな……」