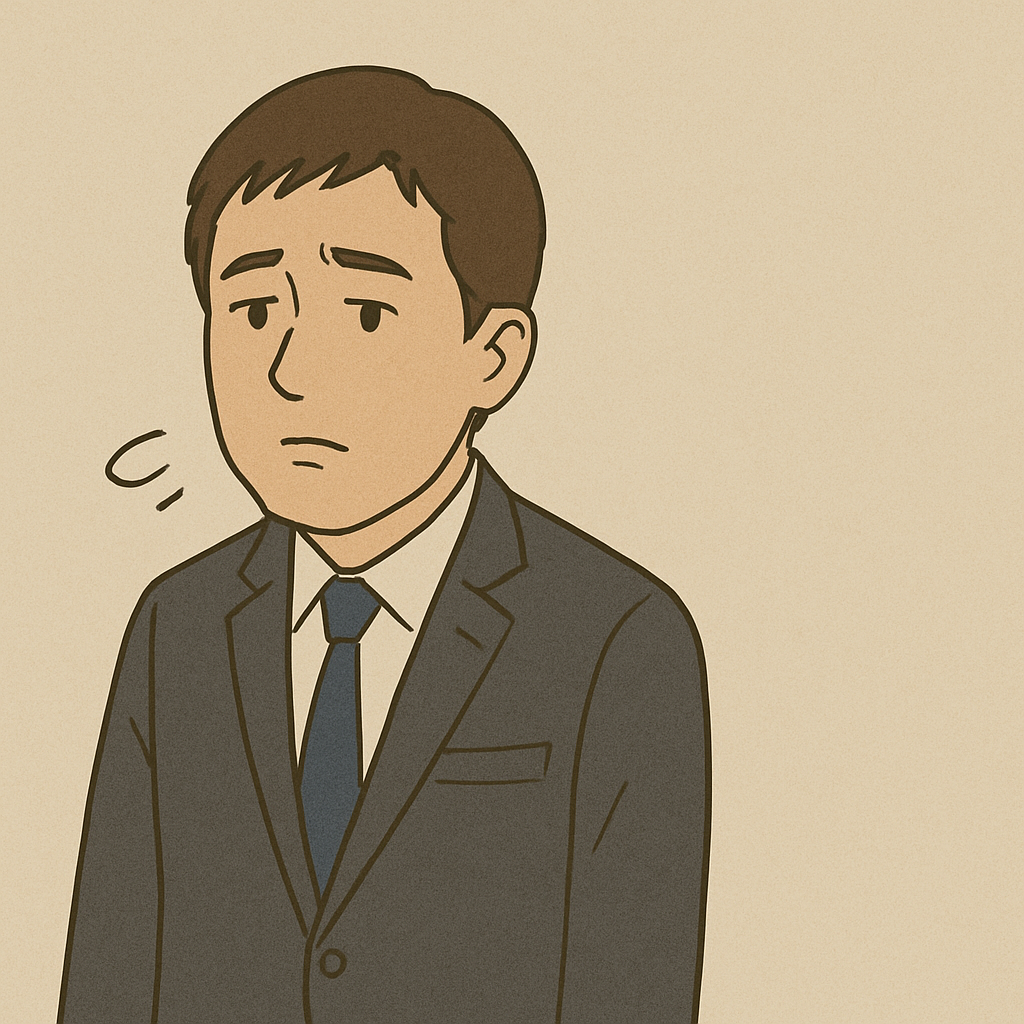依頼のはじまり
八月の湿気に包まれた午後、事務所のドアがぎいと軋んだ音を立てて開いた。入ってきたのは、腰の曲がった老婦人だった。うちわを片手に、「お暑うございますねぇ」と小さく笑ったその顔には、何かを抱えているような深い影があった。
婦人が差し出したのは、築六十年の平屋の登記事項証明書だった。名義変更の相談かと思ったが、そこには奇妙な点があった。最新の所有者欄が、見覚えのない名前に変わっていたのだ。
不動産の名義変更をめぐる違和感
「この家、私の息子が住んでいたはずなんです。でも、いつの間にか他人の名前に……」そう呟く婦人の声はかすれていた。登記簿を確認すると、たしかに三か月前に名義が変わっていたが、正規の手続きを経た形跡がない。
抵当権も仮登記も見当たらない。まるで誰かが跡形もなく家族の記録を塗り替えたかのようだった。書類上は問題ないはずの移転登記に、うっすらと不気味なものを感じた。
現れた老婦人の涙と言葉
「登記って、こんなふうに、家族がいなくなったみたいに変えられるものなんですか」婦人の言葉に、一瞬、答えに詰まった。彼女の話では、息子は二年前から音信不通だという。
隣人から「この家、売られたらしいですよ」と聞いて慌てて法務局に行き、登記簿を取得したのだという。涙で滲むその目を見て、軽い案件だと思っていた自分を恥じた。
調査開始
まずは登記の履歴を洗い出すため、法務局へ向かった。暑さと書類の山に囲まれて、軽くサウナ状態。パソコンで登記情報を引き出しながら、手書きの備考欄に目を凝らす。
すると、妙なことに気づく。仮登記が一度行われていた形跡があるのに、現在のオンラインデータには反映されていないのだ。これは見過ごされがちな落とし穴だった。
法務局で見つけた不可解な登記履歴
補正済と記された仮登記が二年前に申請されていた。その直後に死亡届が出されている息子の名前。まさか、死亡届と仮登記のタイミングが一致しているとは。
「やれやれ、、、また厄介なものに首を突っ込んだな」思わず口に出た。まるでサザエさんの波平がいきなりルパン三世に出てきたような、そんな異次元感だった。
仮登記の裏に隠された過去
記録をたどると、当初の仮登記は息子が単独で申請したもので、所有権を仮に自分に戻そうとする形になっていた。だが、本登記には至っていない。
さらに奇妙なのは、現在の所有者が登場するまでの間に、相続登記や贈与の記録が一切ないということだ。仮登記のまま放置された状態で、なぜか第三者に本登記がされていた。
サトウさんの推理
「誰かが仮登記の状態を悪用したってことですね」サトウさんは眼鏡をくいっと持ち上げた。冷たい麦茶を口に運びながら、机に並べた戸籍や登記簿のコピーを一瞥する。
その無駄のない動きに、元野球部としての僕の動体視力は無力だった。サトウさんはすでに、答えの手前に立っているようだった。
家系図から浮かび上がる第三の相続人
彼女は戸籍を読み解いて、息子には認知していない隠し子がいる可能性を指摘した。「この養子縁組届、なぜか破棄されてますけど、一度は法務局に出されてます」
相続権を持つ人間が別にいたとしたら、本来の登記手続きも変わってくる。相続を装った第三者が、本人になりすまし手続きを進めた可能性が見えてきた。
手書きの契約書に残された痕跡
古い書類の山の中から、手書きの売買契約書が出てきた。ボールペンで書かれた署名が、息子のものとは明らかに筆跡が異なる。
しかも契約書の右下には、小さな「印影修正済」の文字。これが、すべての鍵だった。誰かが登記だけを先に進め、現実の所有関係を偽装した証拠だった。
シンドウの失敗
正直に言うと、最初の段階で気づけたかもしれなかった。登記原因証明情報の欄に、誤字があったのだ。それだけで申請が跳ねられるケースもある。
しかし今回は、なぜか通っていた。気づかないふりをする審査官の存在も含め、何か大きな力が働いているような気がしてならなかった。
登記原因証明情報の見落とし
「こんなミス、気づいてたら……」後悔がじわじわと広がる。だが、これが現実だ。過去は書き換えられないが、未来は修正できる。
司法書士としてやるべきことは明確だった。登記を戻す手続き。そして、正しい相続人を確認すること。それだけだった。
やれやれと呟いた昼下がり
書類を携え、法務局に再度向かう途中、汗で背中がじっとりと張りついた。隣を歩くサトウさんが、ほんの一瞬だけ笑った気がした。
「やれやれ、、、世の中、紙とハンコだけじゃ動かないんですね」それが僕の口癖だったが、今日はなぜか自分で言って、自分で慰められた気がした。
真相への糸口
区役所で死亡届の提出日を確認すると、登記申請と同日だった。しかも、提出者の氏名が第三者のものであることが判明した。
つまり、息子の死亡を利用して、誰かが登記変更を行ったのだ。その人物こそが、今の所有者名義人だった。
名義変更直前に起きた死亡届の謎
このタイミングは偶然とは思えない。死亡の確認もされないまま、登記変更を済ませた形跡があった。役所の担当者は、苦い顔で記録を見せてくれた。
「あの人、身分証明書も持ってきてなかったのに、何だか強引で……」と。こうして偽装された手続きの全貌が、少しずつ姿を現してきた。
役所の記録と現地調査の食い違い
僕らは現地にも足を運んだ。近所の人に聞き込みをすると、「ああ、前の人は急に引っ越して、知らない若い人が住んでますよ」とのこと。
それが、名義変更された相手だった。住民票も移されておらず、居住の証拠もない。ただの名義貸しか、何かのフロントだろう。
事件の核心
真相はこうだ。息子の死を知った第三者が、仮登記の放置を利用し、相続人になりすまして登記を済ませ、家を手に入れたのだ。
そのうえで住民票も移さずに、表向きは老婦人が家を放置したかのように装った。すべては、登記の隙を突いた犯行だった。
疑惑の相続放棄とその矛盾
「相続放棄届が出てることにしておきました」犯人のメールの文面には、そう書かれていた。実際には、放棄の手続きは出されていなかった。
書類だけを作り、それらしく見せかけただけ。それが通ってしまうのが、今の制度の怖さでもある。サザエさんの家のように、安心とは限らないのだ。
遺言書のコピーが語る新事実
事件を追う中で、息子が生前に残した遺言書のコピーが出てきた。そこには「この家は母に残す」と明記されていた。
原本は所在不明だが、コピーには筆跡と証人欄も揃っており、十分な証拠となった。登記を取り戻す手続きは、ようやく一筋の光を見せはじめた。
解決編
裁判所での調停を経て、登記の是正が認められた。家は再び婦人の手に戻った。長かった迷路のような事件も、ようやく終わりを迎えた。
老婦人は涙を流しながら、「本当に、ありがとうございました」と深く頭を下げた。僕はただ、静かに頷いた。
登記簿に記された真実
訂正された登記簿を手に、婦人はまるで宝物のようにそれを胸に抱いていた。「これで、息子とまた一緒にいられる気がします」
その言葉に、ようやく司法書士としての仕事の意味を思い出した気がした。紙の向こうには、人の暮らしがあるのだ。
老婦人が語った家族の選択
「あの子は、遠くで苦しんでたんですね」婦人の独白が、部屋の中に静かに響いた。仮登記も偽装も、悲しみの上に成り立っていたのだ。
僕は黙って、その言葉を受け止めた。登記簿に書かれない真実が、そこには確かにあった。
事件のあとで
事務所に戻ると、書類の山が変わらずに積まれていた。「ま、そんなもんだ」僕は椅子に沈み込むと、窓の外をぼんやり眺めた。
サトウさんが、無言でアイスコーヒーを差し出した。氷がカランと音を立てた。
静かに閉じる依頼書類
今回の事件ファイルを封筒に収め、キャビネットにしまった。心なしか、いつもより少しだけ丁寧に綴じた気がした。
終わったのだ。たとえ帳簿の上だけでも、家族が再び一つになれたのなら、それでいい。
サトウさんのため息と冷たいコーヒー
「もう、また厄介なの拾ってきて」サトウさんはそう言いながら、パソコンを打ち続けていた。口調は塩だが、なぜかほんのり温かい。
「やれやれ、、、次は平和な相談だけにしてくれよ」僕はそう言って、コーヒーを飲み干した。苦味が、少しだけ優しかった。