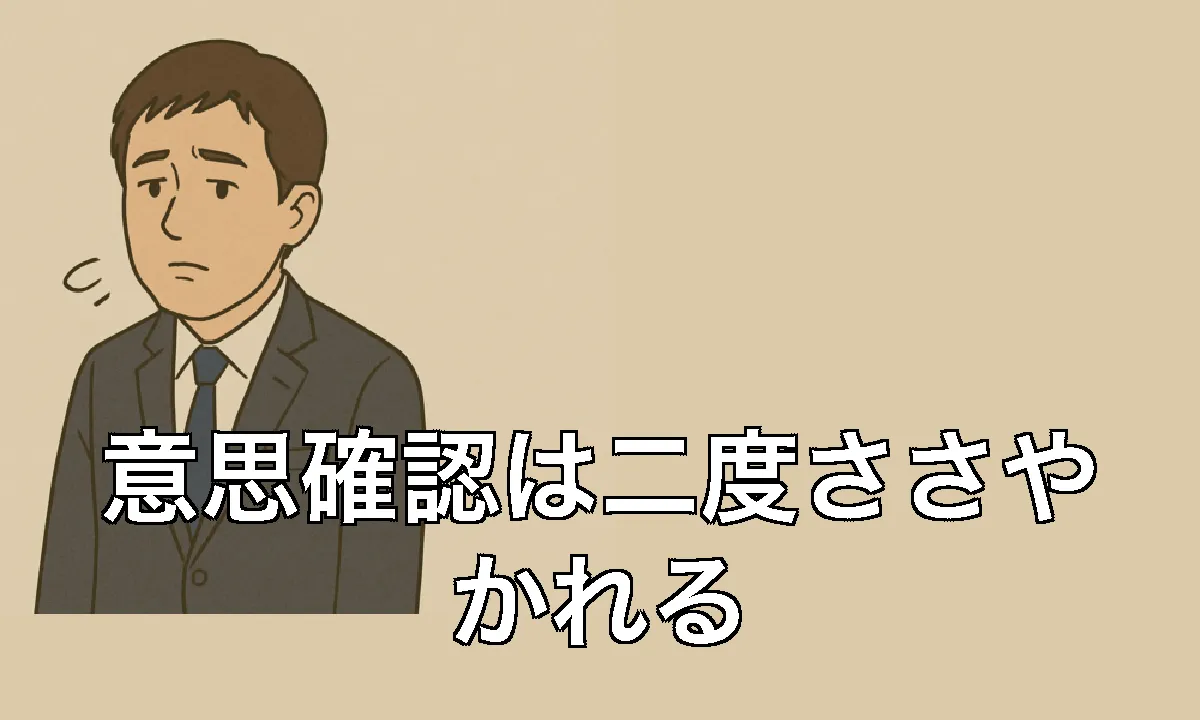はじまりは一通の遺言書
朝一番に届いたのは、一通の遺言書の検認に関する相談だった。提出したのは薄い水色のスーツを着た男性。柔らかく微笑んでいたが、その目はどこか濁っていた。
「母が亡くなりまして」と淡々と語る彼は、口調の端々に確信めいたものを滲ませていた。けれど、差し出された遺言書の内容に目を通した瞬間、私はふと眉をひそめた。
相続の割合があまりに極端すぎる。次男だけにすべてを譲ると明記された内容。しかも、作成は亡くなるわずか一週間前。そんなに都合よく書くものだろうか……?
依頼人の突然の死と不可解な内容
彼女は長年、地域の福祉活動にも力を入れていた。人を疑うより、まず信じる、そんな女性だったと聞く。その人が「他の子どもには一切の遺産を与えない」と記すだろうか。
しかも、遺言書の末尾には、「自筆に間違いありません」と書かれた一文。その筆跡が微妙に震えているように見える。年齢を考えれば自然かもしれないが……。
私は机に肘をつき、何気なく視線をサトウさんに送った。彼女は無言で頷いた。その沈黙の頷きこそ、私にとっては「警告」に等しいのだった。
サトウさんの無言の視線
彼女はすでに何かに気づいていた。私が迷っているとでも言うように、静かに書類の隅を指差す。そこには、わずかに角が折れた付箋が貼られていた。
それは、遺言作成時に使用されたとおぼしきメモ。そこに書かれていたメモはただ一言、「次男に全て」と走り書きされていたが、文字の筆圧が異様に薄い。
「なんか、薄いですね」と言う私に、サトウさんは事も無げに、「コピーに重ねて書いたような文字ですね」と言い放った。……それってつまり、なぞったってことか?
「確認印」の不自然な位置
さらに気になったのは、遺言書の右下にある朱肉の押印。これが妙に斜めに傾いている。一般的に押印は慎重に行うものだが、これはまるで、誰かが急いで押したようだった。
印影も微妙にかすれており、紙質に対して押し付けが浅い。本人が押したものだろうか……?いや、そもそも、彼女の印影ファイルと照らし合わせても微妙にズレている。
「やれやれ、、、またやっかいな案件を引いたな」と独り言を漏らした私に、サトウさんは「また?」と冷たくツッコミを入れてきた。
相続人たちの緊迫した空気
数日後、相続人たちが事務所に集められた。長女と三男、そして例の次男。それぞれの顔に出ているのは警戒と不信。空気が重い。
長女が真っ先に口を開いた。「母がそんなこと、言うわけないじゃない。私の誕生日に毎年手紙をくれた人なのよ」。その目には涙が滲んでいた。
一方、次男は視線をそらしながらも、「遺言がすべてですから」とだけ言った。まるで台詞のように、誰かから言われたことを繰り返しているような口ぶりだった。
次男が握る謎の封筒
妙な違和感を感じていた矢先、次男がカバンから封筒を取り出した。「これが母の最期の願いです」と静かに差し出す。
開けると、中にはもう一通の遺言書。それは、公証役場で作成された日付入りのもの。筆跡も押印も正式なものに見える。そして、そこには「三人に均等に相続させる」と書かれていた。
どういうことだ?日付は、問題の遺言書より一週間前——つまり、法的にはこちらが有効だ。次男は自分に有利な偽造文書を後出しで提出していたことになる。
シンドウの思いつきと勘違い
私は興奮して、「これで勝った!」と内心ガッツポーズをしたが、すぐにサトウさんから小声で「登記されてる不動産の名義、すでに変えられてるんですよ」と耳打ちされた。
……え?と驚く私に、サトウさんはスマホの画面を見せた。法務局のオンライン閲覧で確認された名義変更の履歴。どうやら、次男は偽の遺言を持って申請を済ませていたらしい。
「やれやれ、、、手際が良すぎるってのも罪ですね」私がそう漏らすと、サトウさんはため息をつきながら、「だから言ったのに」とだけ返してきた。
法務局でのうっかり発言
私はすぐに法務局に向かい、事情を説明した。「意思確認が虚偽の可能性がありまして」と熱弁をふるったが、担当官に「それ、登記終わってますよ」とぴしゃり。
その瞬間、思い出した。あのとき押した確認印の話。まさか、あれが偽造とは……。うっかり見逃していた自分が恥ずかしくなった。
「でも大丈夫です」と言ったのはサトウさん。「録音があるはずです。公証役場の確認も取れますし、名義戻しの申立ても可能です」と。さすが、塩対応でも頼りになる。
それでも糸口はつながって
私は再び次男を呼び出した。「一緒に録音を聞いてみましょうか」と提案すると、彼は急に青ざめ、「あれは、記録されてないと思いますが」と口走った。
その一言で、すべてが確信に変わった。つまり、録音の存在を恐れているのだ。事前に内容を捏造していた証拠に他ならない。
実際、公証役場に保存されていた音声データには、本人がしっかりと三人への平等な相続を述べている様子が録音されていた。
録音データに残された「ささやき」
「……本当にこれでいいんですね?」と公証人の声の後、微かに聞こえた母の返答。「……平等が一番ね」。そのささやきが、真実だった。
遺言の重みは、その言葉の一つひとつに宿る。記された文字よりも、声の震えが雄弁に語っていた。
次男の顔から、言い訳という名の仮面が剥がれ落ちるのを私は黙って見ていた。法は冷たいが、真実には温度がある。
真実は確認の奥に
あの「意思確認」とは、形式ではない。心の底から発せられた言葉こそが、本物の意思だ。それを証明するのが、我々の仕事だ。
長女と三男は涙を浮かべながら、録音を再生するスマホに手を重ねた。家族の崩壊を救ったのは、亡き母のわずかな声だった。
そして私は思う。司法書士というのは、書類の番人ではなく、時に心の証人にもなれるのだと。
声の主と手書きの差異
筆跡は似せられても、声は似せられない。そこに残る微細な震え、抑揚、そして「間(ま)」——それらすべてが、彼女の「本物」だった。
今回の件で、改めて思い知った。人の意思というものは、印鑑一つで語り尽くせるものではない。記録と記憶の間で、我々は証拠を探し続けるのだ。
「やれやれ、、、サザエさんみたいに平和には終わらんよな」と私がこぼすと、サトウさんは「それでも最終回にならないのが人生ですから」と、どこか達観していた。
事件の終わりと静かな余韻
事件は解決した。偽造遺言による不正登記は、家裁と協議の末、名義が元に戻された。次男は刑事告発を免れなかったが、それもまた「意思確認」の責任だった。
事務所に戻った私は、机に山積みの書類を見てため息をついた。「これ全部、今日中ですか?」と聞くと、サトウさんが「はい、当然です」ときっぱり。
……やれやれ、推理よりも書類の山の方が、よほど人を追い詰める気がする。そう思いながら、私はペンを手に取った。