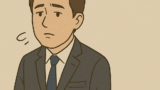古びた依頼書の封筒
朝の事務所に届いた一通の封筒は、いつもの請求書の束の中に埋もれていた。だが、その茶封筒は妙に時代がかっており、どこか昭和のにおいがした。差出人の名前に見覚えがあったが、なかなか思い出せなかった。
封を切ると、中には短い手紙と地図のコピー、そして登記簿の写しが同封されていた。手紙の日付は十年前。書いた本人はすでに故人となっていることを、ぼくは数秒後に思い出すことになる。
「やれやれ、、、」と声に出すと、机の向こうからサトウさんが一瞥をくれた。その目には「またか」という軽い呆れが浮かんでいた。
机の上に置かれた一通の手紙
「この手紙を読んでいるということは、私はすでにこの世にはいません」と書かれた文面には、まるで漫画の探偵物のような芝居がかった雰囲気があった。が、内容は真剣だった。
亡き依頼人がかつて所有していた山林の登記をめぐって、奇妙な事実が記されていた。どうやら土地の名義が、知らぬ間に別人に変わっていたらしい。
「司法書士として、最後にあの土地の真実を明らかにしてほしい」——その一文に、ぼくは思わず背筋を伸ばした。
送り主は十年前の依頼人
送り主は、かつて相続登記の相談で何度かやり取りをした老婦人だった。几帳面で、言葉少なに感謝の手紙をくれるような人だった。
だが、登記完了後、音沙汰がなくなった。あのとき、何か見逃していたのだろうか。ぼくは当時のファイルを引っ張り出し、封筒の中身と照らし合わせた。
ファイルの中の登記識別情報のコピーには、確かに本人の筆跡で「未使用」と赤字で書かれていた。それがどうして、今は他人の名義になっているのか。
消えた登記簿の謎
法務局で調べてみると、登記簿の閉鎖情報に不可解な点があった。現在の地番が別の形式に変わっており、元の記録へたどり着くのに時間がかかるようになっていた。
しかも、変更履歴の書類が物理的に見つからない。職員も「数年前の資料室閉鎖以降、古い帳簿は移管先にあるかもしれません」と曖昧な返答だった。
資料室はすでに無人で、鍵を持つ担当者も不在。ぼくは鍵の管理台帳から名前を辿り、次の訪問先を決めた。
閉鎖された法務局の資料室
資料室の扉はまるで、サザエさんのエンディングに出てくるあの押入れのように重く、ぼくの背中に嫌な汗が滲んだ。だが、開けてみるとそこにはほこりまみれの棚が並ぶだけだった。
その奥に、「昭和五〇年台登記簿」と書かれた段ボールがあり、中に目的の旧地番の情報が見つかった。
だが、地目の記載が奇妙だった。当初は山林として登録されていたが、ある時期に「宅地」に変更されていたのだ。
誰にも見つからなかった地番
その宅地という地番を地図で確認すると、位置が明らかにズレていた。まるで誰かが意図的に地図上の座標を操作したかのようなずれだった。
変更申請人の署名欄には、見覚えのある名前があった。かつてトラブルで知られた測量士だった。ぼくはその名を検索し、所在を突き止めることにした。
事務所はすでに閉鎖されていたが、サトウさんがSNSから私設の掲示板を見つけてくれた。「この人、最近実家に戻ってるみたいですよ」と、スマホの画面をこちらに差し出した。
サトウさんの冷静な推理
「要するに、その測量士が勝手に地目を変更して、他人の名義にすり替えたってことですか?」とサトウさん。
「いや、たぶんもっと巧妙だ。地番の移動を利用して、土地を“消した”んだ」と、ぼくは気づき始めていた。まるで怪盗キッドがトリックを使って宝石を消すように。
元の登記簿には、微かに「計画換地」と書かれていた。土地区画整理法を使えば、地番の変換は合法的に行える。問題は、それが本当に所有者の意志だったのかどうかだ。
旧地番と現地番の罠
計画換地の図面を調べていくと、かつての山林が町の一角の住宅街に変わっていた。そして、その区画は現在、第三者の名義になっていた。
その名義人を調べると、ある不動産業者の代表者名だった。偶然とは思えなかった。旧地番の時点で所有権が移転されていたなら、問題はない。
しかし、移転登記の履歴が不自然に空白だった。登記官の処理も曖昧で、まるで裏で何か操作されたような空気を感じた。
所有者欄に現れた別人の名前
サトウさんが調べてくれた古い謄本には、登記原因が「贈与」となっていた。だが、故人が贈与契約を交わしたという記録はどこにも残っていなかった。
贈与契約書の写しを求めて不動産業者に連絡すると、「うちではその書類は預かっていませんね」と、明らかに嘘をついている口調だった。
そのやり取りを録音していたぼくは、法務局に苦情を申し立てる覚悟を固めた。もう、見過ごすわけにはいかなかった。
村の古老が語った記憶
土地の現地確認のために向かった村で、ひとりの古老に話を聞くことができた。「ああ、その土地な。婆さんが大事にしとったよ。あの山の裏に小屋があったはずじゃが、、、」
ぼくとサトウさんは案内された裏山に足を踏み入れた。そこには、草に埋もれた平屋の小屋がひっそりと佇んでいた。中は埃だらけだったが、封筒に包まれた何かを見つけた。
それは、一冊の古い手帳だった。
空き家の裏に埋もれた小屋
小屋の天井裏にあったその手帳には、故人が書いた日記と、地目変更に関するメモが記されていた。「この土地だけは、誰にも渡してはならない」——ページの隅にそう書かれていた。
日記は測量士との確執や、不動産業者とのやりとりも記録しており、何より「契約していない」と明言されていた。
この手帳が、すべてを覆す証拠になる。ぼくはそう確信した。
そこに眠っていた手帳
事務所に戻り、ぼくは手帳のコピーを法務局と県の司法書士会に提出した。結果、土地の所有権移転登記は不正なものとして抹消された。
不動産業者は行政指導を受け、測量士も処分を受けることになった。「正義は勝つ」とは言わないが、少なくとも依頼人の意思は守られた。
「依頼、完了です」と、サトウさんがぽつりと呟いた。その声は珍しく、少しだけ柔らかかった。
やれやれ、、、また一つ終わった
ぼくは椅子に深くもたれかかり、天井を見上げた。「やれやれ、、、また変な話に首を突っ込んじまったな」と独り言を漏らす。
サトウさんは「毎回そう言ってますけどね」と冷たく言いながら、コーヒーをぼくの前に置いた。まるでエンディングテーマが流れ出すような静けさだった。
だが、机の上にはもう一通、新しい封筒が届いていた。
サトウさんの無言の労い
その封筒を手に取ると、差出人の名前にまた見覚えがあった。どうやら、次の事件も一筋縄ではいかないようだ。
「また?」とサトウさんが眉をひそめた。ぼくは苦笑いして返しただけだった。
この街には、まだまだ司法書士の出番があるらしい。
そして机の上に新たな依頼
陽が差し込む窓の外では、蝉が鳴いていた。暑い夏はまだ続く。ぼくはゆっくりと書類に手を伸ばし、サトウさんが出す書類バサミの音に耳を澄ませた。
今日もまた、事件と書類とコーヒーの一日が始まる。
そしてたぶん、ぼくはまた「やれやれ、、、」と言うことになる。