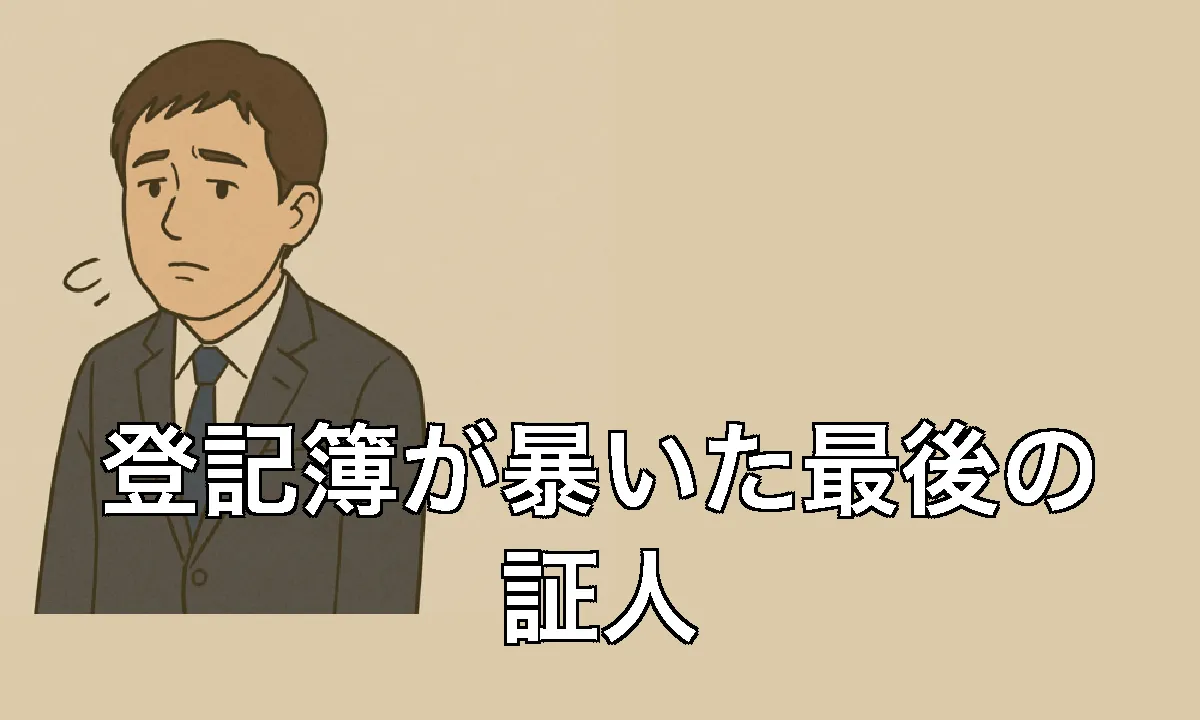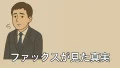朝の来客と一通の書類
午前八時、まだコーヒーの香りが漂う事務所に、重たい足音と共に男が入ってきた。歳は六十を超えているだろう、どこか影のある表情だった。差し出されたのは、折り目が古びた登記事項証明書だった。
私は書類を受け取り、ざっと目を通した。田舎によくある山林の名義変更の相談かと思ったが、記載された筆界と現地の状況が妙に食い違っているように見えた。嫌な予感がした。
依頼人は無口な初老の男性
男はほとんどしゃべらなかった。「昔の家を整理していて…」とだけ言い残し、所在なげに視線を落としたままだった。身なりは整っていたが、どこか浮世離れした雰囲気があった。
私は内心で「この手の依頼は厄介なんだよな」と思いつつも、司法書士として放っておくわけにはいかない。なにせ登記簿は、黙っていても真実を語るやつなのだ。
古びた登記事項証明書に記された違和感
書類に記された地番と、横に書かれていた地目が一致していなかった。何よりも、名義人の変更履歴に飛びがある。昭和五十五年から平成にかけて、空白の十年があるのだ。
その期間中、何があったのか。なぜか登記の名義が変わっていないまま、相続されているように見える。私はその空白に、かつて読んだ怪盗漫画のような匂いを感じていた。
サトウさんの冷静な観察
「この字、違いますよね」と言ったのはサトウさんだった。彼女は登記簿をスキャンし、手元の資料と照らし合わせていた。あいかわらず冷たい目で、こちらを見ることもなく。
「あ、ああ、確かに筆跡が違うな…」と私が答えると、「言われなきゃわかりませんよね」と一言。塩対応にも慣れたが、毎度のことながらグサッとくる。
気づいてしまった不一致の地番
サトウさんが指摘したのは、地番の末尾が二桁違うという点だった。一見、誤記のように見えるが、地図を確認するとその場所はすでに民家が立っている。
つまり、登記簿上の場所と現地の土地がズレているのだ。これは合筆登記や分筆登記が絡んでいる可能性がある。いや、それにしても不自然すぎる。
図面と実地のズレが意味するもの
公図を確認し、私は嫌な汗をかいた。合筆された土地が、途中で一部だけ名義変更されている。しかも、その時期には相続登記も発生していない。何かが隠されている。
「これ、完全に誰かが意図的にやってますよ」とサトウさんが淡々と言った。やれやれ、、、また厄介な案件を引き当ててしまったようだ。
過去の名義人にまつわる噂
調査のために地元の不動産業者を訪ねた。彼は古い記録簿を見せながら、ぽつぽつと話し始めた。「ああ、この土地? たしか昔、事故があってな…」
聞けば、その土地では火事があり、名義人が亡くなったという話だった。だが、それに関する登記は一切なかった。不審な点が増えるばかりだった。
消えた名義人と地域の都市伝説
「夜中に白い着物の人が立ってたって、昔はよく言ってましたよ」と不動産屋が苦笑まじりに言う。サザエさんの磯野家とは真逆の、暗くて重い家庭の匂いがする。
どうやらこの土地には、世間に語れない過去があるようだった。名義人が事故死したというのも、単なる噂かもしれない。あるいは、意図的にそう広めた誰かがいたのか。
一枚の公図が語る真実
古い公図を確認するため、市の資料室へ足を運んだ。そこで見つけたのは、手描きの境界線が引かれた昭和三十年代の公図だった。
その中に、明らかに削除された跡があった。訂正印も押されていない。不自然に消された区画が、事件の中心であることは間違いなかった。
公図と登記の食い違い
登記簿上の面積と、公図上の面積が一致していない。その差は三坪。小さなズレだが、そこに建っていた家は火事で焼けたという。
このズレは偶然ではない。何かを隠すために、意図的に作られた帳尻合わせだ。私はその確信を得た。
昭和期の合筆が導いたミス
更に調べると、昭和五十五年に一部筆界が合筆されていたことがわかった。だが、その登記手続きには矛盾が多すぎる。
署名者の中に、既に死亡しているはずの人物の名前があったのだ。これは明らかに不正。となれば、犯人はその頃から仕掛けていたことになる。
嫌な予感と夜の訪問者
その晩、事務所に戻った私は背筋が冷えた。玄関の前に、誰かが立っていたような気がした。だが、出てみても誰もいない。
静まり返った夜に、突然鳴り出す電話。受話器を取ると無音。背後には、確かな何者かの気配が残っていた。
無言電話と誰かの気配
三度目の無言電話のあと、私は事務所のブレーカーを切って静かに待った。やがて、サトウさんが差し入れの缶コーヒーを持って現れた。
「監視カメラ、設置しておいてよかったですね」と彼女は淡々と言った。映像には、玄関先で何かを覗き込む黒い影が写っていた。
サトウさんの冷たい指摘
「あの男、たぶん本当の依頼人じゃないです」とサトウさんが断言した。「机に置いてあった登記簿、最新のじゃなかったです。わざと古いのを見せたんですよ」
やれやれ、、、完全に一杯食わされた。だが、それならば尚更、ここで引くわけにはいかない。司法書士の意地というものがある。
司法書士の調査開始
私は一晩かけて、過去十年分の登記簿を洗い直した。地番の動き、相続の流れ、分筆された日付。そのすべてに、一本の線が引ける瞬間があった。
そこにあったのは、壮大な名義人偽装のトリックだった。まるで金田一少年の事件簿のような構図。犯人は、あの初老の男ではなかった。
登記履歴を一つひとつ洗い直す
昔の登記簿は、毛筆で記されており、癖字を読み解くのにも苦労する。だが、そこには確かな証拠が眠っていた。
ある筆跡が、別の地番の名義変更にも登場していた。それは、土地家屋調査士の筆跡だった。
昔の名義に潜むトリック
実際には亡くなっていたはずの人物が、なぜか最近の登記に登場している。これは相続人を偽った何者かの仕業だ。
登記簿が語るのは、数字だけじゃない。筆跡、訂正印、余白の不自然さ。そのすべてが、真犯人の手口を浮き彫りにしていく。
隠された筆界と埋もれた事実
再度現地を訪れた私は、崖の下にある境界杭を発見した。それは、正式な筆界とは異なる場所に打たれていた。
かつてそこには小屋があったが、火事で焼け落ちたとされていた。だが、跡地には一枚の金属片が埋もれていた。
崖地に残された境界杭
その杭には、旧名義人の名前が刻まれていた。正式な境界であったことは疑いようがない。
つまり、登記簿は偽られていたが、杭だけは真実を語っていたというわけだ。
それを見逃していた過去の登記
過去の土地家屋調査時に、この杭の存在が意図的に無視されていた可能性が高い。つまり、当時から偽装が仕込まれていたということになる。
そして、それを主導した人物の名が、再び私の目の前に浮かび上がってきた。
そして見えた相続の真相
真相はこうだ。名義人は火事で死んだのではない。行方不明になった後、勝手に死亡届が出されていたのだ。
その隙に、土地は身内によって密かに売却されていた。そして、それを可能にしたのが一人の司法書士だった。
遺言書の不自然な日付
公正証書遺言に記された日付が、名義人の失踪日と一致していた。そんな偶然があるだろうか。
さらに証人の一人が、当時未成年だったことも判明。完全にアウトだ。
証人の署名に仕掛けられた細工
署名のインクが他と違う。紙質も違う。つまり、あとから書き換えられたということ。
全てがつながった。犯人は、依頼人のふりをした男ではなく、その背後にいた人物だった。
サトウさんの最後の一手
サトウさんは、依頼人が置いていった封筒をこっそり解析していた。そこに使われていた糊が、近年の製品ではないと気づいたのだ。
つまり、あの封筒は偽物。中の登記簿も、古いものをコピーしただけ。すべては見せかけだった。
書類の折り目が語る使用時期
サトウさんはさらに、折り目の深さから保管期間まで特定した。おそらく十年以上押し入れに入っていたものだろう。
それを今になって持ち出した理由、それこそが事件の動機だった。
机の中にあった破られた下書き
机の奥から出てきたメモ用紙には、「今さら隠し通せない」と走り書きされていた。
真犯人は、恐怖に駆られて自らの罪を暴露しようとしていた。だが、間に合わなかった。
結末と真犯人の正体
証拠をすべて揃えた私は、県警に通報した。かつて名義人だった男は、生きていた。戸籍上は死亡していたが、別の名で暮らしていた。
全てを仕組んでいたのは、その男の兄。弟の失踪を利用し、自分の借金を返すために土地を売ったのだった。
登記簿が導いた決定的証拠
登記簿は黙っているが、嘘はつかない。正しく読めば、すべてを語ってくれる。
私はそのことを改めて実感した。やれやれ、、、たかが一枚の書類、されど一枚の真実だった。
依頼人の真の目的と涙の告白
本当の依頼人は、名義人本人だった。彼はすべてを知っていて、過去と向き合うために、登記簿を持って事務所を訪れたのだった。
「弟が許せなかった。でも、あなたのおかげで目が覚めました」と、彼は涙を流した。私はそっと、コーヒーを差し出した。