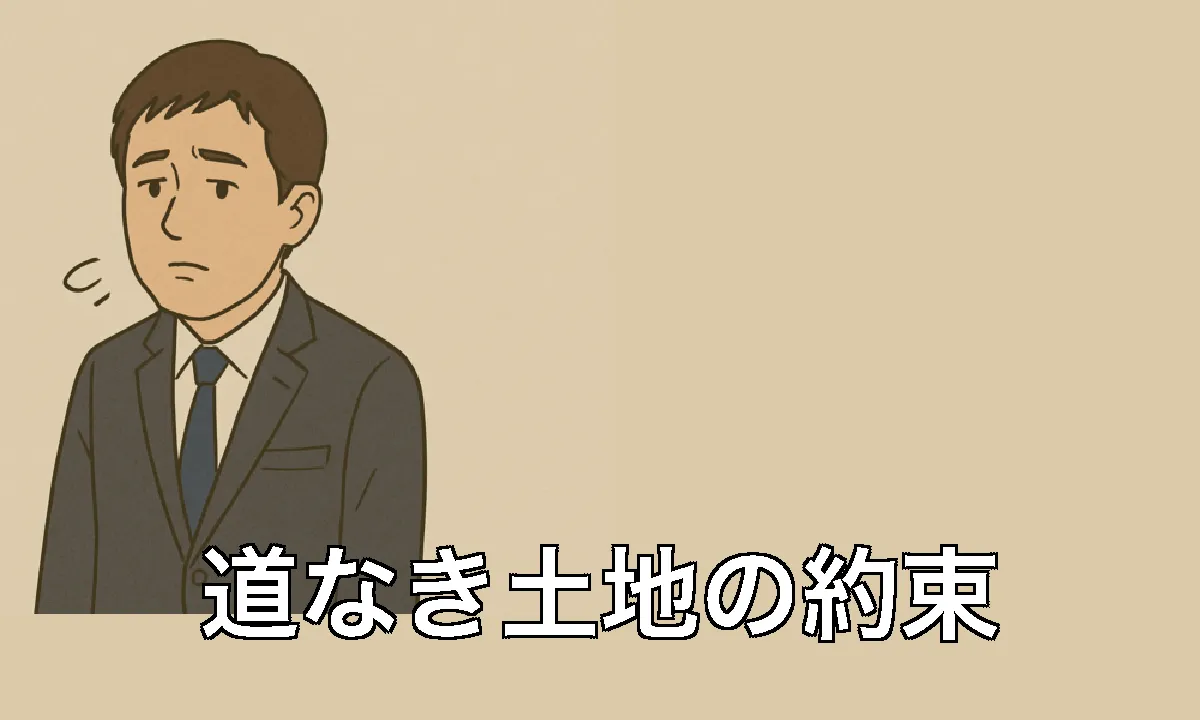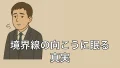はじめに降ってきた地図
茶封筒に入った謎の手書き地図
朝一番、事務所のポストに投げ込まれていた茶封筒は、差出人のないものだった。中には古びた手書きの地図と、土地の登記事項証明書のコピーが入っていた。雑な線で描かれたその地図には、赤いボールペンで「ここに注意」とだけ書かれていた。
送り主の名前は見覚えのある筆跡
地図の端に書かれたメモ書きの筆跡を見て、俺はハッとした。これは三年前、相続放棄の手続きをした依頼人のものだ。彼はあの時、「土地はいらない」と言い切っていた。だが、なぜ今さらこんなものを送りつけてきたのか。
接道義務の死角
道路に接していない土地の怖さ
不動産の取引で、土地が道路に接していないというのは致命的な瑕疵だ。再建築不可、融資不可、価値ゼロ。いわば“不動産界の妖怪ぬりかべ”みたいなものだ。今回の地図には、その接道が曖昧な記述が目立った。
図面と現地の矛盾
法務局で取得した公図では、確かに土地は二メートルだけ道路に面していた。だが、送られてきた手書き地図では、その接しているはずの部分に民家の塀が描かれている。つまり、現地ではもう「道」は消えている可能性が高い。
依頼人は嘘をついているか
元地主の告白と矛盾
俺は当時の依頼人に連絡を取った。電話越しに聞こえた声は、思ったよりも元気そうだった。「あの土地、実は他人の塀がはみ出しててさ…俺、怖くなって逃げたんだよ」彼は笑っていたが、どうにも乾いた音だった。
登記情報との食い違い
登記上は、境界に異常はなかった。だが現地の写真を見る限り、明らかに塀が越境している。これでは売買も登記もできやしない。やれやれ、、、俺の出番ってわけか。厄介ごとがまた一つ、降って湧いた。
サトウさんの冷静な推理
私道と公道の定義の罠
「これ、接してるの私道ですよね。しかも、所有者が登記されていない」いつの間にか背後に立っていたサトウさんが、ディスプレイを覗き込んで言った。その声は冷たくも頼もしい。「要するに“接道してる”って言っても、建築基準法的にはアウトってことです」
境界杭が語る真実
現地に赴き、境界杭を探すと、それは思いもよらぬ位置に埋まっていた。かつて道だった場所は、今は庭石と物置に侵食されていた。近所の住人が勝手に使っていたのだ。しかも十年以上。つまり時効取得の可能性もある。
やれやれ、、、俺の出番か
元野球部の動体視力が生きる時
ふとした拍子に、地図の端に小さく書かれた「境界杭→」の矢印が目に留まった。俺はその細かすぎる文字を読み取り、直感的に杭の位置を推測した。元野球部の動体視力、伊達じゃない。いざスコップで掘ってみると、そこにはまだ誰にも見つけられていない杭があった。
現地調査で見つけた裏の道
その杭が示す場所は、かつての農道と繋がっていた。地元の古老に話を聞いたところ、「昔はみんなその道を通って田んぼに行ったもんだ」と証言が得られた。これで“通行実態”が認められれば、建築基準法の特例を使える可能性が出てくる。
地図の空白に隠された動機
立地条件が変える土地の価値
その土地の隣には、大型ドラッグストアの出店計画があった。もし道路に接していれば、買取額は跳ね上がる。誰かが意図的に接道を消し、その価値を下げて買い叩こうとしていたとしたら…。これは、土地をめぐる陰湿な経済的殺意だ。
意図的に消された接道の証拠
さらに古い航空写真を取り寄せたところ、明らかに道だった部分が途切れていく過程が映っていた。年度ごとに塀が広がっていた。これは無意識の越境ではない。計画的犯行だ。サザエさんの波平のような見た目の隣人が、まさか裏で“カツオ的な計略”を働かせていたとは。
真犯人の不在と司法書士の正義
告訴ではなく登記で勝負
俺たちは警察に駆け込む代わりに、登記上の回復と特例の適用に全力を注いだ。通行実態、古い資料、住民証言、そして杭の発見。これらをもとに建築審査会に申請書を提出し、ようやく接道義務のクリアにこぎつけた。
紙の地図が語ったもうひとつの遺志
後日、依頼人から再び手紙が届いた。「あの土地は、父の形見なんです。だからこそ誰にも奪われたくなかった」地図に込められたものは、単なる道の情報ではなかった。これは、世代を超えて守りたいものへの“静かな叫び”だったのかもしれない。
結末と後味
土地は売れたが心にはひっかき傷
土地は無事、ドラッグストア系列に高値で買い取られた。依頼人は「これでようやく父に顔向けできる」と言って涙を流した。俺は何も言わず、ただうなずくだけだった。仕事とはいえ、やりきれない後味が残る事件だった。
サトウさんの冷たい一言とその意味
「結局、地図より現場ってことですね」サトウさんが帰り際にそう言った。その表情はどこか笑っていたような、あきれていたような。俺はうなだれながら、「やれやれ、、、もう少し優しくしてくれてもいいのに」とつぶやいた。