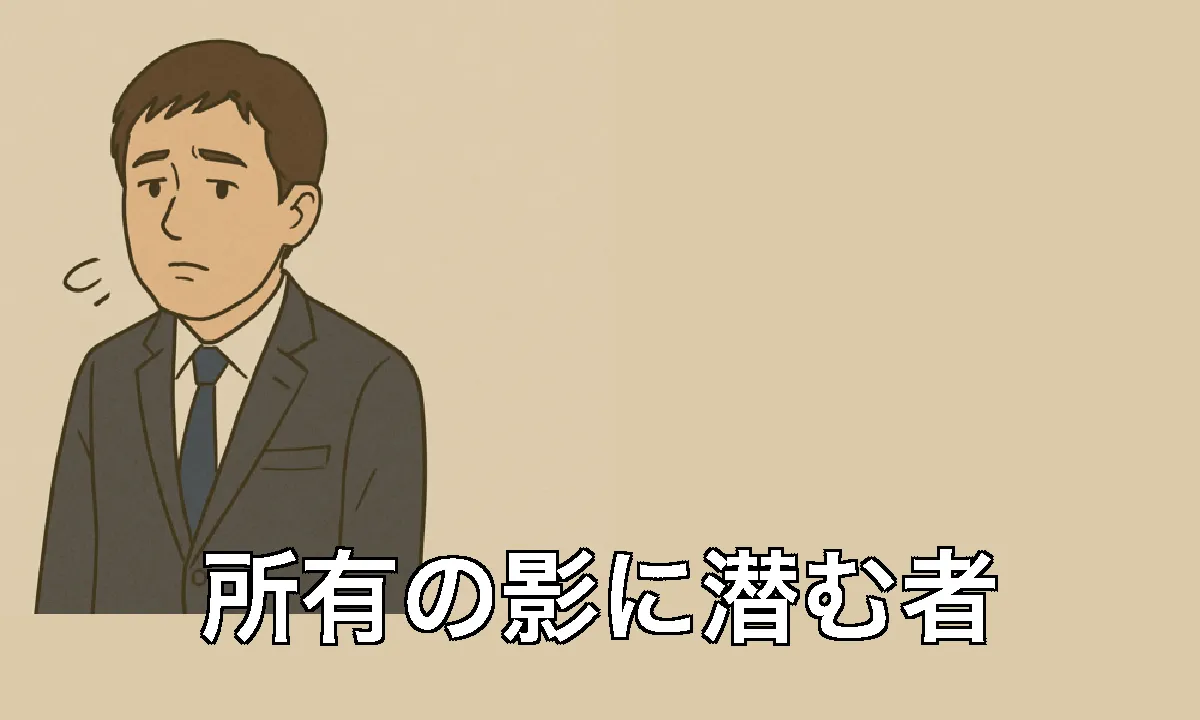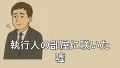奇妙な相談者
登記簿に現れない名前
朝から重い腰を上げて事務所のシャッターを開けたとたん、スーツ姿の中年男性が足早に駆け寄ってきた。目は血走り、手にはしわくちゃの古い登記識別情報通知書。第一声は、「この土地の真の所有者は、実は私なんです」だった。
思わず「やれやれ、、、」と呟いた。月曜の朝に出てくるフレーズじゃない。土地の所有権をめぐるトラブルなんて珍しくないが、何かが引っかかった。通知書の発行年月日が、妙に古すぎるのだ。
登記簿を閲覧すると、確かに彼の名はどこにもなかった。そこに記載されていたのは、第三者の全く無関係な名義だった。相談者は「騙された」と繰り返したが、むしろこっちが騙されてる気分だった。
笑わない依頼人
話を進めても、男の表情は変わらない。訴訟を起こすつもりもない。ただ「名義を戻したい」という。証拠もあるらしいが、それを見せる前に「まず信じてほしい」と言うあたり、怪しさ満点。
まるでアニメ『名探偵コナン』の冒頭で現れる、決まって事件の鍵を握るキャラみたいだった。「誰かがこの土地を乗っ取ったんだ」と語る口ぶりも、脚本家が書いたように完璧すぎた。
「とりあえず、関係書類をすべて見せてください」と促すと、彼は鞄から封筒を一枚取り出した。その厚みと年季の入り具合からして、一筋縄ではいかない案件の予感がした。
不可解な名義変更
過去の登記記録を洗う
まずは過去の登記履歴を追った。司法書士の仕事のうち、地味だが最も重要な部分だ。数回の所有権移転を経て、現在の名義人に至っている。ただ、その中の一件、平成14年の移転登記に不自然な空白があった。
「これは、、、書類が足りない」とサトウさんが呟く。彼女が見逃すはずがない。しかもその登記の申請者は、いま依頼人が「乗っ取られた」と主張する相手と同一人物。香ばしくなってきた。
登記申請の添付書類が不足していた可能性がある。それが意図的なものであれば、これはただの不備では済まされない。背後に何かある。そんな気がした。
消された名義人の痕跡
職権で閉鎖された登記簿の写しを法務局で取得した。そこには、数年前までまったく別の人物の名が記載されていた。依頼人の主張が本当ならば、この名義変更は虚偽登記に該当する可能性がある。
しかし、名義が変わった理由を裏付ける書類がまったく残っていない。不動産登記において「ない」ということほど厄介なものはない。消されたのか、もともとなかったのか。
本当に「存在しない所有者」が現実にいるとすれば、それは司法書士にとって一種のホラーだ。過去の登記がどこまで正当で、どこから嘘なのか。答えは法務局ではなく、現地にあるかもしれない。
サトウさんの冷静な推理
地番の読み間違いが招く真実
事務所に戻ると、サトウさんがふいに言った。「これ、地番違いかもしれません」。調査した地番と、依頼人が主張している地番が1つずれている可能性があると、過去の住宅地図を広げながら指摘した。
まさかと思ったが、地番が飛んでいるエリアだった。つまり、依頼人が主張する土地と、現在の名義人の土地は、元々隣接しているが別物。混同しやすい構造になっていたのだ。
しかし、それだけでは辻褄が合わない。地番の勘違いで名義が変わるなんて、普通は起こらない。やはり、誰かが意図的に仕組んだと考えるべきだろう。
「これはわざとでしょうね」
サトウさんは机をトントンと叩きながら言った。「この申請書、筆跡が変なんです。添付の委任状と微妙に違う」。書類の細かい部分まで見逃さないのが、彼女の恐ろしいところだ。
筆跡鑑定まではいかずとも、確かに違和感がある。委任者の署名もどこか稚拙で、印鑑も不鮮明。経験的に言えば、第三者が勝手に作成した可能性が高い。
「意図的に似た地番で申請をかけた上で、委任状も偽造した」——サトウさんの推理は鋭く、そして現実的だった。これではまるで、登記簿を使った怪盗のトリックだ。
現地調査の罠
元地権者の証言
現地を訪ねると、隣地に住んでいたという老婆が事情を知っていた。「昔はあの人が畑をやってたよ、たしか名前は、、、」と言って依頼人の名前を口にした。その証言が決め手になった。
非公式ながらも、実際に使っていた者と所有者が異なっていたことを示す証言。不法占拠と見るか、口約束の売買と見るか。解釈次第で結論は分かれる。
だが重要なのは、依頼人がまったくの虚言ではなかったということ。この証言によって、彼の主張に一定の信ぴょう性が出てきた。
所有者不明土地に隠された意図
地元では時々あることだ。相続が放置され、登記が更新されず、名義が宙に浮いたままの土地。その混乱に乗じて、偽の登記申請をかける者もいないわけではない。
今回もそのケースに限りなく近い。依頼人が使用していたが、登記上は第三者。混沌とした登記情報のなかで、誰かが「空白」を利用したのだ。
しかもその誰かは、登記実務に精通している。素人が仕掛けたトリックではなかった。犯人は、司法書士か、行政書士か、それとも、、、
やれやれ、、、古い因縁か
「昔の揉め事ってのは根が深いんだよ」
過去の関係者を洗っていくと、現在の名義人と依頼人は、かつて親戚同士だったことが判明した。どうやら相続の際に分筆と登記申請を巡って揉めていたらしい。
その時の「恨み」が今回の事件の動機につながっている可能性が高い。いわば、法を利用した復讐劇だ。表向きには完璧な登記だったが、裏に人間の感情が渦巻いていた。
僕はため息をついた。「やれやれ、、、」因縁がついた土地ってのは、やっぱり面倒だ。
真の所有者は誰なのか
隠された相続登記
最終的に、依頼人の親族のひとりが残していた未登記の遺産分割協議書が発見された。そこには依頼人が本来の所有者であることが明記されていた。これで勝負は決まった。
きちんと登記されていなければ、その権利は第三者に主張できない——それが原則だ。だが今回は、登記制度を悪用した側の意図があまりに明確だった。
司法書士として、そして人間として、どちらを守るべきか。迷いはなかった。僕は、依頼人の正当性を示すための登記手続きを始めた。
司法書士シンドウの逆転
うっかりが導いた一手
調査中に誤って地番を一つ隣と間違えたのが、皮肉にも真相解明の突破口になった。あの間違いがなければ、今でも登記簿の中で迷子になっていたかもしれない。
「やっぱり僕って、うっかりミスが武器になる男なんですよ」と言ってみたが、サトウさんは無反応だった。まあ、いつものことだ。
ただ、今回ばかりは冗談ではなく、実際にそれが勝因だったのだから、少しは褒めてほしかった。
裏書きに残された決定打
依頼人が最後に差し出した、古い売買契約書の裏に、小さく「登記は後日本人が行う」と手書きされた文字があった。それは、現在の名義人が関与していた証拠でもあった。
筆跡鑑定の専門家にも確認し、偽造の可能性はほぼゼロ。これが決定的証拠となり、登記の回復と修正が認められた。依頼人は涙ぐみながら、何度も頭を下げてきた。
僕はただ、「こちらも勉強になりました」とだけ答えた。嘘じゃない。勉強にはなった。疲れたけど。
サトウさんの無言の賛辞
「今回はまあまあでしたね」
事務所に戻ると、サトウさんがいつものようにPCをカタカタと打ちながら呟いた。「今回はまあまあでしたね」。珍しく評価された気がして、ちょっとだけ照れてしまった。
いや、待て。「まあまあ」ってなんだ。あれだけ頑張ったのに。いや、むしろ「まあまあ」で済んでるあたり、僕が成長したってことなのか?
そんなことを考えていると、彼女が缶コーヒーを机の上に置いた。微糖じゃなくて、なぜか今日は加糖だった。それだけで、少しだけ報われた気がした。