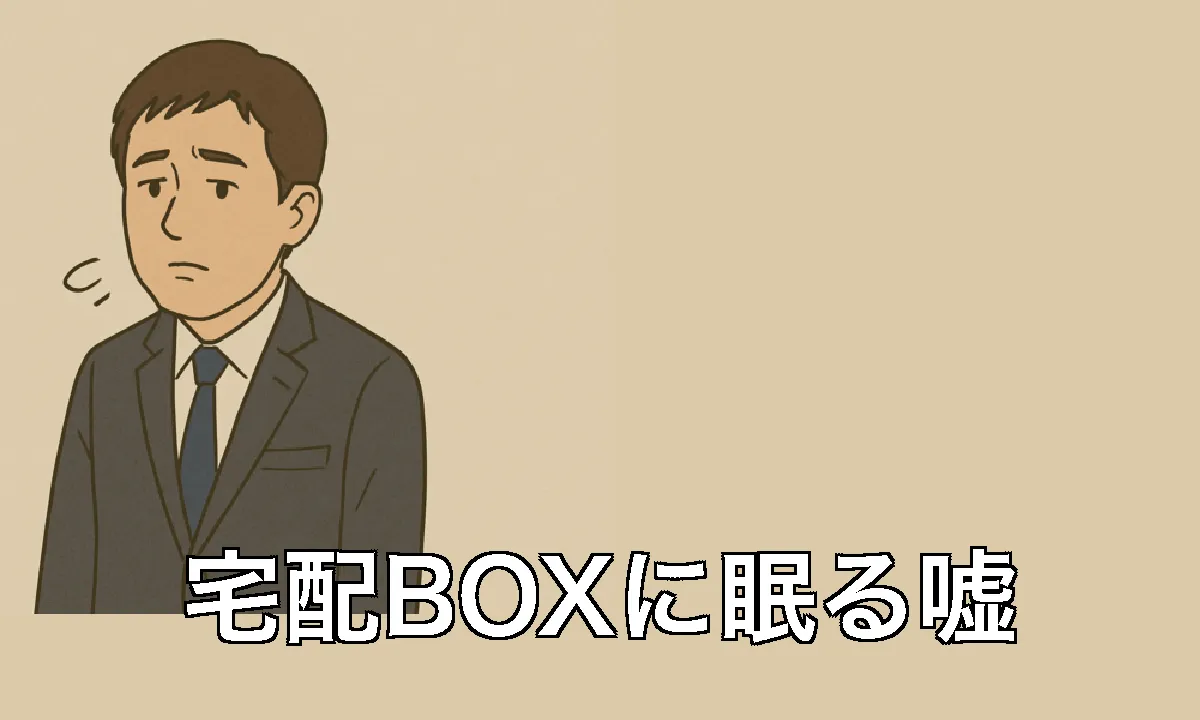朝のコーヒーと不在票
朝、湯気の立つインスタントコーヒーをすすりながら、不機嫌な気分で机に向かった。机の上には昨日の郵便物、そして赤いスタンプの押された不在票がひときわ目立っていた。
「また宅配か。最近やけに届くな」
そう独り言を呟いたが、心当たりはなかった。司法書士業というのは、時に謎の荷物が届く仕事でもある。だが今回のは、ただの誤配にしては様子がおかしかった。
いつも通りのはずだった
不在票に記された配達員の印字が滲んで読めず、差出人も曖昧だった。だが、依頼人からの電話一本が、その日常を一気に変えた。
「先生、あの荷物、宅配BOXからなくなってるんです」
聞けば依頼人は、離婚調停中の妻宛に重要な資料を送り返したという。それを「自分の手で取り戻したい」と言ってきたのだ。どうにもきな臭い。
依頼人の異常な要望
「取り戻したいって、それもう届けた後でしょう?」私は念を押した。だが依頼人は「中身を確認されたら困る」とだけ言って電話を切った。
書類なら再発行できる。そう考えるのが普通だ。それでも彼は焦っていた。何か、隠したい事情がある。
私の中の探偵ごっこ魂が静かに目を覚ました。
荷物を取り戻したい理由
私は昔から『名探偵コナン』を観て育った世代だ。何か怪しいと感じたときには、「これは事件だ」と決めつける悪い癖がある。
依頼人が取り戻したい荷物、それはきっと単なる紙切れじゃない。私は事務所の事務員、サトウさんに事情を話した。
「調べましょう。管理組合に聞けば開錠履歴が取れますよ」サトウさんは相変わらずクールだった。
宅配BOXの鍵がない
管理人室で出てきたのは、開錠履歴のコピーだった。だが不思議なことに、依頼人が言う時間には開錠されていなかったのだ。
それどころか、その日には何の操作履歴もなかった。「あり得ません」とサトウさん。
「それってつまり、誰かが物理的に鍵で開けたってこと?」私は思わず口にした。
開錠履歴と管理組合
管理人は曖昧な表情を浮かべながら、「予備の鍵は組合の理事が持っている」と答えた。
「理事って、確か…」私は思い出した。依頼人の元妻、つまり荷物の送り先が現役の理事だったのだ。
やれやれ、、、また厄介な話になってきた。
サトウさんの鋭い一言
事務所に戻ると、サトウさんが言った。「あの女性、最初から開けるつもりだったんじゃないですか?」
「あの女性」とは、依頼人の元妻のことだ。つまり彼女は、予備の鍵を使って荷物を抜き取ったというのか?
「証拠がないと何とも言えないけど、、、犯人っぽいな」私は呟いた。
防犯カメラより役に立つ観察眼
「監視カメラには映ってません」と管理人に言われたが、サトウさんは「それでも足元を見れば分かります」と即答した。
「足元?」
「ヒールの跡。宅配BOX前にありましたよ、同じ靴跡が2回」
消えた宅配業者の影
念のため、宅配業者にも確認を取った。だが「その日、対象住所に配達はしていない」という回答だった。
不在票は、依頼人が自作した可能性があった。
つまり、荷物の行方より先に、配達そのものが虚偽だった可能性が出てきたのだ。
登録されていない荷物番号
追跡番号も存在しなかった。完全にでっち上げだ。私は一気に、依頼人に不信感を抱いた。
なぜ彼はそんなことをしてまで「荷物を取り戻したい」と言ったのか。
答えは簡単だった。「本当は送ってなどいなかった」のだ。
犯人は依頼人の身近にいた
彼は荷物を「送ったふり」をして、相手が自分の思い通りに動くかを試していた。
離婚調停中、相手の行動を監視し、心理的に揺さぶるための、言わば小細工だった。
だがその行動が、すでに刑法のラインを越えていた。
鍵を知っていた者の特権
「宅配BOXの暗証を知っていたのは元妻だった」その前提に私たちは囚われていた。
だが本当に鍵を使ったのは、依頼人自身かもしれなかった。
彼が、管理人室の書類に忍ばせていた紙片を見て、サトウさんが一言、「これ、鍵の番号じゃないですか?」と指摘した。
荷物の中身が語る真実
そして、ついに「本物の荷物」が見つかった。公園のゴミ箱に、中身を抜かれた空箱が捨てられていた。
その箱に貼られていたラベルには、手書きで「私のこと、忘れないで」と書かれていた。
サザエさんの最終回に出てきそうな、哀しい執着の形だった。
それは単なる配送品ではなかった
荷物の中には、二人で写った古いプリクラと、指輪が入っていたという。
依頼人は「処分できなかったから、彼女に送り返したかった」と話した。
だがそれは、法的には立派なストーカー行為だった。
やれやれまたトラブルか
警察に報告することになり、私は報告書の山にため息をついた。
「やれやれ、、、結局、宅配より重たいのは人の感情ってやつか」
サトウさんは無言で書類を差し出し、私の背中を軽く叩いた。
司法書士の出番が来た
荷物の内容や送り主の動機、それに関わる法的問題まで、今回も結局すべて私の担当となった。
元野球部の根性は、こういう時にしか役に立たない。
「この事務所、いつか爆発するな、、、」私は冗談めかして呟いたが、サトウさんは笑わなかった。