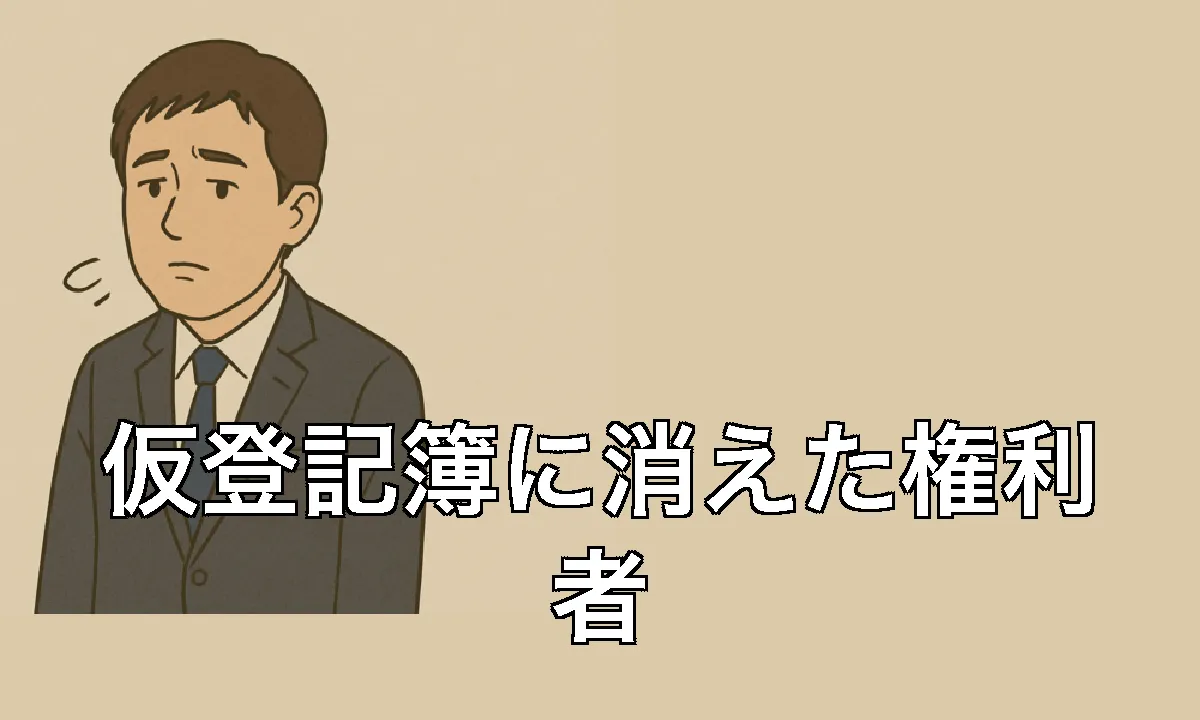依頼人の来訪と奇妙な一言
午前九時ちょうど。古ぼけたブリーフケースを小脇に抱えた依頼人が事務所にやってきた。髪はきっちり七三分け、白い手袋までしている姿はどこか浮世離れしていた。
「この家、登記簿上では父名義のはずなんですが、見てください、消えてるんです」そう言って差し出されたのは、一枚の登記事項証明書だった。
確かに、甲区欄の所有権移転の記録が不自然に空白になっている。これは見過ごせない。
見慣れぬ登記簿のコピー
コピーの質は粗かったが、確かに「所有権移転」の記載が途中で途切れていた。普通なら旧所有者から相続か売買か、何かしらの理由で移転しているはずだが、そこに記録がない。
「これは、、、登記ミスか、それとも故意か、、、」私はつぶやいた。サトウさんはすぐに申請年月日を指差す。
「この日付、平成ではなく昭和ですよ。今の登記簿の様式じゃありません」
消えた所有権の謎
古い帳簿の写しを法務局から取り寄せると、そこには確かにあった。父親名義の登記が。だが、ある時期を境に、登記簿が別の番号へと差し替えられていた。
「合筆です」サトウさんが淡々と言う。「隣地と一緒にされたんです。たぶん、何か隠すために」
なるほど、それならば権利の履歴が途切れていてもおかしくはない。問題は、誰が、なぜそんなことを。
元所有者の影
合筆された隣地の元の持ち主を調べると、地元で悪名高い不動産屋の名前が出てきた。十年前に突然倒産した「マルヨシ不動産」だ。
彼らは、昭和のバブル期に強引な買収を行い、登記に関しても怪しい動きをしていたという噂がある。
「たしかサザエさんの家の隣にも、急にコインパーキングができた話がありましたよね」サトウさんが言う。なるほど、地上げ屋の影が見えてきた。
昭和の売買契約書が語るもの
古い売買契約書を探し当てた。昭和58年の日付で、確かに依頼人の父親がその土地を買ったことが記されている。
しかし、所有権移転の登記がされていない。いや、正確にはされたが、別の地番に吸収されて消えた。つまり、実態と登記が一致していないのだ。
ここでようやく、土地の現所有者が誰なのか、本当の意味で分からなくなる。
公図の境界線が動いた日
さらに調査を進めると、公図に記されている境界線が、ある年を境にわずかに動いていることが分かった。
「測量ミス?」私は言ったが、サトウさんは首を横に振った。「意図的です。たぶん、建物がはみ出したことに気づいたから」
そしてその調整のタイミングが、登記の合筆と一致していた。誰かが仕組んだ可能性が高い。
聞き込みと過去の噂
現地に足を運び、周辺住民に話を聞いた。古くから住む近所の老人が、ぽつりと漏らした。
「あの土地はねえ、昔、夜逃げした人がいてね。不動産屋が勝手に整地したんだよ」
どうやら、正当な手続きがされずに事実上の支配だけが続いた時期があったらしい。
地元の不動産屋が漏らした一言
地元の別の不動産屋に話を聞くと、「あそこ?ああ、あれは登記めちゃくちゃだよ。触れちゃいけないやつ」
どうやら業界内では有名な“登記の沼”だったらしい。やれやれ、、、まるで名探偵コナンの灰原が出てきそうな話だ。
つまり、過去の不正が今も尾を引いているということだ。
地役権に絡む古い話
さらなる調査で、実はその土地には昔からの地役権、つまり通行権が設定されていたことが分かった。
「でも、これは公道じゃなくて、私道ですね」とサトウさんが指摘する。これが合筆された理由の一端だった。
不都合な通行権を抹消するために、地番を統合して権利関係をぼかしたのだろう。
サトウさんの冷静な推理
事務所に戻り、これまでの資料を机に広げて検討する。サトウさんはコーヒーを飲みながら一言。
「これ、最初に登記した司法書士がグルじゃないですか?」
その可能性に私も気づいていた。だが、証拠がない。
ひとつだけズレている情報
ふと、申請書の写しに目を通すと、一つだけ違和感があった。委任状の印影が、登録されているものと違う。
「これ、、、偽造か?」思わず口にした。つまり、登記自体が虚偽だった可能性がある。
「でも、それを追うには、、、覚悟がいりますよ」サトウさんがぼそりと言った。
申請代理人欄にある名前
そこに記された司法書士の名前を見て、私は思わず身を乗り出した。「こいつ、、、研修で一緒だった奴だ」
すでに廃業しているが、当時はかなりの“やり手”として名を馳せていた。
裏技も多く、時には一線を越えることもあると噂されていた。今こそ、その真相を暴く時だ。
過去の仮登記が浮かび上がる
さらに奥深く調べていくと、昭和の終わりに仮登記がされていた記録が出てきた。それは、失効していると思われていたが、、、
「効力が残ってる、、、?」
仮登記の原因たる債権が、実は時効消滅していなかった。それが消えた所有権の裏の真実だった。
登記簿から読み取る裏の意図
仮登記は消えても、実態は残る。そのことを利用して、あえて正式な登記をせず、闇の中に権利を隠したのだ。
しかも、それをやったのが司法書士というのだから、言葉が出ない。
「こりゃ、昔の探偵漫画みたいなトリックだな、、、」思わず苦笑いする。
合筆登記と単独申請の罠
この合筆登記、単独申請で行われていた。つまり、相手方の同意を得ていない。
その上、錯誤を装って訂正が入っていたが、それが逆に決定的な証拠となった。
「司法書士を名乗る者として、許されない行為だな、、、」
真犯人との対峙
すでに司法書士を廃業していたその男は、近隣の町で細々と古物商をしていた。
彼のもとを訪ねると、開き直るようにこう言った。「時効だよ。もう誰も損してない」
「いや、依頼人は今も困ってる。俺たち司法書士は、過去の記録を正す義務があるんだ」
司法書士の矜持と説得
私の言葉に、男はしばらく黙った。やがて、机の引き出しから一通の書類を差し出した。
そこには、かつての仮登記の正本と、合筆前の地番記録の写しがあった。
「あんたには負けたよ、、、やっぱり、俺たちはただの書類屋じゃなかったな」
やれやれ、、、最後は俺か
その日の帰り道、車を運転しながら私はつぶやいた。「やれやれ、、、最後は俺が動く羽目になるんだな」
助手席のサトウさんは一切笑わない。ただ黙って、書類を抱えていた。
でも、私は少しだけ誇らしかった。これが司法書士の仕事だと思えたからだ。
事件の決着とその余韻
数週間後、登記の是正が完了した。依頼人の父名義は、正式に登記簿上に復活した。
土地の境界線も修正され、通行権も回復された。
長年の霧が晴れたような、そんな静かな達成感があった。
正しい登記へ導くために
登記は、ただの手続きではない。それは人の権利と歴史を記録する、社会の基盤だ。
誰かの都合でそれを歪めることは、決して許されない。
私たちの仕事は、そういう歪みを少しずつ、正していくことだ。
静かに戻る事務所の日常
「今日はまた、誰か来ますかね?」と私が言うと、サトウさんが時計を見て答えた。
「あと20分後に、相続登記の相談が一件入ってます」
私は肩をすくめてコーヒーをすすった。「やれやれ、、、休む暇もないか」