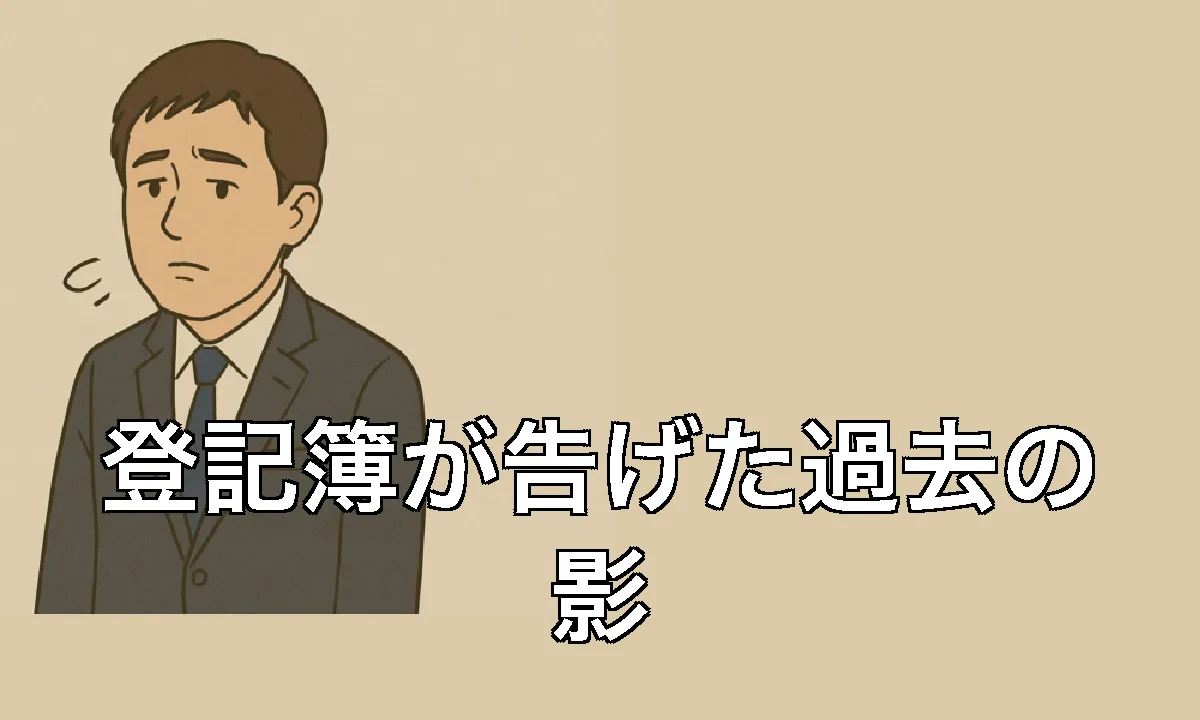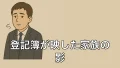登記の依頼と違和感
朝一番、薄曇りの空を仰ぎながら事務所のドアを開けると、すでに来客が椅子に座っていた。 年の頃は六十代、背筋がピンと伸びた女性。机の上に封筒をそっと置き、「相続登記をお願いしたいんです」と切り出した。 書類を手に取った瞬間、妙な違和感が背筋を走った。登記簿謄本と戸籍のコピー、それに一枚の遺言書。全体的に整ってはいるが、何かが引っかかる。
古い家屋の相続登記
対象となるのは、昭和初期に建てられたという木造の古民家。山間部の静かな土地にぽつんとある家らしい。 「父が生前に一人で暮らしておりました」と依頼人。だが、その住所はどこかで見た覚えがある。 「サトウさん、この番地、前にも見たよな?」と声をかけると、塩対応の事務員が面倒くさそうに眉をしかめた。
サトウさんの冷静な指摘
「……たぶん、先月の贈与登記の物件と同じですね。だけど名義人が違います」 サトウさんの言葉に背筋がぞっとする。贈与で名義変更された家が、今度は相続で登記依頼されている? 登記簿上では現在の所有者は既に変更済み。遺言書の内容が事実なら、話が食い違っている。
遺言書に残された矛盾
手元の遺言書は自筆証書で、日付は二年前。被相続人は「この家を娘のタエに相続させる」と書いている。 しかし登記簿では、すでにその一年前に第三者に名義が移っている。 これでは、家はすでに被相続人の所有ではなかったはずだ。遺言の効力自体が疑わしい。
記載された住所の食い違い
しかも、遺言書に記された番地が微妙に異なっていた。町名までは同じだが、最後の数字がずれている。 登記簿で照会した結果、隣接地だった。つまり、遺言に記された物件は既に取り壊されていた空き地のほう。 「まさか、そんな、、、」と依頼人がうろたえる。
日付に潜む違和感
さらに気になるのは、遺言の日付。被相続人が亡くなる一週間前の記載だったが、その頃、入院していたという記録が出てきた。 筆跡もかすれており、病床で書いたにしては整いすぎている。 「やれやれ、、、また面倒な話になってきたな」と、思わず漏らした。
被相続人の過去を探る
地元の役場で戸籍や課税情報を集めるうち、被相続人が十年間行方不明扱いだった時期があることが判明した。 その間、どこで何をしていたかの記録はない。突然戻ってきて、誰にも告げずにその家に住んでいたらしい。 空白の十年、その謎は濃い霧のようだった。
隣人の証言と空白の十年
隣の家に住む老夫婦から話を聞いた。「戻ってきた時、名前が違ってたよ」と夫がぽつりと言った。 どうやら別の姓を名乗っていた時期があったようだ。もしかすると、過去に何かを隠していたのかもしれない。 その姓で検索すると、東京で死亡届が出された同姓同名の人物が見つかる。まさか、二重生活?
登記簿から浮かぶ旧姓の名
法務局でさらに古い登記簿を取り寄せると、かつてその家は旧姓の名義で所有されていた。 つまり、被相続人は過去に一度手放し、偽名で買い戻していた可能性が出てきた。 その理由は、ある事件との関係を隠すためだった――。
手がかりは一枚の古地図
蔵の中から出てきた一枚の古地図。そこには昭和初期の土地の区画が手書きで記されていた。 今とは地番が違っており、空き地だった部分がかつて家の一部だったことがわかる。 つまり、遺言に記された地番は、昔の家の本来の位置だった。
明治期の地番変更と真実
調査の結果、地番変更が明治末期と戦後直後の二度にわたって行われていたことがわかった。 その影響で、現在の登記情報では正確な物件の範囲が分かりづらくなっていた。 依頼人の持つ地図と現在の情報が食い違っていた理由がここにあった。
地図と現在の土地境界のずれ
境界線の誤認により、登記された建物は隣地に一部食い込んでいた。これが原因で過去の相続時にトラブルが起き、名義を偽装した可能性がある。 つまり、今回の相続登記はその偽装を隠すための工作だったのだ。 依頼人がそれを知っていたかどうかは、わからない。
登記の名義人は誰か
調査を進めるうち、ある司法書士の名前が過去の名義変更に関わっていたことが浮かび上がった。 その司法書士は既に廃業しており、所在も不明。記録だけが残っていた。 その名義変更は、現在では考えられないほどずさんな手続きだった。
真の所有者の影
過去の贈与登記の際、売主として記録された人物が、戸籍上存在しないことが判明した。 つまり、幽霊名義での登記だったということ。しかもそれを行ったのが、失踪した司法書士だった。 書類上は問題なく見えても、その裏にある虚構は深い。
偽装相続の可能性
この一連の相続は、所有権の流れを偽装するためのカバーだったと考えられる。 サトウさんがぽつりと呟いた。「詐欺じゃなくても、立派な無効登記ですね」 結局、登記は差し戻しとなり、真の相続人の再調査が始まった。
解決編 登記簿が語る真実
後日、依頼人が再訪し、「全部知ってました」と告白した。 彼女はかつての被相続人の内縁の妻の娘であり、正式な相続権を持たないことも承知していた。 だが「父の最後の願いを形にしたかった」と、涙ながらに語った。
本当の遺産継承者
法的には無効となったが、最終的に土地は特別縁故者の手続きを経て、依頼人に帰属する可能性が高くなった。 法と感情、その間にある揺らぎを、登記簿が静かに教えてくれたような気がした。 「サザエさんの家族みたいに、うまくはいかないもんだな」と、独り言ちる。
明かされる動機と決着
その後、事務所に戻ると、サトウさんがいつものようにパソコンをカタカタと打っていた。 「次の案件、また相続です」――冷たい声に思わず肩が落ちる。 やれやれ、、、俺の平穏はいつ来るんだろうか。