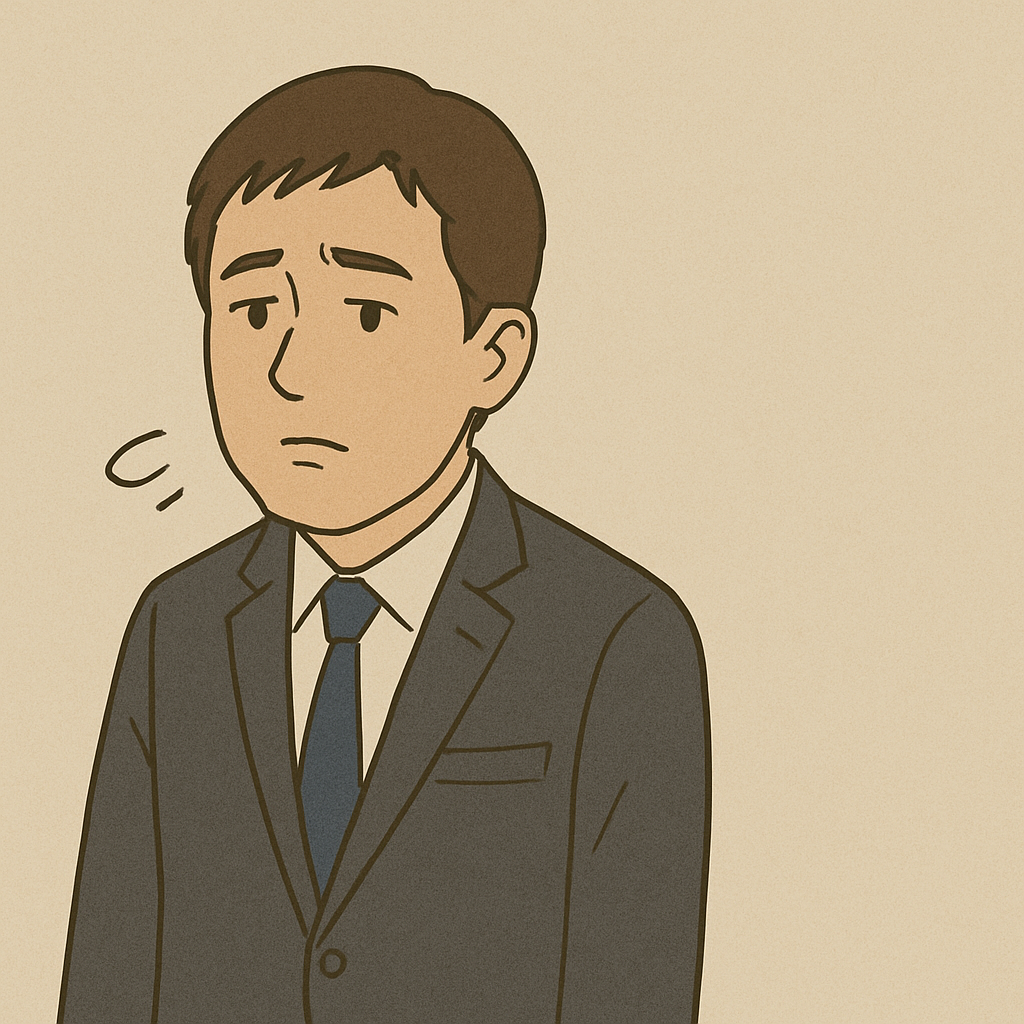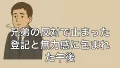気づけばまた、自分語りをしていた
自分の話ばかりしてしまう癖に気づいたのは、事務員さんの苦笑いを見たときでした。「先生、また同じ話してますよ」と柔らかく言われて、ハッとしたんです。あれ、俺、またかと。日々の業務の中で、ふとした時間に話題を振るつもりが、いつの間にか過去の武勇伝や仕事の愚痴に脱線している。それが一度や二度ではない。おそらく、聞いてほしいという気持ちがにじみ出てしまっているのでしょう。誰かと会話をしているつもりが、いつの間にか独り語りになっている。そんな自分に自己嫌悪を覚えつつも、やめられないのは、やはりどこかに「聞いてもらいたい自分」がいるからなのかもしれません。
なぜ話題がいつも“自分”に戻ってしまうのか
相手の話を聞いていたつもりでも、少し気を抜くと「あ、それ俺も経験あるよ」と自分の話にすり替えてしまう。この癖は、ある意味“自分を肯定したい欲求”の現れだと感じます。とくに士業という仕事柄、普段は「人のために動く」ことが当たり前。だからこそ、ふと力を抜いた瞬間、自分の存在価値を確認したくなるのかもしれません。承認欲求というと聞こえが悪いですが、「誰かに覚えていてほしい」「少しでもすごいと思ってほしい」…そんな子どもじみた感情が、40代になっても消えないのです。
事務員との会話で見えた「独りよがり感」
ある日、事務員さんとの昼食の会話中、思い切って聞いてみました。「俺の話、ちょっとくどい?」と。すると彼女は苦笑しながら、「いや、嫌ではないですけど…毎回“同じ話”されると、ちょっと予測しちゃいますね」と。その瞬間、内心ズーンと落ち込んだのは言うまでもありません。でも、正直な感想をくれたことがありがたくもありました。話すことに夢中になりすぎて、相手のリアクションや気持ちを置き去りにしていたことに気づかされたのです。「誰かと話す」のではなく「誰かに話してる」だけだった。独りよがりとは、まさにこのことでした。
会話のキャッチボールが成立しないとき
「聞いてなかったです」…この一言に、心が折れそうになったことがあります。自分が話した内容を、相手がまったく覚えていない。それってつまり、俺の話は“届いてなかった”ということなんですよね。あれだけ熱心に語ったつもりが、ただの独り言になっていた。このとき初めて、「会話って一方通行じゃダメなんだ」と身に染みました。相手がちゃんと受け取ってこそ、会話は成立する。キャッチボールになっていない時点で、それは“発信”ではなく“垂れ流し”なんだと痛感しました。
“話しすぎる”のは孤独の裏返しかもしれない
独身で一人暮らし、事務所でも一人。誰かと話す機会がそもそも少ない生活だからこそ、誰かと接するときに「ここぞとばかりに話してしまう」ことがあります。まるでダムが決壊するように、溜め込んだ言葉を一気に放出してしまう。でも、その相手が望んでいない時だったら…それはただの押しつけになってしまう。誰かと話したい気持ちと、誰かに聞いてほしい気持ちは違うんだと最近ようやく気づきました。孤独って、無自覚に人をわがままにするんですね。
“伝える力”と“黙る力”のバランス
士業という職業柄、説明する力や言葉を尽くす力は大切です。でも、それは「必要なとき」に限った話。何でもかんでも語ればいいというわけではないと、最近になってようやく思うようになりました。特に相談者の話に対して、自分の経験談で返すクセは危険です。相手が必要としているのは、アドバイスよりも共感であることが多いのに、自分は正論や過去の成功例ばかり並べていた気がします。伝えることと、黙って寄り添うこと。そのバランスこそが信頼を生むのだと、少しずつ理解し始めました。
相談者に必要なのは共感であって武勇伝ではない
過去のトラブル解決経験を語ると「頼りがいがある」と思ってもらえる気がしていました。でも、実際には「へえ、すごいですね」で終わってしまうことがほとんど。相談者は自分の不安を聞いてほしいだけで、自分の話に対する「過去の成功談」は求めていないことが多いと気づいたのです。「それ、わかりますよ」とひとこと添えるだけで、空気が変わる。相手の気持ちに沿った言葉を選ぶことが、どれだけ大切かをようやく理解しました。
「昔はね…」が口癖になっていないか
気づけば「昔はこうだった」「昔の俺ならこうしてた」なんて言葉ばかり口にしている。これ、かなり危険な口癖だと思っています。昔の自分を引き合いに出すことで、今の自分を守ろうとしているような気がしてならない。過去にしがみついて、現在の弱さを隠しているだけ。年齢を重ねると、自信の裏に弱さが隠れるものですが、だからといって“過去の栄光”で現在の評価を稼ごうとするのは、やはり見苦しい。耳が痛い話ですが、自戒を込めてここに書いておきます。
沈黙を恐れないことも、信頼の一部
沈黙って、つい怖くなりますよね。何か話さなきゃ、間が持たない、気まずい…。でも、本当に信頼関係がある相手とは、沈黙すら安心できる時間になるものです。司法書士として相談を受けているときも、焦って言葉を重ねず、少し沈黙してみる。相手が考える時間を待つ。その余白が、相手に安心感を与えることもあります。言葉は時に盾になりますが、使いすぎると刃にもなる。黙ることも、プロとしての技術なのかもしれません。
話すことで救われている自分もいる
こんなふうに、自分の話ばかりしてしまうことを悩みながらも、正直に言えば、それに救われている面もあります。誰かに話すことで、自分の中のモヤモヤが整理されていく。言葉にすることで、少しずつ自分の気持ちが見えてくる。だからこそ、話すことを完全に否定するのは違うと思っています。大切なのは、その話が“独りよがり”になっていないかどうか。聞いてくれる人がいるからこそ、話す意味がある。そのことを忘れないようにしたいと思います。
声に出すことで整理される気持ち
一人で考えていても、どうにもまとまらないことが、誰かに話すことでスッと見えてくる。そんな経験、ありませんか? 実は、声に出すことで脳が情報を再構築し始めるらしいんです。だから、自分の話ばかりするのも、「整理したい」「自分を確認したい」という無意識の欲求なのかもしれません。だからこそ、ただ黙って我慢するのではなく、誰に話すのか、どう話すのかを考えるだけでも、自分の話が“役立つもの”になる可能性があるのです。
だからこそ“話し相手”の大切さが身にしみる
自分の話をじっと聞いてくれる存在って、本当に貴重です。事務員さんしかり、昔の友人しかり。そういう人がいるだけで、気持ちが整う。逆に言えば、その人たちに甘えてしまわないよう、自分自身も「聞く側」に立つ意識が必要だなと思います。聞き手があってこその“話”。一人よがりにならず、感謝を忘れず、話すことを続けていけたら…。そんなふうに、少しだけ前向きに考えるようになった今日この頃です。
変わりたいと思った瞬間にできること
「俺、また自分の話してたな…」と気づいた瞬間が、変わるチャンス。誰だって、すぐに性格は変えられません。でも、小さなことから始めることはできる。最近は、意識的に「今日は相手の話を7割聞こう」と決めてから会話に臨むようになりました。意外とこれだけでも、ずいぶん印象が変わるものです。癖って、自覚するだけでも第一歩。変わろうとする姿勢は、きっと相手にも伝わるはず。そんな小さな一歩から、私は始めています。
「聞く練習」を始めてみる
会話は技術です。そして「聞く」ことは、鍛えられるスキルです。最近はラジオやポッドキャストを聞くとき、話の“間”や相づちの入れ方に注目するようにしています。上手な聞き手って、話を引き出すんですよね。司法書士としてだけでなく、一人の人間として、「この人に話したい」と思ってもらえるような聞き手になれたら、それはきっと仕事にも人生にも大きなプラスになると思っています。
話し上手は聞き上手から
話し上手って、実は「話すのがうまい人」ではなく、「聞き手に合わせて話せる人」のことだと最近感じています。聞き手が何を求めているのか、どう感じているのかを察して、話のペースや内容を変える。これはまさに、聞く力の応用。だからこそ、まずは相手の言葉をしっかり受け取る姿勢から始めようと思います。自分語りのクセを治すために、「聞く練習」は最良の特効薬かもしれません。
聞き役を演じる勇気と、照れくささ
正直、「聞き役に徹する」って最初は照れくさいし、どこか居心地が悪かったです。でも、それって“主役じゃないこと”に慣れていなかっただけなんですよね。誰かの話にじっと耳を傾けて「それ、どうだったんですか?」と深掘りする。そんな会話ができたとき、相手の顔がパッと明るくなるのを見て、「ああ、これでよかったんだ」と納得しました。聞き役って、思ってたよりずっと心地いい役割でした。
“自分の話ばかり”を活かす方向に転換
話したい気持ちが止められないなら、いっそ「話す場」を変えればいい。それに気づいてから、私はこうしてコラムを書いています。文章にすれば、誰かに迷惑をかけずに自分の話を整理できるし、共感してくれる人がいれば救いにもなる。語りたい気持ちは、悪いことじゃない。ただ、その“向け先”を間違えなければいいんだと思います。この歳になってやっと、それに気づきました。
コラム執筆というアウトプットの場
話すことと書くことは似ているようで違います。でも、どちらも「誰かに届けたい」という気持ちが根底にある。書くことで、相手の顔を想像しながら言葉を選ぶようになると、自然と“独りよがり”ではなくなるんです。このコラムが、同じように悩んでいる人の背中をそっと押せたら、それはきっと“自分語り”ではなく、“誰かのための語り”になる。そんなふうに信じて、今日も言葉を綴っています。
失敗談が誰かの役に立つ日もある
偉そうな成功談よりも、正直な失敗談のほうが、人の心に届くことがあります。「ああ、自分だけじゃないんだ」と感じてもらえることが、救いになるから。自分の話ばかりしてしまう自分に悩んでいたことも、こうして言葉にすれば、きっと誰かの“安心材料”になるはず。だから私は、これからも失敗を隠さず書き続けていこうと思います。それが、誰かとつながる唯一の方法かもしれないから。