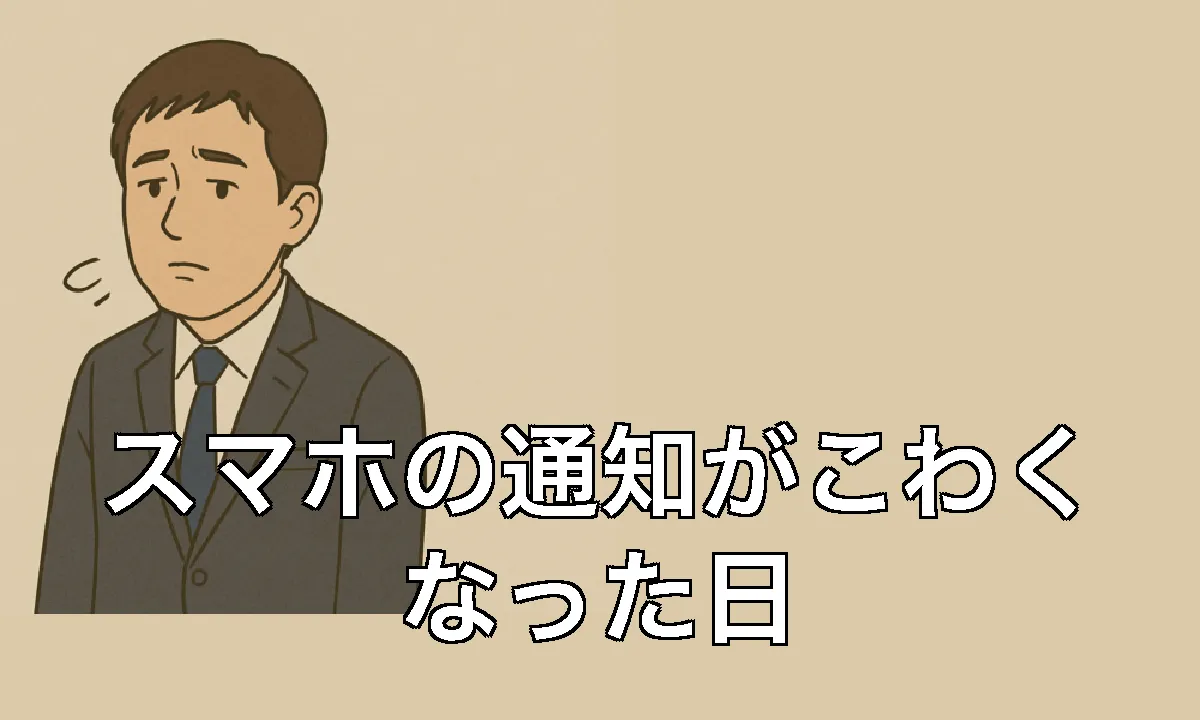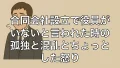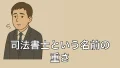スマホの通知が鳴るだけで肩がこるようになった
スマホの通知音、それだけで心がピクッと反応してしまう日がある。昔は便利だと思っていたその機能が、今では神経をすり減らす原因になっている。朝、コーヒーを淹れて机に座った瞬間にLINEが鳴る。業者からか、それとも依頼人か。内容を確認するまでのわずかな時間が、どうしようもなく息苦しい。気づかないふりをしたくても、なぜか見てしまう。そのループが、いつの間にか生活の一部になっているのだ。
昔はむしろ通知が来ないと不安だったのに
司法書士として独立したての頃は、スマホが鳴らないことが怖かった。依頼が来ない=収入がゼロ。そんな恐怖と隣り合わせだったから、1件の通知がまるで救命ロープのように思えたこともある。通知が鳴ればすぐに返す。それが信頼につながると信じていた。ところが、それを何年も続けていくと、「鳴ったら即対応」が当たり前になってしまった。自分の時間を自分で削っているなんて、当時は思いもしなかった。
即レスができてこそプロという思い込み
返信が早いと、相手は安心する。それは確かだ。だけど、その安心を提供するために、こちらの精神が削られているという事実には、なかなか気づけない。「あの先生、レス早くて助かるよ」と言われるたびに、自分の首を絞めてる気がしていた。通知が鳴った瞬間、「今は手を止めてでも返さないと」と思ってしまう。そして気づくと夜中でも画面を見ていた。そんな生活を、正しいと思い込んでいたのだ。
それでも通知が来るたびに集中が切れていく
登記の調査中や、書類の確認をしているときでも、ピコンと音が鳴るとすべてがストップする。しかも大した内容じゃないことも多い。取引先からの「よろしくお願いします」の一文、確認済みの資料に「OK」のスタンプ。それだけで集中が切れて、もう一度同じ資料を読み直す羽目になる。積み重ねれば、それは無視できない時間の浪費になる。時間も、集中力も、通知によって削られている現実がある。
大至急お願いします系の通知に慣れすぎた結果
「急ぎでお願いします」という文言に、最初は緊張していた。でも今では、どこか麻痺してしまったような感覚がある。大抵は、こちらの手を止めてでも対応すべき内容ではない。けれど“急ぎ”と書かれているだけで、反射的に優先してしまう。そうして本当に重要な作業の手が止まる。効率を求めるどころか、通知の処理に追われている日々。自分がスマホに振り回されている実感が、日に日に増している。
本当に至急のものなんてそうそうないのに
冷静に考えれば、「至急でお願いします」と言われる内容の多くは、実際には明日でも間に合う案件だ。それでも、相手が「至急」と言ってきたら、こっちは「至急」でやるしかない。これが続くと、徐々に“緊急”の感覚が壊れてくる。何もかもが火事のように感じてしまい、どんな案件にも疲弊してしまう。結果的に、本当に急ぎのときに対応する体力が残っていないという、なんとも皮肉な状態になる。
スマホが鳴るたびに仕事モードを強制される
たとえ家にいても、スマホが鳴ると瞬時に仕事モードに切り替わってしまう。気が抜けない。お風呂に入っていても、通知が鳴れば髪の毛が濡れたままでも確認してしまう。もはや条件反射だ。休日でも「念のためスマホを確認しておこう」と思ってしまう。そうやって、心が休まる瞬間がなくなっていく。「スマホが鳴らないと落ち着かない」から、「鳴るのが怖い」に変わっていったのは、たぶんこの頃だ。
休日すら心が落ち着かなくなる構造
日曜の朝、スマホを横に置いて散歩に出た。なのに、途中で何度もポケットを確認してしまった。「何か来てるかも」「返さないとまずいかも」。完全に“通知依存”の状態だった。休日なのに、心は常に構えていて休めない。通知が来る=責任が発生する、という感覚が染みついていた。気づけば、休日が休養にならない。そうやって知らぬ間に、疲れがたまっていくのだ。体よりも、心が先に悲鳴を上げていた。
通知を気にしてるのは自分だけじゃないはず
ふと事務員さんの様子を見ると、彼女もまたスマホを気にしながら仕事をしていた。業務とは関係ない通知でも、何かに追われるように画面を確認する姿は、どこか疲れた表情をしていた。自分だけじゃなかったんだなと思った瞬間、少しだけ救われた気がした。でも同時に、「これはもう職場全体の空気の問題かもしれない」と感じた。無言のプレッシャーが、みんなの神経を静かに削っていたのだ。
事務員さんも無言でスマホを気にしていた
ある日、「今日はLINE多いですね」と事務員さんがつぶやいた。僕はその一言でハッとした。僕自身が通知に振り回されていて、それを無意識に周囲に伝染させていたのだ。彼女もまた、必要以上に即レスを意識してしまっていた。僕のやり方が、職場の“空気”を作ってしまっていた。反省と同時に、少し胸が痛くなった。無理に頑張らせてしまっていたのかもしれない。これはもう、自分から変わらなければならない。
ちょっと鳴っただけでが積もるストレス
通知の音は一瞬でも、心に与える影響は大きい。「ちょっと鳴っただけ」と思われがちだけど、積もり積もると、それは立派なストレスになる。特に真剣な作業をしているときには、集中力を切らす原因になるし、心理的な負担も大きい。通知を受け取る側がどんな状態かなんて、発信側には見えない。そのギャップが、さらに疲れを生む。音の小さな攻撃に、じわじわとやられていく日々が、確実に存在している。
全員が疲れてるのに気づかないフリの職場
僕たちはたぶん、全員が“疲れている”ことをわかっている。でも、その空気を壊すのが怖くて、誰も声をあげない。効率よく、ミスなく、早く。そんな理想ばかりを追いかけて、心の声を無視している職場。「通知は仕方ないもの」と思っていたけれど、それに潰されそうになっている人がすぐ隣にいた。僕たちはもっと、不完全で不器用でもいいのかもしれない。まずは自分が、その空気を変える勇気を持つべきだと思った。
スマホと適切な距離をとるための小さな決意
ある日、思い切って通知の音を全部オフにした。最初は不安で仕方なかったが、数日たつと「鳴らない」という状態に慣れてきた。そして、不思議と集中できる時間が増えた。対応が遅れても、大きな問題になることは少なかった。むしろ、しっかり考えてから返信できるぶん、内容の精度は上がったように感じる。スマホは便利だけど、すべてを受け入れる必要はない。そう自分に言い聞かせている。