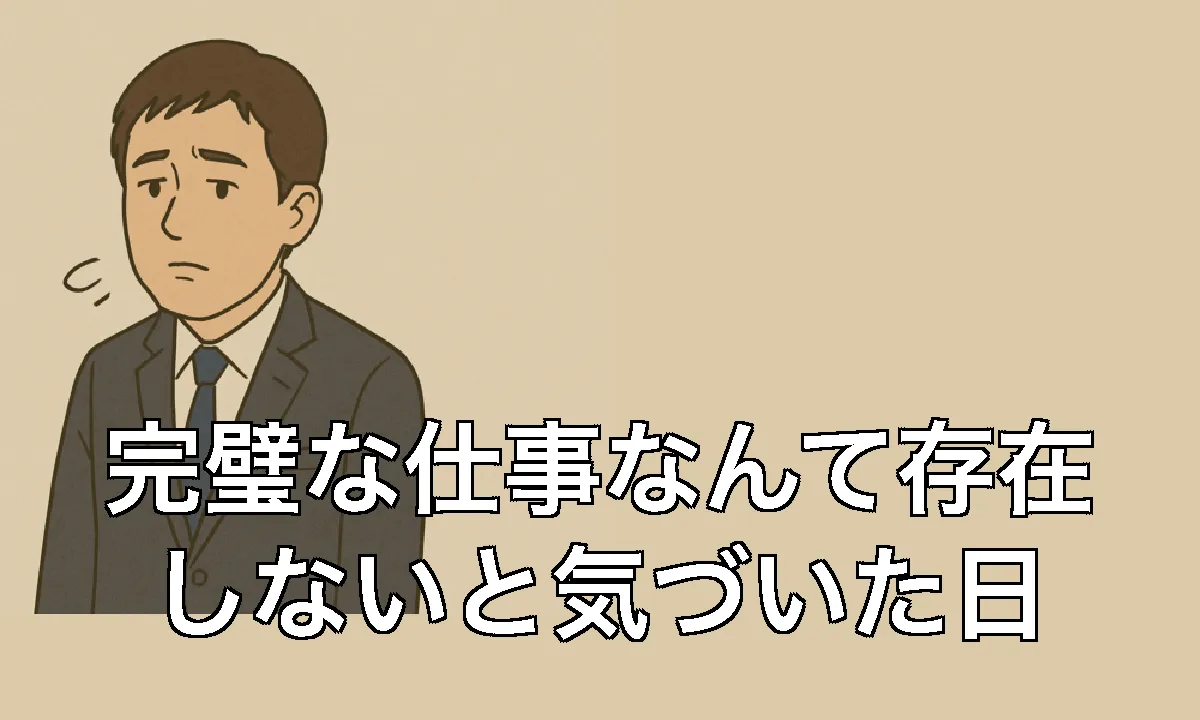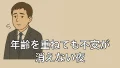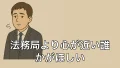完璧を求めすぎて疲弊した自分がいる
司法書士という職業柄、「ミスは許されない」という空気の中で長年仕事をしてきました。でも最近ふと、「完璧な仕事ってそもそも存在するのか?」と自問するようになったんです。登記に漏れがあれば信用問題、書類の記載ミスがあればお客様の信頼は地に落ちる。それが怖くて、無意識に自分を追い詰める日々。疲れているのに帰れず、休日にも確認作業。そんな生活を続けていると、いつしか「仕事を好き」という感情すら失われていきます。求められる精度の高さが、心を消耗させていくのです。
「ミスしないこと」が前提になっている現場
いつからでしょうか、「ミスをしてはいけない」ではなく、「ミスをして当然だろ」という空気すらなく、「ミスは絶対にするな」という暗黙のルールが業界に根づいてしまっているのは。これがまた厄介で、失敗がゼロで当たり前、という空気があると、たとえ細かな修正程度のことでも大ごとになる。しかも、誰かがそのプレッシャーの中で我慢していると、次の人もそれを引き継ぐ形になるんですよね。私も例にもれず、「ここでしくじったら終わり」という場面で呼吸が浅くなったことが何度もあります。
少しの誤字が信用問題になる世界
登記簿の氏名に一文字でも間違いがあると、訂正手続きだけでなく、お客様との信頼関係にもヒビが入ります。以前、法定相続情報一覧図の「子」の漢字を旧字体で書いてしまったことがありました。結果、提出先で差し戻され、依頼人から「大丈夫なんですか?」と心配の声。それがこたえました。たかが一文字、されど一文字。これが司法書士という仕事の怖さでもあり、辛さでもあります。機械のような正確さを求められる世界で、ヒューマンエラーが許されないのです。
訂正印一つにも重たい空気が流れる
あるとき、不動産の登記原因証明情報の一部に誤植が見つかり、慌てて訂正印を押して提出し直したことがありました。たったそれだけのことで、依頼人が「本当に大丈夫ですか?」と不安げに見てくる。こっちは冷や汗をかきながら平静を装うしかない。でも内心では「こんな小さなことが信頼を削るのか」と心がズーンと重くなるんです。訂正印ひとつが、ただの印ではなく、プレッシャーの象徴のように感じるときがあります。
ミスが怖くて動けなくなる瞬間
時には、何かを始める前から「また何か見落としているかも」と不安が押し寄せ、手が止まってしまうことがあります。人は「失敗を恐れるあまり、動けなくなる」ことがあると言いますが、司法書士の仕事はまさにそれ。頭では「確認すればいい」と分かっていても、不安が先に立ってしまう。いちいちファイルを開いて、過去のやりとりを振り返って、結局1時間かけて動けないまま終わる午後。そんなことが、私の職場でも日常茶飯事です。
朝から「今日はやらかしませんように」と念じる
朝一番、コーヒーを飲みながら手帳を開くと、心の中で「今日は何も起きませんように…」と唱える自分がいます。本来なら「いい一日になりますように」って願うのが普通なんでしょうが、私の場合はまず“やらかさないこと”が目標になる。しかも、それが叶ったとしても「ほっとした」という感情しか残らないんですよ。達成感ではなく、安堵。これじゃ仕事が楽しいわけがないんですよね。でも、ミス一つで振り出しに戻る可能性があるから、どうしても怖さが先に立ってしまうんです。
電話対応一つで胃が痛くなる理由
電話が鳴るたびに、一瞬ビクッとするんです。特に、登記が進行中の案件の関係者からの番号だったりすると、「何か問題が起きたのか?」と勝手に悪い想像をしてしまう。事務員が出てくれても、「折り返してくれとのことです」と言われた瞬間、胃がギュッとなる。そんな経験、ありませんか?電話って、ミスの通知装置のように感じてしまうことがあるんです。そんなことないと頭ではわかっていても、体は正直です。
確認のための確認に振り回される日々
「確認したはずだけど、もう一度確認しよう」──これを何度も繰り返していると、自分でも何が正しいのか分からなくなってくるときがあります。事務員にも「もう確認しましたよ」と言われつつ、それでも自分でやらないと気が済まない。結果、二重チェック三重チェックで、業務効率はガタ落ち。でも、それをやめてミスしたらと思うと、やっぱり手が止められない。確認のための確認に、私はいったいどれだけの時間を費やしているのだろうか、とふと思うことがあります。
事務員との連携ミスで自己嫌悪
一人で抱えるには限界がある。だからこそ事務員に任せる。でも、人に任せればミスのリスクも生まれる。そのミスが起きたとき、「任せた自分が悪いのか」「伝え方が悪かったのか」と、頭の中が自己嫌悪でぐるぐるする。そんな日もあります。もちろん事務員を責めたくはない。でも、責めないことで自分が責められる構図もつらい。中小事務所ならではの悩みかもしれません。
言ったつもり、伝えたつもりの落とし穴
「これお願いね」と口頭で伝えたつもりでも、相手には届いてなかった。あるいは、伝わった内容が違っていた。そんな行き違いが、ミスにつながる。たとえば「今週中に提出で」と言ったつもりが、「金曜までに」と受け取られ、木曜提出が間に合わなくなるようなズレ。口頭の怖さを痛感します。文字にしても曖昧だと意味がないし、かといって毎回マニュアル化も現実的じゃない。だからこそ、人との信頼関係と丁寧な伝達が必要なんですが、それが難しいんですよね。
怒るほどのことでもないのに、空気が悪くなる
小さな行き違いでも、積み重なると空気が重くなる。「こんなことで怒っても仕方ない」と思って飲み込んだ言葉が、自分の中で澱のように溜まっていくのを感じます。一方で、事務員側も「またやっちゃった」と落ち込んでいて、お互いに気まずい空気が漂う。怒りたいわけでもないし、責めたいわけでもない。でも、事務所内がピリピリしてしまう。誰も悪くないのに、誰も笑っていない。この空気が一番つらいんです。
「もう一人いれば」の妄想と現実の経費
正直、「もう一人スタッフがいれば…」と何度思ったかわかりません。でも、田舎の小さな司法書士事務所にはそんな余裕はありません。求人を出しても来ないし、人件費だってギリギリ。だから今いる事務員に頼るしかない。そう思うと、イライラした自分が申し訳なくなる。理想と現実のギャップに毎日揺さぶられながら、なんとかやりくりしている日々です。妄想では回る事務所も、現実はなかなか思い通りにはいきません。