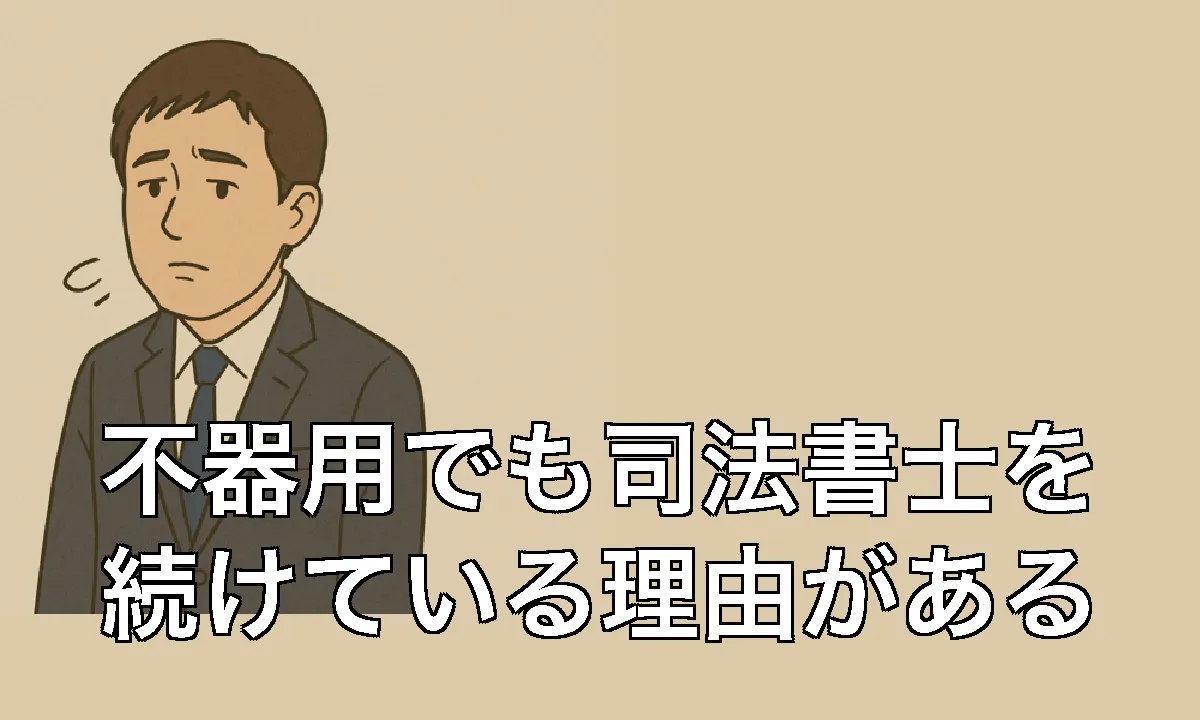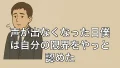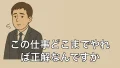自分は不器用だと気づいたのはいつからか
「俺って、ほんと不器用だな…」と自覚したのは、思い返せばかなり早い段階だったように思います。小学生の頃から図工や家庭科は苦手で、どうにか提出物を出しても先生に「丁寧にやりましょう」と赤字で書かれるのが常。クラスの中でも要領の良い子たちは、ちゃちゃっと終わらせては余裕そうにしていたのに、自分は何倍も時間をかけても結局「雑」と言われる仕上がり。器用さって才能なんだなと、早くから悟ってしまっていた気がします。
小学校の図工で毎回C評価だった頃の話
特に印象に残っているのは、小学4年生の図工の授業で紙粘土の動物を作った時のことです。周りの子たちは可愛らしい犬や猫を作る中、自分の粘土は何度やっても耳が落ちたり、目が変な位置についたりして、最終的に「これは何?」と先生に聞かれる始末。自分では頑張っているつもりでも、他人から見ると出来が悪い。「頑張ったけどこれかよ…」と落ち込んだあの感覚は、今でも記憶にこびりついています。
野球部でもバントしか任されなかった青春
中学から高校まで野球部に所属していましたが、そこでも「不器用さ」は露呈していました。バッティングがとにかく苦手で、豪快なスイングよりも、確実に当てる方がマシだと判断されたのでしょう。試合ではいつもバントのサイン。守備でも送球が安定しないため、レギュラーになるには程遠く、ベンチの端っこが定位置でした。それでも部を辞めなかったのは、仲間と過ごす時間が好きだったからであり、「下手でも居場所がある」という野球の懐の深さに救われていたのだと思います。
なぜそんな自分が司法書士を目指したのか
器用さとは無縁の人生を歩んできた自分が、なぜ司法書士などという「正確性」が命のような職業を目指したのか。正直に言えば、最初は「独立できる仕事に就きたい」という漠然とした思いからでした。当時は会社勤めに疲れていて、「このまま使われるだけの人生でいいのか」と悶々とする日々。そのときたまたま資格雑誌で見かけた「司法書士は開業できる」という言葉が、妙に胸に刺さったのです。まさかそれが、人生最大のチャレンジになるとは思ってもみませんでした。
一発勝負の人生をかけた資格試験
司法書士試験は難関中の難関。特に自分のように頭の回転が速いタイプではなく、記憶力も凡庸な人間にとっては、相当な努力が必要です。受験勉強中は「これ本当に受かるのか?」と何度も心が折れかけました。でも、逆に言えば器用じゃないからこそ、がむしゃらにやるしかなかった。繰り返しノートに書き殴り、条文を音読し、寝る前に六法全書を抱えて布団に入るような日々。人生をかけて挑む価値があると信じて、ひたすら机に向かっていました。
合格までにかかった年数と思考回路
結局、自分が合格するまでにかかった年数は5年。もっと早く受かる人もたくさんいますが、自分にはこのペースが限界でした。最初の頃は「1年でなんとか…」と思っていたものの、現実はそんなに甘くありませんでした。それでも諦めなかったのは、「これに落ちたらもう後がない」という切羽詰まった気持ちと、「どうせ不器用なんだから、人より多くやるしかない」という腹のくくりがあったからです。
受験仲間に見下されていた日々
受験予備校に通っていた頃、明らかに自分より要領よく勉強を進めている人たちがいて、彼らから微妙に距離を置かれていたこともありました。「あいつは受からないだろうな」みたいな視線を感じることも。でも、それも燃料でした。人に見下されることで、逆に「負けてたまるか」と踏ん張る力になっていた。器用にやれないなら、泥臭くしがみつくしかない。それが自分のやり方だったんです。
実務は想像以上に器用さが問われる
ようやく合格して開業してみると、実務の世界は試験以上にシビアでした。登記申請書類の作成や、依頼人への説明、法務局とのやり取りなど、すべてにおいて「正確性」と「丁寧さ」が求められます。「不器用だけど誠実」というだけでは通用しない場面も多々あります。何度も修正を求められたり、依頼人に誤解を与えてしまったこともあり、今でも毎日のように「俺って向いてないんじゃないか」と思いながら仕事をしています。
書類を揃えるという地味な戦い
書類作成においては、ミスが命取りです。例えば登記申請で1文字でも住所がズレていたら、補正が必要になりますし、時間も信頼も失われます。それを防ぐために、同じ書類を何度も見直し、声に出して読み上げ、チェックリストと照合して…と、まるで機械のような確認作業が続きます。器用な人ならもっと効率よくできるのでしょうが、自分には無理。だからこそ、「しつこいくらい丁寧に」が信条になっています。
登記情報と現実のズレに振り回される
登記上の地番と現地の表示が一致しない、名前の漢字が住民票と異なる、印鑑証明の日付が間に合わない――そんな「微差」に、日々頭を抱えています。「ああ、なんで一発で終わらないんだ」と落ち込むこともしょっちゅう。でも、こういう細かいミスを一つひとつ潰していくことが、依頼人の信頼につながっているんだと思うようにしています。不器用な自分でも、誠実さだけは手放さずに。
細かいチェックを繰り返す日常
事務所では、毎朝まず前日の書類を確認するところから始めます。前日に仕上げたつもりの書類も、一晩置くと意外と誤字脱字が見つかるものです。事務員の女性と二人三脚で、ダブルチェック・トリプルチェック。これがないと、自信を持って提出できません。器用じゃないからこそ、チェックの精度だけは妥協しない。そんな毎日です。
それでも続けられている理由
自分のような不器用な人間でも、司法書士という仕事を何とか続けていられるのは、「この仕事が自分にとっての居場所だ」と感じているからかもしれません。要領の良さはないけれど、愚直に積み重ねてきた信頼と経験が、少しずつ自信になっています。たまに「先生、ありがとう」と言われたときは、本当に涙が出そうになります。報われる瞬間があるから、また次の日も頑張れる。それがこの仕事の魅力なんだと思います。
器用じゃないからこその慎重さが役立つ
「お前は不器用だけど、だからこそ信用できる」と言ってくれた依頼人がいました。器用に立ち回れる人ほど、ミスを見逃しやすいという側面もある。自分のようにミスを恐れて慎重にならざるを得ない人間は、逆に信用につながる部分もあるようです。欠点を強みに変えるって、こういうことなのかもしれません。
「先生ありがとう」と言われる瞬間の救い
依頼人からの「ありがとう」は、報酬よりもずっと心に残るご褒美です。特に、相続や不動産登記などで悩んでいた方からの感謝の言葉は、自分の存在意義を再確認させてくれます。「この仕事を選んでよかった」と思えるのは、そんな瞬間があるからです。
事務員の存在に助けられている現実
最後に言っておきたいのは、事務員さんの存在なくして今の自分はありえないということです。自分の弱点を補ってくれる存在がそばにいるからこそ、ギリギリのバランスでこの仕事が回っている。感謝してもしきれない思いでいっぱいです。
器用な人に囲まれることでバランスが取れている
世の中、器用な人ばかりじゃありません。でも、周囲に器用な人がいることで、不器用な自分も役に立てる場面がある。自分の苦手を素直に認めて、人に頼ることも大切だと学びました。不器用な人間なりの、等身大の働き方。それをこれからも続けていこうと思っています。