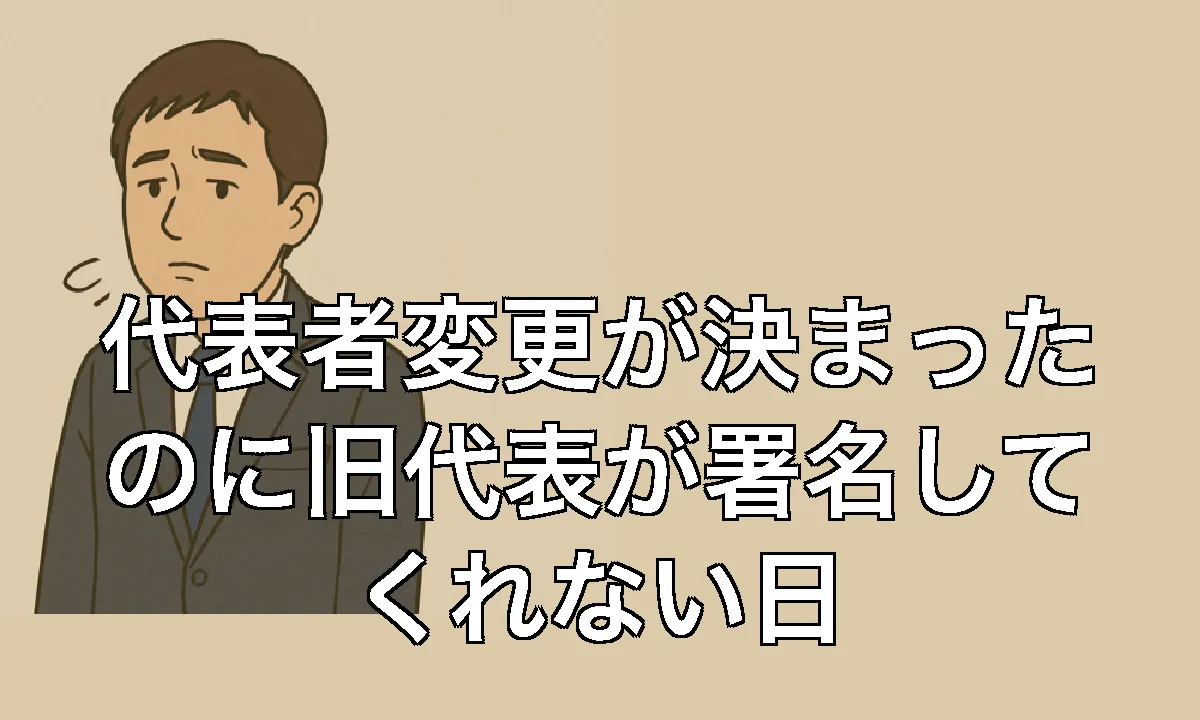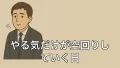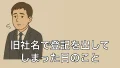突然の連絡から始まった代表者変更の登記依頼
その日もいつものように事務所で黙々と書類を整えていたところ、一本の電話が鳴った。法人の代表者が交代することになり、登記をお願いしたいという内容だった。こうした依頼は特に珍しくない。むしろ、手続きとしてはシンプルな部類に入る。しかし、電話口の声に、どこか不穏な空気を感じた。依頼主の声はどこか遠慮がちで、そして焦りを隠せない様子だった。こういうときは、だいたい一筋縄ではいかない。
気乗りしない声色での初回相談
事務所に来所されたのは新しく代表に就任する予定の男性。物腰は柔らかいが、やや困ったような表情をしていた。「実は、前の代表がなかなかサインしてくれなくて」と話すその言葉に、ああ、やっぱりと思った。中小企業ではよくあることだ。登記の世界では、いくら新代表が決まったとしても、旧代表の協力がなければ話が前に進まない場面がある。
「あの人が代表を降りたがっていて」からの始まり
聞けば、旧代表は自ら退く意向を示していたという。年齢的にも体力的にも経営がきつくなってきたとのこと。それなら円満に引き継ぎが済みそうなものだが、そううまくはいかないのが現実。「あの人が代表を降りたいって言ったのに、いざとなると音信不通になって…」と、新代表は肩を落としていた。まるで、引退すると言いながらバットを手放せない元野球部のエースのようだ。
言葉の端々に感じた不穏な空気
旧代表との関係についてたずねると、新代表は口ごもった。「まぁ、いろいろありまして」と曖昧に笑う。そういうときは、だいたい“いろいろ”の中身が問題なのだ。会社の金銭トラブル、社内対立、感情のもつれ…。司法書士としては事情を聞いても介入はできない。だが、その“いろいろ”が手続きの行方を大きく左右する。やれやれ、面倒な予感しかしない。
旧代表者がサインを拒むという想定外
数日後、新代表から再び連絡があった。どうやら旧代表に連絡がついたとのことだったが、開口一番「もう関わりたくないから書かない」と言われたらしい。その一言で、代表者変更の登記は完全にストップしてしまった。書類にサインがなければ登記はできない。これは形式上の問題ではなく、法的な要件である。つまり、署名拒否は手続きそのものを無にする力を持っている。
「いやもう関わりたくないんで」電話口の一言
旧代表に電話を入れてみた。本人確認と趣旨説明のためだ。しかし、その反応は予想以上に冷たかった。「もうその会社とは縁を切ったので。面倒なことには関わりたくありません」。淡々とした声が電話の向こうから返ってきた。その口調には感情の揺れもなく、決意すら感じた。まるでバットを折ってしまった元エースが、二度とマウンドには立たないと心に決めたかのような断絶だった。
ここまでスッパリ拒否されるとは
これまでにも協力を渋る旧代表に出会ったことはある。だが、ここまでキッパリと拒絶されたのは初めてだった。通常は説得や説明を重ねることで、最終的には折れてくれるケースが多い。今回はその手が通用しない。本人の意思が完全に固まっているのだ。法律上、任意の署名が必要な以上、強制力をもって進める手段はない。どうにもならない現実が目の前にあった。
元代表が頑なになる事情を深掘りしてみた
人はなぜそこまで拒むのか。冷静になって考えてみた。もしかすると、過去のしこりや、人間関係の悪化、あるいは会社に対する怒りがあるのかもしれない。書類に署名するという行為が、彼にとって“未練”や“責任”を象徴するものであり、それを断ち切る手段として拒否しているのかもしれない。いずれにせよ、司法書士にはどうしようもない領域の話だ。
登記のプロとしての立場と依頼人との板挟み
「先生、どうにかならないんですか?」と新代表からの電話。できることなら何とかしてあげたい。しかし現実には限界がある。司法書士にできるのは、手続きのサポートとアドバイスだけ。関係修復や説得は依頼者側の役割になる。だが、依頼者にしてみれば「お金払ってるのになんで」という気持ちになるのも理解できる。その狭間でこちらも疲弊していく。
現代表の焦りと不満の矛先がこちらに向く
「だったら、他の方法はないんですか?このままだと会社が回らないんです」と語気を強めてくる依頼者。気持ちは分かる。しかし、旧代表のサインなしに進められる特例なんて存在しない。いくら丁寧に説明しても、理解が追いつかないと「司法書士が融通利かせてくれない」と誤解されることもある。これは登記あるあるだが、つらい瞬間だ。
「なんとかしてくださいよ」と言われても
一度、感情的になった依頼者から「先生の方から旧代表に直接言ってくれれば、説得できるんじゃないですか」と言われたことがある。だが、それは完全な越権行為になる可能性がある。司法書士が感情の調停役を担うのは、職務の外だ。しかし、現場ではしばしばそれを求められる。自分の立場と相手の期待のギャップに苦しむことも多い。
できることとできないことの間でもがく
「法律上できません」と言ってしまえば楽かもしれない。だが、それでは依頼者の気持ちを切り捨てることにもなる。少しでも事態が動くように、あらゆる可能性を探りながらギリギリのラインで言葉を選び、対応を模索する。正直なところ、ものすごく消耗する仕事だ。これは、机上の知識だけでは対応できない現場力が求められる瞬間だ。
署名がもらえないと登記は進まない現実
手続き上、必要な書類に署名がなければ登記申請はできない。それは誰がどう言おうと変わらないルールである。だからこそ、どんなにスムーズに手配していても、一つの署名で全てが止まる。まるで、9回裏ツーアウト満塁でバッターがバットを振らないまま試合が終わってしまうような、やるせなさが残る。
「本人の意思」が壁になる場面
登記は書類が揃えば終わるもの、と思われがちだが、実際は人間の「意思」が絡む場面が多々ある。特に、代表者変更のようなケースでは、旧代表の意志確認が肝になる。それが「拒否」だと、どれだけこちらが完璧な書類を準備しても無駄になる。登記の最終的なボトルネックは、法律ではなく人の気持ちなのだと痛感する。
代替手段はあるか できることの模索
理論上、裁判や仮処分などの法的手段を講じて旧代表の協力を取り付けることはできる。だがそれには時間も費用もかかる。中小企業にとっては現実的ではない選択肢だ。結局、当事者間での話し合いが最も確実であるという、もどかしい結論に落ち着くことが多い。こちらとしても、歯がゆさが残るばかりだ。
登記の“止まり方”にもいろいろある
一言で「登記が止まる」といっても、その理由は様々だ。書類の不備、印鑑の不一致、そして今回のような署名拒否。止まり方の質によって、こちらの対応も変わってくる。今回のように感情的な拒絶が原因の場合、書類を整えるだけではどうにもならない。人間関係が登記を左右する。そんな現実を、またひとつ知った気がする。
結局うまくいかなかった でも得たものもあった
この案件は、最終的に登記申請には至らなかった。新代表も「いったん保留にします」と諦めた様子だった。司法書士としては、仕事として完了できなかった悔しさが残る。しかし、同時に「無理なものは無理」と割り切る感覚も大事だと実感した。すべてを抱え込んでいては、こちらの心が持たない。
仕事としては未了 でも少し気が楽に
「今回はありがとうございました」と新代表に言われたとき、少しだけ救われた気がした。登記が終わらなくても、誠実に向き合ったことは伝わったのだと思う。結果だけではなく、過程にも意味がある。そんなことを久しぶりに実感できた。
諦めることも時には必要だと気づかされた
完璧主義ではやっていけない。割り切るところは割り切る。粘るべきところと引くべきところの判断、それこそが現場で身につく力だ。この案件はその「引き際」を教えてくれた。そんな経験もまた、司法書士の仕事の一部だと思いたい。
心の中の「もうええわ」が救ってくれる
元野球部だった自分が、三振してベンチに帰るときに思っていたこと。「次や次」。今回も同じ気持ちだった。「もうええわ」と心の中でつぶやいて、次の案件に集中する。そうしないと、この仕事はやってられない。それでもまた、誰かの困りごとに向き合おうとする自分がいる。なんだかんだ、きっとこの仕事が好きなんだと思う。