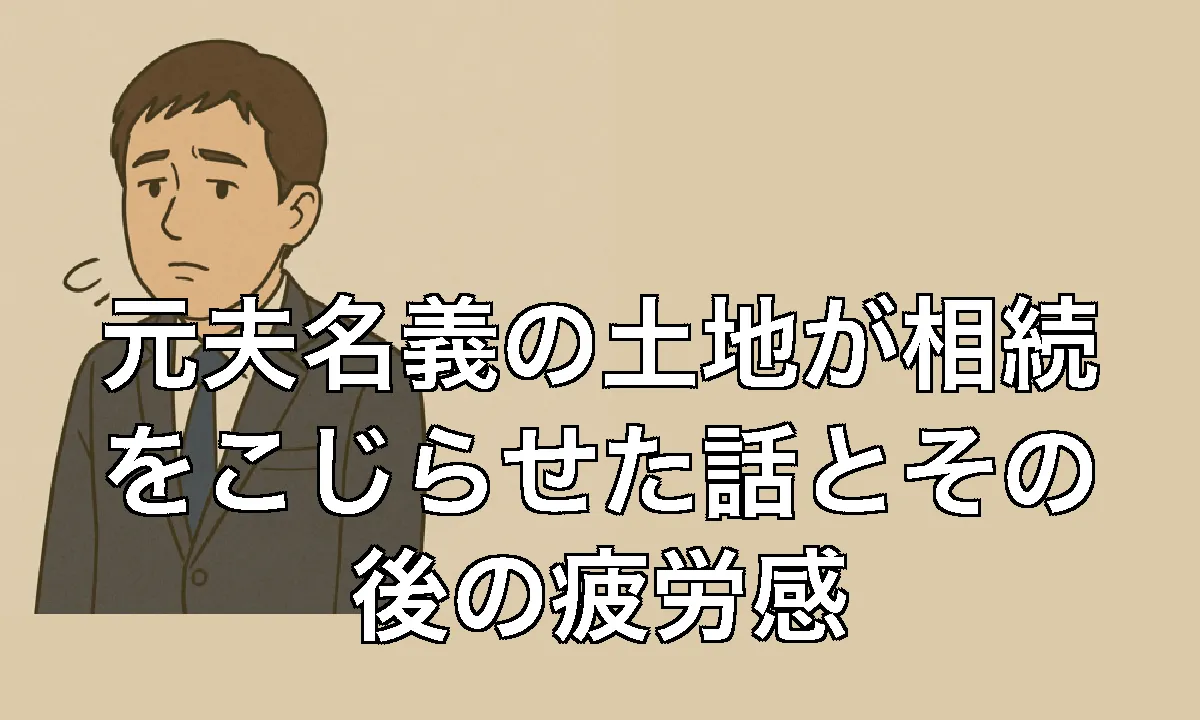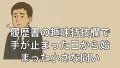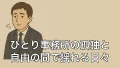想定外だった元夫名義の土地
相続にまつわる話は、予想外の方向からやってくることが多い。だが、今回ばかりは正直まいった。遺産分割協議に関わった案件の中で、まさか「元夫名義の土地」がここまで混乱を招くとは思わなかった。事務的な処理のつもりが、感情のこじれと法律の隙間に飲み込まれるような案件だった。相続人同士の微妙な人間関係や、過去の出来事に触れざるを得ない時間が続き、精神的な疲労が想像以上だった。
離婚後もそのままだった登記のツケ
今回問題になったのは、離婚後に名義変更がなされていなかった土地だった。元夫が所有名義のままにしていた土地を、妻がずっと使用していた。そのまま年月が経ち、妻が亡くなり、子どもたちが相続を受ける段階になって混乱が始まった。関係者全員が「もう母のものだった」と思い込んでいたのに、登記簿にはしっかり元夫の名前が残っている。その一行が、相続人たちの表情を一変させた。
「名義変更はあとでいい」の先延ばし
当時、離婚時に土地の名義変更を後回しにしたことに関して、「忙しかったから」とか「そこまで深く考えていなかった」という話を遺族から聞いた。でも、不動産における“あとでやる”は、本当に危ない。司法書士として何度も目にしてきたが、相続のタイミングで先送りのツケが一気に押し寄せるのだ。「あの時やっていれば」という声を何度聞いたことか。
相続が始まってからの地雷化
名義が元夫のままだったという事実が発覚してから、遺産分割協議は実質ストップした。「それ、うちの相続じゃないじゃん」と言い出す相続人、「いや母が住んでたんだから当然でしょ」と主張する相続人。全員が自分の立場に正義を持っていて、話がかみ合わない。私がいくら冷静に説明しても、「なんで今さらそんな話になるんだ」と感情的になる場面もあった。
誰のものか分からない土地が招く混乱
実はこの土地、登記以外の証拠も非常に乏しく、妻が“事実上の所有者”だったという証明も難しかった。固定資産税の納税記録こそ妻名義だったものの、元夫との合意書や明確な契約書は見つからなかった。こうなると、形式上は元夫の土地ということになる。相続人たちの納得も難しく、協議は混迷を極めた。
相手方の態度が豹変した瞬間
それまで穏やかだった相手方の長男が、「これはうちの父の土地だ」と主張し出した瞬間、空気が一変した。「今まで黙っていたけど、こちらの権利を無視されては困る」と冷静ながら鋭く切り込む様子に、他の相続人たちは動揺した。人は、土地やお金が関わると、まったく別の顔を見せる。それは私自身が何度も見てきた光景だ。
登記簿と現実のズレに頭を抱える
現実には妻が管理し、暮らしていた土地なのに、登記簿に名前がなければそれを証明する手段が乏しい。書類を一つ一つ精査しても、結局「法的にはこう」と言わざるを得ない。ここに来て、法律の“形式主義”が相続人の感情を追い越してしまった。私はただ、淡々と法的手続きを説明するしかなかった。
遺産分割協議が止まった日
その日は、空気が凍りついた。誰も口を開かず、書類の上で時計の音だけが響いていた。「今日は、これ以上進められないですね」と静かに口にした自分の声が妙に響いた。遺産分割協議は、一旦中断となった。全員が頭を抱えて、沈黙のまま帰っていった。司法書士である私は、その中立の立場で感情を持ち込むべきではないが、心の中では「勘弁してくれ」とつぶやいていた。
相続人同士の不信感が一気に噴出
協議の場から帰ったあと、個別に連絡を受けた。「あの人たちは信用できない」と話す長男、「あの土地、ずっと母が世話してたんです」と主張する次女。お互いの不信感は根深く、話はすれ違い、もはや相続というよりも人間関係のもつれそのものだった。司法書士は法的な手続きをサポートする役割にすぎないのに、時に心の仲裁まで求められる。
「どうしてそんなものが残ってるの」の声
次女の一言が印象的だった。「なんで、そんなものを名義変更してなかったの?母は毎年固定資産税払ってたのに!」と怒気まじりに言われたが、相手にその思いは届いていなかった。目に見える「証拠」がないと、正当性が伝わらない。人の想いと、登記の記録のギャップがこんなに重くのしかかるとは、想像以上だった。
書類を前に黙り込む家族たち
再び集まった協議の場では、全員が沈黙していた。A4用紙の上にある登記簿謄本、古い契約書、税金の納付書――誰もがその“証拠”たちに支配されていた。言葉では説明できないモヤモヤが積もり、結局また話は進まずに終わった。この時ほど、法の限界と感情の重さを感じたことはない。
仕事の重みと孤独の夜
その日の帰り道、事務所に戻った私は、無言で椅子に腰を下ろした。誰かに愚痴を言いたかったが、事務員さんはすでに帰宅。頼れる上司もいなければ、慰めてくれる人もいない。夕飯はコンビニ弁当。パソコンの前で、それをつつきながらため息が止まらなかった。司法書士って、こんなにも孤独なのか、と改めて思わされた。
事務所に戻ってからも悶々とする
「今日は何もできなかったな」と自分を責める夜。書類の山を前にしても、やる気は出ない。仕事のやりがいがどうとか、誰かの役に立っているとか、そういう感覚よりも「疲れた」という思いが強かった。独身で一人で仕事を回す生活は、気楽なようでいて、こういう時には余計に堪える。
愚痴をこぼせる人もいない夜
元野球部だった頃は、負け試合のあとでも仲間と飲みに行き、くだらない話で笑っていた。でも今は、試合もなければ仲間もいない。独りで勝手に始まり、独りで終わる仕事の日々。たまに「これ、誰のためにやってるんだろう」と思ってしまう。優しさを持ってやっているつもりが、ただの自己満足なんじゃないかと不安にもなる。
元野球部のノリはここでは通じない
「声出していこう!」なんて、自分に言い聞かせても、事務所には誰もいない。プレッシャーもミスも、全部自分の責任。自分で背負って、自分で処理する。その繰り返し。仲間と助け合うことの楽しさを知っていたぶん、その不在が痛い。元野球部のような熱い掛け声も、今や空回りだ。
司法書士として生きるとは
それでも、翌朝は来る。眠い目をこすって、メールをチェックし、電話に出る。トラブルもまた、日常の一部。司法書士は淡々と、だけど一つ一つを丁寧にこなしていく仕事だ。誰かが安心して暮らせるように、見えない部分を支えるのが役目。感謝されないことも多いが、それでもやめようとは思わない。
誰にも知られない小さな戦い
大きな事件でもなければ、ニュースにもならない。拍手もされない。でも、机の上の一通の書類には、誰かの人生が詰まっている。名前、住所、権利、義務。そのすべてを、確かな形に整えていく。これは、誰にも気づかれない、小さな戦いだ。だがその静かな戦いが、社会を成り立たせているのだと信じたい。
それでも明日もまた登記は続く
今日がつらくても、明日はまた別の登記が待っている。書類を整え、説明し、間違いのないように処理していく。愚痴をこぼしても、また朝が来て、仕事は始まる。司法書士という職業は、そんな日々の連続だ。それでも、たまに誰かが「ありがとう」と言ってくれると、少しだけ救われる気がする。