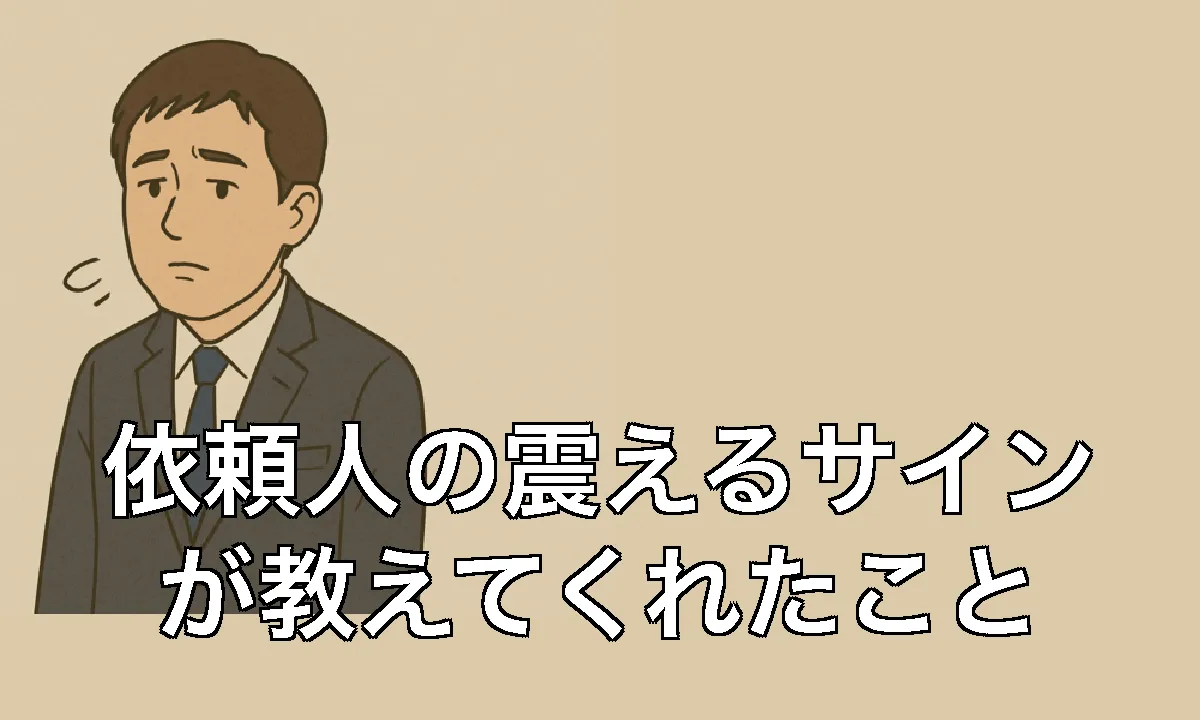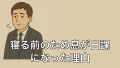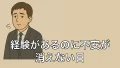字が読めないという現実に立ちすくんだ日
ある日の午後、少し早めに到着された高齢の依頼人が、登記申請のために必要な書類に署名をしようとした瞬間、その手が小刻みに震えていたのを今でもよく覚えている。丁寧にペンを持ち、何度も紙に触れながらサインを試みるも、文字は震えて曲がり、何が書かれているのか判別できない。司法書士という職業柄、文字の正確さや本人確認は絶対的な要素だ。しかし、その日目の前にあったのは、制度ではなく、人間だった。事務的に「やり直してください」と言える空気ではなかったし、自分の中のモヤモヤがしばらく晴れなかったのを覚えている。
書類を前にした沈黙
「これで大丈夫ですかねぇ」と、不安げに依頼人が顔を上げたとき、私は言葉を詰まらせた。確かにサイン欄には何か書かれているが、これを登記官が読めるとは到底思えない。だが、「読めません」と突き返すのも酷な気がして、一瞬、時間が止まったような沈黙が流れた。過去に何百人と署名を見てきたが、こんなにも「言えない」サインは初めてだった。司法書士の仕事は、法律と人間の間に立つこと。その間には、こうした言葉にしにくい葛藤が無数にある。
依頼人の手が震える理由
高齢による震えだけでなく、何度も「すみません」と頭を下げる姿からは、社会的な自信の喪失や、日常的に感じている無力さがにじみ出ていた。加齢とともに、思うように体が動かず、字も書けなくなる。それは恥ずかしいことではないのに、本人が一番恥じている。周囲に迷惑をかけたくないという思いが、逆に心を萎縮させる。私は元野球部で、字を書くのはあまり得意じゃない。でも、手が震えて書けないという感覚は、正直想像以上だった。自分が老いたとき、同じように人に気を使いながらサインをするのだろうか、とふと思った。
責任の所在はどこにあるのか
法的には、本人の意思確認が取れ、かつ署名が本人によるものであるなら、形式的には問題ないとされる。だが現実には、「読めない署名」は実務上のトラブルの火種になりかねない。じゃあ誰が止めるのか?誰が「これはダメです」と判断するのか?司法書士である私?それとも法務局?この曖昧な境界線に立たされるたび、「自分の判断」が責任を背負うのだと痛感する。本当にこれでいいのか、という疑問は、処理を終えても胸の中に残り続ける。
高齢の依頼人と向き合うということ
これまでも高齢の依頼人と接する機会は多かったが、今回のように「本人の不安」が手に伝わってくる経験はあまりなかった。形式ではなく、その人自身と向き合う覚悟が求められる。その人が人生で何度目かの大きな決断をしようとしている、その場に自分がいるということ。それは大きな意味を持つ。だが、業務としての制約がそれを邪魔することもある。その狭間で何度も立ち止まるのが、司法書士の現場だ。
優しさと業務の板挟み
「このまま提出してみますか?」と私は声をかけた。内心では、再度書き直してもらった方が安心なのは明らかだったが、その一言が言えなかった。優しさと逃げの境界はいつも曖昧だ。業務としては、厳しく対応したほうがいいのかもしれない。だが、人として、その選択ができなかった。結局、私はリスクを承知でサインを受け取った。自己満足だったかもしれない。でも、あの時の依頼人の安堵した笑顔が、今でも頭に焼きついて離れない。
家族の代筆は有効か
最近では、家族による代筆や代筆委任のような形での対応を求められることもある。しかしこれがまた難しい。「本人が書けないから代わりに書きました」と言われたら、果たしてそれで良いのか?という疑問がわいてくる。一見合理的な選択に見えるが、実際には本人の意思がどこまで反映されているのか分からない。それが「見えないリスク」としてのしかかってくる。
本人確認と意思の問題
代筆であっても、結局は本人の意思確認が肝になる。でも、字が書けないというだけで、意思能力がないわけではない。そのあたりの線引きが曖昧なまま現場が処理を求められるのが現実だ。意思確認のために、会話を録音したり、第三者の立ち会いを求めたりすることもあるが、すべてが完璧に証明されるわけではない。法律は合理的でも、人はそんなに割り切れない。
実務での落とし穴
形式的には代筆でもなんとかなるケースもある。だが、あとになってトラブルになることもある。「あのとき本当に本人が同意していたのか」と疑われたとき、こちらに責任が向く。そうならないよう慎重に進めるが、それでも「完璧」はない。この「グレーゾーン」に日々悩まされる。実務は、教科書通りには進まないのだ。
自分の無力さを突きつけられる瞬間
「これしか書けなくてごめんなさい」と、依頼人が小さく呟いた。私はそれを聞いて、言葉が出なかった。自分が何か役に立ったわけでもないのに、「ありがとう」と言われる。無力なのに感謝される。そのたびに、自分の中に空虚な気持ちが広がる。この職業のもどかしさは、成功体験ではなく、こうした場面に集約されている気がする。
できないことの苦しさ
司法書士になった頃は、「できること」が増えるたびに嬉しかった。しかし今は、「できないこと」に直面することのほうが多く、それが苦しい。特に相手が高齢だったり、身体的に不自由だったりすると、こちらの無力感が増す。人を支えたいと思って始めた仕事が、人の弱さを目の当たりにしたとき、ただの業務に感じてしまうことがある。理想と現実のギャップが、年々重くのしかかる。
説明する言葉も見つからない
「法的には難しいんです」とか「形式上問題があるんです」といった説明が、時に人を傷つける。正しいことを言っているはずなのに、どこか冷たい。そう感じると、自分の口から出る言葉に自信がなくなる。説明をしようとしても、納得させられる言葉が見つからない。自分が悪いのか、制度が悪いのか、もうよく分からない。
プロとしての限界
プロフェッショナルとは、どんなときでも一定の品質で仕事をする人のことだと思っていた。けれど、目の前の人が泣いていたら、そんな言葉は通用しない。感情を切り離せと言われても無理がある。プロだからこそ冷静でいなければいけないのは分かっている。でも、私は人間だ。自分の限界を認めるのは悔しいけれど、そこから逃げるわけにもいかない。
それでもこの仕事を続ける理由
正直、何度も辞めようかと思った。誰にも感謝されない日もあるし、むしろ理不尽に怒鳴られる日もある。それでも続けているのは、「それでもやる人がいなければ困る人がいる」と思うから。うまく言えないけれど、この不器用な自分にも、誰かの役に立てる場面があるのなら、それを大切にしたいと思っている。
ただの手続き屋ではない
世間から見れば、司法書士はただの手続き屋かもしれない。でも、私はそう思わない。紙のやり取りの裏には、人生の節目や決断がある。それを支えるのが、自分の役割だ。地味だけど、必要とされる場面はある。誰も注目しない仕事だけど、誰かの人生に寄り添える仕事。そう信じてやっている。
一人の人間として向き合う
結局のところ、司法書士である前に、一人の人間として相手と向き合うことが大事なんだと思う。制度の中でできることは限られているけど、その中で最大限を尽くす。それがこの仕事の本質じゃないかと思う。カッコつけたことは言えないけど、今日もまた、誰かの震える手を見て、心を動かされた自分がいる。
それが報われることは少ない
報酬も感謝も得られないことの方が多い。むしろ、苦情や疑いの目にさらされることの方が多い。でも、それでもいいと思っている。誰かの「どうしよう」に応える存在でいたい。誤解されても、黙って処理を進める。そんな地味な存在でも、誰かの生活を下支えしているのだと、自分に言い聞かせながら。
でも誰かがやらなきゃならない
震える手でサインする依頼人の姿を見るたび、「やっぱり自分がやらなきゃ」と思う。他の誰かではなく、自分がその場にいた意味を考える。向いていないかもしれない、要領も悪いし、モテもしない。でも、だからこそ、こういう地味で人の見えない部分に寄り添えるのかもしれない。そう思って、今日も机に向かう。