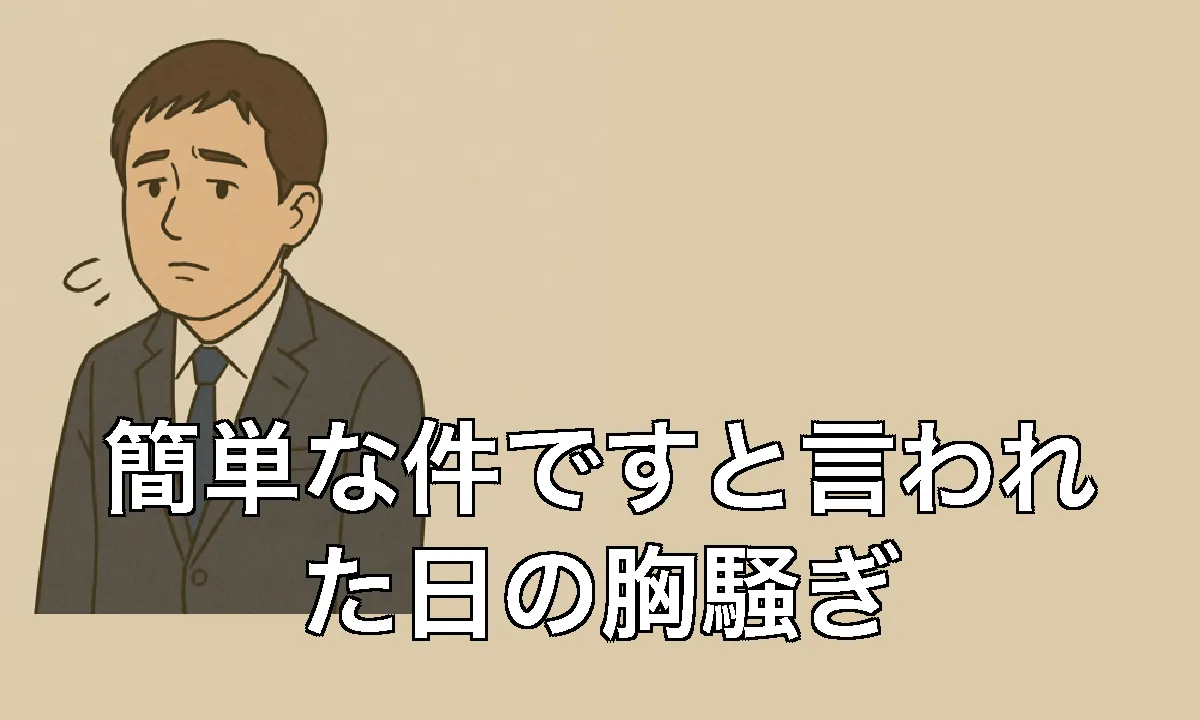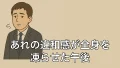その一言が始まりだった
「先生、簡単な件なんですが…」と電話口で言われた瞬間、なぜか背筋に冷たいものが走る。地方で司法書士をやっていると、こういう“簡単な件”が、だいたい簡単では終わらない。すべてがそうではない。だが経験則的に、「簡単です」と言うお客様ほど、説明が足りなかったり、資料が足りなかったり、あるいはそもそも手続きの内容を誤解されていることが多い。最初は善意で受け止める。しかし、繰り返されるうちに、身構えてしまうのも無理はないのだ。
お客様の「簡単な件です」はなぜ警戒すべきか
このセリフ、無邪気そうでいて、じつは“情報の省略”が隠れている場合がある。たとえば「名義変更だけです」と言われたが、よく聞いてみると相続登記だったり、しかも相続人が海外在住だったり。言葉の裏には、依頼者の主観的な「簡単」の基準があり、それが我々専門職の「複雑」の基準と噛み合っていないことがあるのだ。
具体的な説明なしで始まる依頼の怖さ
「簡単な名義変更」と聞いて訪問を受けたが、ふたを開けてみたら、親族間で争いもあり、戸籍も昭和初期から遡らなければならなかった案件があった。しかも、依頼者本人は「全部そろってます」と自信満々。実際に確認すると、必要な戸籍は3割ほど。思わず「どこが簡単やねん」と独り言が漏れてしまったのを覚えている。
想定外が次々に出てくるパターン
途中で「ついでにこれも」「あ、それもお願い」と雪だるま式に要望が増えていくのも“簡単な件”あるあるだ。結果的に、予定していた作業の3倍以上の時間がかかり、スケジュールが押し、昼ごはんも食べそびれる。「先生、手早くて助かるわ~」なんて言われても、こちらは空腹でクラクラだ。
事務所の空気が一変する瞬間
私の事務所には一人だけ事務員がいる。ベテランでよく気が利くのだが、電話の内容を伝えるとき「簡単な案件らしいです」と言った瞬間、ふたりして無言になる。経験上、その言葉は“注意喚起”と同義なのだ。こうして空気がピリッと引き締まる。
事務員との沈黙のアイコンタクト
私がパソコン画面を見つめたまま固まると、彼女も無言でうなずく。ふたりの間には、「これは長引くぞ」「一筋縄じゃいかんぞ」という以心伝心がある。事務員がそっとスケジュール表を確認する様子を見ると、申し訳なさと不安が同時に押し寄せる。
進めても進めても終わらない書類たち
「これだけで済みます」と言われた書類が、気づけば10枚、20枚、補正対応まで含めればその倍。印刷してもしてもプリンターが止まらない。業務終了後、机に積み上がった書類の山を前に、「これ…いつ片付くんや…」と疲労困憊でつぶやいた日もある。
実は簡単ではない理由
本当に簡単な件であれば、たいていは本人で済ませられる。司法書士に依頼がくるということは、どこかに“障害”や“煩雑さ”があるはずなのだ。そこを丁寧に聞き取り、整理して、想定される落とし穴をあらかじめ塞いでおく。それが仕事であり、腕の見せどころでもある。
登記簿と現実のギャップ
登記簿を見て、「ああ、これは典型的な相続登記だな」と思っていたら、住所変更がされておらず、しかも改姓まであるというパターンも多い。依頼人が「関係ないと思ったから」と言って後出ししてくる情報に、頭を抱える。
相続人が全国に散らばっていた
戸籍を追っていくと、相続人が北海道から沖縄まで、果ては海外在住の人までいたことがある。それを“簡単”と言えるのは、全国の相続人に会ってもらう手間や郵送や確認作業を、まるで“魔法のようにやってくれる”と思っているからなのかもしれない。
ご本人確認の難しさと戸籍の迷路
中には、本人確認が難航し、免許証も期限切れ、戸籍も旧姓のままで、正直に言って「これはどうやって進めようか…」と立ち止まった案件もある。こちらが手順を組み立て、穴をふさぎ、説明文を添えてようやく形にしたが、それを“簡単だったね”と総括されたときは、さすがに笑うしかなかった。
「ちょっとだけお願い」が一番重い
「先生、ついでにこれも…」という言葉ほど、危険なものはない。一見親しみやすい依頼に見えて、裏には手間やリスクが隠れている。ちょっとのつもりが、半日飛ぶ。これ、野球で言えば、バントの構えからフルスイングされるようなものである。
聞けば聞くほど状況が深まっていく
最初は「名義変更だけ」だった案件が、実は離婚を挟んでいたり、前の配偶者との共有だったり。聞いていくうちに「あ、それも関係あります?」「え、そこまで調べるんですか?」となり、結局、初動で聞いておけばよかったという反省の連続。
「あれもこれも」と後から増えるオプション地獄
「ついでに会社の登記簿も整理してほしい」「あ、駐車場の契約書も確認して」と後出しオプションが連鎖すると、もう業務の軸がぶれる。しかも、お客様は「お手数ですが」と言いつつ、笑顔で言ってくる。この笑顔が、一番こたえる。
元野球部でも投げたくなる瞬間
野球部出身の自分は、どれだけ打たれても投げ続けるタイプだった。でも、この仕事では時に「もう降板させてくれ…」と言いたくなることもある。精神力よりも、淡々と処理し続ける集中力が問われる場面が多い。
エラー続出の案件に精神が折れそうになる
補正が重なり、提出書類に不備が見つかり、法務局とのやり取りが混線するとき、まるで内野手全員がエラーしているような気持ちになる。こちらがしっかりしていても、情報源が曖昧だと、土台がグラつくのだ。
完璧主義が仇になるとき
「抜けがないように」「完璧な書類を」と気を張りすぎると、自分が潰れてしまう。少しのミスも許されないプレッシャーが日々の中で積もっていく。そういう時ほど、昔の監督の「肩の力を抜け」という声を思い出す。
事務員の方が冷静なこともある
慌てているのは自分だけで、横にいる事務員が「先生、まずコーヒー飲みません?」と差し出してくる。その一言で、我に返る。彼女の方が一枚上手かもしれない。いや、実際にそうだろう。
バッターボックスに立ち続ける意地
「自分がやるしかない」という思いだけで、なんとか続けているところがある。やめたいと口では言いつつ、どこかで「次こそは」と思ってしまう自分もいる。野球と同じで、結果が出るまで打席を降りたくないのだ。
途中で投げないことだけが自分の誇り
人から見たら不器用で、仕事のスピードも決して早くない。でも、最後までやり抜く。お客様の「ありがとう」一言に、全てが報われた気がする。やめたくなるたびに、その一言を思い出している。
過去の自分に教えてやりたい心の準備
司法書士を目指していた頃、「簡単な件も多い」と言われたことがある。その言葉を信じた若い自分に、「それ、罠だぞ」と言いたい。覚悟さえあれば、どんな複雑な案件も、なんとかなる。心の準備があるかどうかで、だいぶ違う。
この経験が教えてくれたこと
苦労した案件ほど、学びがある。そして、同じ失敗を繰り返さないように少しずつ改善していく。それが司法書士の地味な、でも確かな成長だと思う。簡単じゃなかったからこそ、得られるものがある。
「簡単」という言葉の裏にあるものを疑え
言葉の軽さに惑わされてはいけない。「簡単」と言われても、必ず事実確認と書類チェック、関係者の確認を徹底する。それが、地雷を踏まない唯一の手段だと身をもって知った。
誰かにとっての簡単は誰かにとっての地獄
依頼者は本当に悪気がない。ただ、見えている世界が違うだけ。こちらは「法」と「手続き」の視点、相手は「感覚」と「印象」の世界。そこにギャップがあるのは当然なのだ。
最初のヒアリングに全力をかけるべき理由
「簡単な件」の正体を明かすには、最初の聞き取りがすべて。丁寧に掘り下げることで、のちの苦労がぐっと減る。今は、どんな案件でもヒアリングだけは野球のノック練習のように繰り返して鍛えている。
それでも人の役に立っている実感はある
どんなに大変でも、誰かの役に立っているという実感がある限り、司法書士という仕事は続けられる。自己満足かもしれないが、それがこの職業の支えなのだ。
完了報告の電話がくれる小さなご褒美
「無事終わりました、ありがとうございました」とお客様に伝える瞬間、やっと肩の荷が下りる。その小さな“終わり”が、また次に向かうエネルギーをくれる。
また頑張れる理由は結局そこにある
日々の忙しさやトラブルに疲れても、またやろうと思えるのは、誰かの役に立てたという実感が残るから。地味で報われにくい仕事だけど、それでも、今日もまた“簡単な件”に向き合っていく。