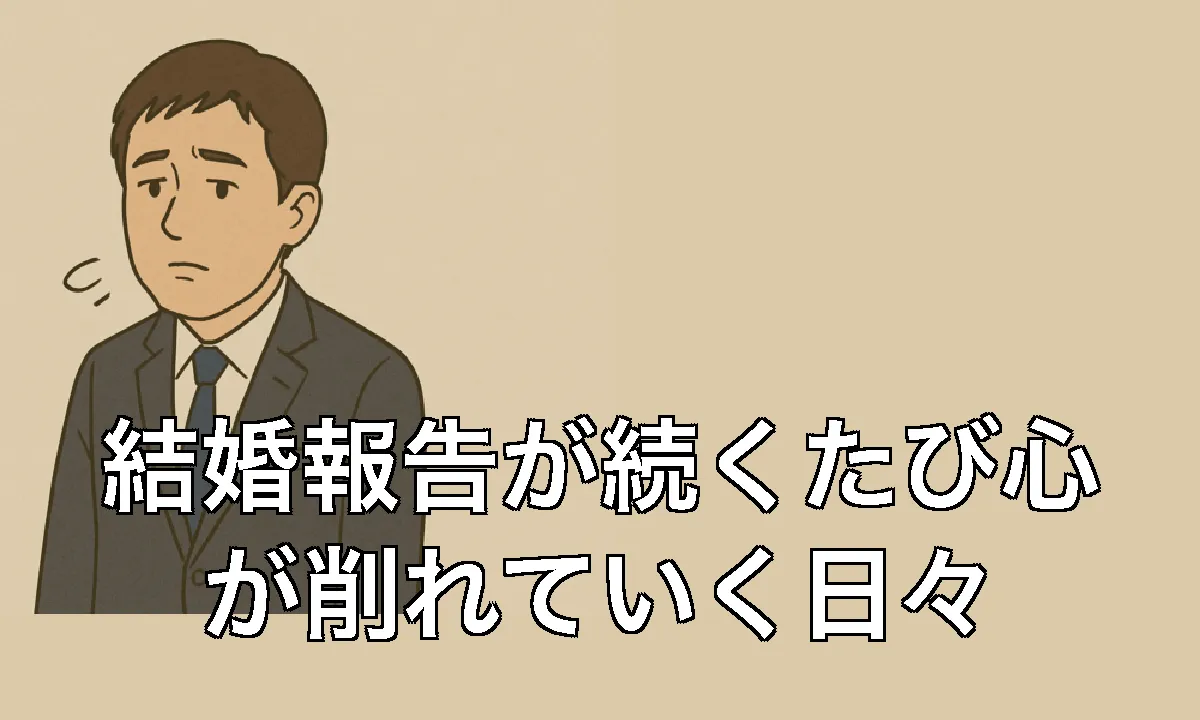なぜこんなにも結婚報告が刺さるのか
最近やたらと「結婚しました」の報告が多い。友人、元同級生、かつて一緒に野球をしていた仲間まで、みんな当然のように家庭を築いている。SNSでは笑顔のツーショットと指輪の写真。幸せそうな空気が画面越しに押し寄せてきて、スマホを置いたあと、妙に疲れてしまう。別に妬んでるわけじゃない、そう思いたい。でも、どうしても心がざわつく。私は、ただ仕事に追われ、気がつけば今年も独りだった。
喜ばしいニュースのはずなのに
結婚はめでたいことだと頭では分かっている。むしろ祝福されるべき話題だし、自分も「おめでとう!」と反応する。でも、打ったその一言のあと、画面の向こうの笑顔と自分の部屋の静けさのギャップに、ふっと心が沈む。まるで、誰かの明るさが自分の影を強調しているような気さえする。誰かの幸せは、自分の現状と無意識に比較されてしまうものなんだろう。そんなことすら考えたくないのに。
独身者の心のスキマを抉る言葉たち
「次はあなたの番だね」「いい人いないの?」…たわいない会話の中に、妙な棘がある。悪気がないのはわかってる。でも、その一言でずしんと心が重くなる。たとえるなら、古傷に指を突っ込まれるような感覚。結婚していないという状態が、どこか「未完成」であるかのように扱われる瞬間が、こんなにも苦しいとは思わなかった。年齢を重ねるごとに、その沈黙はさらに重たく、答えづらくなっていく。
次はあなたの番だねの呪い
「次はあなたの番だね」——その言葉、もはや呪いに近い。何度聞いたことか。笑ってやり過ごすけれど、内心では「そんな番が来る予定はない」と苦笑している。言われるたび、社会のレールに乗れていない自分を実感させられてしまう。誰も悪くない、でもその一言が、心の奥に重く残る。番なんて、自分で決めるものでしょう?…そんな強がりを飲み込むたび、少しずつ、心が削れていく。
司法書士という職業の孤独と無言のプレッシャー
地方の司法書士なんて、誰からも見えにくい存在だ。誰かの登記を淡々と処理し、手続きを進め、提出期限を守る。それが当たり前になっているけれど、その裏で孤独と向き合う時間も多い。依頼人とは業務的な会話が中心で、心を通わせるようなやり取りは少ない。事務所に戻れば、静かすぎる空間が広がっている。誰ともつながっていないような感覚。結婚報告が刺さるのも、この孤独が根底にある気がする。
祝福してもらう側になれないという現実
ふと考える。自分が誰かに「結婚しました」と報告する日なんて来るんだろうか。祝福される立場になる日は来るのか。正直、想像がつかない。今の生活には、そういった未来が見えない。日々、山のような書類に追われて、休みの日は寝るだけ。出会いもなければ、恋愛に時間を使う余裕もない。気づけば、自分の人生に期待することをやめていた。淡々と仕事をこなし、今日も一人、コンビニ弁当を温めている。
人に寄り添う仕事なのに自分には誰も寄り添わない
司法書士は、人の人生の大事な場面に関わる職業だ。不動産を買ったり、相続したり、会社を作ったり。そのすべてに立ち会って、書類で支えている。でも、そんな「人生の転機」を支える側でありながら、自分の人生には誰も寄り添ってくれない。誰かに「お疲れさま」と言ってもらえることも少ない。クライアントには頼りにされても、プライベートでは誰にも頼られていない。そんな日々が、結婚報告の眩しさを余計に引き立ててしまう。
笑顔の裏で書類とだけ向き合う日々
「人と関わる仕事っていいですね」と言われたことがある。確かに関わってはいる。でもそれは、印鑑をもらうための関わりだ。感情をぶつけ合うような深い関係ではない。今日も私は、笑顔で依頼人を迎えながら、内心では「早く終わらないかな」と思ってしまうこともある。仕事は嫌いじゃないけれど、どこか虚しさがある。机の上に山積みの書類、それを処理する自分。そのループの中で、自分の人生の実感がどんどん薄れていく。
事務員との距離感に悩む日もある
事務所にはひとり事務員がいて、毎日一緒に仕事をしている。もちろん頼りになるし、助かっている。でも、ふとした瞬間に距離を感じることもある。たとえば、雑談で家庭の話をされたとき。自分にはない世界の話に、なんと返せばいいかわからない。話を広げると余計に寂しくなるし、避けると無言が気まずい。仕事上は問題ないけれど、人としてのつながり方にいつも戸惑ってしまう。
優しさと気まずさの狭間で揺れる会話
たとえば昼休み。「子どもが今度運動会で…」という話に、頷きながらも内心では逃げ場を探している自分がいる。冷たいわけじゃない。ただ、うまく会話に入れないのだ。自分にはわからない話題だし、踏み込むのも怖い。少しだけ優しく笑って、それでやり過ごす。そんな会話が続くと、「この距離がちょうどいいのかもしれない」と思うようになる。関係が壊れないように、必要以上に関わらないようにしてしまっている。
ふとした瞬間に感じる家庭の匂い
仕事終わり、事務員さんが「今日はカレーの予定です」と言って帰っていったとき、なぜか胸がぎゅっと締め付けられた。何気ない会話のはずなのに、「誰かと一緒にご飯を食べる」ことの温かさを強く感じたからかもしれない。私はというと、冷蔵庫に残った豆腐と、期限ギリギリの卵で済ませるつもりだった。そのコントラストに、思わずため息が出た。こんな些細なことでも、孤独を思い知らされる瞬間がある。
雑談一つで心がざわつく
雑談の中に紛れる幸せの断片。それが一番こたえる。向こうは悪気もなく、ただの日常会話として話しているのだろう。でも、こっちはその何気ない話に反応できずにいる。話を合わせて笑っても、心の奥では「自分には一生ない風景かもしれない」と思ってしまう。そのたびに「仕事に集中しよう」と自分を律する。だけど本音を言えば、たまには誰かと何も考えずに話したい。ただ、それができる相手が、いない。
元野球部だったあの頃と今の自分
高校時代、毎日汗だくになって白球を追いかけていた。声を出して、仲間と励まし合って、同じ目標に向かっていた。あの頃は、自分が何者かになれる気がしていた。仲間がいて、居場所があった。今はどうだろうか。誰にも声をかけられず、誰とも背中を叩き合わず、一人で戦っている。成長はしたかもしれないが、心の温度は、あの夏の日よりもずっと冷たい。
仲間がいた時間と今のひとり作業の差
野球部の仲間たちは、今では多くが家庭を持っている。たまに集まる飲み会でも、話題は子どもの成長やマイホームの話。私はただ、聞き役に徹しているだけ。話についていけないというより、「それ、俺には関係ないな」と思ってしまう。昔は一緒に同じグラウンドで汗を流していたのに、今はまるで別の人生を歩いている。ひとり作業に慣れすぎてしまったのかもしれない。
グラウンドでは声が届いたのに
かつては「ナイスプレー!」と声をかければ、それが仲間の力になった。自分の声が誰かに届き、何かが動く実感があった。でも今、事務所でいくら声を出しても、誰にも届かない。パソコンのキー音だけが響く静けさの中、自分が「いてもいなくても変わらない存在」に思えてしまう日もある。あのグラウンドの喧騒が、懐かしくてたまらない。
今は誰にボールを投げればいいのか
誰かにボールを投げたくなる瞬間がある。キャッチしてもらいたい思いを、言葉にして投げたい。でも、受け取ってくれる相手がいない。仕事ではボールのように案件が飛び交うが、それは心をやり取りするものじゃない。私が投げたいのは、もっと人としての想いなのかもしれない。けれど、投げる前からあきらめている自分がいる。
それでも明日も誰かのために登記する
こんな日々でも、仕事がなくなると困る。誰かが私を必要としてくれる限り、この仕事は続けていくつもりだ。愚痴をこぼしながらでも、登記が完了して「ありがとう」と言ってもらえたときは、やっぱり少し救われる。自分が存在している意味を、少しだけ感じられる瞬間だ。結婚報告には疲れるけれど、それとは違う形で、自分も誰かの人生に関わっている。それだけは、忘れないようにしたい。