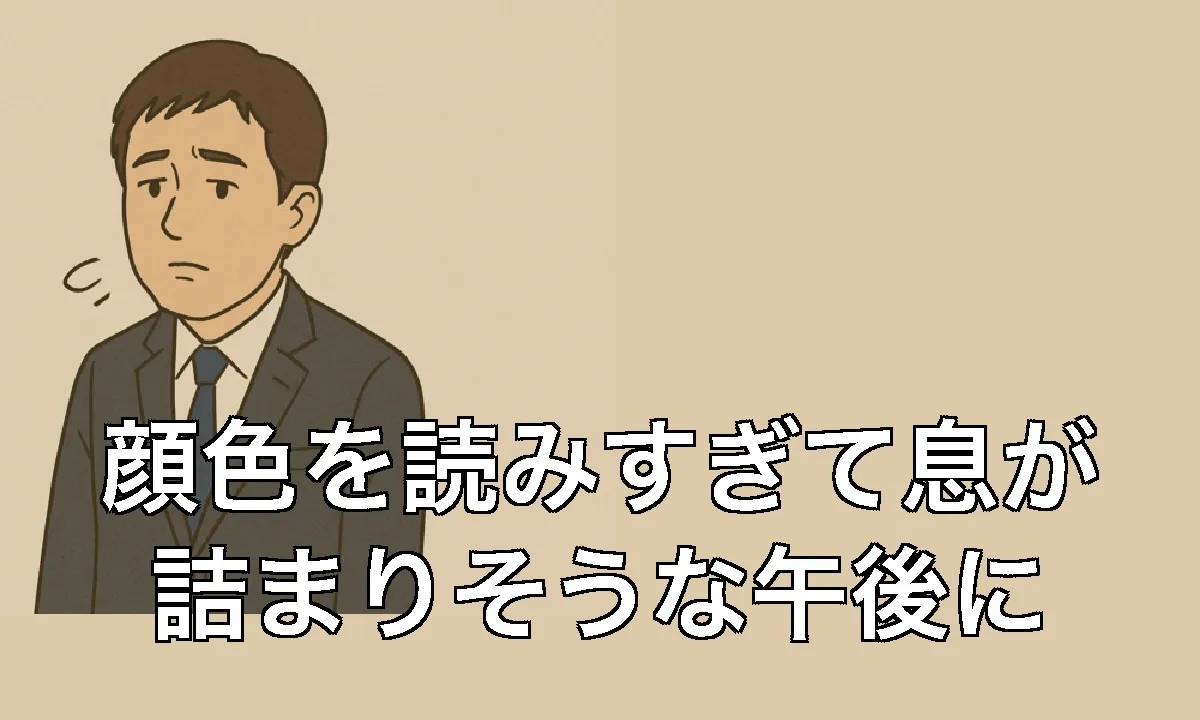気づけば人の顔色ばかり気にしている日常
司法書士として働くなかで、どうしても「人の顔色」をうかがってしまう瞬間が増えました。依頼人の声のトーン、法務局の担当者のちょっとした表情、事務員さんの微妙な沈黙。どれも気になってしまって、夕方にはぐったりしています。こんなふうに感じているのは自分だけじゃないと思いたいけど、「気を遣いすぎだよ」と言われても、それを止める方法がわからない。気づけば自分の呼吸すら浅くなっていたりして、本当に息が詰まりそうな午後もあります。
依頼人の一言に振り回される性分
「先生なら分かってくれると思って」と言われると、ついなんとかしてあげなければと動いてしまう。そんな自分が嫌いになれないのがまた厄介です。以前、相続関係の複雑な相談で、明らかに対応が難しい件があったのですが、「先生、困ってるんですよ…」という一言に心を持っていかれ、気づけば土日返上で動いていました。仕事として割り切れれば楽なのに、どうしても“人として”応えたいという気持ちが出てきてしまうんです。
「先生なら分かってくれますよね」の圧
この「分かってくれますよね」という言葉、恐ろしい呪文みたいなもので、心のブレーキを壊してくるんです。悪意がないのは分かっています。でも、無意識に相手の期待に応えようとスイッチが入ってしまう。気づけば無理なスケジュールを詰めてしまったり、電話に出るタイミングすらビクビクしていたり。仕事上の理屈では断れるのに、気持ちの上で断るのがどうしても苦手なんですよね。
共感力が高いのか断れないだけなのか
「共感力がある」と言えば聞こえはいいけど、たぶん実態は「断る勇気がない」だけなのかもしれません。昔からそうでした。中学の頃、野球部の後輩が道具を忘れて怒られていると、自分が預かってたことにして叱られたこともあります。責任感とかじゃなくて、ただその場の空気を穏やかにしたかっただけ。今もそれが変わっていないのだとしたら、少し情けなくもあります。
法務局の担当者にもビクビク
法務局に書類を提出するときも、つい担当者の顔色をうかがってしまうのが癖になっています。ちょっと眉をひそめただけで「あ、何かマズいことしたかも」と不安になる。こっちは提出するだけの立場なのに、まるで面接を受けてるような緊張感。相手はそんなつもりないと分かってるのに、勝手に一人で内心オロオロしてしまうんです。
「この件ですが」でドキッとする習慣
電話や窓口で「この件ですが…」と言われると、心臓が一瞬止まりそうになります。何か書類の不備か、間違いか、もしかしてクレームか。頭の中で最悪のケースを先回りして想像してしまう。実際は単なる確認で済むことが多いのに、慣れることはありません。あの一言に反射的にビクッとしてしまう自分が、本当に情けない。
心拍数で登記の状態が分かりそうな自分
「登記完了しました」と言われたときの安堵感は、まるで試験に合格したみたいな感覚です。逆に「補正が必要です」と言われると、鼓動が早くなるのが自分でも分かる。もはや心拍数で登記の状況が把握できるんじゃないかと思うくらい。それくらい、自分の気持ちが顔色に支配されている証拠なんでしょうね。
気を遣うのが仕事と言われればそれまでだけど
司法書士の仕事って、確かに「気を遣ってナンボ」みたいなところがあります。特に相続や成年後見、会社設立なんかは、相手の不安や混乱に寄り添うことが求められます。でも、それと“顔色を伺い続けること”は別だと最近思うようになりました。気づかないうちに、自分が疲弊してしまっているのです。
顔色を読まないと進まない案件もある
たしかに、相手の感情を汲み取って話を進めることは重要です。泣いている方に事務的な説明をしても響かないし、怒っている人にはまず落ち着いてもらう必要がある。だけど、必要以上に“空気を読む”ことに徹すると、どこかで嘘の自分を演じることになってしまう。それが積み重なると、心のどこかで「これは本当に自分の仕事なのか」と思ってしまう瞬間があります。
でも結局は「無理です」と言う羽目に
顔色を読み続けて、相手の希望に近づこうとした結果、どうしてもできないラインにぶつかる。「やっぱり、それは無理です」と伝えるときの空気の重さは、何度経験しても慣れません。最初からそう言っておけば楽だったのかもしれない。でも、顔色を見てしまうから、つい曖昧に答えてしまって、自分で苦しくしてしまうんです。
傷つけずに断るスキルの難しさ
やんわり断る技術って、本当に難しい。言葉の選び方、タイミング、声のトーン…すべてが試されます。研修で教わるようなものじゃなく、結局は経験と感覚なんですよね。でも、その感覚が鋭すぎると、相手のちょっとした動揺にも敏感になって、逆に断るのがしんどくなる。まったく、損な性格だと思います。
事務員さんの前でも気を遣いすぎている
たった一人の事務員さん相手でも、つい気を遣ってしまいます。機嫌を損ねたらどうしようとか、言い方がきつかったかなとか、あとでぐるぐる考えてしまう。別に怒られてるわけでもないのに、自分の言葉に過剰に反応してしまうのは、やっぱり「顔色を読みすぎる」癖のせいなんでしょうね。
雑談ひとつにも気配りが必要だと思ってしまう
「今日、寒いですね」と言ったあと、相手の反応が薄いと「なんかマズいこと言ったかな」とか思ってしまう自分。雑談すら一つの“業務”のように感じてしまう。こんなこと、他の人に話しても笑われるだけでしょうけど、本気で悩んでるんです。気を抜くって、どうやるんでしたっけ。
もう少し鈍感だったら楽だったのかもしれない
ちょっとくらい鈍感で、空気が読めないくらいのほうが、長くこの仕事を続けられるのかもしれないと思うことがあります。でも、それができないからこそ、今の自分があるのも分かっていて、もどかしい。まるで呼吸の仕方を忘れてしまったかのように、常に構えている感覚。たまには素で生きてみたいものです。
野球部時代の図太さはどこへ
昔はもっと図太かったはずなんです。高校の野球部では監督に怒鳴られても、「またかよ」と思って笑ってました。ミスしても「次、打てばええやろ」と開き直れた。でも今は、ちょっとした指摘にすらビクビクする自分がいます。あの頃の無鉄砲さが少しでも残ってたら、きっと今より呼吸しやすかったと思うんですが…。
声だけは大きかったあの頃と今の小声
「おーい!」とグラウンドで叫んでいた声も、今じゃ電話口で小声になってる。相手の反応を気にして、言い直したり、声を抑えたり。自分の存在を小さくしようとしているような感覚。そんな自分を、あの頃のチームメイトが見たらどう思うだろう。たぶん「どうしたん?」って笑われる気がします。
それでも誰かの役に立てるならと思っている
それでも、この性格が誰かの救いになっているのなら、意味はあると思いたい。たとえ疲れても、誰かが少しでも安心できたり、信頼してくれたりするなら、それでいい。理想論かもしれません。でも、そうでも思わないと、この仕事、続けられないですからね。
顔色を読むのも才能だと思いたい
「空気が読める」のは悪いことばかりじゃない。相手の不安に気づけたり、怒りを和らげられたりするのも一つのスキルだと思うようにしています。だから、今日も息が詰まりそうになりながら、それでも顔を上げて、相手の表情を見てしまう。そして、また一日が終わります。
誰にも言えない苦労を抱える人の支えになれたら
自分がこれまで感じてきたしんどさや気づかいが、同じように誰かを助けられるのなら、それでいい。誰にも言えずに悩んでる人がいたら、「分かりますよ」と言ってあげたい。今日も顔色を読みすぎて、ちょっと疲れた午後。でも、そんな午後が誰かの安心に繋がっているなら、悪くないかもしれません。