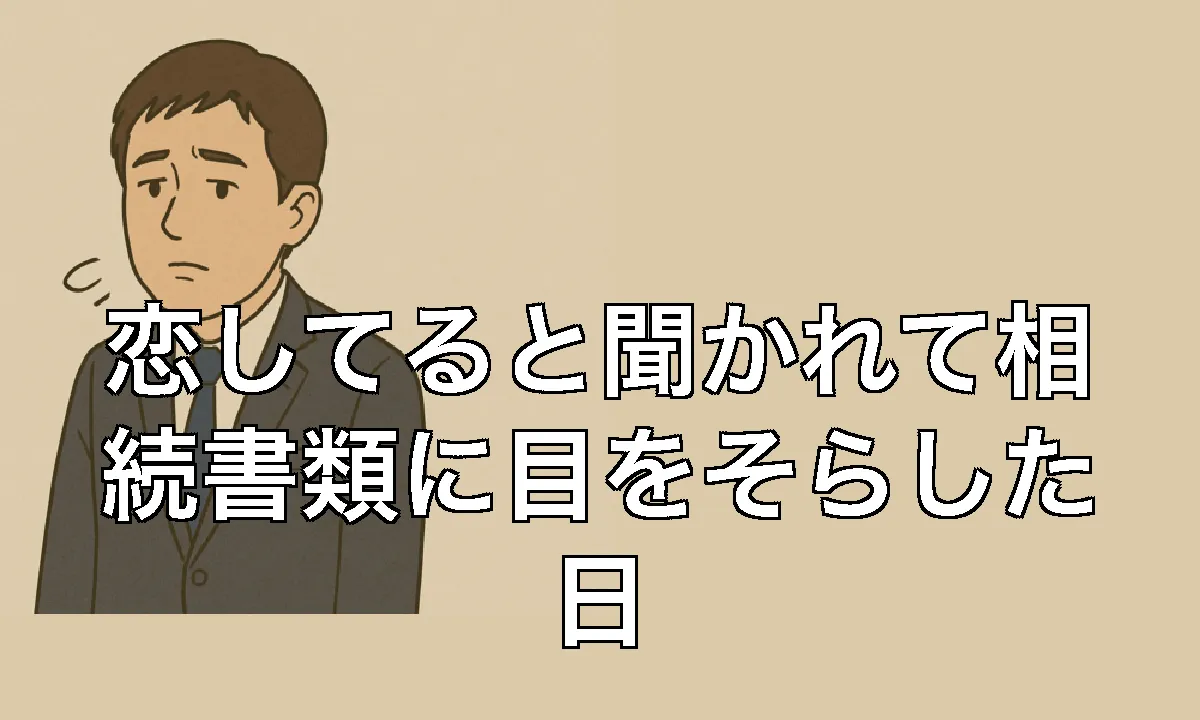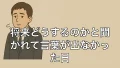朝一番の来客が残した言葉に動揺する
事務所のドアが開いたのは、朝の9時過ぎ。まだコーヒーも飲みきれていない時間帯だった。初老の女性が一人、相続の相談に訪れたのだが、受付票を記入しているときにふと漏らした。「先生って、恋してる?」と。私は一瞬、耳を疑った。相続の相談に来た方が、いきなりそんな質問をしてくるとは思ってもいなかったからだ。答えられなかった。笑ってごまかして、そのまま書類の説明に入ったけれど、心の中はその一言でざわついていた。
まさか「恋してる?」なんて言葉を聞くとは
相談内容は典型的な相続案件だった。亡くなったご主人の名義の不動産について、遺産分割協議書を作成してほしいという依頼。それ自体は日常茶飯事だし、淡々と進めればいいのだが、冒頭の「恋してる?」の一言がどうにも頭から離れなかった。仕事柄、人の感情に触れることは多い。でも、自分の感情に向き合うことは少ない。この仕事を長くやっていると、感情を排除する癖がついてしまうのだ。だからこそ、恋なんて言葉に反応する自分に驚いていた。
相談じゃなくて人生の切れ端のような話だった
話を聞いていると、その女性は単に相続の相談に来たわけではなかった。ご主人との別れが寂しくて、「何かしら手続きが残っているうちは、まだ隣にいる気がする」と話してくれた。私は、ただ頷くだけだった。こういうとき、司法書士としての自分と、人としての自分との距離感に戸惑う。人生の終わりに立ち会うことが多い職業だからこそ、言葉に詰まることもある。そんな中で投げかけられた「恋してる?」という言葉は、彼女なりの人生の振り返りだったのかもしれない。
それでも僕は「書類」で返すしかなかった
最終的には、遺産分割協議書を整え、登記申請の準備を整えた。事務的には完璧だったと思う。でも、それでよかったのかと、どこかで引っかかっている自分がいた。彼女の「恋してる?」という問いかけに、私は結局、何も返せなかった。ただの一司法書士としての役目を果たしただけ。人としての反応を、どこかに置き忘れてしまったような気がしてならない。
感情と事務手続きのはざまで揺れる日々
司法書士という仕事は、感情と無縁なように見えて、実はとても感情的な側面を持っている。特に相続に関わるとき、人の喪失や葛藤、未練に触れることが多い。ただ、それを業務として受け止め、処理しなければならない。感情を抱いても、それを表に出すことはできない。そのはざまで、いつも心が引き裂かれるような感覚を覚える。
依頼者の涙に弱いのは昔からだ
私は昔から、泣いている人を見るとダメだった。特に女性の涙には、本当に弱い。野球部時代、マネージャーが泣いていたのを見て、全員の前で真顔になれなかったのを思い出す。司法書士になってからも、それは変わらない。依頼者が涙を流しながら話すとき、心がざわついて、書類に集中できなくなるときもある。でも、涙に寄り添うのが正しいのか、それとも無表情で処理を進めるのが正しいのか、いつも悩んでいる。
共感しても、助けられるのは手続きだけ
どれだけ相手の気持ちを理解しても、私にできるのは「書類を整えること」だけだ。たとえば、家族がもめているときに、私が間に入って説得するわけにはいかない。あくまでも中立で、法的に正しい形に導く。それが司法書士の役割だ。共感したところで、遺産が均等に分かれるわけでも、感情が整理されるわけでもない。だからこそ、余計に無力感を覚える。
もっと人間らしい対応ができたらと思うとき
それでも、たまに思う。もっと人間らしい対応ができたらいいのに、と。たとえば「よく頑張ってきましたね」とか「大変でしたね」と、自然に言葉が出せる人間になれたら、と。だが現実は、そういう一言すら迷ってしまう。変に感情を出すと、逆に相手を傷つけてしまうのではないかという不安がある。司法書士として、まだまだ自分は未熟だと思い知らされる瞬間だ。
自分の生活に恋の余地はあるのか
そんな日々を過ごしていると、ふと我に返ることがある。自分の生活に「恋」なんて感情を抱ける余地はあるのだろうかと。朝から晩まで書類と向き合い、誰かと連絡を取り合っても、用件はすべて「登記」か「相続」か「会社設立」。誰かの気配が残るのは、PCの履歴と電話の伝言だけ。たまにLINEが鳴っても、同業の士業仲間からだったりする。
忙しさのせいにして何年が過ぎたのか
気づけば、恋愛から遠ざかって何年も経っていた。最初は「今は忙しいから」と思っていた。でも、その「今」がずっと続いている。終わる気配がない。事務員に「先生、もう少し自分のことも大事にした方がいいですよ」と言われて、笑って流したけれど、心のどこかでは図星だった。自分のことを後回しにしてきた結果、誰かと向き合う時間も余裕も、いつの間にか消えていた。
夜に響くFAXの音が会話の代わり
静かな夜、事務所でひとり作業をしていると、時々FAXの音が響く。それが唯一の「会話」みたいに思えることがある。誰かが何かを送ってくれているという、わずかなつながり。そのくらいしか、人との関係を感じられないこともある。でも、だからと言って孤独が好きなわけではない。ただ、どうやってその殻を破っていいのかわからないだけだ。
元野球部だったころの自分が今を見たら
高校時代、野球部で汗だくになっていたあの頃。真っ黒に日焼けして、泥だらけで帰宅していた自分が、今の私を見たらどう思うだろう。「おまえ、何してんだよ」と笑うかもしれない。書類に囲まれて、誰かの人生の終わりに関わる仕事をしている今の私に、当時の私は共感してくれるだろうか。
汗まみれで走っていたあの夏
毎日が単純だった。走って、打って、怒られて、笑って。そんな日々が恋しくなることもある。体力的には今よりずっときつかったはずなのに、心はもっと自由だった気がする。あの頃は、誰かを好きになることも自然だった。今は、誰かを想うことすら面倒に感じてしまう。何が変わったのか、自分でもよくわからない。
目の前の相続案件に夢中な今
今の私は、目の前の仕事をこなすことで精一杯だ。相続登記の期限、書類の不備、役所とのやりとり、依頼者との打ち合わせ。それらが毎日、容赦なく押し寄せてくる。誰かを好きになる余裕なんて、どこにあるんだろうと思う。でも、それって本当に「余裕」がないからなのか? それとも、そう思い込むことで、自分を守っているだけなのか。
恋の話なんてどこへいったのか
恋愛って、もっと身近なものだったはずなのに、いつからか遠い話になってしまった。気づけば、書類の山が目の前にあるだけで、誰かと心を通わせるような瞬間がない。もしかしたら、書類にしか向き合えない自分を、相続の相談者は見透かしていたのかもしれない。「先生って、恋してる?」――その一言は、きっと彼女だけでなく、自分自身に向けた問いでもあったのだ。