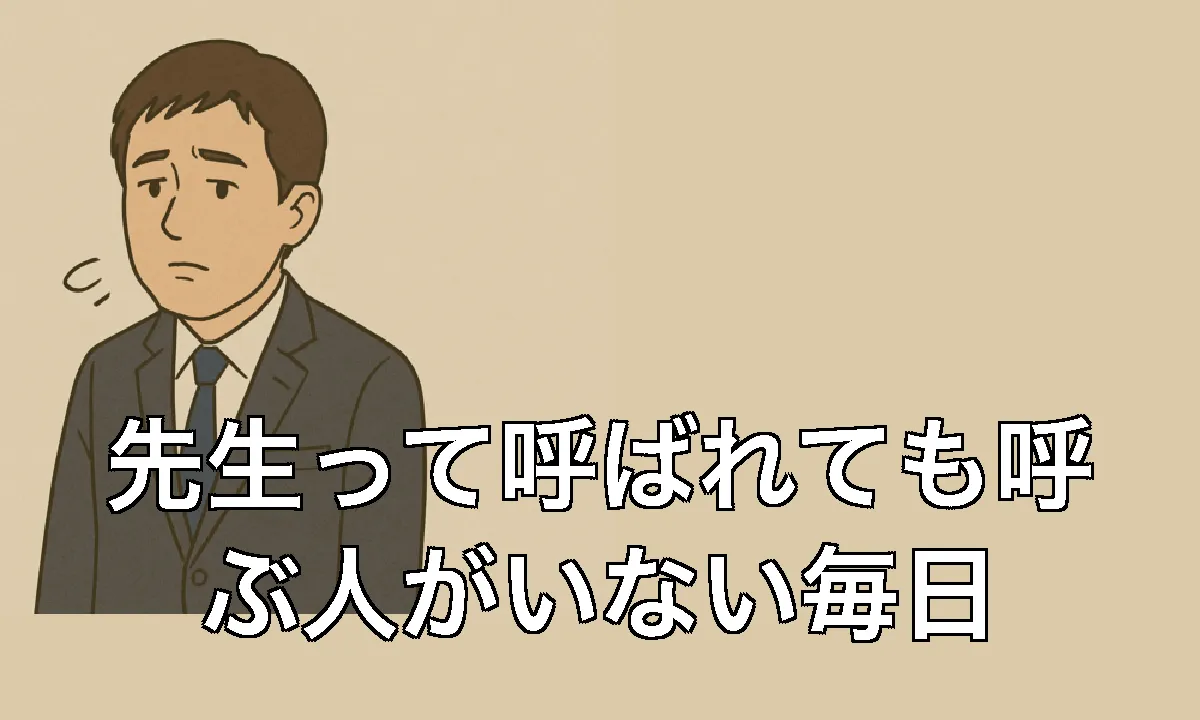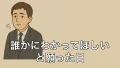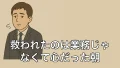先生と呼ばれることの意味を考える日々
「先生」と呼ばれるたびに、胸がざらつく。司法書士として独立し、事務所を構えて十数年。名刺には立派な肩書きが印刷され、相談者は私を「先生」と呼ぶ。でも、その響きはどこか遠い。誰かの役に立てているのかもしれない。でもふとした瞬間に思う。「俺は、誰かに名前を呼ばれているだろうか」と。忙しさにかまけて、そんな小さな問いを見ないふりしてきたけど、最近になってやけに重くのしかかるようになってきた。
肩書が先に歩いていく感覚
司法書士という職業柄、相手はこちらの名前を知らなくても「先生」と呼んでくれる。それが礼儀でもあるし、ある種の信頼の証なのかもしれない。けれど、その言葉には中身がないように感じることがある。名前を飛び越えて、肩書だけが先に独り歩きしている感覚。「先生だから」「先生にお願いすれば安心」——それは確かにありがたい。でも、私は肩書ではなく、一人の人間として誰かに向き合っていたかった。気がつけば、自分という人間がそこにいないような気さえしてくる。
名前を呼ばれた記憶が遠くなる
最後に誰かに「稲垣さん」と呼ばれたのはいつだっただろうか。友人も少ない。恋人もいない。家族とは最低限の連絡しかしていない。仕事の電話や面談では必ず「先生」と呼ばれる。たしかに、形式としては正しい。でも、名前を呼ばれない時間が積み重なるにつれて、自分が空気のように感じてくる。たまに昔の野球部の仲間から連絡が来た時、「稲垣!」と呼ばれる声がやけに温かく響いた。あれが本当に「自分」を呼んでくれた瞬間だったのだと思う。
「先生」と言われても実感がない
「先生、こちらお願いします」「先生にお任せします」——依頼者からの言葉に、ありがたいはずなのに、なぜか戸惑う。自分がそれに見合うだけの人間なのかと、毎回試されているような気になる。仕事は真面目に取り組んでいるし、法律や手続きをミスしないよう細心の注意を払っている。でも、「先生」として完璧でなければならないような重圧を感じると、自分の弱さや迷いを言い出せなくなる。それが積み重なって、誰にも頼れない孤独へと繋がっていく。
一人事務所のリアルな孤独
開業してから十年以上、ずっと一人でやってきた。今は事務員さんが一人来てくれているが、基本的には私のワンオペ状態だ。仕事の内容も、判断も、責任も全部自分。小さなことでも誰かと相談できたらと思うけれど、現実はそう甘くない。相談する相手がいないというより、相談する時間も気力も残っていない。だからこそ、「先生」なんて言葉が、余計に虚しく感じるのかもしれない。
電話の向こうにも「仲間」はいない
日々の業務で電話は欠かせない。登記所、法務局、銀行、依頼者。どれも仕事上必要なやり取りだ。でも、そこに「会話」はない。あるのは「確認」と「指示」と「お願い」ばかり。電話を切ったあと、ふと静まり返った事務所で感じるのは、「誰とも話してない」という感覚だ。これが何日も続くと、声がうまく出なくなることもある。無言の時間が日常になりすぎて、誰かと気軽に話す術を忘れてしまった。
事務員が休むと、誰とも話さない日
うちの事務員さんは本当に助かっている存在だ。でも彼女が休む日——たとえば体調不良や急な用事で休んだ日なんかは、完全に「無音」の時間になる。朝から晩まで誰とも言葉を交わさない。ただメールと資料と書類に追われ、気づけば日が暮れている。夕方、誰とも会話していないことに気づいてぞっとする。昔は誰かに会うことが楽しみだったのに、今では誰にも会わずに過ごすのが普通になってしまった。
背中を押してくれる誰かがほしかった
司法書士になったとき、本当は誰かに「よく頑張ったな」と言ってほしかった。でも、そんな言葉をかけてくれる人はいなかった。自分で選んだ道だから、自分でなんとかするしかない。そう思って歯を食いしばってきた。でも、今でもふとした瞬間に、誰かに認めてもらいたい気持ちが湧き上がる。成功しても、称賛してくれる人がいないと、それはただの「結果」に過ぎない。支えてくれる人がいたら、少しは違ったのかもしれない。
元野球部の俺が今投げているのは
かつては球場で声を張り上げていた。チームプレーが好きだった。仲間がいた。勝っても負けても、共に笑い、涙を流す日々があった。今、自分が投げているのは、静かな事務所で一人処理する書類の山。どこにも届かない思いを押し殺して、ひたすら処理を進める毎日だ。あの頃の自分が今の自分を見たら、どう思うだろうか。ひとりぼっちで黙って戦う姿を、誇らしいと思うだろうか。それとも、少し哀しいと思うだろうか。
声も出さずに投げ続ける「印鑑」
今の仕事で一番「投げる」もの。それは印鑑だ。契約書、登記申請書、書面確認……全部に印を押す。淡々と、ミスなく、ただ正確に。ボールのように勢いよく投げることもない。声援もない。汗を拭く瞬間すらない。ひたすら机の前で、押すだけの作業。それが大事な仕事だと分かってはいるけど、ときどき「俺は何をやってるんだろう」と虚しくなる瞬間がある。かつての情熱が、乾いた紙の上に吸い込まれていくようで。
試合に負けるより堪える「ミスの訂正」
若い頃、試合で負けたときのあの悔しさは今でも覚えている。でも、今の仕事での「負け」はもっと深い。たとえば、登記にミスがあって訂正を求められたとき。誰にも言い訳できないし、ミスの責任はすべて自分にのしかかる。その処理をする時間、胃が痛くなる。試合なら、仲間が励ましてくれる。でも今は、一人で処理して、一人で反省して、一人で立て直す。誰にも頼れない敗北が、地味に堪える。
応援の声が聞こえない職場
かつてベンチから飛んでくる「ナイスピッチ!」という声が励みだった。今、私の職場には応援の声はない。静かな事務所で、パソコンの音と印刷機の音だけが響いている。依頼者からの「ありがとう」は嬉しい。でも、それは応援とは違う。自分が頑張っていると実感できる「人の声」が、今の生活には欠けている。そういう日々が続くと、心がだんだん鈍くなってくる。何のために頑張っているのか分からなくなるときがある。
それでも誰かの力にはなれているか
それでも、思うのだ。「誰かの役に立てているかもしれない」と。相談に来た人が不安そうな表情から、少しでもホッとした顔になったとき、自分の存在が意味を持ったように感じる。名前じゃなくても、先生でもいい。その人にとっての安心になれるなら、それは誇るべきことなのかもしれない。そして、そうやって誰かの力になった経験のひとつひとつが、また自分の支えになっていくのだろう。
「ありがとう」の一言に救われる瞬間
ある日、登記の相談に来た初老の男性が帰り際にこう言った。「先生、本当に助かりました。ひとりで悩んでたから、話せてよかった」と。その一言で、しんどかった気持ちが少しだけ軽くなった。報酬でも、書類でもなく、その「ありがとう」が心の真ん中にスッと入ってきた。そういう瞬間があるから、また明日も仕事をしようと思える。呼ぶ人がいない毎日でも、呼ばれることで誰かに寄り添えるなら、それは悪くない日々なのかもしれない。