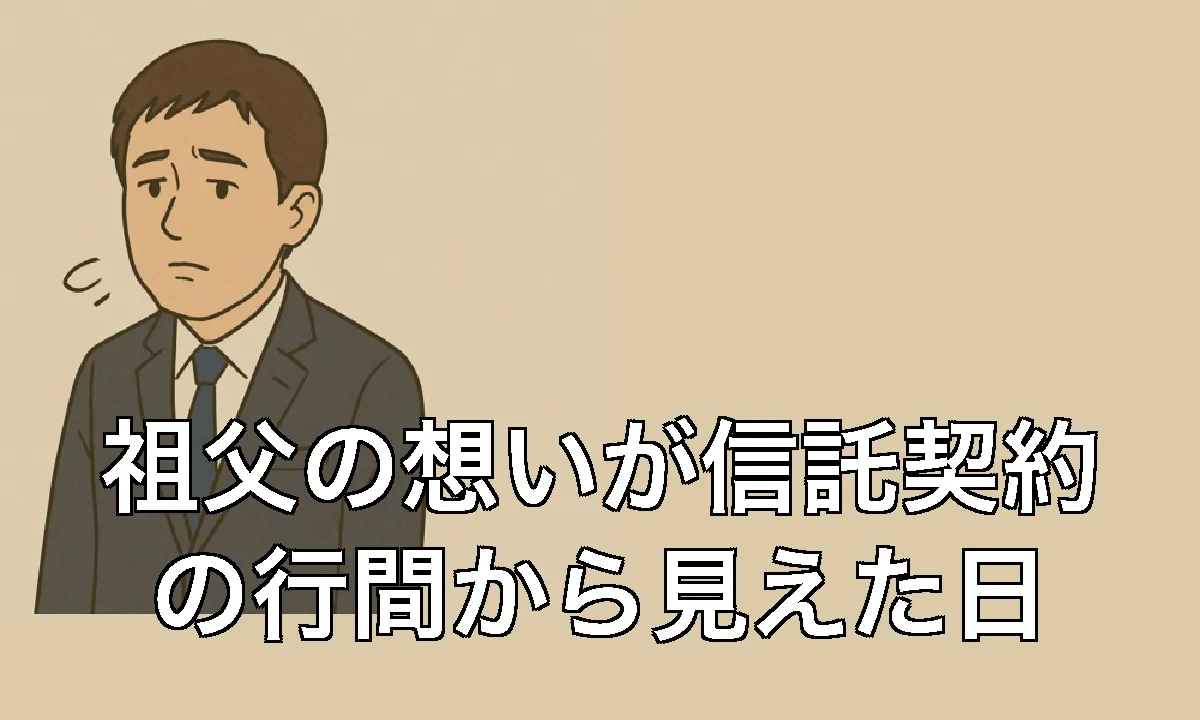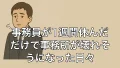なぜか胸がざわついた一通の信託契約書
その日も、いつもと変わらず事務所に書類の山が届いていた。新規案件の一つとして送られてきた信託契約書。受託者の欄に自分の名前が記載されていた時は、一瞬目を疑った。依頼者の名前は見覚えのあるもので、実家の住所が記載されていた。「まさか」と思いながら最後まで読み進めると、それが亡き祖父からの信託契約であることがわかった。司法書士としては冷静に処理すべき書類のはずなのに、手が止まり、胸の奥にざわざわとした違和感が残った。
事務的に処理するはずだったはずが
普段なら、依頼者の意向を確認し、粛々と契約内容を確認して登記へと流れる。だが今回は違った。受託者が“孫○○”と明記されていた。名字ではなく、下の名前で。そこに形式ではない意志を感じた。生前、祖父は無口な人だった。言葉で感情を表すタイプではなく、どこか距離のある存在だったが、書面のその一文から、あたたかい眼差しが浮かんでくるようだった。まるで、生前には言えなかった何かを、契約書に託してきたかのようだった。
「受託者は孫○○」の一文が意味を変えた
たかが契約、されど契約。そこに記された「孫○○」の一文は、法的な指定であると同時に、祖父が最後に残した“選択”でもあった。多くの選択肢があった中で、なぜ自分だったのか。司法書士としての能力? それとも家族としての信頼? そう考え始めると、手続きの進行よりも、心の整理の方に時間がかかってしまった。書類は黙っているのに、心の中では祖父との会話が何度も再生される。
押印の代わりに感じた重み
祖父の名前の横にある印鑑。押印の跡が少しかすれていた。おそらく体力が衰えていたのだろう。だが、そこには「ちゃんと伝えたい」という意志が感じられた。形式的に捉えれば、押印は印鑑証明と一致すれば問題はない。けれど、このときばかりは違った。印鑑の重みが、そのまま祖父の人生の重みのように感じられた。契約書を持つ手が、少し震えた。
亡き祖父の名前を前に言葉を失う
普段の業務なら、依頼者の名前は記号でしかない。だがこのときだけは違った。祖父の名前が書かれた欄を見つめながら、言葉を失った。もう話せない人の言葉を、契約書から読み取ろうとしていた。名義、財産、目的…すべてに意味を持たせたかった。こんなにも形式と心が交わる瞬間があるとは思っていなかった。
登記の実務では測れない「想いの遺し方」
司法書士の仕事は、法的に整った書類を正確に処理すること。しかしこの信託契約には、それだけでは片づけられない想いが詰まっていた。祖父がどんな気持ちでこれを書いたのか、どうしてこの内容にしたのか。実務としてではなく、個人として向き合わざるを得なかった。こんな経験は初めてだった。
過去のやり取りを思い出してしまう瞬間
祖父とは、そんなに深い会話をしてきたわけではない。ただ、小学生の頃、キャッチボールをしてくれた姿や、高校の野球部の試合に黙って見に来てくれたことを思い出した。信託契約書の文面から、そんな記憶がぶわっと蘇った。あの人は、言葉ではなく行動で示す人だった。だからこそ、この契約もまた、言葉ではない想いが込められていたのだろう。
信託契約に詰まっていた祖父の人生観
契約書はA4用紙数枚分のボリュームだが、その行間には人生があった。祖父が何を大切にしてきたか、どんな風に家族を見ていたのか。その価値観が、読み手である私にじわじわと染み込んできた。決して感情的な言葉は使われていないのに、伝わってくるものがあった。
「金は残してやらん でも考える力は残す」
財産の多くは、孫である私の将来に活用するよう信託されていたが、使い道は明記されていなかった。「必要だと思ったときに、必要な分だけ使え」とだけ書かれていた。その言葉に、祖父の人生観がにじんでいた。単に“残す”のではなく、“託す”。管理を任せるのではなく、判断も含めて任せる。これは信頼の証であると同時に、一種の試練のようにも思えた。
あの日の小言が意味を持ち始めた
「考えろ」「自分で決めろ」。中学時代から言われてきたその言葉が、うっとうしくてたまらなかった。だが今になって、その小言が信託契約書の中に形を変えて現れている気がした。祖父にしてみれば、人生の集大成としてのメッセージだったのかもしれない。ようやく、その意味を受け止められる年齢になったのだろうか。
司法書士としてではなく孫として読んだ契約書
この契約書だけは、職業としてではなく家族として向き合わざるを得なかった。手続きの流れを確認しながら、何度も感情がこみ上げてきた。冷静でなければならない立場のはずなのに、涙をこらえる時間が必要だった。こんな風に仕事と私情が交差する経験は、そうあるものではない。
残された家族への細やかな配慮
契約書には、他の家族への分配も明記されていた。そこには、祖父の目線での「家族の距離感」が見えた。特に、ある人物には一切渡さないという明確な指示があった。厳しいようでいて、そこには深い理由が隠されていた。
「特定の財産を長女には渡すな」の裏にある優しさ
祖父と長女、つまり私の伯母は生前あまり仲が良くなかった。だが、その背景には金銭トラブルや介護の問題があったことを後から知った。渡さないという選択は、憎しみではなく、伯母がさらに苦しまないようにという配慮だったのかもしれない。信託契約は、ある意味で“家族の歴史の記録”でもあった。
契約に感情を込めるという矛盾
法律上、信託契約は合理的であるべきだ。だが、今回ほど“感情”が支配する契約もなかった。記載されていないけれど、行間ににじむ感情。司法書士としての知識と経験では読みきれない「想い」の存在を、初めて知った気がする。契約の限界と、契約の可能性。その両方を思い知らされた。
司法書士という立場での複雑な感情
これまでは「仕事」と割り切っていた。でも今回はそうはいかなかった。身内の案件、それも祖父の遺志を含んだ契約書を、自分で処理するという矛盾の渦中に立たされたのだ。プロとしてどう振る舞うべきか、そして孫としてどう向き合うべきか。答えは出ないままだった。
業務としての処理と感情の整理
締切や登記のスケジュールは待ってくれない。頭では分かっているけれど、心がついていかない。処理をしながらも、祖父の姿が何度も浮かんでくる。契約の内容にチェックを入れるたび、感情がぶり返してくる。いつもはスムーズに終わる業務が、このときばかりは異様に長く感じた。
感情移入してはいけない でも無理だった
司法書士は、感情を排して法に忠実であるべき存在。でも、このときばかりは無理だった。亡き祖父の想いが書面に染みついている。読むたびに、誰にも見せなかった祖父の横顔が浮かぶ。手続きが終わってホッとした反面、これで本当に良かったのかと自問自答する気持ちも残った。
手続き完了の報告書が妙に重たかった
最終的に、登記も含めてすべてが完了し、関係者に報告書を送付した。いつもなら「業務終了」のルーチン作業に過ぎない。けれど今回は違った。封筒を閉じるとき、手が止まった。もう祖父からの仕事は来ない。その現実に、ふと孤独を感じた。
法と心のはざまで
司法書士という仕事は、法を扱う。だがそこに、人の心が関わってくることもある。祖父の信託契約は、その極端な例だった。これからも、たくさんの契約書に触れるだろう。でも、あの一通だけは、自分の中で特別な意味を持ち続けると思う。
「効力」より「遺志」をどう伝えるか
契約の本質は、法的な効力にある。だが、それだけで済まされるものでもないと実感した。「誰に」「どう渡すか」ではなく、「何を伝えたいか」。そこを汲み取れる司法書士でいたいと、少しだけ思えた自分がいた。祖父の契約が、そういう視点を与えてくれた。
ただの紙に見せない努力はできているか
どんなに正確でも、心が通っていなければ意味がない。契約書を「ただの紙」にしないためには、私たちがどれだけその背景に目を向けられるかにかかっている。祖父の信託契約は、その姿勢を問いかけてくれたのだと思う。