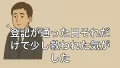朝起きた瞬間から感じる違和感
目が覚めた瞬間、「今日も一日が始まってしまった」という感情が先に出てくる日がある。司法書士という職業は、一見すると安定していて堅実な仕事に思えるかもしれない。だが、実際は神経をすり減らすような日々の連続で、目に見えないプレッシャーが常に肩にのしかかっている。そんな日常に、ふとしたことで心の糸が切れかける瞬間がある。
前の日の疲れがまったく抜けない
昨日の疲れがそのまま残っている感覚。身体が鉛のように重く、布団から抜け出すのに15分もかかった。書類チェックや電話対応、急ぎの案件処理。あれだけ頑張ったのに「今日もまだ全部終わってない」の現実が待っている。仕事に終わりがない感覚は、自信ではなく焦りと不安を生む。積み重ねた経験があるはずなのに、それを実感できる余裕すらない朝だった。
寝たはずなのに寝た気がしない理由
寝た時間だけを見れば6時間は確保した。でも夢の中でも仕事のことを考えていたような気がする。夢にまで登記の話やお客様の顔が出てくると、もはや心が休まっていない証拠だろう。目覚ましの音が鳴る前に目が覚めるときは、得をした気分ではなく、むしろ「もう少し寝たかった」という喪失感のほうが勝っていた。
疲れの正体は心の中にあった
身体の疲れだと思っていたものは、実は精神的なものだったと気づくのに時間がかかった。仕事の成果が目に見えにくく、人からの感謝もすぐには得られない仕事だからこそ、「頑張っている自分」に確信が持てなくなる。孤独な作業の中で、自分の価値を見失いそうになる。元野球部だったころのように「声を出せば仲間が応えてくれる」環境が、どれだけ自信を支えていたかを思い知らされる。
身支度をする手が止まるとき
いつもと同じルーティンのはずなのに、ある日ふと手が止まった。Yシャツにアイロンをかけている途中、動きが止まり、しばらく立ち尽くしていた。「なんのために頑張っているんだろう」と思った瞬間、心のブレーキがかかったようだった。年齢のこと、独身のこと、仕事の将来性…考えても答えが出ないことが、朝の静けさに混ざってずっしりとのしかかってくる。
鏡に映った自分を直視できない
鏡の中にいる自分がどこか他人のように感じるときがある。昔はもう少し若く見えていた気がするし、笑顔もあった気がする。だが今は、目の下のクマと眉間のシワばかりが目に入る。「なんだか疲れた顔してるな」と思ったとき、自信という言葉が一番遠く感じられた。身なりを整えるのも、自分のためではなく「最低限の礼儀」という義務感だけだった。
ネクタイすら煩わしく感じる朝
ネクタイを結ぶ手が重く感じる日がある。それは、仕事の重圧を象徴するような感覚だった。ひとつひとつの動作が「今日もやらなきゃいけないこと」としての意味しか持たなくなると、身だしなみすら苦痛になる。ネクタイをゆるめたいのは、体ではなく心なのかもしれない。そんなとき、事務員の元気な挨拶が妙にまぶしく聞こえる。
小さなミスが重なった日の午後
午前中の忙しさを乗り切り、少し落ち着いた頃にやってくる「午後の自信喪失タイム」。とくに、細かなミスが連発するときは精神的な打撃が大きい。自分では気づかないうちに疲れて集中力が落ちていたり、焦って確認を怠ってしまったり。ミスの内容以上に、それに気づいたときの自己否定感のほうが心に刺さる。
書類の抜けに気づいた瞬間
依頼人に提出する直前に、添付書類のひとつが抜けていることに気づいた。普段なら見逃さないはずの項目。すぐに差し替えはできたけれど、心の中では「なんで見落としたんだ」と自分を責める声が止まらなかった。たった一枚の紙に、積み重ねた信頼が吹き飛びそうになる感覚は、司法書士にとって最大の恐怖のひとつかもしれない。
なぜ見逃したのかという自問
あとから冷静に考えれば、時間に追われていたとか、他の案件に気を取られていたとか、理由はいくつかある。でも、その理由を並べるほどに「それでもやるべきだった」という反省が胸に残る。完璧を求めるからこそ、ミスに対する自己嫌悪は根深くなる。周囲が気づかないような小さなことでも、自分の中では大きな「失点」として残ってしまう。
事務員のため息に傷つく
何気なく漏れたため息に反応してしまう。もちろん彼女に悪気はない。こちらの焦りや苛立ちが伝わっていたのかもしれないし、単に疲れていただけかもしれない。でも、あの「はぁ…」という音に、自分への評価が含まれているように感じてしまう心の弱さがあった。「頼りないと思われたかな」「もっとしっかりしなきゃ」そんな焦燥感が、また次のミスを呼び込むという悪循環。
依頼人の反応が妙に冷たく感じる
依頼人とのやり取りで、ふとした態度や言葉が引っかかることがある。「ちょっと分かりにくいですね」と言われただけでも、自分の説明力のなさを責めたくなる。事実、分かりやすく伝える力は司法書士にとって重要だ。だけど、説明を工夫しても伝わらなかったとき、「自分には向いてないのかも」と思ってしまう。人と接する仕事は、少しの言葉で心が揺れる。
自分の話し方が悪かったのか
相手の表情が曇ったとき、まず最初に疑うのは自分の話し方。語尾の言い回し、声のトーン、タイミング。正解が分からないまま、何度も頭の中でシミュレーションしてしまう。「あの時こう言えばよかったかもしれない」という後悔が、自信を少しずつ削っていく。説明する力よりも、自分を責める力のほうが強くなってしまうのがつらい。
信頼を損ねたという焦燥
一度失った信頼は取り戻すのが難しい、というのはわかっている。だからこそ、「あの一言で信頼を失ったのでは」と思い始めると、夜まで引きずる。冷静になれば過剰反応だったかもしれないが、当事者の自分にはそれを客観視する余裕はない。信頼という不確かなものに依存しているからこそ、自信もまた不安定なままだ。
自信を失う夜の考えごと
一日を終えたはずなのに、気持ちが休まらない。夕食を食べ終えても、仕事のことが頭をよぎる。独身で家に誰もいないことが、こんなにも心を静かにしてしまうとは思わなかった。テレビの音が虚しく、スマホの通知が来ない夜は、まるで存在を忘れられたような孤独に襲われる。
テレビもスマホも虚しく感じる理由
画面に映る芸能人の笑顔や、友人たちのSNS投稿。どれも自分とは別世界の出来事に思えてくる。誰かと話したい気持ちはあるけど、自分から連絡する気力もない。たとえ返信が来ても、会話が続く自信がない。こうして、ますます閉じこもってしまう。画面の中が明るいほど、自分の部屋が余計に暗く感じられる。
誰とも話さなかった一日
依頼人や役所の人とは話したけれど、「心からの会話」は一つもなかった。事務的なやり取りばかりで、感情のこもった言葉は交わしていない。そんな日は、自分がただの処理装置のように思えてくる。言葉を交わすことで人とつながる実感が持てるのに、それがなければ心の空白は大きくなる。独り言だけが、かろうじて自分の存在を保ってくれている。
「自分って何なんだろう」と思う瞬間
ふと立ち止まって、自分という存在の意味を考えるときがある。誰かの役に立っているのか、それともただ流れ作業をこなしているだけなのか。夢や目標が遠のいていく中で、「今の自分」は何者なのかを見失いかけることがある。司法書士という肩書きが、自分を表す最後の砦のように感じられる夜だった。
昔の自分と比べてしまう癖
今の自分がふがいなく思えると、どうしても昔の自分と比べてしまう。高校時代、野球部で声を張り上げていた頃は、こんなふうに自信を失うことなんてなかった。仲間と励まし合い、悔しさを分け合いながら乗り越えてきたあの時間が、今となっては夢のようだ。あの頃は「自分はできる」と信じていた。
野球部の声が大きかった頃の記憶
あのグラウンドの土の匂い、汗まみれのユニフォーム、誰かがエラーしても皆でカバーし合った記憶。そこには「独りじゃない」という実感が確かにあった。今の仕事では、誰かに任せるわけにはいかず、失敗すればすべて自分の責任。声を出す相手すらいない世界では、あの頃のような自信は育ちにくい。
今の静けさに重なる孤独
夜、すべての音が消えたとき、胸に押し寄せてくるのは「このままでいいのか」という問いだった。答えは出ない。でも、その問いに向き合うことだけは、まだ諦めていない証かもしれない。自信は日々の小さな積み重ねから生まれるもの。明日、ほんの少しでも「今日は大丈夫だった」と思えるように、また朝を迎えるだけだ。