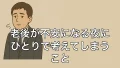朝のコーヒーが苦いだけで泣きそうになるとき
いつもの朝。コンビニで買った缶コーヒーを片手に、事務所のシャッターを開ける。何も特別なことはない。ただそれだけの日常なのに、ふと缶のコーヒーが妙に苦く感じて、「ああ今日もしんどいな」と思った瞬間、ぐっと涙が込み上げてきた。泣く理由なんてない。寝不足でもないし、大きなトラブルがあったわけでもない。けれど、じんわりと、目の奥が熱くなる。なんでこんなことで?と思いながらも、その感情が押し返せない。自分でも驚くけれど、こういう瞬間が最近増えている。
ただの疲れでは片づけられない感情の波
「疲れてるだけでしょ」なんて言われそうだけど、自分の中ではもう少し深いものだと思っている。ひとり事務所で抱える業務量、誰にも相談できない案件の重さ、事務員に気を遣いながらも余裕のない自分。そういった積み重ねが、気づかないうちに心を蝕んでいく。気づいたときには、体じゃなくて心のほうが限界を迎えていた。息を吸っても吐いても重たい。何をしていても満たされない。そんな漠然とした不安や虚無が、静かに心に溜まっている。
「誰にも頼れない」のが当たり前になる怖さ
昔はもっと仲間がいた。相談できる同期もいたし、飲みに誘ってくれる先輩もいた。でも今は、愚痴をこぼす相手すら思い浮かばない。地方に引っ込み、独立して、すべての責任を背負ったのは自分の選択だったとはいえ、頼れる誰かがいない日々は想像以上に堪える。仕事がうまく回っているときはいい。でも、何かがつまずいたとき、ひとりで耐えるのが当然になると、どこかが壊れていく。誰かに甘えたい、そう思っても、それを口に出すことすら難しい。
元野球部の自分が泣くなんてと思っていた
学生時代は、泣くなんてことはほとんどなかった。炎天下のグラウンドで泥だらけになっても、試合で負けても、悔しさはこらえて前を向くのが当たり前だった。そんな自分が、今はたかがコーヒーの苦さひとつで涙がにじむなんて。情けない、そう思いながらも、でもこれが現実だ。頑張り続けることで心の柔らかさが削れていく。気合いじゃどうにもならないことが、歳を重ねると確かにあるのだと、ようやくわかってきた。
依頼者の「ありがとう」が心に沁みすぎる理由
先日、遺産整理を終えた依頼者から「本当に助かりました」と頭を下げられた。その瞬間、不意に涙腺が緩んだ。あまりにも普通の「ありがとう」だったのに、心に突き刺さるような重さがあった。きっと、自分の頑張りを誰かに認めてもらいたかったのだ。報酬でもなく、実績でもなく、ただ「あなたがいてくれてよかった」と言われたくて仕事をしていたんだなと、そのとき気づいた。
言葉ひとつで限界がゆるむ瞬間
毎日の業務に追われる中で、精神的に張りつめていた糸が、その一言で緩むことがある。それまで我慢していたものが、一気にほどけてしまう。依頼者の言葉はときに薬になり、ときに刃にもなる。こちらがどれだけ気を張っていても、たった一言で心の状態が変わってしまうのだ。だからこそ、「ありがとう」は重い。救われたと思う瞬間と同時に、自分がどれだけ疲れていたのかを思い知らされる。
自分の存在が誰かの役に立っていたという証
司法書士の仕事は、日常の裏方だ。目立つことはないし、派手さもない。でも、誰かの不安や悩みを解決する仕事であることは間違いない。そうした日々の積み重ねの中で、自分の存在が誰かの役に立っていたと実感できることほど、救われるものはない。お金でも名誉でもない、たった一人の「ありがとう」が、心の深い部分を照らしてくれる。
でもそれがまたプレッシャーにもなる不思議
感謝されると、うれしい。それと同時に「次も期待に応えなきゃ」と思ってしまう。優しさに救われながらも、その優しさがまた鎖になる。このジレンマは、いつまで経っても慣れない。良い仕事をするほど、自分の中の基準も上がってしまい、それに応えようとする自分がさらに疲れていく。ありがとうは光でもあり、影でもある。
事務所に一人きりで感じる空虚な静けさ
夕方、事務員が帰ったあと。誰もいない事務所に一人で残って作業していると、静けさが妙に堪える。時計の音、パソコンのファンの音、自分のキーボードを打つ音だけが空間を支配する。こんなにも静かな場所で、なぜ心はこんなに騒がしいのか。ひとりきりの時間が長いほど、自分の内側にある孤独や不安と向き合わされる。
賑やかさが恋しい日々
以前は、騒がしいのが苦手だった。静かな環境のほうが落ち着くと思っていた。でも今は違う。誰かの話し声や笑い声が、無性に恋しい。賑やかさがあることで、人は自分の存在を再確認できるのかもしれない。静けさはときに、自分がこの世界に一人だけしかいないような錯覚を生む。
音がないという現実に押しつぶされそうになる
音のない空間にいると、自分の呼吸音や鼓動さえ気になる。そんな些細なことが、心を不安定にする。「あれ、自分って今ちゃんと生きてるのかな?」とさえ思う。事務所という閉じた空間で、日々の業務に追われていると、ふとした瞬間に存在の不確かさを感じてしまう。音がない、それだけで人はこんなにも不安になるのだ。
なぜか涙が出るのは弱さではなく警告かもしれない
理由もなく涙が出る。それは心が壊れたサインではなく、むしろ「これ以上頑張らないで」という心の叫びなのかもしれない。見えないところで無理をしている自分に、体が先に反応してくれているのだと、最近はそう考えるようになった。無理をしていないふりをして、限界に気づかないままでいると、本当に壊れてしまう。
心の容量がオーバーフローしているサイン
人にはそれぞれ、心のバケツの容量があると思う。コップ一杯で溢れる人もいれば、風呂桶並みに耐えられる人もいる。でも、自分の容量を超えてしまえば、どんな人でも溢れてしまう。そのとき出てくるのが、涙。自覚がないまま蓄積されたものが、何かの拍子にこぼれ落ちる。そうなってからでは遅い。もっと早く、自分の心の状態を見つめる必要がある。
悲しいから泣くのではない、という事実
涙は、悲しいから出るとは限らない。むしろ、悲しさ以外の感情が原因のことの方が多い気がする。安心、疲労、孤独、達成感、無力感――言葉にできない感情たちが、形になって現れるのが涙なのかもしれない。だからこそ、自分の涙を恥ずかしいとは思わないようにしている。ただ、自分の心が「そろそろ限界だ」と教えてくれているのだと、受け入れるようにしている。