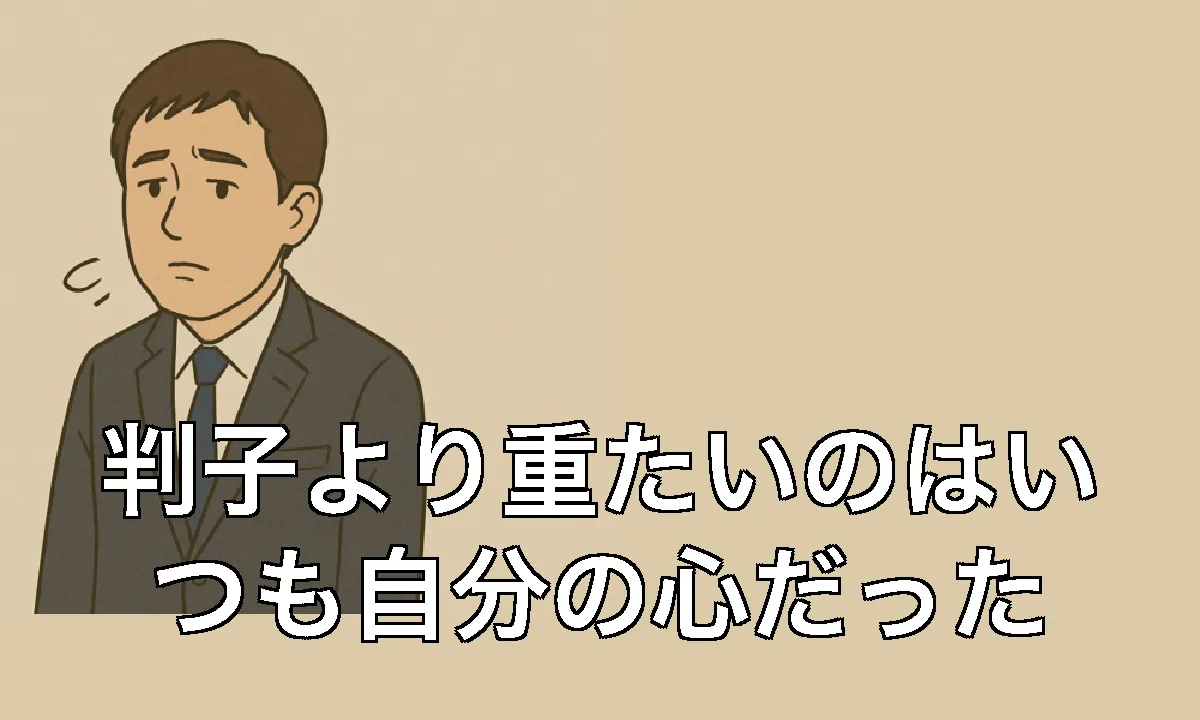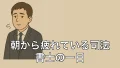押すだけのはずがこんなにしんどいなんて
書類に判子を押す。ただそれだけの作業のはずなのに、どうしてこんなにも気力を使うのか。司法書士になって20年、いまだにその「一押し」に躊躇する日がある。責任の重さだとか、訴訟リスクだとか、もちろん理屈はわかってる。でもそれだけじゃない。誰かの人生が、家族が、過去が未来が、自分の押した印で動き出すと思うと、ため息が止まらなくなる。紙の厚さは0.1ミリでも、心に乗る重さは何トンだってある。
紙に押す印鑑の重さと心のバランス
以前、役所に提出する重要な書類に印を押す際、妙に手が震えた。朝から眠りが浅く、気が立っていたのかもしれない。ちょうどその前日に、ある高齢者の成年後見申立ての話を聞いたばかりで、その内容が胸に刺さっていた。相続や売買とは違って、人生の終盤をどう過ごすかという問題。こんな心の状態で押していいのか? でも依頼人は待っている。結果として、印鑑は押した。でもその夜、布団の中で「俺の押印は、本人のためになったんだろうか」と自問し続けた。
責任を背負いすぎて肩が上がらない
元野球部だった頃、肩が上がらなくなるまでノックを受け続けた経験がある。それと少し似ている。自分ひとりの責任なら、多少の痛みも我慢できる。でも今は違う。誰かの人生に関わるというプレッシャーが、慢性的な筋肉痛のように精神にのしかかってくる。肩がこっているというよりも、「常に緊張してる肩」だ。リラックスできる時間がほとんどない。温泉に浸かっても、湯上がりに「明日あの登記の補正来るかも」と思い出すと、すべてが台無しになる。
些細な書類ミスが眠れない夜を呼ぶ
ミスって、いつも些細なんです。「フリガナが全角と半角混ざってた」とか、「印影が薄い」とか。誰も気にしないようなこと。でも法務局は見逃さないし、登記は止まる。補正通知が来ると、心拍数が跳ね上がる。夜遅くまで事務所で補正を直し、事務員には「もう帰って」と言いながら自分だけ残業。家に帰っても眠れない。布団に入っても、頭の中は「次の案件もチェックしなきゃ」「あの資料出し忘れてないか」とぐるぐる回っている。
「誰も気づかないだろう」が怖い仕事
一般の人からすると、「このぐらい大丈夫でしょ?」という感覚がある。でも司法書士の世界ではそれが命取りになる。過去に、登記簿の一部が間違っていたせいで、売買契約が白紙になった案件を見たことがある。しかもその間違いは誰も気づかないような一文字の違いだった。だけど、その一文字が誰かの人生を変えてしまうことがある。だから、「誰も気づかないだろう」と思っても、絶対に気を抜けない。それが、常に心を削ってくる。
気軽に頼まれても軽くはならない
「ちょっとだけ見てもらっていいですか?」という相談が、一番気を重くさせる。依頼じゃない。報酬も発生しない。でも内容は複雑で、重たい。頼んでくる側には悪気はないし、自分もつい「いいですよ」と言ってしまう。だけど、あとから後悔する。案件として整理されていない話を咀嚼するのは、本当に疲れる。なのに、断れない。元来の気の弱さと、「役に立ちたい」という気持ちの板挟みで、また一つ疲労が積もっていく。
「ちょっと見てほしいんだけどさ」地獄のはじまり
あるとき、知り合いの紹介で来た人が、「これ簡単な案件なんですけど」と言って一式の資料を渡してきた。開けてみたら、相続人が10人以上、しかも疎遠な人ばかりで、話が全然まとまっていない。これを無料で見てくれと言うのか…と絶句した。でも断れなかった。その夜、家でビールを飲みながら「またやっちまった」と反省。人の好意に甘える人もいるし、こっちが自分の価値を安く見積もってるのかもしれない。けど、断るのも怖いのだ。
無報酬の相談とモヤモヤの後味
無料相談って、やっぱり疲れる。報酬の話をしないままズルズルと内容に踏み込んでしまって、終わったあとに「じゃ、ありがとうございました」と軽く言われると、なんともいえない虚しさが残る。自分の頭をフル回転させて答えたのに、労力が評価されない。かといって、請求するタイミングも逃してしまっている。情けない話だけど、そういうことが何度もある。心の中で「自分って、仕事としての線引きが下手すぎる」と自責が始まる。
善意の罠にいつも引っかかる
「ちょっとだけだから」「相談だけだから」と言われると、断れない。それは、こちらが“善人であろうとする習性”にとらわれているからかもしれない。人助けしたい気持ちはある。でもそれが、自分をすり減らしていることに気づくのはいつも後になってからだ。優しさは時に、自分の首を絞める。その事実に気づいても、性格は簡単には変えられない。今日もまた、善意という名の罠に、ゆっくりとはまりにいく自分がいる。
頼られることと利用されることの境界線
この仕事をしていると、「頼られること」と「利用されること」の区別が曖昧になってくる。感謝されるときは嬉しいけれど、見返りが何もないときは、「これってただの都合のいい人じゃないか」と思う。とくに地方では人間関係が密だから、断ると角が立つ。だから断れない。頼られるたびに、自分の存在価値を感じながらも、内心では「また使われた」と思っている。その矛盾が、自分の心を少しずつ重くしていく。
誰にも相談できないまま日が暮れる
この仕事、孤独なんですよ。相談できる同業者もいないし、事務員さんには仕事の愚痴なんて言えない。自分の無能さをさらけ出すようで、怖いから。SNSに愚痴をこぼすわけにもいかず、結局は溜め込む。日が暮れても、頭の中は今日の後悔と明日の不安でいっぱい。暗い事務所の電気をひとりで消す瞬間が、一番心に堪える。ああ、今日も誰にも本音を言えなかったなと。
事務員さんには言えない疲れ
一人雇っている事務員さんには感謝している。細かい作業や電話対応など、本当に助けられている。でも、その人に愚痴をこぼすのは気が引ける。こちらが弱音を吐けば、職場の雰囲気も悪くなる気がして、結局いつも「大丈夫です、なんとかします」と言ってしまう。心の中では全然大丈夫じゃないのに、言えない。だから、自分の苦しみはいつも心の中で反芻することになる。
友達はみんな会社員になっていった
大学の同期や昔の野球部仲間は、だいたい会社員になっている。結婚して、子どもができて、ローンを組んで家を買って。自分だけが別のレールを走っている気がしてくる。自営業は自由だとよく言われるけど、自由と孤独は紙一重だ。飲みに行っても、仕事の愚痴を言い合える仲間がいない。「今日も補正きたわ〜」なんて言っても、誰もわかってくれない。だから、また黙って帰る。
独身司法書士という孤独な生態
恋愛?もう何年もしていない。合コンや婚活に行っても、職業を言うと微妙な反応をされることがある。「司法書士ってなにする人?」と聞かれ、「登記とか、相続の書類作る仕事」と説明すると、それ以上話が広がらない。そもそも忙しくて、平日に人と会う余裕なんてない。たまに早く帰れても、スマホを眺めて終わる。こうして気づけば45歳。誰かと生きるイメージが、どんどん薄くなっていく。
土日も仕事 どこで誰と出会えばいい
友人から「出会いないの?」と聞かれるけど、そもそも土日も普通に仕事してるんだから、出会いようがない。役所が平日しか開いていないから、どうしてもその分の調整が土日に食い込んでくる。事務所にいるか、現地調査してるか、どちらか。街コンなんて行っても、こっちは名刺1枚持っていくだけで精一杯。仕事が頭から離れないんだから、そりゃうまくいくわけない。
合コンより決済が優先される人生
ある土曜、合コンに誘われていたのに、午前中に急な決済が入った。断ろうかと思ったけど、お客さんが「どうしてもこの日しか時間がない」と言うので、そっちを優先。結局、合コンには行けず、誰にも文句は言われなかったけど、ふと鏡を見たとき「俺、何やってるんだろう」と虚しくなった。恋愛より仕事を選ぶ。その積み重ねが、いまの自分を作っている。
それでも今日も判子を押していく
どれだけ愚痴を言っても、結局、翌日にはまた事務所に来て判子を押す。疲れても、文句を言っても、逃げられない。だけど、そんな日々のなかでも、ふとした瞬間に報われることがある。「先生のおかげで助かりました」と言われた時、涙が出そうになるくらい嬉しい。だから、まだこの仕事をやめない。判子より重いこの心と向き合いながら、明日もまた机に向かう。
一通の感謝の手紙がくれた光
以前、相続の手続きを手伝った依頼人から、手書きの感謝状が届いたことがある。達筆で丁寧に書かれた文章に、「あなたのおかげで家族の気持ちがひとつになりました」と書かれていた。それを読んだ瞬間、ずっと張り詰めていた心が少し緩んだ。「この仕事、悪くないな」そう思えた瞬間だった。どんなに苦しくても、この手紙がある限り、きっとやっていける。
自分の価値は自分が最後に決める
司法書士の仕事は評価されにくい。成功しても、誰にも知られないことが多い。でも、自分の中で「これはいい仕事だった」と思える瞬間があれば、それでいい。周りがどう思おうと、自分自身が納得できるかどうか。それが、この仕事を続けていく支えになっている。今日もまた、誰にも知られず、誰にも評価されず、でも確かに誰かを助ける一日が終わる。