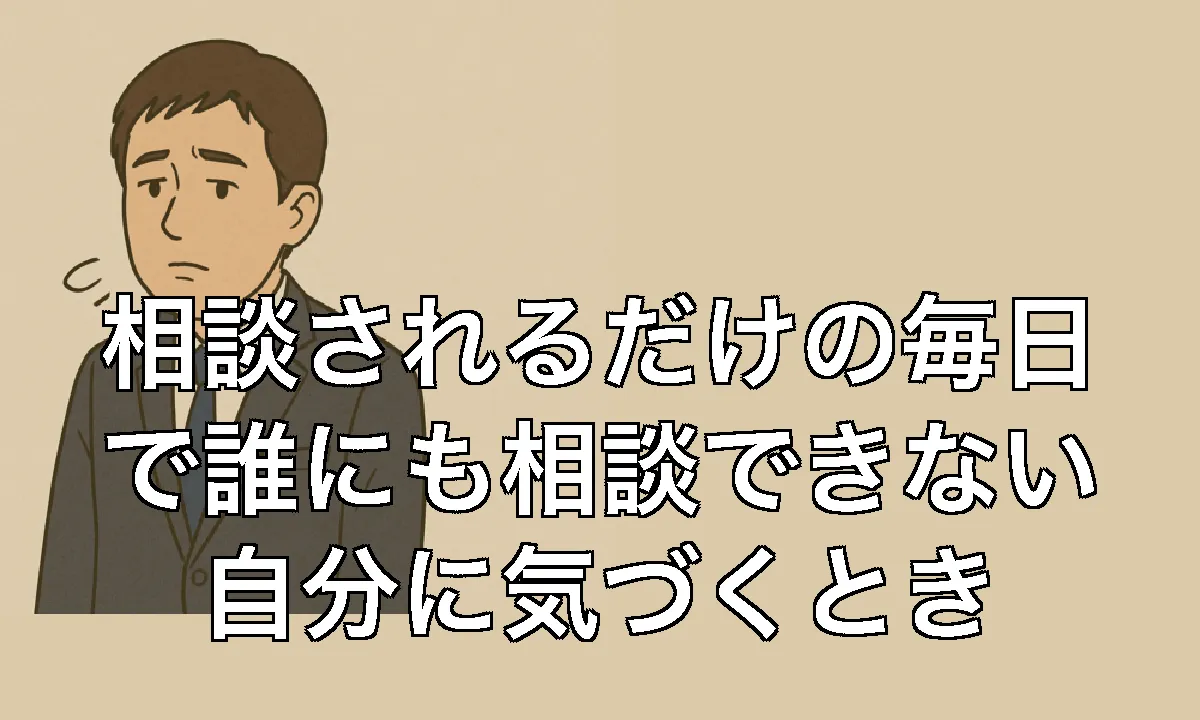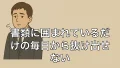いつも聞き役に回る司法書士という立場
司法書士という職業柄、人から相談を受けることは日常茶飯事です。相続、登記、借金問題。時には泣きながら語る依頼者もいます。こちらも真剣に受け止め、なんとか解決の道を一緒に探る。人の人生の節目に関わる仕事ですから、プレッシャーも重く、責任も重大。でもその一方で、「先生には話しやすいです」と言われながら、自分自身は誰にも話せないことが増えていくという矛盾。気づけば、聞き役のまま一日が終わり、自分の声をどこにも出せずにいることが増えました。
「頼られる人」は「弱音を吐けない人」になっていく
頼られることは、ある意味で誇らしいことです。「この人に聞けば何とかしてくれる」と思ってもらえるのは、プロとしての信頼を得ている証拠でしょう。でも、その裏では自分の中に「弱音を吐いてはいけない」という意識がどんどん強くなっていくのを感じます。たとえば風邪をひいても、「これくらいで休むのは情けない」と自分を責めてしまったり。いつしか人としての自然な弱さすら封じ込めて、ロボットのように働いてしまうようになるのです。
悩みを話す相手がいないまま日々が過ぎていく
たとえばこんな日がありました。朝から相続の相談が3件、昼休み返上で公証役場、午後は役所と法務局を駆け回り、帰ったら電話と書類の山。ふと時計を見るともう夜の10時。何も食べていない。誰かに「今日は疲れた」とLINEするような相手もいない。相談相手がいないというより、そもそもそんな発想すら出てこなくなっていました。誰かに話すという行為が、どこか遠いものになっていくのです。
気づけば誰にも本音を話していない
夕飯をコンビニで買って、事務所の机で一人食べながら、「なんでこんなに無言なんだろう」とふと思う瞬間があります。自分が今日一日、どんな感情でいたのかすらわからない。仕事は淡々とこなせても、心のどこかが枯れていくような感覚。同業の知り合いが飲み会で盛り上がっている様子をSNSで見ても、そこに自分が行く気力はない。誰にも嫌われていないけど、誰にも本音を話せない。そんな状態に、気づいたときはもう深みにはまっていたのです。
仕事上の相談はされるのに自分の悩みは吐けない
司法書士という肩書きがあるだけで、自然と人からの相談が集まります。法律的なことだけでなく、「こんな時どうしたらいいですか?」という人生相談まで来ることもあります。それに応えるのがこの仕事。でもふと、こんな疑問がよぎります。「じゃあ自分の悩みは、誰に相談すればいいんだ?」と。誰に聞いてもらえるのか、わからないまま、心の中で言葉が行き場を失っていくのです。
お客さんや同業者からの期待がプレッシャーになる
「あの先生なら大丈夫」「いつも冷静だよね」と言われれば言われるほど、感情を表に出せなくなっていきます。同業者同士でも、妙なプライドや競争意識があって、弱みを見せにくい。たとえば、ちょっと経営が苦しいときに「最近どうですか?」と聞かれても、「まあ、順調だよ」と無理に笑ってしまう。そうやって、自分をどんどん追い詰めていくのです。
「先生」という呼び方が心の距離を生む
司法書士という仕事についている限り、「先生」と呼ばれることは避けられません。最初は気恥ずかしさがあったけれど、今ではそれがむしろ壁になっているように感じます。先生と呼ばれることで、自分の人間味や弱さが見えにくくなり、相手からも「この人はしっかりしているから大丈夫」と思われる。それはそれでありがたいけど、心の距離はどんどん開いていくようにも感じます。
事務所の中にある静かな孤独
小さな司法書士事務所。事務員さんがいても、それぞれに忙しく、黙々と作業をしている時間が多い。話しかければ応じてくれるけれど、ふとした雑談すら憚られる空気がある。静かで効率的、でもその静けさが心に響いてくることもある。気がつけば、今日も誰とも「気持ち」の会話はしていない。そんなことがよくあります。
事務員さんとの距離感も考えてしまう
事務員さんはよく働いてくれていて、とても助かっています。でもやっぱり立場の違いがあるからこそ、何でも話すわけにはいかない。たとえば「最近ちょっと落ち込んでてさ」なんて軽く言えればいいけど、そんなことを口にしたら職場の空気が重くなる気がして、言えない。そんな気遣いの積み重ねが、ますます孤独感を強めていくのです。
昼休みもひとり 電話が鳴るのが憂鬱になることも
昼休みに一人で机に座って弁当を食べているとき、電話の着信音が鳴ると、心の中にドッと重みが走ります。「また何かトラブルかも」と身構えてしまう。昼休みも完全に休めず、いつもどこか気を張っている。かつての野球部時代、昼飯をみんなでわいわい食べていた頃が懐かしくなることもあります。今は静かすぎる。気楽すぎて、逆に寂しい。
たまには愚痴をこぼしたいと思う夜もある
「疲れた」と一言だけでも口にできたら、少し楽になるのかもしれない。だけど、誰に言えばいいのかわからないし、言ったところで解決しないことも知っている。そうやって、また黙って風呂に入って、眠れない夜を過ごす。愚痴を吐く場所がないというのは、地味だけど確実に心を蝕んでいきます。
元野球部でもホームベースには帰れない
野球をやっていた頃、ミスをしても仲間が「ドンマイ!」と笑ってくれた。ベンチがホームで、戻れば誰かが待っていてくれた。今は違う。帰る場所はあっても、心の意味での「ホーム」はない。どこかで「自分の居場所って、ここで合ってるのかな」と感じる夜もあります。プロである前に、自分もただの一人の人間だと、思い出したいのに。
独身であることと相談できないことの関係
結婚していれば、パートナーにちょっとした話を聞いてもらえるのかもしれない。もちろんそれは理想論だけど、独身でいる今、そういう心の支えがないことの寂しさは日に日に増しています。誰かに「おかえり」と言ってほしい。そう思う夜は、たぶん思っているより多い。
心を許せる誰かがいたらという空想
もし、誰かに「今日はどうだった?」と聞かれたら、たぶん話し出したら止まらないんじゃないかと思う。仕事のこと、家族のこと、体の不調、将来の不安。全部を一気に話して、笑われてもいいからスッキリしたい。そんな想像をして、「いや、そんな相手いないし」と自分に突っ込んで、何となく現実に戻ってくるのが日課です。
強がりと寂しさの間で揺れる感情
「一人でも大丈夫」「自由で気楽」そうやって自分を納得させてきたけど、本音では「やっぱり寂しい」と感じる瞬間もある。でもその寂しさを人に見せるのは、すごく勇気がいる。だからまた強がってしまう。強がれば強がるほど、どんどん自分の気持ちが遠のいていく。そんなループから抜け出す方法は、まだ見えていません。
それでも今日も誰かの役に立っている
そんなふうに、誰にも相談できないままでも、今日もまた一件の相談に応じている自分がいる。悩んでいた依頼者の顔が、ほんの少しほぐれると、「この仕事をしていてよかったな」と思える瞬間もある。孤独だけど、無意味ではない。相談される人生には、それなりの意味もあるのだと信じています。
優しさが報われる瞬間はちゃんとある
数年前、登記の手続きで何度も通った高齢の女性が、「先生のおかげで安心して引っ越しできました」と手紙をくれたことがありました。たった一通の手紙でしたが、それを今でも引き出しにしまってあります。そんな小さな報酬が、意外と支えになっていたりするんですよね。