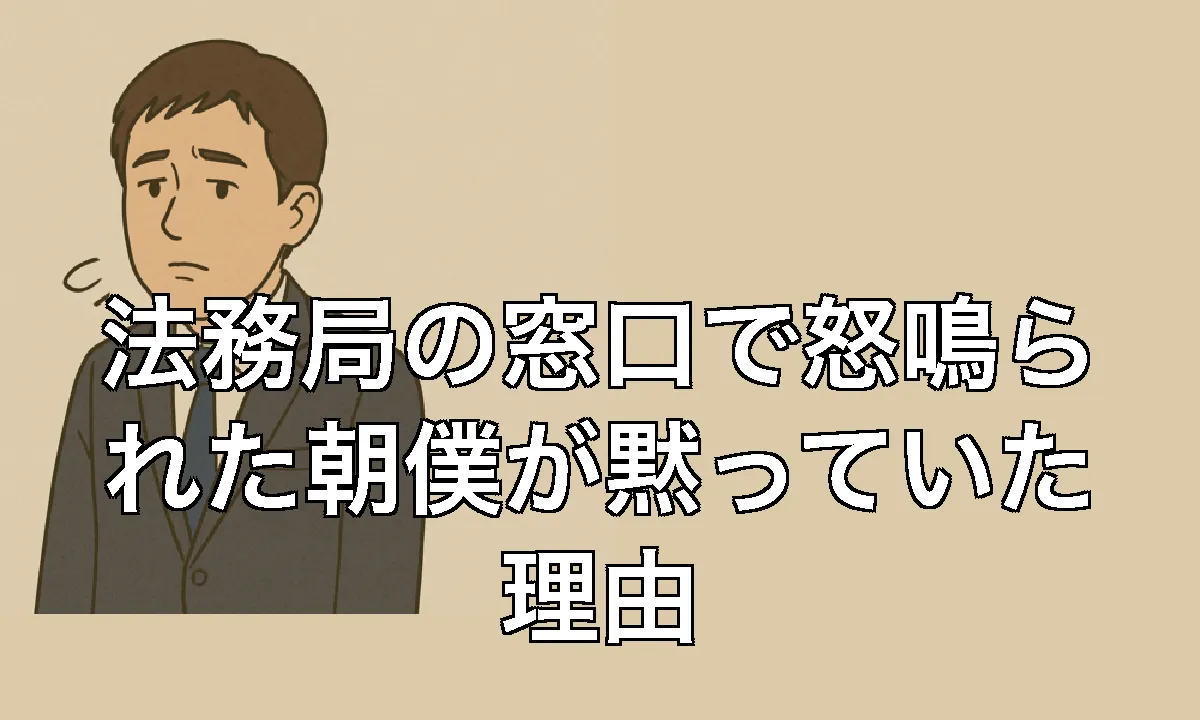朝一番の法務局で始まった最悪の一日
その日は、朝からどんより曇った空だった。天気と同じく、心の中にもどこか重たいものを感じていた。登記の確認で必要な書類を提出しに、いつもの法務局へ足を運んだ。正直、特別な気合いもなく、ただ「いつも通りに処理が進めばいい」と願っていた。でも、そんな期待はもろくも崩れ去る。受付で対応した高圧的な利用者に突然怒鳴られたのだ。「説明になってない!ちゃんと仕事してんのか!」。声の大きさに驚き、頭が真っ白になった。
怒鳴り声は予告なしに飛んできた
普段、法務局では多少イライラした対応はあっても、ここまで直接的な怒鳴り声を浴びることは滅多にない。なのに、その男は開口一番、まるで怒鳴るために来たかのような勢いでまくし立ててきた。「何回も来てるのに、こっちは分かってないってことか!」。一瞬、何のことかも分からなかった。自分の説明が不十分だったのか、それとも相手が勝手に勘違いしているのか、それを考える余裕さえも奪われた。ただ、目の前の人が明らかに怒っている、それだけが事実だった。
何が相手の地雷だったのか分からない
怒鳴られた理由を後から何度も思い返してみた。でも、結局はっきりとした原因は分からなかった。事前に確認していた書類も、案内も、通常通りだったはずだ。それでも相手には「不親切」に映ったらしい。こっちは精一杯説明したつもりでも、相手の期待に届かなければ意味がない。そんな風に責められている気がした。そして、責められることに慣れてしまっている自分に、もっと落ち込んだ。
説明になってないと言われて返せなかった言葉
本当は言いたかった。「が、それはこちらの責任ではありません」と。でも、そんな言葉は飲み込んだ。正論を返しても火に油を注ぐだけだと知っていたから。反論する気力もなかった。ただ、静かに謝り、その場を早く終わらせることだけを考えた。反射的に謝ってしまう自分にも腹が立った。けれど、それが一番平和に収まる方法なのだと、わかってしまっている自分もいた。
職員の視線と沈黙が胸に刺さる
怒鳴り声が響いたあと、周囲の職員たちは目を合わせないようにしながらも、確実にこちらを見ていた。その無言の視線が、何よりつらかった。擁護もなければ、慰めもない。ただの傍観者。たぶん彼らにとっては「よくあること」なのだろう。慣れたような無反応。それが一層、自分の無力さを際立たせた。
慣れたような顔で見てくる職員
一人の職員と目が合った。すぐに目を逸らされたけど、その瞬間の表情が妙に頭に残った。「またか」という諦めたような、冷めたような表情だった。きっとこの手のトラブルは、彼らにとって日常なのだろう。だけど、当事者になったときの痛みは、日常なんかじゃすまされない。心がざらついていくのを感じた。
また怒鳴られてる人かそんな空気に感じた
「あの人、また怒鳴られてるね」そんなふうに見られている気がした。実際に口に出されたわけじゃないけれど、空気というのはときに言葉よりも重い。司法書士という仕事は、時に専門職としての尊厳を削られる。それを改めて突きつけられた瞬間だった。
口ごたえしなかったのは弱さなのか
怒鳴られても言い返さなかった。それは弱さだったのか。それとも大人としての対応だったのか。頭では後者だと分かっていても、心は「何も言えなかった自分」を責め続ける。昔はもっと反発心があった。納得できないことには言い返していた。でも、いつの間にか「怒られ慣れ」して、感情を飲み込むことが増えていた。
怒鳴られると何も考えられなくなる
怒鳴られると、思考が止まる。冷静になろうとしても、身体が先に反応してしまう。汗がにじみ、手が震える。そういう経験は、野球部時代の鬼監督の罵声で染みついてしまったのかもしれない。だからこそ、理不尽な怒りに対しても、本能的に言葉を飲み込んでしまう。それが身についてしまった習性なのだ。
昔なら反論できたかもしれない
学生時代、もっと若かった頃なら、きっと「それは違います」と言い返していたと思う。あるいは、気まずくなってもいいから、自分の正しさを主張したかった。でも、今はその気力が残っていない。仕事の段取り、トラブル回避、後処理の面倒さ――そんなものを瞬時に計算して、口を閉じる。
けれど今は怒らない選択をしてしまう
怒鳴り返すことは簡単だった。でも、その後の自分を考えると、怒らない方を選んでしまう。怒ることで誰かが得をするわけでもない。結局、一人で感情を処理して、いつものように黙々と働くしかない。そんな日々が続くと、どこかで何かが壊れていく。
未来の自分が笑えるように書き残す
こうして文章に残すことには、ほんの少しの救いがある。今日怒鳴られたことも、沈黙してしまったことも、自分の弱さも、書いてしまえば整理される気がする。きっと未来の自分がこれを読み返したとき、少しだけ笑ってくれるんじゃないかと思うのだ。「こんな日もあったけど、よくやってたよ」と。