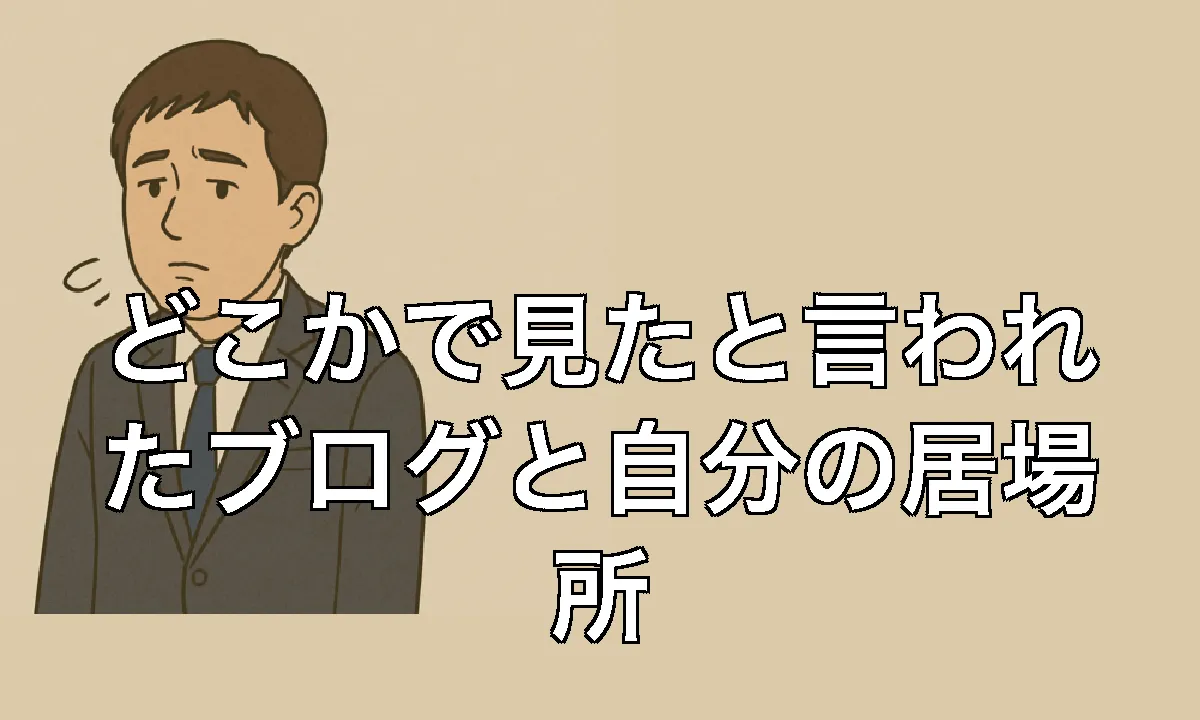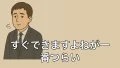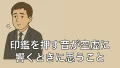言われた一言が引っかかって仕方ない
「あれ、このブログ、どこかで見たことある気がする」。そんな何気ない一言が、胸に刺さって抜けなかった。自分なりに言葉を選び、時間をかけて書いたつもりだったのに、誰かのコピーのように思われたのだろうかと疑心暗鬼になる。似たような内容のブログは世の中に山ほどあるし、情報が被るのは仕方がないことかもしれない。それでも「見たことある」と言われたとき、まるで自分の存在そのものが否定されたような気がして、情けなくなった。たかがブログ、されどブログ。地味で報われにくいこの仕事の中で、少しでも自分らしくありたかったのかもしれない。
どこかで見たってどういう意味だろう
「どこかで見た」という言葉の意味は、本当にいろいろだと思う。良い意味で「印象的だった」ということかもしれないし、悪い意味で「また似たような内容か」と言われているのかもしれない。どちらにせよ、はっきりと意図が分からない言葉ほど、人を悩ませるものはない。特に、自分の中にある「独自性」を大事にしていると、ちょっとした類似点を指摘されるだけで、自信がぐらついてしまう。SNSやブログには、そんな曖昧で雑な反応が山のようにあるけれど、まさか自分の書いたものがそれに埋もれているとは思いたくなかった。
オリジナリティって何なんだろうと考え始めた
「オリジナリティって何なんだろう?」そう思い始めたのは、ブログに限らず仕事でも感じる疑問だった。登記の手続きや相談対応でも、「前の事務所ではこう言われました」とか「それってネットに書いてました」と言われることがある。じゃあ自分の仕事って何だ? どこに価値がある?と思う。情報が溢れすぎた時代、司法書士としての自分らしさって、何をもって証明できるのだろう。真面目にやっていても、それが「どこかで見たような対応」なら、意味がないんだろうか。
被ってしまうのは罪なのか
どうしても内容が被ってしまうことはある。それは仕方のないことだと思っている。そもそも法律や登記の制度には決まったルールがあるから、似たような説明になるのは当然だ。でも、それを「他でも見た」と言われると、まるで罪を犯したかのような気持ちになるのは不思議だ。誰かの真似をした覚えもないし、むしろ自分の言葉で届けようとしている。それなのに、独自性を否定されると、自分の存在まで否定されたような気になるのは、きっと日頃の孤独と向き合っているからだろう。
ブログを書き始めたのは誰かとつながりたかったから
地方の小さな司法書士事務所で、たった一人の事務員と毎日こなしていく日々。誰とも会話せずに終わる日もある。そんな日々の中で、誰かに自分の存在を知ってほしくて始めたのがこのブログだった。仕事の知識を発信するつもりが、気がつけば日々の出来事や、自分の思いまで綴るようになっていた。正直、読んでもらえなくてもいい。ただ、誰かがふと立ち寄ってくれて、「ああ、この人も頑張ってるんだな」と思ってくれたら、それだけで救われる気がした。
一人の事務所での孤独と会話のない日常
誰かと顔を合わせる機会が減った。手続きは郵送やオンラインで済むようになり、電話すらかかってこない日もある。そんな中で、事務所の空気は静まり返っていて、事務員さんも最低限の業務をこなしたら黙ってパソコンに向かっている。自分が何か間違ったんじゃないかと不安になったりもする。誰かと話すことすら億劫になる日もあれば、話したくてたまらない日もある。そんな矛盾した気持ちをどう処理したらいいか、いまだによくわからない。
野球部の頃の仲間と比べてしまう今
昔の野球部時代は、毎日がにぎやかだった。怒鳴られても、仲間がいた。汗まみれになっても、分かち合う相手がいた。今は、成功も失敗も、自分の中で処理しなければならない。誰にも弱音を吐けないし、言っても理解されない。あの頃は、何気ない会話や冗談がどれほど支えになっていたか、今になって痛感する。誰かと一緒に頑張るって、こんなにも心強いことだったのかと、ブログを書きながら思い出す。
声をかけられないまま過ぎていく日々
コンビニで買い物しても、誰かとすれ違っても、挨拶すら交わさないことが増えた。元々そんなに社交的な方ではないけれど、今は本当に声を出す機会が少なくなってしまった。誰かに話しかけたくても、変に思われたらどうしようとか、余計なことを考えてしまう。独身でいることを責めるわけじゃないけど、やっぱり誰かと一緒に笑える時間があればいいのにな、と思う瞬間がある。ブログだけが、そんな気持ちを正直に書ける場所になっている。
言葉の奥にある本当の不安に気づく
「どこかで見た」と言われて落ち込んだ自分。でも、その裏にあるのは、自分自身の不安だったのだと思う。誰かと違っていたい、でも孤独にはなりたくない。そんな矛盾した思いを抱えながら、ブログを書いていたことに気づいた。誰かに響いてほしい、でも比べられたくない。そんなわがままを抱えていたのは、きっと自分だけじゃないはずだ。
似てるって言葉の裏にある嫉妬や共感
実は、「似てるね」と言われた人も、自分に何かを感じ取っていたのかもしれない。嫉妬だったり、共感だったり。同じような立場で頑張っている人ほど、つい他人の言葉が気になるものだ。自分もそうだ。他の司法書士さんのブログやSNSを見ては、「自分より上手いな」とか「この人はうまくやってるな」と思ってしまう。だからこそ、同じように見られることに、不安と期待が入り混じってしまうのだろう。
誰かも同じように悩んでいるかもしれない
たぶん、ブログを書いている他の司法書士さんも、同じように言葉を選び、迷いながら更新しているんじゃないかと思う。似てると思われないか、反応がもらえるか、誰かを傷つけていないか。小さな事務所で一人戦っている自分たちは、孤独を感じやすい。でも、その孤独をほんの少しでも埋められるのが、こういうブログやコラムなのかもしれない。
自分の言葉で書き続ける理由を見つけた
どんなに誰かと似ていても、自分の経験や思いは、自分だけのものだ。誰かと被っても、自分が感じたことを書けば、それはもうオリジナルだと思えるようになってきた。誰かのために書くのではなく、自分自身が生きてきた証として、言葉を残していく。それが、いまの自分にとっての意味になっている。
それでも届いている実感があった瞬間
ある日、見知らぬ方から「ブログ読んでます」と言われた。驚きと共に、心から嬉しかった。その一言で、今までの迷いや不安が少しだけ溶けた気がした。誰かに届くというのは、こういうことなんだと実感できた。たった一人でも、その人の中に自分の言葉が残るなら、それで十分なんだと思えた瞬間だった。
誰かにとってのちょうどいい言葉になれたかもしれない
何かを専門的に説明するわけでもなく、役立つ情報ばかりでもない。それでも、誰かが「なんとなく安心した」と思ってくれたなら、それだけで書く意味はあると思う。司法書士だからこそ見える景色、独身であることの寂しさ、地方での孤独。そんなものに価値があるとは思っていなかったけれど、言葉にしたことで誰かの“ちょうどいい”になれたなら、それは大きな意味を持つ。
司法書士という立場で書く意味
法律の専門家である前に、一人の人間としての声を出す。それが、いまの時代に求められていることなのかもしれない。誰よりも近くで依頼者の人生と向き合っているからこそ、感じることがある。だからこそ、自分の言葉で、自分のリズムで書いていく。それがきっと、これからの司法書士に必要なことだと思っている。
誰かに届くまで続けてみようと思えた夜
「どこかで見た」と言われてもいい。似てると言われても、それでも、自分の言葉で書いていこう。今日も誰かが、同じように孤独と戦っているかもしれないから。ブログを書くことが、自分自身の居場所になっている限り、誰かに届くその日まで、続けてみようと思う。