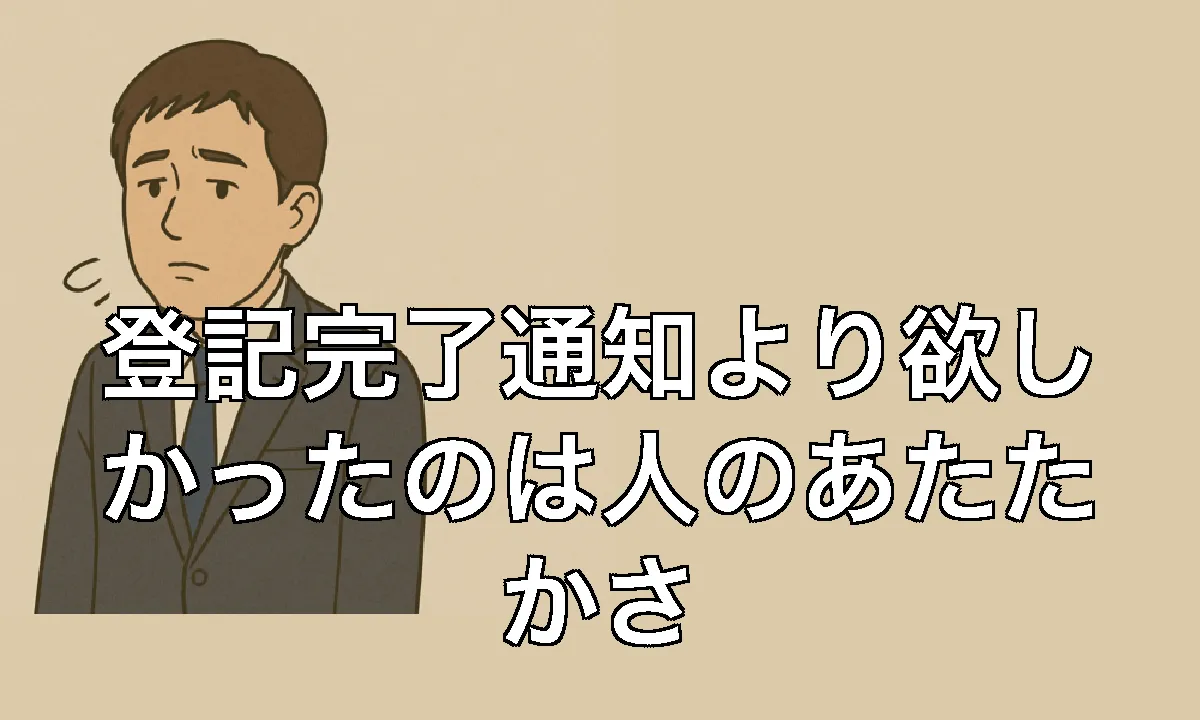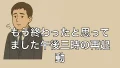登記完了通知が届いても心は晴れない日がある
「登記終わりました」と、システムから自動で発行される完了通知。それをクライアントに送信するたびに、なぜかぽっかりとした空しさが胸をよぎる。法務局からの通知書は確かに大切な書類で、仕事の一区切りでもある。それなのに、そこに“完了感”はあっても“達成感”がないのはどうしてだろうか。いつからか、この仕事が「処理」になってしまった気がしてならない。そんな感情を誰にも伝えられず、今日も一人、送信ボタンを押している。
仕事は順調なのに、なぜか虚しさだけが残る
登記が無事に終わり、報酬も入る。事務員もきちんと動いてくれている。外から見れば何の問題もない司法書士事務所だ。だが、内心では「これでよかったのか」と考えてしまう。たとえば、住宅購入の登記。人生の大イベントのはずなのに、こちらが送るのは定型メールとPDFだけ。相手からも「ありがとうございました」より「確認しました」の一言で終わることが多い。こちらは必死で段取りし、登記ミスのプレッシャーとも戦ってきたのに、たったそれだけかと落胆する瞬間がある。
完了通知がただの「作業報告」に見えてしまう瞬間
完了通知というのは、本来喜ばれるべき知らせだ。しかし、実際には感情のこもらない“事務連絡”として扱われることが多い。とくに電子申請が主流になってからは、受け取る側も「メールが来たな」程度の反応で済ませてしまう。あるとき、深夜までかかって仕上げた案件を朝一番で送信したが、返信は「了解」の一言だけだった。その瞬間、自分の仕事って本当に意味があるんだろうか、と心が沈んだ。人とのやりとりが、ただの通知で終わるのは、なんとも味気ない。
クライアントの人生の節目に立ち会っているはずなのに
登記は不動産や相続など、人の人生の節目と深く関わる業務だ。だからこそ、その場面に少しでも寄り添いたいという思いがある。だが現実は、慌ただしく手続きを進めるうちに、気づけば「事務処理係」になってしまっている。たとえば、新築住宅の登記を終えたとき、本来なら「おめでとうございます」の一言くらい添えたい。でも時間がなく、定型文で済ませてしまう。自分の優しさを犠牲にしてまで、業務をこなしている気がして、それがまたつらい。
ありがとうの言葉が聞きたかっただけかもしれない
別に褒めてほしいわけではない。ただ一言、「ありがとう」「助かりました」と言ってもらえたら、それだけでどれだけ報われることか。司法書士という仕事は、結果が「当たり前」と思われがちだ。登記がうまくいって当然、遅れれば責任追及。そんな空気の中で、誰かがこちらの努力を見てくれていたと感じる瞬間は、ほとんどない。だけど、だからこそその一言の力は計り知れない。感謝がほしいなんて、我ながら小さい人間だと思う。でも、やっぱりほしいのだ。
感謝のひと言が、どれほど救いになるか
一度だけ、依頼人の年配の女性から丁寧なお礼の手紙をもらったことがある。便箋に、手書きで「先生にお願いして本当によかった」と書かれていた。その紙切れ一枚で、疲れがふっと消えた気がした。その手紙はいまも机の引き出しに大事にしまってある。感謝の言葉は、人の心に火を灯す。高額な報酬でも、高評価レビューでもない。何気ない、でも真心のこもった「ありがとう」。その言葉が、この仕事を続ける支えになる。
「早く終わらせてくれて当然」そんな空気が辛い
最近は特にスピード重視の傾向が強く、「まだですか?」と急かされることも多い。迅速な対応はプロとして当然だとは思っている。でも、まるで宅配便のように「早く終わって当たり前」な感覚で接されると、こちらも心が疲弊する。登記には確認作業や法的判断が必要で、雑には扱えない仕事だ。それなのに、まるでスイッチ一つで終わるように考えられている現状に、心が擦り減っていく。
昔の仕事には、もっと人の匂いがあった
昔はもっと依頼人と顔を合わせて話す時間があった。たとえそれが短い時間でも、笑いがあったり、世間話があったり、人間らしいやり取りがあった。今はコロナの影響もあって、リモートで完結することが多くなり、そういう温もりがなくなってしまった。確かに効率は上がったが、心が置き去りにされている。あの頃の雑談こそが、自分にとっては大切な仕事の一部だったのだと、今になって痛感している。
孤独な机に向かいながら思い出す野球部の仲間
一人で静まり返った事務所の机に座っていると、ふと高校時代の野球部を思い出す。仲間と声を出し合い、励まし合いながら白球を追っていたあの頃。苦しい練習でも孤独ではなかった。今は違う。誰とも言葉を交わさず、PCの前で黙々と申請書を作っている。誰かと喜びを分かち合う場面が、めっきり減ってしまった。あの声を掛け合う感覚を、仕事でもう一度味わえたら、きっとこんなに孤独じゃないのにな。
声を掛け合うことの大切さを、なぜ忘れてしまうのか
「おつかれ」「ありがとう」そんな簡単な言葉を交わすだけで、人間関係はずいぶん変わるはずだ。けれど、業務に追われていると、そうした一言すら省略してしまいがちだ。特に一人事務所では、声を出す機会そのものが少ない。だからこそ、自分から意識して言葉を出さなければと思う。あの頃の野球部のように、声を掛け合うことが人を支える。司法書士として、まずは自分がその姿勢を忘れないようにしたい。
書類ではなく心を扱う仕事であると信じていた
司法書士になった頃、私は書類の処理だけでなく、人の人生に寄り添う仕事だと思っていた。実際、そういう場面もあった。でも、年数が経つにつれて、いつの間にか「書類を早く正確に処理する人」になっていた気がする。それが大切な業務であることは否定しない。ただ、人の人生に関わることの意味を見失いたくはないのだ。心が通う仕事をしたい。その気持ちは、今も私の中にある。
いつの間にか「作業」に追われてしまった現実
依頼件数が増えるにつれ、効率を追い求めるようになった。メールはテンプレート、やり取りは最小限。気づけば、心の通わない処理屋になっていた。事務員の前でも、笑顔が減ったと言われた。忙しいのは事実だが、自分が失っているものにも、そろそろ気づかないといけないのかもしれない。少しだけ手を止めて、「この人はどんな思いでこの依頼をしてきたのか」を想像する。それだけで、仕事の意味が少し変わってくる気がしている。
司法書士という仕事に、あたたかさを取り戻したい
仕事に追われ、感情を削って生きる日々の中で、それでも私はあたたかさを求めている。司法書士という仕事には、もっと人間らしさがあっていい。たった一言の感謝、一つの笑顔があれば、それだけで報われることもある。効率化が進んでも、心だけは機械にしてはいけない。どんなに孤独を感じても、「あたたかい仕事だった」と言えるように、今日もまた、目の前の依頼に向き合っている。
効率では測れない「人とのやり取り」の価値
スピードや正確さはもちろん大切だ。でも、依頼人が安心できること、納得できること、そして信頼してくれること。それらは数字では測れない価値だ。だからこそ、心ある対応を忘れてはいけないと思う。目の前にいる一人の人間を大切にする。その積み重ねが、司法書士という仕事の誇りにつながると、私は信じている。
自分自身が人に優しくすることを忘れずにいたい
どんなに疲れていても、誰かに優しくされたいなら、まず自分から優しくするべきだと、最近思うようになった。事務員に対しても、依頼人に対しても、そして自分自身にも。無理に明るく振る舞う必要はないけれど、小さな気配りや言葉ひとつで、空気は変わる。自分の心に少し余白を持つこと。その意識が、少しずつ職場にあたたかさを取り戻すきっかけになると信じている。
誰かの小さな感謝を受け取る日を信じて
すぐに何かが変わるわけじゃない。でも、今日も一人の依頼人に丁寧に接すること、それだけで何かが少し動く気がする。もしかしたらいつか、「先生に頼んでよかった」と言ってくれる誰かに出会えるかもしれない。その日のために、今日も地味で報われにくい仕事を重ねていく。完了通知の代わりに、誰かの心の中に何かが残る。そんな仕事ができたら、それが本当の“完了”なのかもしれない。