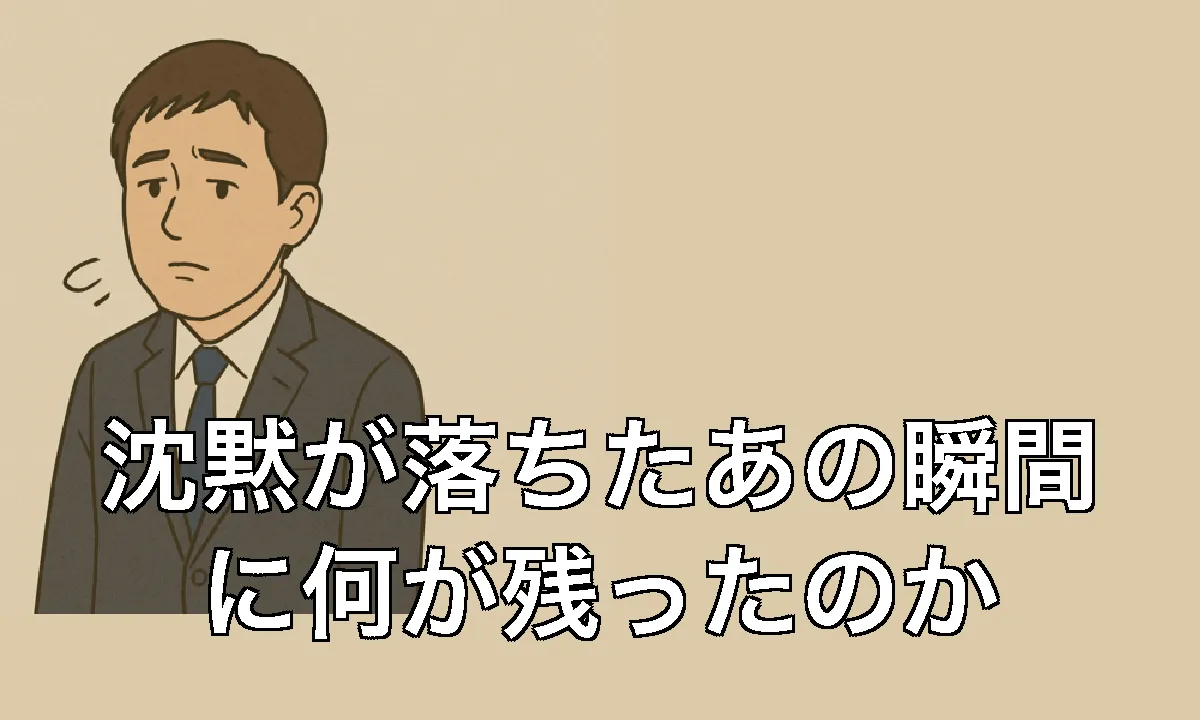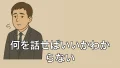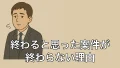終わったはずの話し合いに残るもの
「以上で説明は終わりです」そう言った瞬間、部屋に訪れたのは静寂でした。事務員との簡単な打ち合わせだったのに、なぜか空気が重い。話し合いは終わったのに、終わっていないような…そんな感覚。司法書士という職業は、業務上の説明が終われば「はい」で済むことが多い。でも、時々その「はい」の後に続く沈黙が、妙に心に引っかかる時があります。たった数秒でも、その沈黙には言葉より重いものが含まれている気がしてならないのです。
静まり返る空間に漂う違和感
たとえば、相続登記の打ち合わせ後、遺族の方が一言も発せず帰ろうとした時がありました。形式的には何の問題もなく手続きの説明は終えていたのに、その「静けさ」が違和感として残ったんです。たぶん、こちらが法律上のことだけを伝えて終わらせてしまったから、感情の置き場を失わせてしまったんでしょう。空気はピリついてない。でも、重い。それは、心の中に浮かんでいた「これで本当にいいのか?」という問いを、誰も口にできなかったからだと思います。
言葉よりも重たい沈黙の正体
司法書士の仕事は、説明責任があっても感情のフォローまでは義務じゃない。だけど、「説明を受けた人の沈黙」って、何か言いたいのに言えない、もしくは、もう言っても無駄だとあきらめたときに起きることが多い。それは、怒りでも失望でもなく、無関心でもない。むしろ、心のどこかでまだ何かを求めている。でも、それを伝える手段がわからないから沈黙になる。そう考えると、あの静けさは単なる無言ではなく、複雑な感情の塊なんだと気づかされます。
それでも誰も口を開かなかった理由
なぜ誰も言葉を発しなかったのか。それは、私自身が「これ以上触れてはいけない」と感じてしまったからかもしれません。変に掘り下げて地雷を踏んでもいけないし、時間も限られている。結果、黙って流してしまう。それが続くと、まるで仕事が「事務処理」になってしまうんです。言葉にできないことに触れるのは怖い。でも、その怖さに蓋をしてしまうと、何か大事なものを見失うような気がしています。
結論が出たのに納得できない心
表面的には「結論が出た」という形になる話し合いも、心の中までは整理できていないことがあります。特に不動産の名義変更や遺産分割の場面では、法的な手続き以上に感情の処理が必要になる場合がある。でも私たちはそこに踏み込む立場ではない。だから、説明が終わると一瞬の沈黙が訪れる。その瞬間、「ああ、これは納得じゃなくて妥協だな」と気づくことがあるんです。
「はい、わかりました」の裏にある本音
以前、兄弟間の相続争いの末、長男が手続きを一任する形になった案件がありました。弟の方は黙って座っていて、「はい」と一言だけ返して帰っていきました。その「はい」の重みがずっと胸に残っています。本当は納得していない。でも、空気を読んで飲み込んだ。私にはそれがわかったからこそ、手続きを進めるたびに胸の奥がざわつく感覚がありました。言葉にしてくれたら楽なのに、言えないことの方が多い。司法書士って、そういう「言えない」を横目に業務をこなしていく職業なのかもしれません。
自分だけが違う方向を見ているような感覚
そういう時、自分だけが別の方向を見ているような孤独感を覚えることがあります。相手は家族の関係や過去の積み重ねを背景に考えていて、私は法律と手続きの筋を見ている。同じテーブルにいるのに、全然違う景色を見ているような感覚。それが、「沈黙」という形であらわれることもあるんです。だからこそ、自分の言葉が届いていない気がして、妙に虚しさが残るんでしょうね。
司法書士という仕事と沈黙の距離
司法書士という仕事は、実務の正確さと効率が求められる一方で、人の人生の節目に立ち会うことも多い仕事です。そこには感情が付きまといます。でも、感情には触れず、形式的に淡々と進めることが良しとされる。この「業務の論理」と「人間の情」のズレこそが、沈黙を生む温床になっているのかもしれません。
事実を伝えることと、気持ちを置き去りにすること
事実だけを伝える。それは司法書士として正しい姿勢です。でも、正しさだけで人の気持ちは動きません。とくに、相続や離婚、借金の整理など人生のしんどい局面に関わるとき、単なる情報提供では心がついてこない。話し合いが終わって沈黙が訪れた時、「あ、置いてきぼりにしてしまったな」と感じることがある。そのとき私は、自分が“ただの手続き屋”になってしまったことを少し悔しく思うんです。
登記完了の報告に返ってくる「ふーん」
書類が完成して登記が無事終わったことを電話で伝えると、時々「ふーん、わかりました」と気の抜けたような返事が返ってくることがあります。努力してまとめた仕事なのに、報われた感じがしない。相手にとっては終わって当然のこと。けれどこちらとしては、見えないところでたくさんの調整や確認を重ねている。そこで返ってくる一言が「ふーん」だと、どっと疲れが出ることもあるんですよね。
黙って受け止めるしかない場面ばかり
こちらの思いが伝わらなくても、誤解されても、基本的には黙って受け止めるしかありません。言い返したくなる時もあるし、「もっと分かってよ」と叫びたくなることもある。でも、そういう感情は全部飲み込む。沈黙って、実はそういう“飲み込んだ感情の堆積”なんじゃないかと思うことがあります。
誰かが何かを言ってくれたなら
あの時、誰かが一言でも言葉を発してくれていたら――そう思うことは何度もあります。でも、結局は誰も言わなかった。私も含めて。なぜなのか。答えは簡単ではありませんが、その背景にあるのは「壊したくない空気」と「期待しすぎた自分」なんだろうと思っています。
沈黙を破るのが怖いのはなぜか
「何か言わなきゃいけない」と思いながらも、変に空気を壊すのが怖くて黙ってしまう。そんな場面が何度もあります。特に、立場の違う人たちの前では、一言の重みが違う。沈黙を破ることが、その場を支配してしまう危険性を含んでいるから、自然と「このままでいいか」となってしまうんです。でもそれって、本当に「このままでいい」のか。自問自答は続きます。
無責任な一言の破壊力
一度だけ、軽く「それで納得されてるんですか?」と聞いたことがあります。完全に地雷でした。依頼人の顔が一瞬で曇り、その後の関係もぎこちなくなった。沈黙を破るには覚悟がいるし、破り方を間違えると関係性が壊れる。だから、結局は無難に黙る方が正解になってしまう。なんだか、もどかしいですね。
それでも言葉を選んでしまう自分
私は結局、いつも言葉を選びます。そして選びきれず、何も言わないことも多い。気を遣いすぎて、核心に触れられない。でも、それがこの仕事なのかもしれないとも思います。言葉を尽くすより、黙って受け止める。それが求められる場面が多すぎて、逆に言葉が不器用になってしまった気もしています。
それでも前に進むしかないという現実
どんなに沈黙が重くても、どんなに虚しさが残っても、仕事は進んでいくし、日常は止まってくれません。結局、誰かがやらないといけない。私がその役回りになっているだけ。そう思って、今日も机に向かいます。
独身のまま迎えた今という日常
45歳、独身、地方で事務所経営。モテた記憶もないし、今さら恋愛も面倒くさい。でも時々、誰かと話したくなる夜があります。事務員さんは気を遣ってくれるけど、やっぱり本音までは話せない。だから、沈黙と一緒に過ごす時間が増えていく。それでも、文句を言いながらも、続けている。仕事が自分の一部になってしまったからかもしれません。
野球部時代のチームプレーと今の孤独
昔は野球部で、仲間と声をかけ合いながらプレーしていました。あのときの「声」は、励ましでもあり、支えでもありました。今は違います。誰かとチームを組むというより、一人で投げて、一人で捕っているような感覚。声がないから、自分の心の声を聞きながら仕事をしています。でも、やっぱりあの「掛け声」が恋しくなることもあります。
愚痴は出るけど投げ出せない理由
毎日、「もうやめたいな」と何度も思います。でも、やめられない。お客さんが待っているし、事務員さんの生活も背負っているし、何よりこの場所で積み上げたものを、そう簡単に手放せない。愚痴ばっかりだけど、それでも踏ん張っている自分が、ちょっとだけ誇らしいような気もしています。