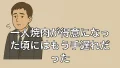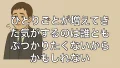毎日のように繰り返す言葉がある
「印鑑ください」。これ、もう口癖になっているんじゃないかと、自分で怖くなるときがある。朝の挨拶よりも先にこのセリフが出てしまうのが日常で、誰かと顔を合わせるたび、無意識に口から出てしまう。それだけ、司法書士の仕事では「印鑑」という存在が中心にある。だけどそれが、もう何年も同じセリフを繰り返していると思うと、少しむなしくなる。昨日も今日も明日も、「印鑑ください」と何度言うんだろう。そもそもこのセリフがない日は、来るのだろうか。
朝の一言目が印鑑ください
事務所に入って一番最初に交わす言葉が「おはようございます」じゃない日が、もう何日あっただろう。封筒の束を片手に、郵送書類のチェックをしながら「ここに印鑑お願いします」って言ってる自分に気づく。目が覚めきってなくても、体はその作業を覚えてるんだからすごい。だけど同時に、これって本当に人間らしい働き方なのか?とふと疑問にもなる。
眠気より先に口をつくルーティン
朝、コーヒーより先に手が伸びるのは朱肉と印鑑マット。事務員さんより少し早く来た日なんかは、ひとりで印鑑押してるうちに「あれ、今日って何曜日だっけ?」ってなる。眠い頭のまま、ただ書類と向き合って、押す、押す、押す。この繰り返しに、いつからか感情が乗らなくなっていたことに気づく。
おはようより先に出るこのセリフ
「おはようございます」の代わりに「印鑑、ここお願いします」と声をかけてしまう自分が嫌になる日もある。人と人とのやりとりなのに、最初の言葉が事務的すぎて、ふと孤独を感じてしまう。「機械じゃないんだから」と思いつつ、それでもやることは山積みで、気づけばまた「印鑑ください」と言っている。
業務の中心は印鑑の確認と押印
結局、登記手続きでも契約書の処理でも、最終的には「ちゃんと印鑑があるか」のチェックに戻ってくる。これが抜けていたら全部無効になる可能性があるし、それを防ぐために目を光らせる。だけど、そこにかかるエネルギーがどれだけ大きいか、外からはなかなか見えない。
本人確認も終えたのにまだ印鑑
何重にも確認して、身分証も写しを取って、委任状もちゃんと揃っていても、最後に「印鑑がなかったので再度お願いします」と言わなきゃいけない時の徒労感は大きい。「あれだけ準備したのに…」と心の中でがっくり肩を落とすけど、顔には出せない。今日も一歩ずつ、確実に前に進むしかないのだ。
効率化と信頼の狭間で
印鑑というものは、効率化とは真逆の存在かもしれない。電子署名が普及してきたとはいえ、まだまだ実務では紙とハンコが主役。お客様にとっては「ちゃんと押してある」ことで安心感を持ってもらえるけど、内心は「これ、本当に要るのか?」と自問自答する場面も多い。
印鑑くださいの裏にあるもの
何気なく口にする「印鑑ください」の一言には、いろんな感情が潜んでいる。事務所内であれ、外出先であれ、その一言の裏には、自分が求める責任と信頼のバランスがある。軽く聞こえるかもしれないけど、実はけっこう神経を使っている。
確認してもらうことのストレス
「ここに印鑑ください」ってお願いするたび、相手の反応をうかがってしまう。機嫌が悪そうなときや、忙しそうなときは特に気を遣う。こっちもやりたくてやってるわけじゃないけど、必要だから頼むしかない。その繰り返しに、少しずつ心が削れていく。
事務員さんに頼むときの気まずさ
うちの事務員さんはとても真面目でよく働いてくれる。でも、毎日のように「ここ押して」と渡すたび、申し訳なさもある。たまに「またですか…」と苦笑されると、余計に言いづらくなってしまう。とはいえ、やらなければいけないから頼む。これが地味に精神的な負荷になる。
お客さんに求める時の無力感
登記の立ち合いや契約の場で、お客さんに印鑑をお願いする時のあの空気。緊張していたり、急いでいたり、印鑑を忘れてきていたり。こちらは一応プロとして冷静に対応するけど、内心は「今このタイミングでそれか…」と動揺している。笑顔を作りながら、冷や汗をかく瞬間だ。
ハンコがもたらす安心と不安
「印鑑があるから安心」と言われることがある。確かに形式としての完了感はある。でも一方で、押してさえあれば本当に大丈夫なのか?という不安もつきまとう。書類の本質や内容の理解より、ハンコがあるかどうかが優先されている現状に、違和感を覚えることがある。
押印さえあれば大丈夫という空気
特に高齢のお客様に多いが、「ハンコ押せば終わり」と信じている方も多い。中身を読まずに、黙って押す人すらいる。こちらとしては、内容を理解して納得した上で押してほしいと思うのだが、そううまくはいかない。形式が信頼されすぎているのも、考えものだ。
間違っていたら誰が責任を取るのか
もしも書類の内容にミスがあっても、印鑑が押されていたら手続きは進んでしまう。そして後から「違ってました」となると、その責任の所在が問題になる。それを未然に防ぐために何重にも確認し、念を押し、それでもまた「印鑑ください」と言わなければならない。
印鑑にまつわる笑えないエピソード
「印鑑ください」と言うだけのシンプルな行為に、実はいろんなドラマがある。中には笑い話にならない、心底疲れる出来事もある。あれもこれも、記憶にこびりついて離れない。
違う場所に押された印影の悲劇
たとえば、重要な書類に限って、印を押す位置を間違えてくるお客さんがいる。よりによって原本に、しかも訂正できない欄にドンッと押されていた日には、頭を抱える。再度取り直し、説明し直し、郵送し直し…。あの瞬間は笑えない。
訂正印の連鎖で原本が修羅場に
一度間違えると、訂正印を何個も押すことになる。それで見た目もグチャグチャ、第三者が見たら「これで本当に大丈夫なのか」と思うような書類になってしまうこともある。内容は正しいのに、印象だけで不信感を抱かれてしまう。それがまたつらい。
押し忘れと戻ってくるお客様
完璧だと思って渡した書類に、実は一か所押し忘れがあって、もう一度お客様に来てもらう。お客様に謝りながらも、自分の中では「チェックしたはずなのに」と悔やんでいる。人間だもの、ミスはある。でもそれが毎日のように積み重なると、やっぱりつらい。
あと一個だけのリターンマッチ
「あと一個だけなんです」と言いながら、再訪してくれたお客様を見ると、申し訳なさでいっぱいになる。でもそこで「大丈夫ですよ、よくあることですから」と言ってもらえると、心が少し救われる。そしてまた明日も、「印鑑ください」と言ってしまう自分がいる。
誰のための印鑑なのかを考える
毎日繰り返すこの言葉に、時々意味を問いたくなる。「これは誰のために押してるんだろう」と。自分のため?お客様のため?制度のため?それともただの形式?そう考える時間があるだけ、まだ心が動いている証拠かもしれない。
紙文化と電子化のはざまで
最近では電子契約も増えてきて、ハンコがいらない手続きも出てきた。でもまだ地方では、特に高齢者を相手にする場面では、紙と印鑑が絶対的な存在。デジタルとアナログの狭間で、揺れ動く自分がいる。
電子契約もやっぱりハンコ文化の壁
オンラインで完結できる便利さを説明しても、「紙のほうが安心する」「ハンコがないと不安」と言われることは多い。結局、形式が人を安心させている。でもその安心は、誰かの手間の上に成り立っている。
自分が頼む側であり守る側でもある
「印鑑ください」と言うたび、自分が責任の一端を背負っていることを感じる。その一押しが、未来に残る文書になる。だから軽く扱えないし、頼む側としても気を抜けない。結局、守るために頼んでいる。
信頼とは印鑑だけで測れないもの
本当に信頼されているかどうかは、印鑑の数じゃない。どんなにハンコをもらっても、相手との関係が築けていなければ意味がない。「印鑑ください」は、その裏にある信頼関係の確認でもある。そう思って、今日もまた、お願いするのだ。