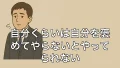押すだけのはずなのに気持ちが沈むとき
書類に判子を押す。そんな作業、一日の中で何度も繰り返す。事務所の机の引き出しにある、あの朱肉と一緒に置かれた小さな認印。でもある日、その「押す」という行為がやけに重たく感じた。事務員が帰ったあと、ひとり残って最後の書類にポンと印を押す瞬間、ふと「誰かに押してほしい」と思ってしまったのだ。自分で決めて、自分で押して、自分で送る――それが司法書士の仕事で、独立開業している身の当たり前。でも、孤独が滲む瞬間は、こんなところにも潜んでいる。
判子に込められたものは重い
ひとつの判子には、責任や決断や時には覚悟が詰まっている。「押したからには引き返せない」なんて大げさに思えるかもしれないが、司法書士にとっての一印は、それくらいの重さがあるのだ。間違って押せば業務上の大きなミスになるし、後々トラブルになれば説明責任も伴う。たかが印鑑、されど印鑑。そう思えば思うほど、なぜか押す手が止まる日もある。
単なる業務なのに妙に孤独を感じる
クライアントとのやりとりが終わり、書類が整ったら、あとは自分の仕事。仕上げに印を押して終わり。でも、仕上げるその瞬間が、なぜこんなに寂しいのか。昔は同じ事務所で数人の仲間と働いていたこともあったが、独立してからというもの、誰かと一緒に判子を押す機会なんてほとんどない。どこかで「誰かと共有したい」と思っている自分がいる。
責任を伴う印鑑の重圧
「この一押しが、登記の流れを決める」と思うと、緊張する。慣れた仕事もある。でも、たまに起こる特殊案件や、ギリギリで調整が入るケースなど、「これ本当に大丈夫かな」と心のどこかで疑ってしまう時がある。そんなとき、誰かに「大丈夫ですよ」と背中を押してほしい。だけど結局、判子を押すのは自分一人だ。これが個人事業主のリアル。
誰かに頼れたら楽になるのに
「人に任せるのが苦手なんです」と言えば聞こえはいいけれど、実際は自分が信じ切れていないだけなのかもしれない。仕事の性質上、どうしても最終確認は自分が行うことが多く、その分孤独もつきまとう。「ここ、確認しておいてください」と言って、安心して任せられる人がいたらどれだけ助かるか。だけど現実は、そう簡単じゃない。
一人事務所の限界点
事務員は一人。しかも、彼女には家庭があるので、急な残業を頼むのは難しい。自分の確認ミスを防ぐために、深夜まで書類とにらめっこすることもある。ミスは許されない世界だからこそ、全部を自分で見直す。その結果、「ああ、誰かに見てほしい」「一緒に押してくれよ」なんて、心の中で独り言をつぶやいてしまう夜もある。
事務員に任せきれないもどかしさ
事務員さんはよくやってくれている。本当に感謝している。だけど、「ここまでは任せられるけど、ここから先は…」という一線がある。その線を超えるには、法的な知識と経験が必要になる。何かあったときの責任は自分に返ってくるからこそ、最後のところはいつも自分で抱えてしまう。その結果、精神的な荷物だけが増えていく。
「代わりに押してくれよ」と心の中でつぶやいた
ある日、書類が山積みになった夕方、ふと「誰か代わりに押してくれよ…」と口に出してしまった。事務所には自分ひとり。誰にも聞かれていない。でも、そんな言葉が漏れるくらいには、疲れていたし、寂しかった。別に甘えたいわけじゃない。ただ、「ここにもう一人いれば」と思う瞬間があるだけなんだ。
元野球部の癖に甘え下手な自分
高校時代、野球部のキャプテンだった。声も大きかったし、後輩の面倒を見るのも好きだった。でも、それが裏目に出たのか、「頼る」ことに罪悪感を覚えるようになった。自分で背負うのが当たり前。そう育ってきたせいか、大人になってからも「助けて」と言えないまま、ずっときてしまった。
頼るのが下手なまま歳をとった
気がつけば45歳。相談できる同業の仲間もいるけれど、こんな小さな愚痴を言える関係性ってなかなかない。「なんか今日は押すのがしんどくてさ」なんて言ったところで、笑われるのがオチだろうと、自分で勝手に思い込んでいる。その結果、また判子を見つめる夜が増えていく。
強がりが自分を苦しめる
「俺は大丈夫」そうやって自分に言い聞かせてきた。でも、本当はそうじゃないことくらい、自分が一番よく知ってる。疲れているし、弱音も吐きたい。だけど吐いたところで何も変わらない。そう思ってしまう自分が、一番厄介だ。だからこそ、判子を押すたびに「これでいいのか?」と揺れる。
独身のまま司法書士を続けるということ
家庭がないから自由でいいじゃないか――そう言われることもある。でも、本当にそうか? 仕事の愚痴を聞いてくれる相手もいなければ、仕事終わりに温かいごはんが待っているわけでもない。結局、家に帰ってテレビをつけて、コンビニの弁当を食べて、寝るだけの毎日。それが日常になっている。
家庭がないことの業務への影響
仕事の相談ができる相手がいないというのは、地味にキツい。同業者との情報交換もある。でも、どこか本音では話せない部分が残る。「ああ、これ、話せる人が家にいれば違ったかな」と思う瞬間は正直ある。独身だからといって自由なわけではない。むしろ、自分の世界に閉じこもってしまいやすいのだ。
休めない責任感と孤独のバランス
「自分がやらなければ誰もやってくれない」そんなプレッシャーがある。事務員に任せきれない部分があるからこそ、休むことに強い罪悪感がある。結果的に、体調が悪くても出勤し、頭が回らない日でも判子を押す。それが「仕事」だと言ってしまえばそれまでだが、そんな働き方が心身にいいわけがない。
この仕事の孤独に耐えられる日と、そうでない日
司法書士として生きるということは、ある意味で「孤独を受け入れる」ことなのかもしれない。でも、その孤独に耐えられる日もあれば、どうしようもなく心が折れそうになる日もある。そんな日には、この小さな判子がやけに大きく見える。
判子一つでぐらつく心
日々の業務はルーチン化しているはずなのに、ある日突然、押す手が止まる。「これでいいのか?」と自問してしまう自分がいる。それは書類の内容に問題があるわけではない。自分の気持ちが、ふと不安になっただけなのだ。そんな揺れもまた、ひとりで抱えなければならない。
予定調和が崩れた瞬間の揺れ
クライアントから突然の連絡、思わぬ書類のミス、体調不良。そんな「予定外」が一つでも起きると、普段の安定が一気に崩れる。そしてその波が、判子を押す瞬間にまで影響を与える。「これで本当に大丈夫か?」そんな問いが、頭の中を巡る。その不安は、誰にも打ち明けられない。
ちょっとしたことで限界がくる
ペンがインク切れだったとか、コピー機の紙詰まりが直らなかったとか、ほんの些細なこと。だけど、そんな小さなトラブルが、限界に近づいている自分には大きくのしかかる。涙が出るほど悔しいわけでもない。ただ、「もう無理だな」と思ってしまう。そのタイミングで、判子を押す手が止まるのだ。
それでも仕事を続ける理由
こんなにしんどいのに、どうしてやめないのか。たぶん、それは誰かの役に立っていると実感できるからだと思う。登記が完了して「ありがとうございます」と言ってもらえるとき、ほんの少しだけ、自分の存在価値を感じられる。それがある限り、自分はきっと今日も判子を押すのだ。
誰かのためになっているという感覚
面倒な案件もある。理不尽なクレームもある。けれど、その中に「助かった」と言ってくれる人がいると、すべてが報われるような気がする。それが自己満足だと言われたって構わない。誰かの役に立つために、自分はここにいる。それを信じて、今日もまた朱肉に判子を押している。
愚痴を吐いても辞めない自分
ネガティブなことばかり考えてしまう日もある。文句ばかり言ってしまうこともある。でも、それでも辞めないのは、この仕事に、少しは自分なりの意味を見出しているからだろう。誰かにこの判子を託せたなら…そう思う夜はある。けれど、今はまだ、この手で押し続ける覚悟を、捨てきれていない。