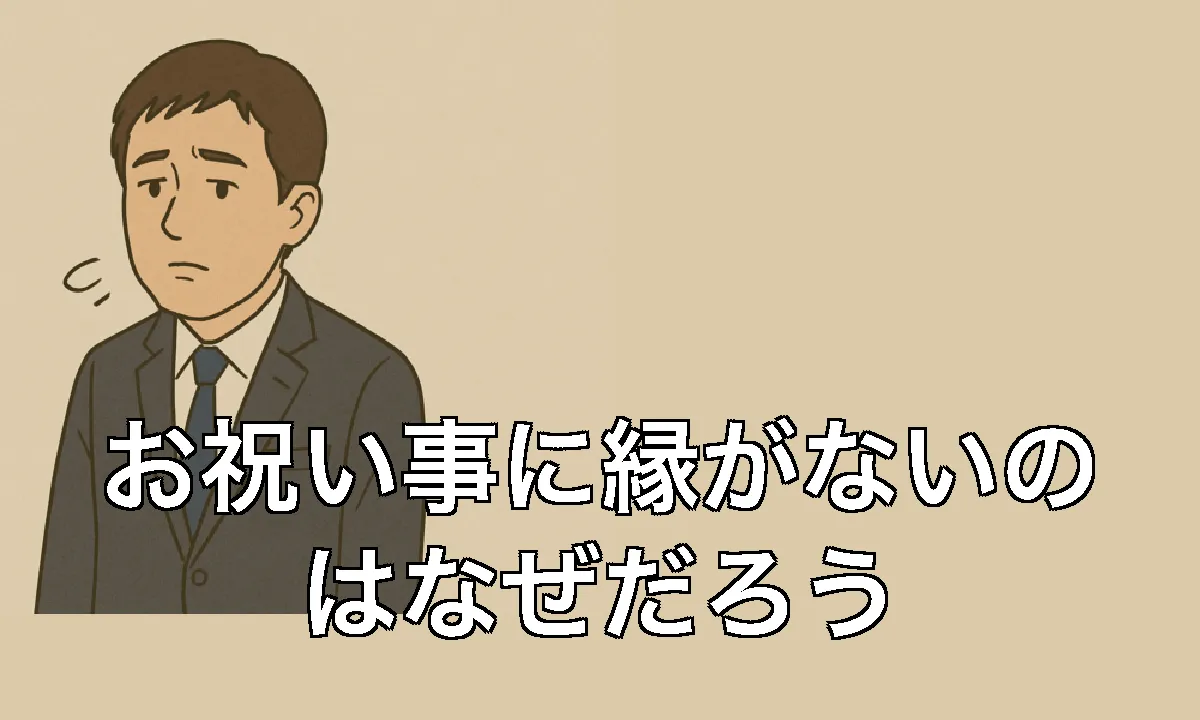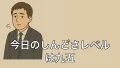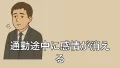祝われる側になった記憶がない
「おめでとう」と言われたことが、人生で何回あっただろう。そんなことを考える夜がある。学生時代も、社会に出てからも、祝われる瞬間はなぜかいつも他人のものだった。誰もが主役になる場面はある。でも、自分だけはその輪の外にいるような気がしてならない。そんな心の距離感が、司法書士という職業の選択にも影響していたのかもしれない。
小さな頃からなぜか主役になれなかった
幼少期、親戚が集まる正月の席でも、ケーキが出るのは従兄の誕生日だけ。自分の誕生日には集まりすらなかった。学校では運動会や発表会があっても、注目されるのは声の大きい子か成績優秀な子。私はどちらでもなかった。野球部でさえ、エースや4番を陰で支えるだけの存在。目立ちたくないわけじゃないのに、結果的に「地味な子」で終わる。祝福の言葉が自分に向けられることはほとんどなかった。
誕生日会は「誰かのついで」だった
誕生日が近い友人がいて、毎年合同で祝われるのが恒例になっていた。でも、ケーキに書かれる名前はいつもその子が先。プレゼントも、主役扱いも、その子が中心で、私は「おまけ」だった。今思えば些細なことだけれど、子どもにとっては大事なことだったのだ。自分だけが主役になる日がないまま大人になり、それが当たり前になっていた。
表彰や拍手と無縁の学生時代
通知表は可もなく不可もなく。運動会でもリレーの補欠止まり。表彰台に立つどころか、拍手をもらった記憶すらない。先生にも特別気に入られるわけでもなく、家庭でも特別に褒められることはなかった。努力しても、その評価は誰かの影に隠れてしまう。そんな学生生活を繰り返していくうちに、「祝われること」は他人事になっていった。
社会人になっても変わらない扱い
就職しても、配属されるのは裏方の部署ばかり。花形の仕事には縁がない。祝勝会や昇進パーティーのような華やかな場面には呼ばれず、机で残業してる間にみんなは宴席へ。自分だけが祝われないというより、「気づかれていない」のかもしれない。司法書士として独立した今でも、その状況はさほど変わらない。
お祝いのLINEは来ないのに業務連絡だけ来る
誕生日当日、朝からLINEの通知が鳴る。期待する自分がいた。けれど開けてみれば、「至急この書類確認してください」とか「いつまでに登記完了できますか?」といった業務連絡ばかり。自分の存在は、仕事の用件の中にしかないような気がする。たった一言、「おめでとうございます」が欲しいだけなのに、それが一番遠い言葉になっている。
開業しても誰にも祝われなかった午後
司法書士として独立した日、本当は誰かに祝ってほしかった。開業届を出して、事務所の看板を掲げて、それで終わり。誰からも花も電報も届かず、静かすぎる午後だった。事務所にひとり座っていた時、「なんでこんなに孤独なんだろう」と思った。達成感よりも寂しさのほうが大きかったのが、今でも忘れられない。
お祝い事から遠ざかる理由を考えてみた
なぜ自分はお祝い事に縁がないのか。そう考えたとき、単なる運の問題だけではないと気づく。むしろ、自分自身の態度や生き方が関係しているのではないか。祝福されるには、ある程度の「関わり合い」や「存在の表明」が必要なのに、自分はそれを避けてきた節がある。
人付き合いを避けてきたツケかもしれない
学生時代、クラスの飲み会やイベントに積極的に参加するタイプではなかった。社会人になっても、飲み会はできるだけ断り、同僚との交流も最小限。誰かと深くつながることを避けてきた。だからこそ、自分の節目を「祝う相手」がいないのも当然なのかもしれない。結局、祝われるというのは人と関係を築いた先にあるご褒美なのだ。
「誘われたら行く」の姿勢では届かない祝福
よく言えば謙虚、悪く言えば受け身。それが私の人付き合いのスタイルだった。「誘われたら行くよ」と言いながら、自分からは決して声をかけない。そんな姿勢では、相手も祝おうという気にはなれないのだろう。祝福は、受け取るだけのものじゃない。日頃の関係性の積み重ねがあってこそ届くものなのだと、今更ながら思う。
自分の気配を消して働いてきた結果か
司法書士としての仕事は、目立たず正確に、が基本。だからこそ、自分の存在を表に出すことに慎重になりすぎたのかもしれない。目立たないことで信頼は得られるが、それは「感情の共有」とは違う。仕事は完璧でも、人としての印象が薄ければ、祝う理由も見つけづらいのかもしれない。
「目立たない努力」は評価されにくい
登記ミスをしない、期限を守る、書類をきれいにまとめる。そんな日々の積み重ねは、評価されにくい。問題が起きないことが前提だからだ。失敗しないように神経を張り詰めていても、それは祝われる理由にはならない。むしろ「当たり前」としてスルーされる。祝われるには、時には少し目立ってみることも必要なのかもしれない。
司法書士という職業がもつ距離感
司法書士という仕事は、誰かの節目に立ち会うことが多い。相続、会社設立、不動産売買。つまり、人が祝われるタイミングに立ち会っているのに、自分自身はその外にいる。お祝いの裏側を支える存在として、どうしても自分が主役になる機会は少ない。これは職業上の宿命のようなものかもしれない。
感情よりも正確さを求められる日々
司法書士の仕事に求められるのは、感情ではなく正確さ。どれだけ丁寧に接しても、登記が間違っていれば意味がない。逆に、無愛想でも仕事が早ければ感謝される。そんな中で、人としての温かさよりも「結果」がすべてになる。そこに祝福や感動を求めるのは、少しズレているのかもしれない。
感謝より「早くやってくれ」が多い職場
登記の依頼を受けると、まず聞かれるのは「どれくらいで終わりますか?」。ありがとうよりも先に、納期が問われる。祝われるどころか、感謝すら後回しになることも多い。それが積み重なると、「お祝い」なんて別世界の話に感じてくる。仕事に感情を持ち込まないようにしてきた代償かもしれない。
誰かの人生の節目を見届けるだけの仕事
登記や契約が完了した瞬間、依頼者にとっては「人生の節目」になる。でも私は、その書類を淡々と処理して次の案件に向かう。まるで、式の後片付けだけを担当するスタッフのような存在だ。主役を祝うための裏方に徹するのが私の仕事。だからこそ、自分の節目が訪れても、それを祝ってくれる人がいないのは、当然なのかもしれない。
自分の感情はいつも後回しにしてしまう
他人のために、常に冷静でいることを求められる。それが当たり前になりすぎて、自分の喜怒哀楽を出すタイミングを失ってしまった。お祝い事に縁がないのは、誰も祝ってくれないからではなく、祝ってもらえるような振る舞いを、自分自身が避けているのかもしれない。そう気づいても、もう笑ってごまかすしかないのだ。