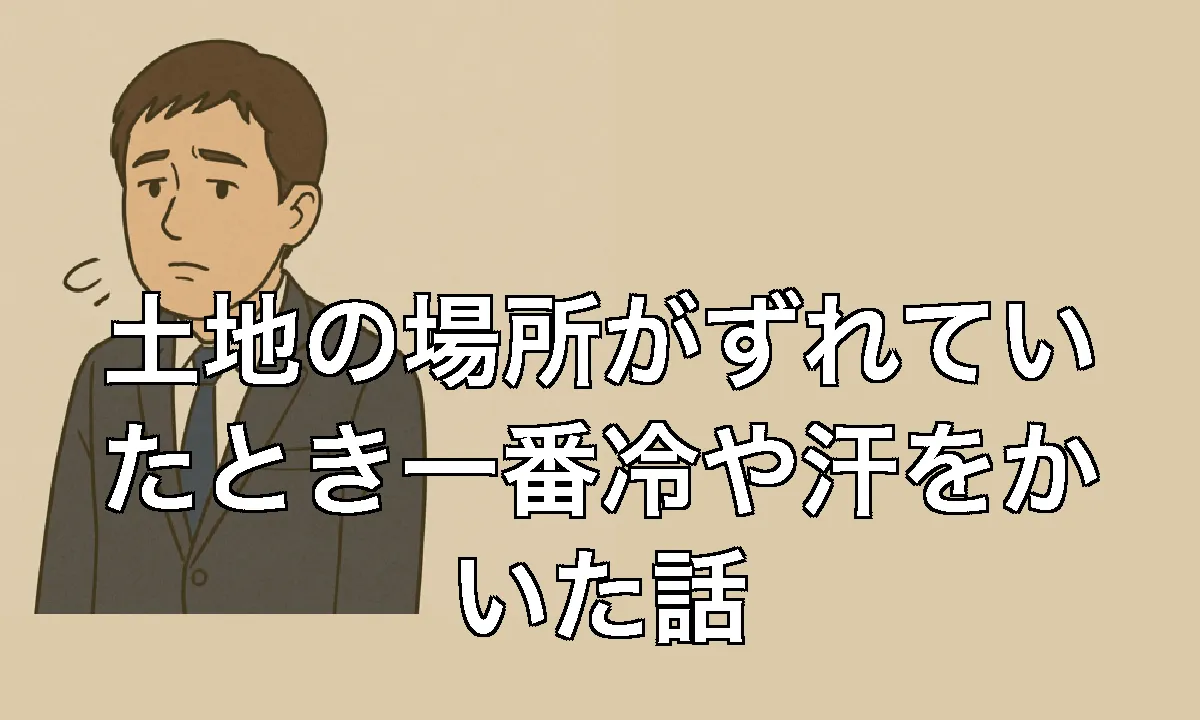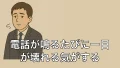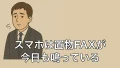土地の場所がずれていたとき一番冷や汗をかいた話
何かおかしいと気づいたのは境界杭の位置だった
あの日も普通の立ち会い業務のつもりだった。依頼された土地の境界確認に立ち会うべく、現地に出向いたのは初夏の午前中。汗ばむ陽気の中、測量士さんと地主さん、隣地の方が立ち並ぶなかで、私の頭の中は「ただのルーチンだろう」と油断していた。だが、杭の位置を確認した瞬間に、明らかな違和感を覚えた。公図の境界線と現地の杭の位置が、どう見ても一致していないのだ。あれ?これ…ズレてないか?そんな疑念が頭をよぎり、じわりと背中に汗がにじんだ。
現地と公図が合わない違和感
図面と現地のズレというのは、正直なところ、珍しい話ではない。昔の測量技術が粗かったり、古い公図に頼っている場合は特にそうだ。しかし、このときは違った。ズレが致命的だった。隣地の庭に食い込むような形で、自分の依頼人の土地が記されていたのだ。いやいや、これは冗談では済まされないぞ。私は慌てて法務局の写しをもう一度確認したが、そこに書かれていた地番と図面は、やはり“正しく”ズレていた。つまり、誰かが間違えたという話ではなく、最初から間違っていた。これが一番タチが悪い。
立ち会いのときの空気の重さ
立ち会いの空気が一気に凍りついたのを覚えている。地主さんは眉間にシワを寄せ、隣地の方は「こっちが境界だってずっと言ってたんだ」と言わんばかりの顔で腕を組んでいる。測量士さんが淡々と状況を説明するものの、誰の言葉も空回りしていた。まるで全員が「これは誰の責任だ?」と探り合っているようだった。私の心の中では、「頼むからこの場が早く終わってくれ」と何度も祈るような気持ちだった。だが現実はそう甘くなかった。
お隣さんの視線が一番こたえた
一番こたえたのは、隣地の方の視線だった。あの、無言の圧力というか、「あんた、司法書士でしょ?」という無言の圧を全身で浴びたあの瞬間。私は正直、心が折れかけた。こちらに落ち度はない。だが、そんなことは関係ない。立ってるだけで“責任ある立場”に見えるのが司法書士というものだ。その日以来、私は立ち会いの日はいつもより30分早く現場に行くようになった。現地確認は慎重すぎるほど慎重にするようになった。
誰が間違えたのかを突き止める作業
現場での違和感が確信に変わった後は、ひたすら書類とにらめっこだ。登記簿、公図、地積測量図、昔の謄本、固定資産税台帳…とにかく掘って掘って掘りまくる。誰が、いつ、どうやってこの番号を書き違えたのか。それとも、最初から番号の振り方自体がおかしかったのか。そういう検証をしていく作業は、まるでパズルのピースを探しているようで、正直しんどい。仕事としてやるには神経をすり減らすにもほどがある。
過去の資料はやっぱり信用できない
こんなことを言うのはどうかと思うけど、過去の資料って、信用できないことが多い。たとえば明治期の公図なんかは、手書きだし縮尺もいい加減。昭和に書き直された公図ですら、筆のクセがそのままズレになって残っていたりする。だから、古い資料に振り回されると本当に時間を食うし、精神的にもきつい。資料が多ければ多いほど、間違いも蓄積してる。それを見抜くのが仕事だけど、こっちも人間だから限界はある。
法務局も間違うんです
たまに依頼者から「法務局の図面だから正確でしょ?」なんて言われるけど、そんなことはない。法務局だって人間が作業しているし、昔は手作業だった。そりゃあミスもある。問題は、そのミスが数十年後に私たちのところに“爆弾”として飛んでくること。ある意味、司法書士って爆弾処理班みたいなもんだなと思う。起爆スイッチに触れないように、でも中身はちゃんと見なきゃいけない。神経、すり減りますよ。
訂正できても残るものがある
今回の件は、最終的には測量士と協力して図面訂正を進め、隣地の方との合意も取って無事に処理できた。でも、訂正できたからといって、すべてが元通りになるわけじゃない。書面上のミスが修正されても、当事者間の感情のズレは残る。隣地の方とはその後も顔を合わせる機会があるけれど、やっぱりどこかぎこちない空気が漂っている。言葉には出さないけど、「あのときの一件」は消えない記憶だ。
書面は直せても関係は直らない
書面というのは冷酷なほどに機械的だ。数字と線を直せばそれで「正解」となる。だが、人と人との関係はそうじゃない。「あの時こうしてくれていれば」とか、「なんで気づいてくれなかったのか」とか、そういう感情の積み重ねは、訂正登記では処理できない。むしろ、訂正の結果、こじれてしまう関係もある。司法書士って、目に見える問題を処理してるようで、実は見えない問題のほうが多い。そう感じることが最近増えてきた。
相談者に責められたわけじゃないのに
依頼者は本当に優しかった。「先生のせいじゃないですから」と何度も言ってくれた。でも、それでも気が重い。誰にも責められていないのに、ずっと心の中に残るモヤモヤがある。これは、仕事に真面目に向き合っている人ほど感じるんじゃないだろうか。どこにもぶつけられない後悔というか、自分の中でしか処理できないやつ。そういうのを一つずつ抱えていくのが、この仕事の一番つらいところかもしれない。
こういうときの感情処理が一番つらい
現場でのストレスより、あとからじわじわ来る感情の整理のほうがつらい。誰にも話せない。事務員にも話せない。家族もいないし、彼女もいない。友達も忙しい。だから、夜中に缶ビール飲みながら「はぁ…」ってため息ついてる。そういうとき、ふと思う。「なんでこの仕事選んだんだろう」って。でも、やめられない。不思議だけど、そういうもんなんです。
それでも続けている理由
何度も心が折れかけた。でも、続けている。理由は…うまく言えないけど、この仕事がやっぱり好きなんだと思う。たまに「ありがとう」って言ってもらえると、それだけで報われる。自己満足かもしれないけど、それでもいい。誰かの役に立てたという実感は、なによりの栄養になる。だから、どれだけ面倒な案件があっても、どれだけ心がすり減っても、また朝には机に向かってる自分がいる。
この仕事が嫌いになれない不思議
理不尽も多いし、報われないこともある。ミスの尻拭いをするような仕事ばかり。それでも嫌いになれない。性格かもしれないし、ただの惰性かもしれない。でも、やっぱり人が困ってると放っておけないんですよね。元野球部だからかな、チームプレーというか、人を支えることに妙な喜びを感じてしまう。だから、このまま地味に続けていくんだろうなぁと思ってる。
誰かの「ありがとう」で救われた話
以前、相続登記で泣いて喜ばれたことがある。お年寄りの依頼者だったけど、「これでやっと落ち着いて眠れる」って。あれは忘れられない。その一言で、2週間悩んでた胃痛がすっと消えた気がした。やっぱりこの仕事は、人の人生に深く関わる仕事だと実感する。派手さはないけど、重みはある。
でもやっぱり疲れる日は疲れる
理屈じゃない。「今日はもう無理」って日もある。そんなときは、無理に前向きになる必要なんかないと思う。疲れたら休めばいい。何もしたくない日は、なにもしない。缶ビール1本だけ開けて、ひたすらぼーっとしてればいい。そういうふうに、自分にちょっとだけ優しくなれるようになってきた。そういうの、大事だと思う。