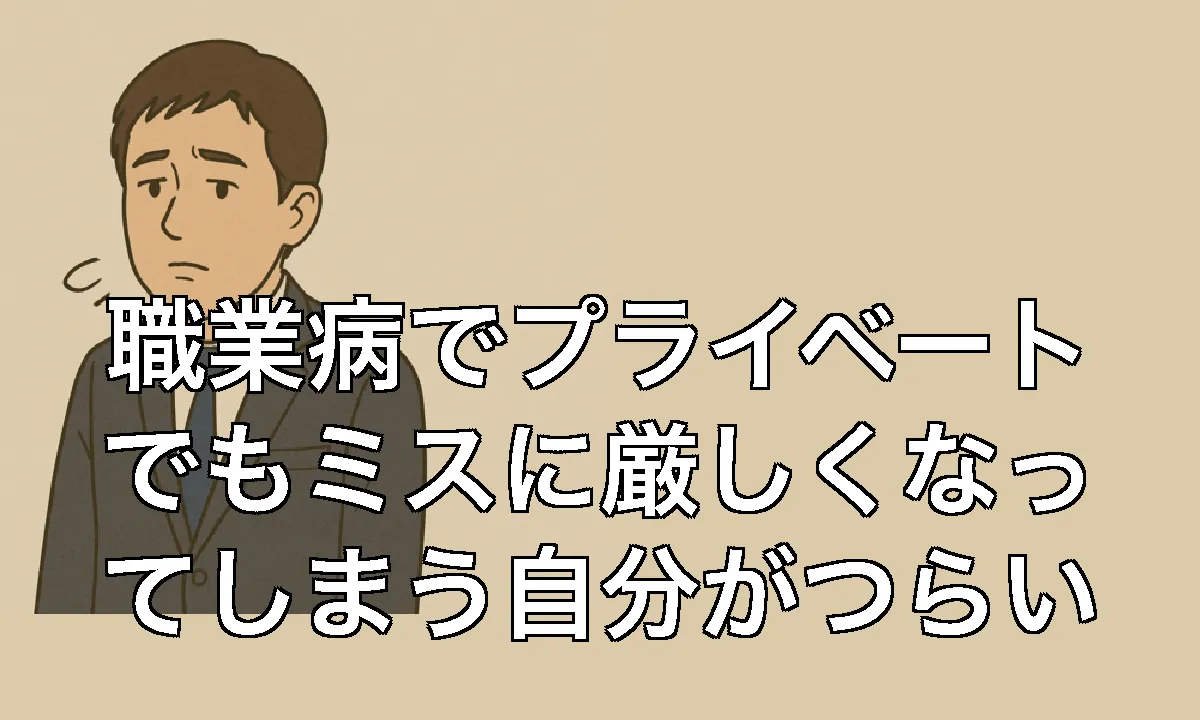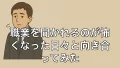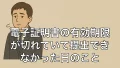気がつけばプライベートでもミス探しをしている自分
司法書士という仕事柄、常に「間違いが許されない」というプレッシャーの中で生きているせいか、気づけばプライベートでもミスに敏感になってしまっている。誰かの発言にちょっとした誤りがあると、指摘せずにはいられない。自分がやらかした時よりも、他人のちょっとした不備がどうにも気になってしまうのだ。仕事上は当然の意識なのだが、日常ではそれがときに厄介者になる。自分でも「細かい」と思いながらも、スイッチの切り替えがどうにもできない。
「間違いを見逃せない癖」が染みついてしまった日常
司法書士として日々書類を確認し、登記内容を一点のミスなく仕上げることに慣れすぎた結果、生活全般で「ミス探し」が無意識に出てしまう。本人確認書類の生年月日、住民票の表記、法務局の受付票のナンバーまで気になる毎日。それがエスカレートして、プライベートな場面でも「そんな小さな間違い、どうでもよくない?」と言われることもある。
スーパーのレシートでも間違い探し
ある日、近所のスーパーで買い物をした時の話。レジを通した後、何気なくレシートを見たら、割引が適用されていないのに気づいた。レジに戻って指摘すると、「」とすぐに訂正してもらえたが、ふと後で思った。「こんな小さなこと、普通は気づかないし気にしないのかも」と。その後ろに並んでいた人の冷たい視線を、今でも忘れられない。
テレビのテロップすら気になってしまう
バラエティ番組を見ていても、字幕の漢字の変換ミスが気になってしまい、笑いよりも「誰がチェックしてるんだ?」という気持ちが先に立ってしまう。友人と一緒に見ていて、「お前ほんと細かいな」と笑われたが、自分では全く笑えなかった。これはもう職業病だ、と諦めるしかないのかもしれないと思う瞬間だった。
気軽な会話にすら「正しさ」を求めてしまう
日常の会話でも、友人や家族がちょっとした言い間違いや勘違いをすると、すぐに訂正してしまうことがある。それが悪気はないと分かっていても、正確でいたいという気持ちが強すぎて、相手の気持ちを無視してしまう形になる。後で「なんであんな言い方したんだろう」と反省するのだが、その場ではつい口が出てしまう。
家族や友人との会話で感じるズレ
たとえば母親が「年金の支給って毎月末だったよね」と言ったとき、「いや、偶数月の15日」と即答してしまい、気まずい空気になったことがある。ただ話していただけなのに、自分の中では「間違いを正した」という達成感すらあった。だが、そういう態度が人を遠ざけているのかもしれない。
冗談を訂正してしまって空気が凍る
冗談で「うちの犬、税金払ってるんだよ」と言った友人に、「犬には納税義務ないから」と真顔で返してしまったときは、自分でも「これはアカン」と思った。場の空気が凍りつき、友人は「冗談通じないなあ」と苦笑。心の中では自分に「頼むから黙っとけ」と何度も言ったが、もはや反射で返してしまうこの癖は根深い。
「注意深さ」と「融通のなさ」は紙一重
司法書士に求められるのは、間違いを見逃さない冷静さと正確さ。そのスキルは確かに仕事での強みだ。しかし、それをそのまま日常に持ち込むと、ただの「融通のきかない人間」になってしまう。人との関係で本当に必要なのは、正しさよりも思いやりなのだと分かっていても、つい「間違い」にばかり目が行ってしまう。
仕事で求められる厳密さが仇になる瞬間
登記における数字の一桁、氏名の漢字の一点でも間違えれば重大なミスになる。それだけに日々、細部に気を配る習慣が身についてしまっている。だが、それを家庭内や友人関係で発揮しても、誰も喜ばない。むしろ相手には「神経質」「融通が利かない」と映ることもある。それでも、気になってしまうのだから困ったものだ。
自分の中の基準を人に押しつけてしまう
あるとき、事務員が「登記済証」ではなく「登記識別情報」と書き間違えていた。それを少し強めに注意してしまい、相手は落ち込んでいた。「そりゃ間違いはダメだけど、言い方が怖いです」と言われ、ハッとした。自分の基準が高すぎて、それを無自覚に相手に押しつけてしまっていたと気づいた。
柔らかく指摘できずに自己嫌悪
注意する時に、つい語気が強くなってしまう。その後で毎回反省して、「もっと優しく言えばよかった」と自己嫌悪に陥るのだが、また同じことを繰り返す。誰よりも厳しいのは、もしかしたら自分自身に対してなのかもしれない。完璧であろうとするその姿勢が、結果的に人を傷つけ、自分も苦しめている。
プライベートに正解なんてないのに
仕事では正解がある。提出すべき書類、期限、法的根拠。だが、プライベートには正解がない。にもかかわらず、つい正しさを追い求めてしまう。「こうすべき」「こうでなければおかしい」という思考に囚われ、自由であるはずの日常が窮屈に感じられることもある。
ミスを責める自分が一番のミス
人のちょっとした間違いにイライラしてしまう。そのたびに、自分の内側にある「許せなさ」が顔を出す。だが、それが一番のミスなのかもしれない。本当に大切なのは、間違いを受け入れること。その許容量のなさが、自分を苦しめているのだと最近ようやく気づいた。
「まぁいいか」と言える余裕がほしい
日常で起きる小さなミスに対して、「まぁいいか」と笑って流せる心の余裕が欲しい。それができれば、人間関係も今より少しは楽になる気がする。完璧主義のままでは、いつまで経っても孤独のループから抜け出せないのかもしれない。
ちょっとした「ゆるさ」で救われた体験
そんな中、救われたのは職場の事務員の一言だった。ある日、書類を一枚ミスしてしまい、机に突っ伏していたとき、「人間だもの、間違えるでしょ」と言われた。その何気ない言葉が胸に沁みた。いつも他人に厳しく、自分にも厳しかった私にとって、その一言は救いだった。
事務員さんの笑顔に救われた日
怒られると思っていたのに、逆に励まされた日。「先生でも間違うんですね」と笑ってくれた。完璧であろうとする姿勢ばかりにこだわっていた自分には、その笑顔が本当にありがたかった。誰かの優しさに触れると、自分の凝り固まった心がほぐれていくのを感じる。
「ドンマイ」一言のありがたみ
野球部時代、エラーをしても仲間が「ドンマイ」と声をかけてくれた。その言葉が、今の仕事の場でもどれほど救いになるか。自分もあの頃の仲間のように、誰かのミスに「大丈夫」と言える人間でありたい。
完璧じゃないからこそ支え合える
人は皆、間違える。だからこそ、助け合える。完璧じゃないことは、むしろ人とのつながりを深めるチャンスなのかもしれない。そう思えるようになっただけでも、この職業病との付き合い方が少しずつ変わってきたように思う。