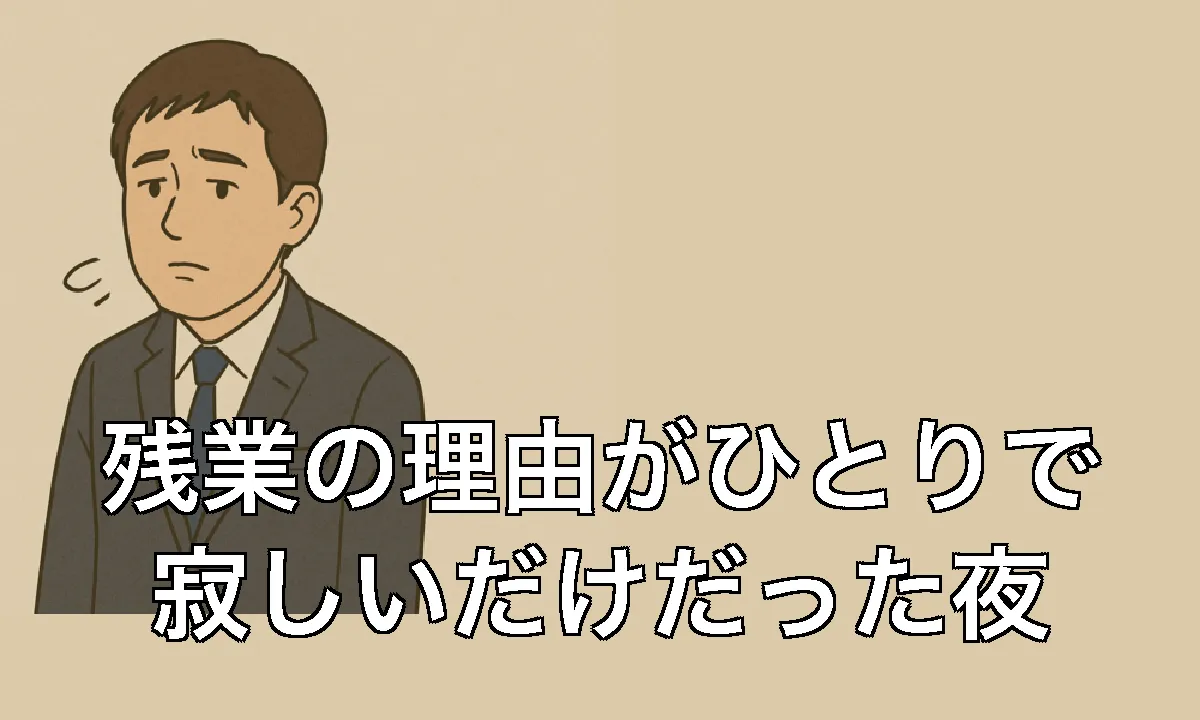誰もいない事務所で迎える夜
夕方6時を過ぎた頃、ふと気がつけば、もう誰もいない。事務員の彼女はとっくに帰っていて、事務所には私ひとり。パソコンの画面だけが青白く光っていて、外は真っ暗。近くのコンビニの看板だけがかすかに窓の向こうに見える。「まだやることあるしな」と独り言をつぶやきながら、特に急ぎでもない案件を開く。けれど、本当は気づいていた。今日はもうやることなんてない。ただ、帰りたくなかっただけだ。
仕事は終わっているのに帰れない
案件のチェックリストには、すでに完了のマークが並んでいる。電話も鳴らないし、メールの返信も済んだ。なのに、私は椅子から立ち上がれない。昔、部活の練習が終わってもグラウンドに残って素振りしていたあの頃のように、誰もいない空間で何かをしていないと落ち着かない。違うのは、あのときは誰かが来てくれる気配があったが、今はそれもない。カチカチとキーボードを打つ音だけが、孤独を誤魔化してくれる。
静まり返った事務所に救われるとき
この静けさが嫌いかと聞かれれば、案外そうでもない。むしろ、誰にも気を使わなくて済むこの空間に、私は少しだけ癒されているのかもしれない。昼間は依頼人とのやり取りに気を張り、職員にも気を遣う。それに比べて、夜の事務所は、自分の呼吸だけを感じることができる場所だ。寂しさと引き換えに得られるこの静けさが、今の私にとっての唯一の「安心」なのだと思う。
照明の色すらぬくもりに思える瞬間
オレンジがかった天井の照明が、やけに優しく見える夜がある。昼間は事務的で味気ない光だったのに、ひとりになった途端、なんとなくほっとするような暖かさを感じる。まるで、「今日も一日おつかれさま」と言ってくれているような気がしてしまう。こういう感情は、少し疲れている証拠かもしれない。それでも、誰かにそう言ってほしかった自分がいたのだと思う。
残業という言い訳の裏側
残業していると言えば、誰かからは「頑張ってるね」と言われるかもしれない。けれど、実態は「ただ寂しかっただけ」ということもある。仕事をしているふりをして、自分の孤独と向き合わないようにしているだけ。そうやって日々の感情をごまかしているうちに、自分でも本当の気持ちがわからなくなる。司法書士としての責任感というより、ただ「居場所がない」から机にしがみついているような夜だった。
仕事が多いわけじゃない
忙しい日もある。だが今日に限っては、仕事は片付いていた。にもかかわらず、なぜか帰りたくない。家に帰れば、テレビの砂嵐のような無音が待っているだけ。だったら、もう少しここにいたほうがマシだと思ってしまう。人は、他人からの期待がないときに、こんなにも簡単に迷子になるのかと感じた。「残業」という言葉の裏には、そんな小さな孤独が隠れている。
忙しいふりが自分を守ってくれる
「今日もバタバタでさ」なんて誰かに言えば、ああこの人は仕事があるんだと見てもらえる。そう思って、実際には誰にも求められていない資料を見直したり、ファイルを片付けたりして時間を潰す。仕事のふりをしている自分を見て、どこか安心している。まるで、無意味な素振りを繰り返していた高校時代の野球部のように。意味があるかどうかじゃない。動いてないと、不安でたまらないのだ。
誰かと話したいけど誰もいない
電話をかける相手も、連絡を待ってくれている相手もいない。友人たちは家庭を持ち、夜はLINEの既読もなかなかつかない。だからこそ、せめて「誰かの役に立っている」という実感だけでも欲しくて、私は残ってしまう。人はやっぱり、どこかで誰かと繋がっていたいのだと思う。でも現実は、終電間際のオフィスで、パソコンだけが光っている。あまりに無機質で、でもそれにすがるしかなかった。
ひとりの時間が怖くなる夜
独り身の気楽さはたしかにある。けれど、それが永遠に続くとなると、心が冷えてくる。自分で望んだはずのひとり暮らしが、ふとした瞬間に「誰もいないことの証明」になってしまうとき、ひどく不安になる。司法書士としての責任感や誇りが、ふと途切れる瞬間。その隙間から、寂しさという感情が、ぐっと心の奥まで入り込んでくる。何も悪いことをしていないのに、どこか自分を責めたくなる夜だった。
家に帰っても待っているのは無音
玄関を開けても、ただの空気の重みだけが出迎えてくれる。テレビをつけても、笑い声がうるさく感じてすぐ消す。冷蔵庫を開けても、惣菜のパックが並んでいるだけ。そんな部屋に戻るくらいなら、もう少しだけオフィスにいたい。夜風に吹かれながらコンビニに寄るのも、だんだん虚しくなってくる。誰かが待ってくれている、という温もりがどれほど人を支えているのかを、最近ようやく実感している。
テレビもスマホも心を満たせない
SNSを開けば、誰かの幸せそうな写真や日常が流れてくる。それを見ては「いいね」も押せず、ただそっとアプリを閉じる。テレビのバラエティ番組の笑い声が、どこか遠い世界のものに感じてしまう。便利なはずのスマホも、誰とも繋がらなければただの板きれ。無音の部屋で、それらを眺めている自分に気づいた瞬間、心の芯がひやりと冷えた。そういう夜が、最近は増えてきている。
冷蔵庫の明かりだけがやけに眩しい
夜中に何か食べようと冷蔵庫を開けたとき、白い光が一気に目に飛び込んできて思わず目を細めた。中にはコンビニ弁当と賞味期限ギリギリの牛乳。それを見た瞬間、自分がどこかで「ちゃんとしているつもり」で生きているだけだったと気づく。冷蔵庫の明かりが、まるで現実を突きつけてくるようで、やけに胸に刺さった。こんな生活を、いつまで続けるのか…答えは出ないままドアを閉めた。
司法書士という仕事の孤独さ
人の人生に深く関わるこの仕事。感謝されることもあるし、責任感もある。でもその分、どこか自分の感情を置き去りにしがちだ。依頼人の悩みや事情に寄り添えば寄り添うほど、自分の心の声が聞こえなくなる。表情は穏やかに、対応は丁寧に。そんなふうに「いい人」を演じていると、ふと一人になったとき、反動のように寂しさが押し寄せてくる。誰かに相談できる仕事じゃない。それがまた孤独を深める。
誰かの人生に寄り添いながら自分は空っぽ
登記の依頼、相続の相談、遺言の作成…。人の一生の節目に関わることが多いこの仕事。だからこそ、感謝される場面も多いし、「頼ってくれている」と実感もできる。でも、仕事を終えて帰るとき、なぜか空っぽの気分になる。「お疲れさま」と言ってくれる人もいなければ、「今日も頑張ったね」と労ってくれる相手もいない。人の人生には寄り添えても、自分の心には誰も寄り添ってくれない現実がある。
ありがとうが嬉しいのに残るのは虚しさ
「助かりました、ありがとうございました」と言われるたびに、やっぱり嬉しい。けれど、その言葉が終わったあと、妙な虚しさが胸に残る。たぶん、それは一時的な役割を終えたあとの、ぽっかりと空いた時間のせいかもしれない。「この人にとって自分はただの通過点だった」と思うとき、どうしても心が追いつかない。仕事で感謝されても、人として必要とされているわけではない。そんな想いが、夜になると膨らんでいく。
それでもまた朝が来る
どんな夜でも、必ず朝はやってくる。眠れないまま迎える朝もあるけれど、それでも出勤して、今日の仕事に向き合う。司法書士として、やるべきことは山ほどある。たとえ孤独でも、誰かの役に立てるなら意味がある。そんなふうに思える日は、少しだけ気持ちが楽になる。自分の存在意義を、仕事を通して確かめるしかない。それでも、今はそれでいいと、自分に言い聞かせるしかない。
孤独を受け入れて前に進むには
孤独を完全に消すことはできない。でも、それを受け入れたとき、少しだけ心が軽くなることがある。誰かに頼ることが下手でも、誰かに必要とされたい気持ちは消えない。だったら、まず自分が誰かを支える側でいよう。司法書士という職業が、私にその役割をくれたのだと思えば、やるべきことはまだまだある。寂しさと折り合いをつけながら、また今日も事務所に灯りをともす。
ひとりでも誰かの力になれること
家族がいなくても、恋人がいなくても、支える相手がいるというのは救いだ。依頼人の「ありがとう」に本気で応えることで、自分の存在が少しずつ肯定されていくのを感じる。ひとりでもできることはあるし、ひとりだからこそ、向き合える場面もある。寂しさを力に変えるには、きっとそれなりの覚悟がいる。だけど、自分で選んだ道だ。だったら、誇りを持って歩いていきたい。
弱音も愚痴も誰かに届けば少しは楽になる
こうやって言葉にするだけでも、少し楽になる。誰にも言えなかった弱音や愚痴も、こうして文字にすれば、きっと誰かに届くかもしれない。もし、同じように夜の事務所で孤独を感じている人がいたら、「あなただけじゃない」と伝えたい。司法書士に限らず、ひとりで頑張る全ての人へ。寂しさは悪ではない。ただ、誰かに理解されることで、それは少しだけ優しくなるのだと思う。