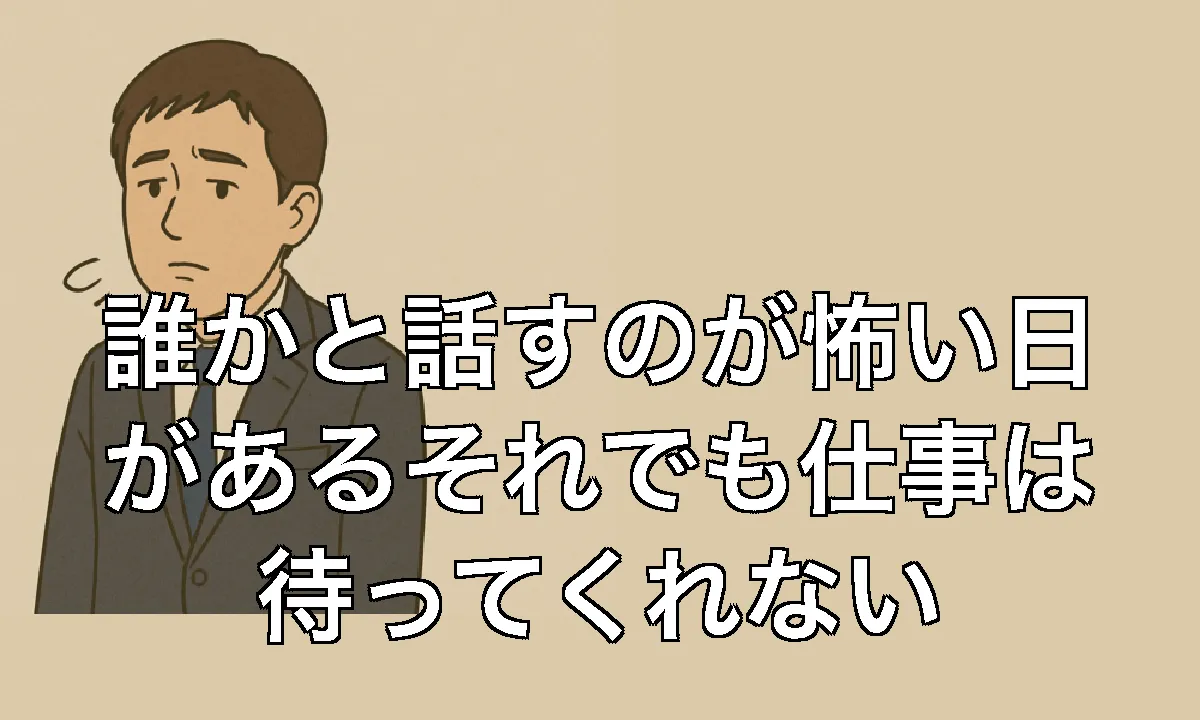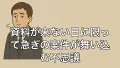誰かと話すのが怖いと感じたあの日のこと
朝、玄関のドアノブに手をかけたまま動けなかった日があった。たったひとことの「おはよう」がどうしても言えそうにない。電話に出るのも怖いし、お客様の前で笑顔を作る自信もない。そんな日は、まるで心が小さく縮こまって、世界との距離が何倍にも広がったように感じる。人と話すことが前提の仕事なのに、言葉を交わすこと自体が恐ろしくなるのだ。思えば司法書士という職業は、案外“コミュニケーション業”である。でも、そんなときほど、仕事は待ってくれない。
朝から無言で始まる一日
ある朝、事務所のドアを開けても「おはよう」と言えなかった。事務員の彼女は、何も言わずにお茶を淹れてくれた。その沈黙がありがたかったが、同時に申し訳なさも感じた。昨日の夜から頭の中がモヤモヤしていて、ちゃんと眠れていなかった。夢の中でも仕事のことを考えていて、起きた瞬間から疲労感が支配していた。そんな状態で誰かと会話するのは、体に合わないサイズの服を無理やり着るような苦しさがある。無理に笑顔を作ろうとしても、頬の筋肉がうまく動いてくれないのだ。
挨拶すら重荷に感じる瞬間
普段なら自然に出る「おつかれさまです」の一言も、喉の奥に引っかかって出てこない。電話のベルが鳴るたび、心臓が跳ねる。あの日はたまたま、銀行からの確認電話が多かった。丁寧な受け答えをしながらも、内心では「早く切れてくれ」と念じていた。口を開くたびに、気力を削られる感覚。会話がただの情報伝達ではなく、エネルギーを激しく消費する行為に変わっていた。
それでも出勤する理由
じゃあ、なぜそんな状態でも出勤するのかといえば、責任感とか生活のためとか、いろいろ理由はあるけれど、正直「惰性」が大きい。ルーティンに乗ってしまえば、少しだけ楽になる。昔、野球部の朝練でも「今日は休みたい」と思った日があったけれど、グラウンドに立てば自然と体が動いていた。それと似たようなものだ。誰かと話すのが怖くても、仕事は容赦なく訪れる。逆に、訪れてくれるからまだ自分は社会の中にいると実感できるのかもしれない。
司法書士という職業の見えない圧
「丁寧で誠実な対応が求められる職業」そんな言葉を何度となく耳にしてきた。たしかにその通りだと思う。けれども、人間である以上、いつもベストコンディションとは限らない。気分が沈む日もあれば、心が擦り切れそうなときもある。そんな時に限って、重要な面談や登記の期日が重なる。心の声は「少し休ませて」なのに、スケジュール帳は「今すぐ動け」と言ってくる。
丁寧に話すことが求められる仕事
司法書士の仕事では、「言い回し」ひとつで相手の印象が大きく変わる。特に相続や不動産の相談では、依頼者の不安を和らげる配慮が必要とされる。だからこそ、こちらの精神状態が不安定なときは、その「丁寧さ」が自分の首を絞める。心の余裕がないと、言葉も刺々しくなるのが怖い。依頼者に悪気なく強い言葉を返してしまい、あとで猛烈に自己嫌悪に陥ったこともある。
常に気を張ることの疲れ
僕は電話でも面談でも、常に「間違いのないように」と自分にプレッシャーをかけてしまう。その結果、どんな会話でも神経をすり減らす。ある意味で、話すことに「緊張」が常について回る。元野球部だからかもしれない。「気を抜くな」と常に言われていた名残だろう。でも、それが積もると、何もしていなくても疲れてしまうのだ。
話すのが怖いとは言えない空気
「話すのが怖い」なんて、相談できる雰囲気ではない。士業としての自尊心も邪魔をするし、同業者にそんなこと言えば「甘え」と捉えられるのではないかと怖くなる。かといって、友人に愚痴るほどの関係もない。結果として、どこにも出せない不安が内側で熟成され、どんどん重くなる。誰かと話すのが怖いのではなく、「話すことで何か壊れるのではないか」という漠然とした恐れなのかもしれない。
事務員との距離感と自分の不器用さ
たった一人の事務員との関係性に気を使いすぎて、逆に距離を感じてしまう。少しの会話で済ませる日はまだ楽だが、雑談を振られた日は「どう返していいか」が頭をグルグル回る。不機嫌だと思われないように、でも無理に明るく振る舞うのも違う気がして、結局不自然な笑顔でごまかすことになる。
近すぎず遠すぎずの距離を保つ難しさ
部下でも友達でもない。けれど、仕事を支えてくれている大切な存在。そんな微妙な関係性のなかで、言葉の選び方ひとつで空気が変わる。たとえば、ミスを指摘するとき。強く言いすぎると萎縮させてしまうし、やんわり言うと伝わらない。結果、気疲れする。誰かと話すことが怖い日は、そういった配慮すら重荷になる。
余計な一言が気まずさを生むこともある
以前、つい冗談のつもりで言った一言が、彼女の表情を曇らせたことがある。それが気になって一日中引きずってしまった。「あれは余計だったな」と反省しても、取り消せない。話すことは修正できない記録のようなもので、だからこそ慎重になってしまう。だが慎重になりすぎると、今度は無口になってしまう。このジレンマがまた辛い。
野球部の上下関係が染みついた自分
高校時代の野球部で鍛えられた「先輩後輩の距離感」が、今も抜けないのかもしれない。上下関係に敏感すぎるせいで、つい構えてしまうところがある。だからこそ「フラットな会話」が苦手だ。無意識に上下を測ってしまう。司法書士という立場もあいまって、柔らかく雑談するスキルが自分には足りていないと感じる。
会話が怖い日こそ紙とペンに救われる
不思議なもので、話すのは苦手でも「書くこと」は心が落ち着く。紙とペンがあれば、自分の内側を整理できる気がする。話すときのような緊張も失言の恐れもない。誰にも届かない言葉でも、とにかく吐き出すだけで楽になる。
書類作成に逃げることで気持ちを整える
誰かと会話するのがつらい日ほど、書類仕事に没頭する。「ここに押印するだけで登記が完了する」という明快さが救いになる。書類は話しかけてこないし、裏切らない。チェックリストを一つひとつ潰していくことで、自分が役に立っている実感が少しだけ戻ってくる。
書くことで自分と向き合う時間ができる
日記のようなものを、たまに書くようにしている。誰かに見せるわけでもないけれど、感情を言語化するだけで、心の霧が晴れる気がする。「今日の俺、会話ゼロだった」と書く日もある。でも、それでいいのだ。話せない日も、自分の一部。そう認めることが、少しずつ心をほぐしてくれる。
話さなくても伝わる何かを信じたい
話すことだけがすべてじゃない。そんなふうに思える瞬間がある。無言でも伝わる空気、背中で見せる誠実さ、そういった非言語のやりとりが救いになる日もある。誰かと話すのが怖いとき、自分が発する「沈黙」すらも一種のメッセージになるのかもしれない。
言葉よりも態度で示す誠実さ
たとえば、手続きをミスなく正確に進めることで、相手に安心感を与える。たとえば、黙っていても席を立って迎えるだけで、信頼が芽生える。言葉を使わなくてもできることは、案外多い。そう信じられるようになると、会話への恐怖も少し和らぐ。
言葉を使わないコミュニケーション
目を見てうなずく、資料を丁寧に揃える、相手のペースに合わせる。そうした「静かなやりとり」ができるようになると、無理して話そうとしなくてもよくなる。会話は武器ではなく、道具のひとつでしかない。話せない日があっても、それでも自分は司法書士として生きていける。