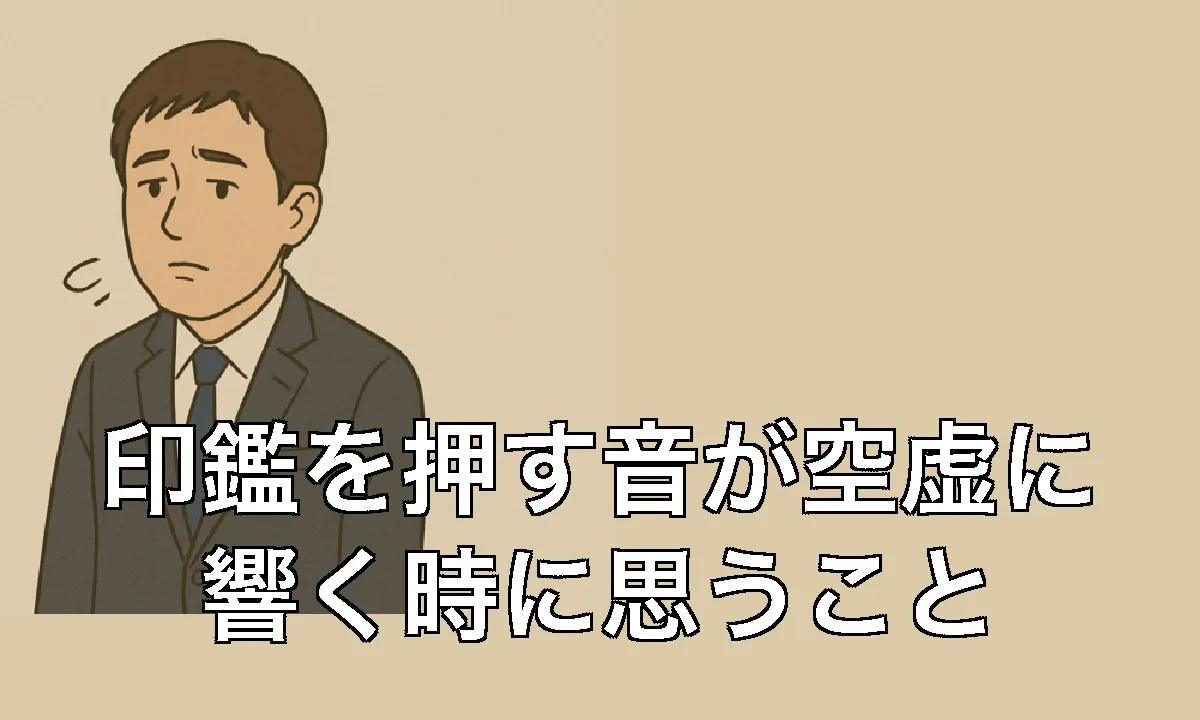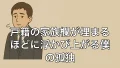印鑑を押す手は動くけれど心が動かない日がある
司法書士という仕事は、黙々と書類を処理し、印鑑を押していく日々の繰り返しだ。案件ごとに違う背景や事情があるはずなのに、気がつけば書類の形式ばかりが目につき、そこにある人の感情や物語が見えなくなっていることがある。事務所に一人で座って、次々と押されていく印鑑の音が、まるで機械のように感じる瞬間。そんなとき、自分がただの“印を押す人”になってしまったようで、ふと虚しさに包まれる。これはきっと、どの司法書士にも一度は訪れる感覚ではないだろうか。
手続きは滞りなく進んでいるはずなのに
仕事そのものは、予定通り進んでいる。登記も遅れなく処理し、依頼人からの感謝の言葉もいただく。それなのに、心の奥にじわりと沈むような違和感が拭えない。むしろ、順調に進んでいる時ほど、その感覚は強くなる。何も問題が起きていないという事実が、かえって「自分はただ手続きの歯車に過ぎないのでは」という感情を引き出してくる。業務上の達成感と、心の充足感は、決して比例しないと痛感する日々がある。
依頼人の言葉が心に残らないことがある
登記の完了報告をして、「ありがとうございました、助かりました」と言われても、最近はその言葉が耳に残らなくなった。慣れすぎたのか、疲れているのか、それとも期待しているのか。とある若い依頼者が「先生にお願いして本当によかったです」と深く頭を下げたときでさえ、自分は笑顔で応えながら、心ではどこか他人事のように受け流していた。かつてなら感動していた場面だ。それがただの「作業結果の報告」になってしまっていたことに気づいて、少しだけ悲しくなった。
感情を切り離すのも仕事の一部だと割り切っていたが
登記や相続の現場では、依頼者の感情に寄りすぎると冷静な判断を欠くことがある。だからこそ、あえて一歩引いたスタンスを取ることを“プロの姿勢”だと信じていた。だが、割り切りすぎて心まで鈍ってしまっては意味がない。業務効率は良くても、心がついてきていない。気づけば「自分が何のためにこの仕事を選んだのか」が見えなくなっている。感情のシャッターを下ろすのも限度がある。冷静と無感情は違う。その違いを、改めて自分に問い直している。
書類の山に埋もれて見えなくなった原点
机の上に積まれた登記申請書や契約書の束を前にして、ふと「俺はなんでこの道を選んだんだっけ」と思うことがある。書類は日々更新され、案件は尽きることがない。それはありがたいことのはずなのに、自分の原点がどこかに埋もれてしまった感覚がある。資格を取ったときの喜び、初めて登記を一人でやり遂げたときの達成感。今はその記憶さえも、書類の中に押しつぶされそうになっている。
司法書士を目指したあの頃の気持ちはどこへ
司法書士試験に合格したとき、心から「人の役に立つ仕事がしたい」と思っていた。正直、地元で開業して、地域の方々の生活を支えられるならそれでいいと、純粋に考えていた。だけど今は、電話対応と期限管理に追われ、気づけば「今月は売上いくらだったか」ばかり気にしている。原点なんて、生活に追われているときに思い出しても意味がない…そう思ってしまう自分が、ますます情けなくなる。
正義感とか使命感とか言ってた自分が恥ずかしい
若いころは「不動産のトラブルや遺産争いを未然に防ぐことが自分の役目だ」と胸を張っていた。法的に正しく処理することが人の幸せに繋がると、本気で思っていた。でも今では「とにかく期限までに書類を出せばいい」という思考が先に立つ。依頼人の背景や気持ちに寄り添う余裕もなくなってきた。正義感という言葉が、遠い昔の自己紹介のように思えてきて、苦笑いすら出なくなった。
でもあの頃はたしかに希望があった
ふと思い返すと、開業したての頃は少しの相談にさえ一生懸命だった。手続きが終わった後に「先生ありがとう」と言われると、まるで人生の分岐点に立ち会ったような気持ちになった。小さな案件でも、大きな意味を感じていた。それが今では、案件の大小で気持ちの起伏すらなくなっている。だけど、あの頃の希望はたしかに存在していたし、思い出すたびに少しだけ姿勢が正されるような気もしている。
事務所に響くのは印鑑の音とため息だけ
静かな午後、電話も鳴らず、事務所には印鑑を押す音だけが響いている。ポン、と乾いた音。そのたびに、自分が“生産している”ことへの証のようでありながら、どこか虚しくもある。書類は片付いていくのに、心の奥にはぽっかりとした空白が残る。時折、隣の席から聞こえる事務員の小さなため息に、自分の気持ちまで重なっていくようだ。
電話も少ない午後に押すひとつの印
「今日は静かだな」と思いながら押す印鑑。こういう日ほど、一人で働いていることを実感する。誰とも話さず、機械のように書類と向き合っていると、「このまま黙って一日終わってしまうんじゃないか」と不安になることがある。業務はこなしている。印も間違いなく押している。でもそれが誰かの人生に本当に役立っているのか、だんだんと分からなくなってくる。
事務員との会話が一日の救いになっている
たわいもない会話。今日の天気、近所のラーメン屋、テレビドラマの話。そんな雑談が、自分にとってどれほど大切な時間になっているか。事務員の存在は、仕事を手伝ってくれるだけじゃない。人間らしさを取り戻すための、数少ない接点なのだと思う。彼女がいてくれるから、なんとかこの仕事を続けていけている気がする。
でも彼女にも愚痴ばかりで申し訳なくなる
相談と称してつい愚痴をこぼしてしまう。売上のこと、依頼人の無理難題、書類の多さ。「そうですね、大変ですよね」と優しく応じてくれる事務員に対して、申し訳なさが募る。彼女にだって感情があるし、毎日同じような愚痴を聞かされるのはしんどいだろう。本当は「ありがとう」と伝えたいのに、それが口に出せない自分がまた、少し嫌になる。
それでも印鑑を押す意味を探し続けている
空虚に響く印鑑の音。だがその音は、確かに誰かの人生の一区切りを支えている。相続の完了、家の名義変更、会社設立。その背後には、笑顔や涙、決意がある。自分がその一端を担っている限り、無意味な仕事ではないはずだ。そう信じて、今日もまた印鑑を押す。
人の節目に立ち会う仕事の重み
結婚、離婚、相続、事業承継…。人生の節目に司法書士が登場する。感情を見せることは少ないが、裏で動いている感情の渦を想像すると、自分の押す印鑑の重みも変わってくる。ある意味、他人の人生の節目を「形」にする役割なのだと気づかされる。その責任を、時に重く、時に誇らしく受け止める自分がいる。
誰かの不安を軽くすることができた日のこと
「初めての相続で不安だったけど、先生のおかげで安心できました」と言われたことがある。書類の山に追われる毎日でも、そういった一言で心が救われる。目の前の作業が、誰かの心を軽くしている。その実感を忘れずにいたい。だからこそ、時には立ち止まり、自分の仕事を振り返る時間も必要なのかもしれない。
空虚な音がほんの少しだけ誇らしく響く日もある
すべてが空虚なわけじゃない。印鑑を押す音が、自分の役割を確認する音になる日もある。「今日も誰かのためになった」と思えた瞬間、その音はただの作業音ではなく、誇りを感じさせる響きになる。そういう日が少しでも増えていけば、この仕事を続ける意味はきっとある。そう信じて、明日もまた書類に向き合う。