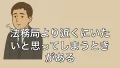なぜあの日だったのか
いつもと変わらない、静かな平日の午後だった。依頼人の一人が帰ったあと、ふと机に突っ伏した瞬間、胸の奥にぽっかりと空いた空虚が広がった。「もう自分は誰からも必要とされていないんじゃないか」そんな思いがよぎった。仕事は順調だ。登記も、相続も、期日も守っている。事務員だってよくやってくれている。けれど、誰かの温かさに触れることが、最近はまるでなくなってしまった。あの日、私はただ一人、事務所の蛍光灯の下で、自分が愛される存在ではないという感覚に飲み込まれていた。
仕事は回っているのに心は止まっていた
「忙しいですね」と言えば、なんとなく満たされている風にはなる。でもその実態は、ただの作業の連続だ。回っているのは手だけで、心はとっくに置き去りになっている。電話が鳴り、書類を確認し、依頼人と打ち合わせをし、また次の予定。まるで自分が機械にでもなったかのような錯覚に陥る。感情を挟む余地はなく、どこか無感覚になっていく。そんなある日、ふと立ち止まってみると、心がまるで止まっていたかのように感じたのだ。
いつのまにか「ありがとう」が減っていた
昔はもっと、依頼人に感謝される場面が多かったように思う。「助かりました」とか「先生のおかげです」とか、そんな言葉に救われていた。けれど最近は、結果が当たり前とされ、感謝も期待もされなくなったように感じる。こちらが不満を表に出せばプロ失格だ。でも人間だから、心の奥底では少し寂しい。もしかしたら、誰かの「ありがとう」がない日々の積み重ねが、自信を削り取っていったのかもしれない。
どこかで自分を見失っていたのかもしれない
「司法書士としてちゃんとやれてるのか?」そんな問いが、ある時期から頭の中をぐるぐる回り始めた。仕事のミスはない、納期も守っている。でも、自分が本当にやりたいことだったのか、と聞かれたら返答に詰まる。資格を取ってから、ただ目の前の案件をこなす毎日に飲まれ、自分の軸がどこにあるのか分からなくなった。「何のためにここにいるんだろう」と思った瞬間、心が完全に迷子になっていた。
ただの一言が胸に刺さる日もある
それは、何気ない依頼人の一言だった。「あ、これくらいなら誰でもできますよね?」と笑いながら言われた瞬間、胸の奥でなにかが崩れた。「誰でも…」その言葉に、自分の存在すら否定されたような気がしてしまった。もちろん悪気はなかっただろう。けれど、誰にも言えないまま、その小さな棘はずっと心の中に残り続けた。その日を境に、誰かと話すたび、どこかで怯えている自分がいた。
依頼人の言葉に妙に傷ついたあの日
「先生って、暇そうでいいですね」。笑いながらそう言った依頼人に、私は苦笑いするしかなかった。その場では流したけれど、心の中では叫んでいた。「暇どころか昼飯抜きで働いてるわ!」と。相手にとっては冗談かもしれない。でも、頑張っている最中にそういう言葉を投げかけられると、本当にしんどい。自分の苦労なんて誰にも伝わらないのだと、ますます孤独が深まっていった。
忙しさで心の鎧を着たままだった
気づけば、誰に対しても当たり障りない態度を取るようになっていた。「良い顔をしておく」のが習慣になり、素の自分を見せるのが怖くなっていた。忙しさにかまけて、自分の本音に蓋をしていたのかもしれない。だからこそ、たまに誰かの無邪気な言葉に出くわすと、鎧の隙間から直に突き刺さるのだ。防御しすぎて、逆に傷つきやすくなっていた自分に気づいたのは、だいぶ後のことだった。
愛されたいと思うのは間違いなのか
司法書士という仕事に就いてから、私は人からの「感情的な評価」より「正確な処理能力」ばかりを気にするようになった。書類が正しくても、心が空虚であることには気づきにくい。「誰かに愛されたい」という感情は、甘えなのか、弱さなのか。そんなことを思う自分を責めていた。でも実は、その気持ちを無視し続けたことこそが、心の摩耗を生んでいたのだと、今は思う。
頼られることと愛されることの違い
依頼人に頼られること、それは司法書士として嬉しいことのはずだ。でも、そこに「人間としての好意」や「信頼」が乗っていないと、どこか空虚に感じてしまう。役割として必要とされるのと、存在として愛されるのは、まったく違う。私はその差を履き違えていた。頼られていれば自信につながると思っていたが、愛されていないという実感が、じわじわと心を蝕んでいた。
「先生だから」と言われる寂しさ
「先生だから安心して任せられる」と言われることがある。一見、褒め言葉のように聞こえるけれど、そこに「個人としての私」は存在していない気がする。ただの肩書、ただの役職として見られているだけ。仕事が終われば関係も終わる。寂しいけれど、それが現実だ。だからこそ、ふとした瞬間に「愛されていない」と感じてしまうのだろう。役割を終えたら、私は誰にも必要とされないのかと。
信頼はあっても好意はない現実
登記を完璧に仕上げようが、相続手続きを迅速に済ませようが、それは当たり前として受け止められる。信頼はされているのかもしれない。でも、そこに情は感じられないことも多い。信頼と好意は別物だ。誰かの人生に関わる仕事だからこそ、心も通わせたいと思ってしまう。でも、それは司法書士という仕事においては、叶わないことなのかもしれない。
独身司法書士の孤独な自己評価
もう何年も、誰かに「好き」と言われた記憶がない。冗談めかして言えば笑える話だけど、本音を言えば、わりとしんどい。自分が誰かの「特別」になれる気がしない。年齢を重ねるごとに、ますますそう思ってしまう。モテないというより、近寄りがたい存在になってしまったのかもしれない。自分で自分に愛される価値がないと思っていたら、誰も愛してはくれないのかもしれない。
誰かに認められたい気持ちが拗れた
「認められたい」という気持ちは、本来なら成長や努力の原動力になる。でもそれが満たされないまま年月が経つと、いつの間にか「拗れた願望」になっていく。誰かに褒められたい、愛されたい、でもどうせ無理だ、と。そんな思考のループから抜け出せない日が続いた。プライドと諦めが入り混じった複雑な気持ちが、自信の芯を削り取っていった。
モテないという烙印のような言葉
「先生ってモテなさそうですよね」。ある若い依頼人に言われた冗談が、意外にグサッと来た。笑ってごまかしたけど、内心では相当傷ついていた。言い返すほどの自信もなかったから、ただ受け流すしかなかった。でも、その言葉がどこか自分の中で「真実」として居座ってしまったのだ。何歳になっても、誰かに必要とされたい。そう思っている自分を否定することが、またつらかった。