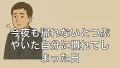裁判所にただいまって言いかけた日
気づけば裁判所が日常になっていた
司法書士になって十数年。気がつけば、裁判所に行くのが「非日常」ではなくなっていた。まるで通勤路の一部のように、足が勝手に裁判所の入口へ向かう。用事があって行く場所のはずが、無意識に「ただいま」と口にしそうになった瞬間、自分の生活がどれほどこの仕事に染まってしまったかを思い知らされた。地方の小さな町で、たった一人の事務員とともに日々の業務をこなす中で、裁判所は戦場でありながら、妙に落ち着く場所になっていた。
最初は緊張していた裁判所の雰囲気
開業当初は、裁判所に足を踏み入れるたびに緊張で汗ばむような思いをしていた。用件を整理して、書類に不備がないかを何度も確認して、それでも「何か見落としているんじゃないか」という不安が頭を離れなかった。職員の対応もどこか事務的で、距離感をひしひしと感じていた。司法書士として未熟だった自分にとって、裁判所は「正解」を求められる試験会場のような存在だったのだ。
無駄に丁寧だったあの頃の自分
今思えば、開業して最初の頃の自分は、妙に丁寧だった。挨拶は語尾まで丁寧語を尽くし、用件を述べるにも「恐れ入りますが……」の連続。職員から見れば「慣れてないな」と丸わかりだっただろう。でも、その頃の自分は「失礼があってはいけない」と気を張っていた。実際には多少の不手際があっても、職員の皆さんは案外穏やかに対応してくれていたのに、こっちは自分で勝手に緊張して、自分で勝手に疲弊していた。
呼び出しベルにすらビクビクしていた日々
書類を提出して、受付番号札を持って待っている間も、呼び出しのベル音にビクッとしていた。自分の番かと過敏に反応し、違ったら違ったでホッとする。そんなことを繰り返していたあの頃。今ではベルが鳴っても「あ、まだか」と思うだけになってしまった。慣れって恐ろしい。緊張感は薄れたけれど、初心のピリッとした空気感を忘れないように、時折ふと、あのビクビクしていた自分を思い出すようにしている。
常連扱いされ始めた瞬間
何度も通っているうちに、裁判所の職員の方々と顔なじみになってしまった。ある日、受付で「また来たんですか」と冗談交じりに言われた時、自分が「常連」として見られていることに気づいた。もちろん悪い意味ではなく、よく来る司法書士として覚えてもらっているのだろう。ただ、それが嬉しいような、寂しいような、不思議な気持ちだった。「また来た」って、ラーメン屋か喫茶店か。
「また来たんですか?」と笑われた朝
忘れもしない、火曜日の朝。事件が立て込んでいた週で、月曜から連日通っていた。その日も書類を抱えて受付に行ったら、顔を見た瞬間、職員の方がクスッと笑って「また来たんですか?」と。別に悪意のある言葉ではなかったのに、なんだかその一言が心に刺さった。笑って返しながら「そうなんですよ〜」と言ったけれど、内心では「いや、ほんとに、俺ばっか来てるな」と苦笑いしていた。
受付の方の名前を覚えてしまった違和感
こちらから名前を呼ぶことはないけれど、名札で名前を覚えてしまっている職員さんが何人かいる。ふとした拍子に心の中で「あ、この人は●●さんだ」と思ってしまう自分に違和感を覚える。まるで常連客が店員さんの名前を知っているような、そんな感覚。でも、ここは裁判所だ。書類を出すだけの場所だったはずなのに、名前を覚えるほど通ってしまっていることに、ちょっとした悲しさを感じる。
書類よりも世間話の方が長くなってきた
最近では、提出書類の説明よりも「暑いですね〜」「また雨ですね」みたいな世間話が長くなることもある。もちろん邪魔にならない程度にだが、ほんの数分のやりとりでも、妙な親しみを感じてしまう。「これが良い関係なのか?それとも、仕事の境界が曖昧になってるだけか?」そんなことを考えながら、今日もまた書類を持って足を運ぶ。お互いにちょっとだけ、日常の一部になってしまっているのかもしれない。
裁判所との距離が縮まった理由
裁判所と妙に仲良くなってしまった背景には、地方ならではの事情もある。小さな町で司法書士の数も限られていて、事件の担当も自然と偏る。事務員も一人きり、分業なんてできるわけもなく、自分が動くしかない。そうなると、必然的に裁判所へ通う頻度も増える。誰に頼るでもなく、全部を背負って進む。そのうち、相手もこちらの状況をわかってくれるようになって、結果的に「近くなって」しまうのだ。
事件が集中するタイミングの闇
不思議なもので、事件というのはなぜか同じ週に重なる。相続関係の訴訟が立て込んだり、保全処分が連発したり。「今週は穏やかだな」と油断した矢先に、ドカンと案件が飛び込んでくる。忙しさの波に飲まれて、休みの日にすら裁判所の夢を見たこともある。これが続くと、本当に自分の職場が裁判所なのではないかと錯覚する。少なくとも、自分の書類は郵便よりも先に届いている自信がある。
スタッフ一人だと回らない現実
事務員はとてもよく頑張ってくれている。けれど、裁判関係の案件となると、やはり司法書士本人が出向くしかないことが多い。訴状の提出や補正、保全命令の受領など、繊細な判断が必要な場面では、人任せにはできない。結果、現場に足を運ぶことになる。月末になると「今月、裁判所に何回行ったっけ?」とスケジュールを見返して呆れる。効率を求めても、現実はいつも足りていない。
代理申請の限界と現地対応の泥臭さ
郵送やオンライン申請が広がったとはいえ、細かな確認や緊急の対応は、現場に行くのが一番早い。そして、泥臭くても直接話すことで解決することも多い。形式だけでは済まない事情が、法務の現場には山ほどある。だから私は今日も裁判所に向かう。自分の足で、汗をかいて、顔を合わせて仕事をする。泥臭さが嫌いじゃないのが、野球部出身の性分なのかもしれない。
それでも救われた一言があった
何度も通って、心がすり減っていたある日、受付の女性がふと「いつもありがとうございます」と声をかけてくれた。何気ない一言だったけれど、こちらは不意打ちを食らったように感じた。その日一日の疲れが、その言葉だけで少し溶けた気がした。仕事の厳しさの中にも、誰かが見てくれている。その事実が、また一歩を踏み出す力になった。
「いつもありがとうございます」と言われて
その言葉をかけてもらったのは、ちょうど三連続で事件が続いていた週の金曜日だった。正直、心身ともにボロボロで、もう帰って寝たい、そんな気分だった。その時、「あ、●●さん、いつもありがとうございますね」とふいに声をかけられた。その一言で、報われた気がした。自分の働きが誰かに届いている、それだけで、また頑張れる。仕事って、結局そこなんだと思う。
正直涙が出そうになった出来事
男四十半ば、簡単に涙なんて見せられない。けれどあの時は、ちょっと危なかった。自分でも驚いた。言葉って、強いなと思う。苦しいときほど、誰かの何気ないひと言が胸に刺さる。私たち司法書士は、誰かのために手続きを整える立場だが、逆に救われることもある。それを思い出しただけで、また今日も書類を握って走れる。仕事って、案外、感情で回ってる。
誰かに見られていた努力って、意外とある
見てる人はいないと思っていた。でも、実は見ていてくれる人がいた。別に感謝されるために仕事をしているわけじゃない。それでも、誰かの中に「この人は頑張ってるな」と思われている。それだけで、少し救われる。司法書士は孤独な仕事だ。でも完全に一人ではない。そのことを忘れずに、また明日、書類を抱えて走ろうと思う。