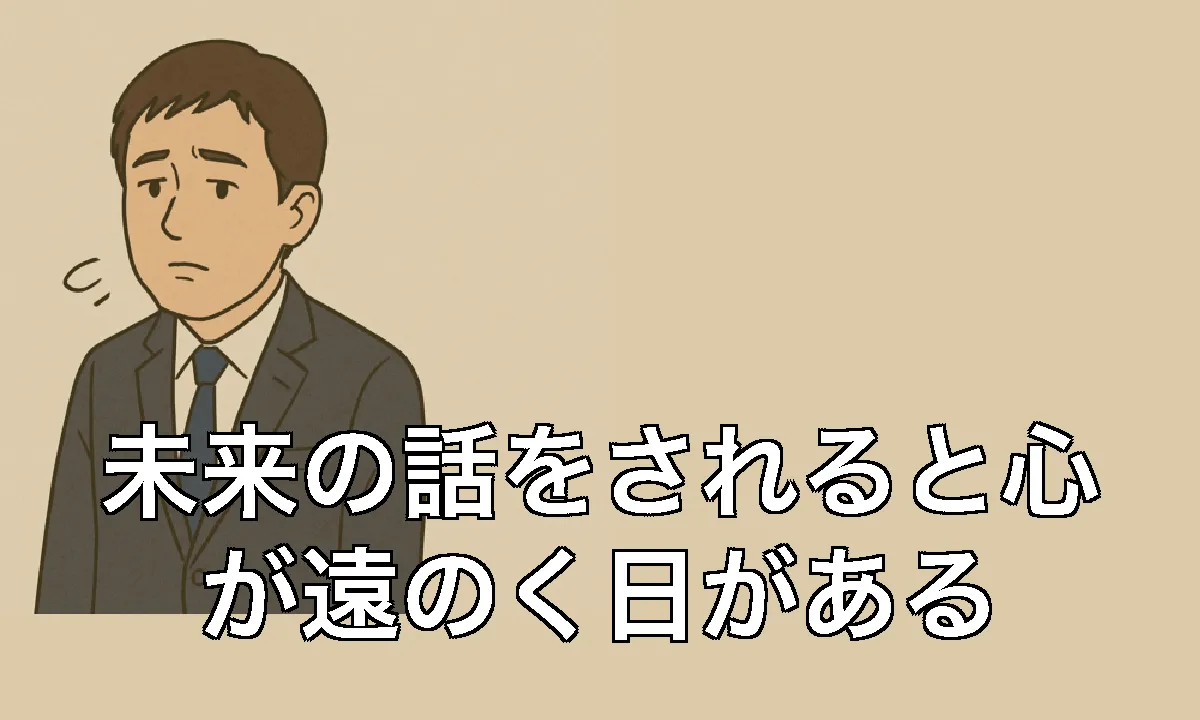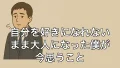未来の話をされると動揺する自分がいる
最近、知人との何気ない会話の中で「これからどうするの?」と聞かれることが増えた。たった一言の質問なのに、なぜか胸がざわつく。相手は軽い気持ちで尋ねているのかもしれないが、こちらとしては、自分の不確かな未来を突きつけられたようで、妙に落ち着かないのだ。司法書士として毎日忙しくしているくせに、ふと将来を思うと、急に手が止まってしまう自分がいる。なんでこんなに「未来の話」が苦手になってしまったんだろう。
「この先どうするの」が雑談に聞こえない
相手に悪気はないことはわかっている。でも、「この先のこと、どう考えてるの?」という質問は、雑談では済まされないほど鋭く心に突き刺さる。司法書士事務所を開いて15年、正直、日々を回すことで精一杯で、明確なビジョンなんて考える余裕もない。最近なんて、仕事終わりのコンビニ飯の選択すら面倒になってきてるくらいだ。そんな自分に未来の設計図なんて描けるわけがない。結局、笑ってごまかすしかできないのが現実だ。
予定を聞かれても空欄のままのカレンダー
「来月、何か予定ある?」と言われるたび、スマホのカレンダーを開くが、プライベートな予定は何も書かれていない。事務所の登記スケジュールや、期限の決まった案件ばかりが並んでいる。休日だって、事務員が休んだら自分が出るしかないし、何か計画を立てようという気も起きない。「将来」とか「休暇」とか、そういう言葉を聞くと、むしろ自分が何も持っていないことを再確認させられるようで辛い。
将来の話に答えるふりがうまくなっただけ
最近は、そういった話題になったときの“うまくかわす”技術が上達してしまった。「まぁ、ぼちぼち考えてるよ」「しばらくは今のままで」など、当たり障りのないセリフを口にして、笑って話題を変える。でも、本音を言えば、まったく何も見えていない。未来が見えない自分を他人にさらけ出すのが怖くて、適当なセリフで隠しているだけ。そんな日々が続くと、心がすり減っていくのがわかる。
誰かと語る未来に自分の居場所が見つからない
他人と将来のことを語るとき、ふと「この人の未来に自分はいるんだろうか」と考えてしまう。これは友人でも恋人でも、誰に対してもそうだ。そもそも、独り身で家族もいないと、未来の話に“誰か”を自然と含めること自体が難しい。司法書士という仕事は、他人の人生の節目に立ち会う職業だけれど、自分自身の節目は、どこにも記されていないような気がしてくる。
結婚も家族も話題になりがちな年齢
45歳という年齢になると、どうしても話題が「家族」「子ども」「老後」に傾きがちだ。法務局や取引先の人たちと話していても、だいたいその流れになる。そんなとき、自分だけが会話の中に入り込めない感覚に陥る。「ああ、またこのパターンか」と思って、うなずくだけになってしまう。誰も責めているわけじゃないのに、勝手に肩身が狭くなるのが情けない。
書類の山より将来の話のほうが重い
登記申請書や委任状、住民票の束を目の前にしたときの方がまだ気が楽だ。未来の話をされるより、書類を捌いているほうがずっと自分らしい気がする。結局、自分が信頼されているのは「今までの経験」や「手際の良さ」であって、「これからの夢」なんて期待されていない。だから、自分も語らなくなる。静かに目の前の仕事をこなすだけになってしまった。
会話の沈黙が未来への不安を映し出す
友人や昔の同級生と会っても、未来の話になると急に沈黙が増える。その沈黙が、お互いの不安や空白を映し出しているようで苦しくなる。気まずさをごまかすために無理に笑うけど、本当は一言も語れないまま終わっていくことが多い。気がつけば、そういう集まり自体に顔を出さなくなっていた。未来について語る場所から、自分を遠ざけるようになったのかもしれない。
司法書士という仕事の先を考えるのがしんどい
この仕事は、やりがいもあるし、感謝されることも多い。けれど、それだけで“これから先”を乗り切れるほど甘くはない。時代の変化、AI、電子申請の進化――。色々と考えるべきことはあるのに、つい現実逃避してしまう。自分の事務所がこの先どうなっていくのか、明確に言語化できない不安が、日々の忙しさに埋もれていく。
「ずっとこのままでいいのか」と問う夜
夜、事務所の電気を消した帰り道。ふと「このまま年を取って大丈夫なんだろうか」と思うことがある。給料も上げられないし、事務員だっていつ辞めるかわからない。頼れる上司もいない、自分が最後の砦だ。そんなプレッシャーを感じながらも、「じゃあ何か変えよう」とはなかなか思えない。今の安定の中に甘んじている自分もまた、否定しきれない存在だ。
世の中のスピードに置いていかれる気がする
若い司法書士がSNSで事務所のPRをしたり、YouTubeで相続の知識を発信していたりするのを見ると、正直、すごいなあと思う。でも、それを真似しようとは思えない。どこか、自分のやり方が“時代遅れ”になってきてる気はしてる。でも、今さら切り替える気力もない。スピード感についていけない焦りと、動き出せない自分へのもどかしさが混ざり合っている。
成長とか拡大とかより目の前の登記で精一杯
たまに経営セミナーとかに出て「事務所の成長」だとか「拡大戦略」なんて話を聞くけど、正直ピンとこない。うちは、まず目の前の登記を正確にこなすだけでいっぱいいっぱいだ。無理に広げても、責任ばかりが増えて苦しくなるのが目に見えている。そんな中で、「未来を語る余裕なんて、あるかいな」と心の中で毒づいてしまう自分がいる。
自分の未来を語ることへの小さな一歩
それでも、こうして文章にしているだけでも、少しは“未来”と向き合えているのかもしれない。誰かと一緒に語るのはまだ怖いけれど、自分自身とは向き合ってみようと思う。未来に答えを出すのではなく、ただ問いかけ続けること。それが、司法書士としてのこれからにも、そして一人の人間としての生き方にも、つながっていく気がしている。
無理に明るく描かなくてもいい
未来の話は、ポジティブでなければいけないわけじゃない。希望がなければ語ってはいけないわけでもない。愚痴混じりでも、弱音を吐きながらでも、語ることで何かが変わるかもしれない。未来は立派な計画書でなくても、ぼんやりした心の地図でもいい。そう思えるようになっただけでも、少しは進んだのかもしれない。
書類の隙間に希望を挟んでもいい
毎日のルーティンの中に、ほんの少しだけ希望を挟んでみる。たとえば、来月ちょっとした旅行の計画を立てるとか、趣味に時間を使うとか。そういう小さな未来のかけらが、思った以上に心の支えになることがある。未来とは、誰かと語り合うものじゃなく、自分が少しだけ楽しみに思えることから始めていいんじゃないだろうか。
誰かと語れなくても自分とは語ってみてもいい
未来を誰かと語れない日があってもいい。でも、自分自身とは向き合ってみてほしい。ノートでもメモ帳でもいい。ひとことでも、「こうなったらいいな」と書いてみる。それだけでも、心の中に小さな灯がともることがある。誰かと語れない未来でも、自分と語れたなら、それは立派な一歩だと思う。