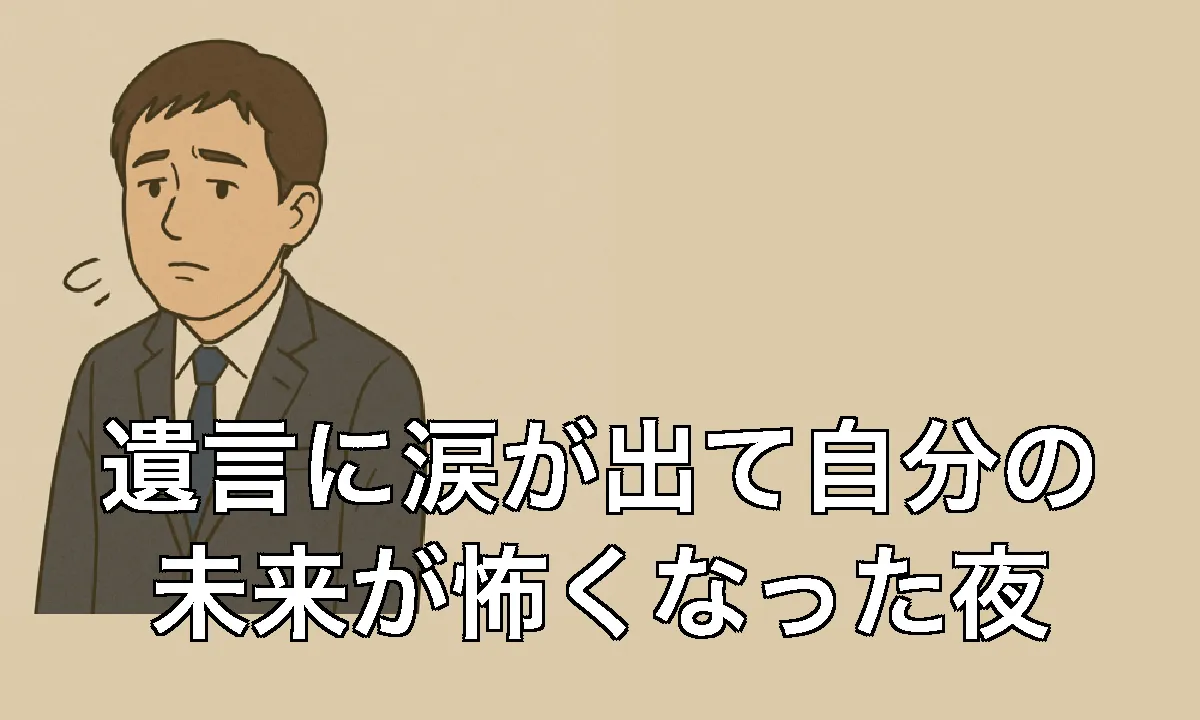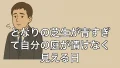誰かの遺言を読んで胸が詰まった日
司法書士という仕事をしていると、遺言書に触れることは珍しくありません。でも、その日の一通は、何かが違いました。書かれていたのは、家族への感謝、これからを生きる人への励まし、そして自分の人生を淡々と振り返る言葉たち。そこには悲しみよりも温かさがあり、読みながら自然と涙がこぼれてしまいました。他人の人生を見つめることが多いこの仕事でも、こんなにも心を動かされるとは思わなかったのです。
自分よりも立派な最期に触れて
その遺言を書いた方は、静かに人生を受け入れていました。若い頃に会社を辞めて家族と喫茶店を始め、最後は「ありがとう」の言葉で人生を締めくくっていました。僕はというと、何かに心から「ありがとう」と言えるほど誰かと深く関われているのか、と自問してしまったんです。毎日書類とパソコンと向き合い、日々に追われるように生きている自分と、静かに幕を閉じたその人との差に、心がざわつきました。
年齢を重ねると涙もろくなるって本当だった
昔は遺言を見ても「形式OK、はい次」と機械的に処理していました。でも最近は違います。45歳になって、親も年を取り、自分の老後や死について少しずつ現実味を帯びてきたのかもしれません。昔の自分なら絶対泣かなかったのに、今では一通の遺言で心が揺れる。これは老化なんでしょうか、それとも感受性が増しただけでしょうか。どちらにせよ、年齢の重みを感じる瞬間です。
静かに机に広げられた封筒の重み
その封筒は、古びた茶色で、何年も前に用意されたようでした。中から出てきたのは、数枚の便箋と手書きの文字。誰かの人生が詰まったその紙を、ただの「書類」として扱うには、あまりにも重たかった。ひとりで事務所に戻って、ふと静けさに包まれたとき、ようやくその「重み」が心に沈みました。こんなにも誰かの想いが詰まった封筒に、自分は何度向き合ってきたのだろうと考え込んでしまいました。
そのときふと自分の人生を振り返ってしまう
遺言の処理を終え、机に戻ってパソコンを開こうとした瞬間、指が止まりました。「もし自分が今、遺言を書くとしたら、何を書くのだろう?」そう思ったとき、書けることが浮かびませんでした。大切な人の名前も、思い出深いエピソードも、伝えたい言葉も、どこか曖昧で。知らぬ間に、ただ時間を消費するような生き方になっていたことに気づかされました。
司法書士としての時間の流れが速すぎる
気がつけばこの仕事も20年近くになります。法務局への往復、登記書類の山、電話応対に事務員との打ち合わせ。ひとつひとつは覚えていないけれど、毎日があっという間に過ぎていく。まるで川の流れに身を任せているようで、自分の意思で進んでいる感覚が薄れていました。気づけば、昔の友人とも疎遠になり、恋人もいない。予定表だけがびっしり埋まっている今に、焦りすら感じています。
気がつけば独身でひとり 誰に何を残せるのか
家族はいない。子どももいない。結婚の予定もない。ふと自分の死後の手続きを想像したとき、残すべき相手が見当たらなかったのです。自分の遺言には誰が涙を流してくれるのか。そもそも誰かが読むのだろうか。自分が扱っている書類を、自分自身のものとして考えた瞬間、背筋がすっと冷たくなりました。どんなに他人の終わりに寄り添っていても、自分の終わりには無関心だったことに気づかされた瞬間でした。
未来の話をすると無口になる理由
未来のことを聞かれると、自然と黙り込んでしまうことがあります。仕事のことならいくらでも話せるのに、自分の人生のことになると、なぜか言葉が出てこない。それは、未来に期待していないからかもしれませんし、描くことを諦めているからかもしれません。誰かの遺言を読んで、改めて「自分には何があるのか」と問い直す時間が必要だと感じました。
目の前の業務だけでいっぱいいっぱい
正直なところ、未来なんて考えていられるほど余裕はありません。毎日飛び込んでくる依頼やトラブルに対応するだけで、1日が終わっていく。事務員のミスをフォローしつつ、法改正に追いつく努力もしなければならない。朝はバタバタと出勤し、夜は疲れてコンビニ弁当を食べて終わる生活。そんな日々の中で、ふと未来を考えると、何も描けない空白だけが広がっていくのです。
事務員さんの老後どうしますが刺さった日
ある日、事務員さんがポロッと「先生、老後どうするんですか?」と聞いてきました。軽い雑談のつもりだったのでしょうが、僕にはグサッと刺さりました。「どうするも何も…まだ考えてない」と苦笑いで返しましたが、内心は動揺していました。老後どころか、1年後すらはっきりしない自分にとって、その質問はあまりにも現実的で、答えが出せないものだったのです。
何も答えられなかった沈黙の時間
質問された後、しばらく沈黙してしまいました。何か答えようとしても、頭の中には「空白」しか浮かびませんでした。その沈黙が、自分の人生の「計画のなさ」そのものを象徴しているように感じられて、恥ずかしかった。遺言で人生を語る人がいる一方で、自分は何一つ語れないまま、ただ時間に流されている。そんな気づきが、あの日の遺言以上に胸に刺さったのです。
司法書士としてのキャリアの先にあるもの
司法書士としての人生を積み重ねてきたけれど、その先には何があるのか。独立したことに満足していたのは最初の数年だけで、今は義務と責任と不安が残っている気がします。このまま続けていけば、それなりに生活はできる。でも「これでよかった」と言える日が来るのかは、正直わかりません。資格や肩書だけでは、心の空白を埋めることはできないと実感しています。
成長か衰退か 誰も教えてくれない現実
年齢を重ねると、誰も「これから先どうすればいいか」を教えてくれなくなります。若い頃は目標があり、進む道がありました。でも今は、自分で道を切り開くしかありません。成長しているのか、ただ現状維持しているのか、それすら見えない。そんな不透明な中で、ただ毎日をこなす自分に「これでいいのか?」と問いかけても、明確な答えが出ないまま日々が過ぎていくのです。
一人事務所の未来像に希望を見出せず
事務員と二人でまわす事務所。効率はいいけど、限界も見えている。自分が倒れたら、すべてが止まる。そんな不安を抱えながらも、誰にも相談できずにいます。求人を出す気力もなければ、引き継ぐ相手もいない。そんな未来を想像するたびに、「じゃあこの先、どうすればいいのか」と自問する。でも、答えは出ない。未来の不在。それが今の僕の一番の課題かもしれません。
それでも今日も遺言を書く側の立場として
自分の未来に答えが出なくても、他人の未来を支えるのが僕の仕事です。誰かが残したい言葉を形にすること。それは尊く、そしてとても重い行為です。遺言の手続きのたびに、自分も少しだけ未来と向き合える気がしています。たとえ今が不安定でも、少しずつ心を整えて、いつか自分の言葉も誰かに届くような遺言を残せたらいいなと、そう願うようになりました。
人の人生を見届ける責任
司法書士として、他人の終わりに関わるたびに、自分の未熟さを思い知らされます。それでも、逃げずに向き合うことが、この仕事の責任だと感じています。遺言という最後の言葉に触れながら、「この人の人生に敬意を払おう」と思えることが、今の僕にできる精一杯です。まだ自分の未来に言葉は持てないけれど、誰かの未来には力を貸せる。そんな気持ちで、今日も封筒を開きます。
書類の向こうにある想いを汲み取れるか
形式だけを追うなら、遺言もただの書類です。でも、その裏にある「伝えたい気持ち」まで想像できるかどうかで、僕の仕事の意味は大きく変わってきます。単なる文言の確認ではなく、そこにある感情を汲み取ること。それができてこそ、本当の司法書士だと思うようになりました。人の最後の声に、どこまで寄り添えるか。それをいつも自分に問い続けています。
誰かのためにペンを握りながら自分に問いかける
今日もまた、依頼人の代筆で遺言をまとめる時間がありました。穏やかな表情で語る依頼人の言葉を、一字一句丁寧に書き留めながら、自分に問いかけていました。「自分の言葉は、誰に届くだろうか」「自分の遺言には、誰が涙を流してくれるだろうか」そんな問いにまだ答えは出せません。でも、ペンを握るたびに少しずつ、自分の未来にも意味を見出せたらいい。そう思いながら今日も働いています。