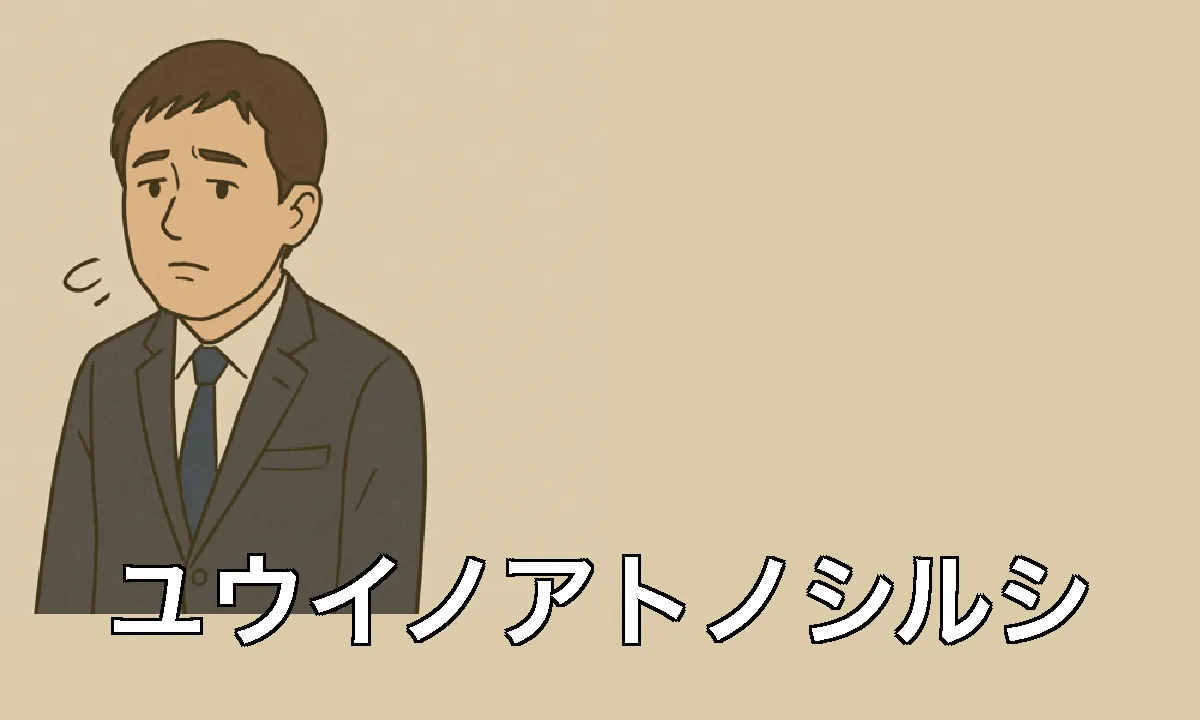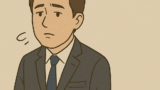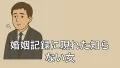朝の来客と封筒一通
午前九時を少し過ぎたころ、事務所のチャイムが鳴った。開業して十数年、この時間帯に現れるのはたいてい、登記で揉めた地主か、相続で険悪になった親族の誰かだ。だが今日の訪問者は、どこか場違いな雰囲気を纏っていた。紺色のスーツに真っ白な封筒、そして一瞬の躊躇。
「遺留分について、ご相談がありまして」そう言って、男は封筒を差し出した。表に大きく書かれたのは、亡き父の名前だった。
知らない依頼人と遺産話
男の名はモリヤマと名乗ったが、戸籍謄本のどこを見てもその名は出てこなかった。亡くなった父親の法定相続人は、長男と長女だけ。だが彼は確かに、「三人兄弟だった」と言う。
話がかみ合わない。遺言書もあるというが、それも封筒の中には入っていない。ただ、「兄に隠された」と彼は頑なだった。やれやれ、、、またややこしい相続争いの匂いがする。
遺留分請求の怪
件の兄が提出してきた遺言書は、公正証書遺言。形式に不備はない。すべての財産を兄に相続させるという内容だった。だが、それだけで弟を排除できるわけではない。
問題は、弟の存在自体が戸籍に記載されていないことだった。これはまるで、サザエさんに出てこない幻の家族みたいなものだ。存在がなければ、請求の権利すら認められない。
法定相続人の数が合わない
法務局で入手した戸籍を見直すと、父が再婚した履歴が見えてきた。その再婚の直前、前妻との子どもが一人除籍されていた。年齢を照らし合わせると、モリヤマの年齢と一致する。
「つまり、お兄さんとは異母兄弟の関係になるかもしれません」とサトウさんが淡々と整理する。彼女の口調はいつも冷たいが、抜け目がない。
サトウさんの冷静な推理
封筒の中に同封されていた古い手紙。それには「お父さんへ」とだけ書かれていた。内容は幼い筆跡で、父親に会いたいと願う子どものものだった。
「これは、本人が父親の存在を知っていたという証です」とサトウさんは断言する。「DNA鑑定さえ取れれば、認知の証拠にもなります」
黙っていた義理の弟の存在
調査を進めると、父親はかつて家庭裁判所に認知申立をしていた痕跡が見つかった。しかし、当時の相手方が手続きを止めた記録があった。つまり、制度上は認知が完了していないままだった。
「もう一度手続きを組み立て直せば、遺留分の請求はできる」と私は判断した。ただし、決して簡単な道ではない。
消された遺言と最後の証人
依頼人の兄から提出された遺言には、不自然な訂正の痕があった。日付の上に白く修正液を塗った形跡。そして、その訂正が行われた日付には、父親はすでに入院していた記録がある。
「この訂正、本人の手によるものではないですね」サトウさんの目が鋭く光る。まるでキャッツアイの瞳のようだった。
謎の第三通と印影の違和感
さらに、遺言の控えが市役所の保管庫から出てきた。そこには、もうひとつ別の内容が書かれていた。三人の子に三等分する、という内容だった。
「これ、印鑑が違います」私はため息をついた。公正証書のものと印影が明らかに異なる。どちらが正規かは、鑑定を待つ必要がある。
司法書士シンドウの逆転一手
公正証書の作成に立ち会った公証人に確認をとると、父親が高齢だったことから、すべての手続きを録音していたことが判明。そこには、第三子の名もはっきりと口にしていた音声が残っていた。
「決まりですね」サトウさんが淡々とファイルを閉じた。その瞬間、私はようやく肩の力が抜けた気がした。
調停前夜の証拠提出
裁判所に提出された証拠は、兄の提出した遺言が不完全であったことを証明するに十分だった。さらに、音声とDNA鑑定結果により、依頼人が実子であることも認められた。
調停はあっけないほどに終わった。兄は肩を落とし、弟は静かに一礼して帰っていった。
事件の決着と残された手紙
後日、依頼人から一通の手紙が届いた。そこには、「あのとき、誰も自分を信じてくれなかった。でも先生は、向き合ってくれました」と記されていた。
封筒の中には、あの日の幼い字で書かれた手紙のコピーも入っていた。父の机の引き出しから見つかったものだという。
誰のための遺留分だったのか
遺産とは、ただの金額や土地ではない。それは時に、認めてほしいという願いそのものだ。私は手紙をしまいながら、ポツリとつぶやいた。
「やれやれ、、、こっちは遺された心のほうが重かったよ」