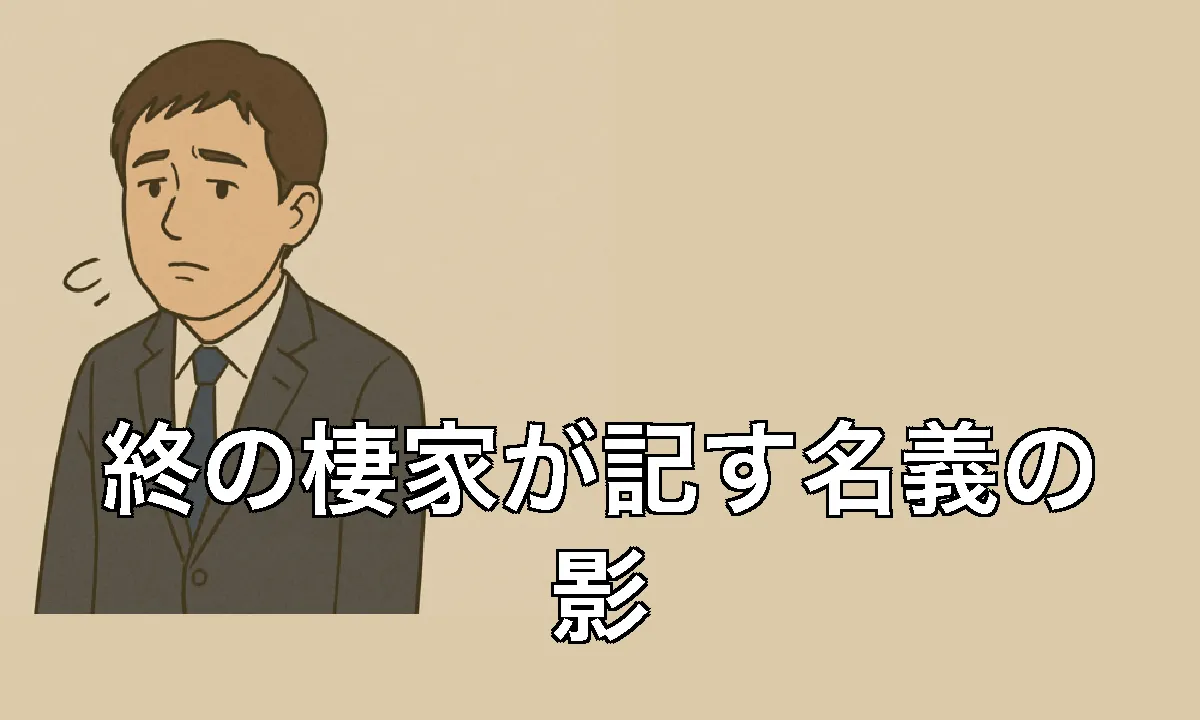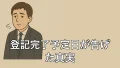古民家の売却と一通の相談メール
朝一番、事務所に届いたのは、50代の女性からの相談メールだった。内容は「母の住んでいた家を売ろうと思ったら、自分が相続していないことになっていた」とのこと。相続登記は済ませたはずだというが、法務局の調査では未登記扱い。どこかで手続きがすり抜けたのか、それとも——。
まるで、波平さんのカツオ追跡劇を見ているような、ひと騒動の予感がした。だが、こちらは頭頂部が広いだけでなく、責任も背負う立場なのだ。
築百年の家にまつわる奇妙な登記
件の家は、山間の町にぽつんと建つ築百年の古民家だった。地目は宅地、建物も未登記ではない。ただ、登記簿に記載された名義人は、依頼人の母ではなく、まったく別の旧姓の女性。昭和40年代に一度名義変更されている形跡があるが、その後変更がない。
依頼人の話と辻褄が合わない。彼女は確かにこの家に住んでいたはずなのに、登記上は別の誰かが所有者となっている。小さな違和感が、やがて不穏な気配を孕んで膨らんでいった。
依頼人が口にしたたった一つの違和感
「母は生前、『この家だけは私の終の棲家だから』って言ってました。でも名義のことは、いつも話を逸らしていたんです」
この証言が、事件の扉を開ける鍵だった。もしかして——母親自身が、家の登記を何かしらの理由で避けていた?
あるいは、そこに過去の「なかったことにしたい事実」が潜んでいるのかもしれない。
シンドウの足が向かった町外れの家
週末、僕は車を走らせてその古民家を訪れた。土壁の風情ある建物で、まだ住めそうな状態だったが、空気に微かな「誰かの未練」が残っているように感じた。近隣の住民は「ずっとお母さんが一人で住んでいた」と証言する。
しかし、現地にあるはずの登記識別情報が見当たらない。それもまた、意図的な隠蔽なのか——。
残された写真と一致しない現況
家の中を調べていると、和箪笥の引き出しに古いアルバムがあった。だが、その表紙に記された苗字は依頼人とは異なるもの。中には、依頼人の母と思しき若い女性が、見知らぬ男性と並んで写っていた。
この家は、単なる実家ではなかった。母親にとって、ここは「誰かと暮らした秘密の棲家」だった可能性がある。
登記簿の名義人が生きている矛盾
さらに調べを進めると、登記上の名義人は現在も生存していると判明した。ただし、既に90歳を超えた高齢者で、現在は遠くの施設に入所中。そこで僕は、サトウさんに戸籍の追跡と登記履歴の洗い出しを依頼した。
彼女の返事は、相変わらずそっけなかったが——「了解、5分で出します」とのこと。やれやれ、、、こっちは2時間かけて現地調査してるってのに。
サトウさんの鋭い指摘と旧姓の謎
サトウさんが追いかけた戸籍から、衝撃の事実が浮かび上がった。依頼人の母親は、一度結婚して「佐々木」という姓になっていたが、その前の姓がまさに登記上の名義と一致していたのだ。
つまり、名義変更は結婚前に行われ、その後手続きがなされなかった。法的には、名義人本人でありながら、婚姻により姓が変わったことで、登記と実態にズレが生じた状態だったのだ。
昭和の名義変更に潜むミスか意図か
当時は、戸籍・登記の連携も今ほど厳密ではなかった。おそらく依頼人の母は、名義のままで放置していたが、再婚などで姓が再び変わり、複雑な記録になったのだろう。
それにしても、なぜあれほどまでに登記の話題を避けていたのか。過去を封じ込めたい動機があったに違いない。
戸籍の追跡で浮かび上がる第二の女性
アルバムの写真のもう一人の女性——それは、母親の妹だった。つまり登記名義は「名義貸し」ではなく、姉妹での錯誤的な共有状態だったのだ。
結局、母が名義を「戻す」ことなく亡くなったことで、相続が不可能になっていた。家を売るには、妹(つまり依頼人の叔母)からの承諾と相続協議が必要となる。
現れた名乗り出た相続人の影
連絡を取った叔母は、淡々とこう語った。「あの家には思い出がある。でも姉が住んでいたことは認めてる。売ってもいいよ」
あまりに素直な回答に、依頼人は逆に泣きそうになっていた。過去のわだかまりを昇華するように、ゆっくりと頭を下げた。
ここは母の終の棲家だった
確かに登記は母の名ではなかった。でも、ここに生き、ここで死んだ。ならば、それが「終の棲家」だったことに変わりはない。
司法書士としての僕の仕事は、「心を記録に整える」ことでもあるのかもしれない——。
遺言が語る生前贈与と隠された真意
数日後、封印された遺言書が見つかった。そこには、「妹と協議し、私の死後は長女に譲ること」と書かれていた。
結局、あの家は、母親の強い想いにより、法的にも依頼人へと移る準備がされていたのだ。
すり替わった名義と過去の錯誤
名義はすり替わったわけではない。ただ、整理されず、時間だけが過ぎていった。登記は事実を映す鏡ではあるが、必ずしも真実そのものではない。
だからこそ、我々司法書士がその鏡を磨く必要があるのだ。
登記変更に潜んだ思い違いと計略
計略などではなかった。思い違い、いや、「わざと」整えなかったのかもしれない。記録に残さないことで、守ろうとした何かがあった。
それはきっと、母親にとっての人生の余白だったのだ。
司法書士の役割は真実を記すこと
家を売る手続きは完了した。登記も移された。だが僕は、そこに「心の履歴」を残すことができたと信じている。
事務員のサトウさんは言った。「たまにはちゃんと仕事してますね」。やれやれ、、、それが褒め言葉に聞こえてしまうのは、なぜだろう。
やれやれとため息をついた午後
午後の光が事務所のブラインドを通して差し込む。僕はいつものように、サトウさんに無言でコーヒーを渡した。彼女は一瞬だけ、表情をゆるめたように見えた。
今日もまた、人の記憶と登記簿の間を泳ぎながら、司法書士という仕事の奥深さをかみしめている。
雨上がりの事務所で二人分のコーヒー
雨が止んだ夕方、コーヒーの湯気の向こうに、過去の名義と想い出が静かに浮かんでいた。
紙の上では語れない真実もある。けれど、僕たちは今日も、それを読み解こうとしている。
そして今日も名義の過去と向き合う
古い家の記録には、人生の重みが詰まっている。名義だけでは語れない、人の想いがそこにある。
「次は未登記の納屋案件ですよ」とサトウさん。やれやれ、、、次の謎もまた、深そうだ。