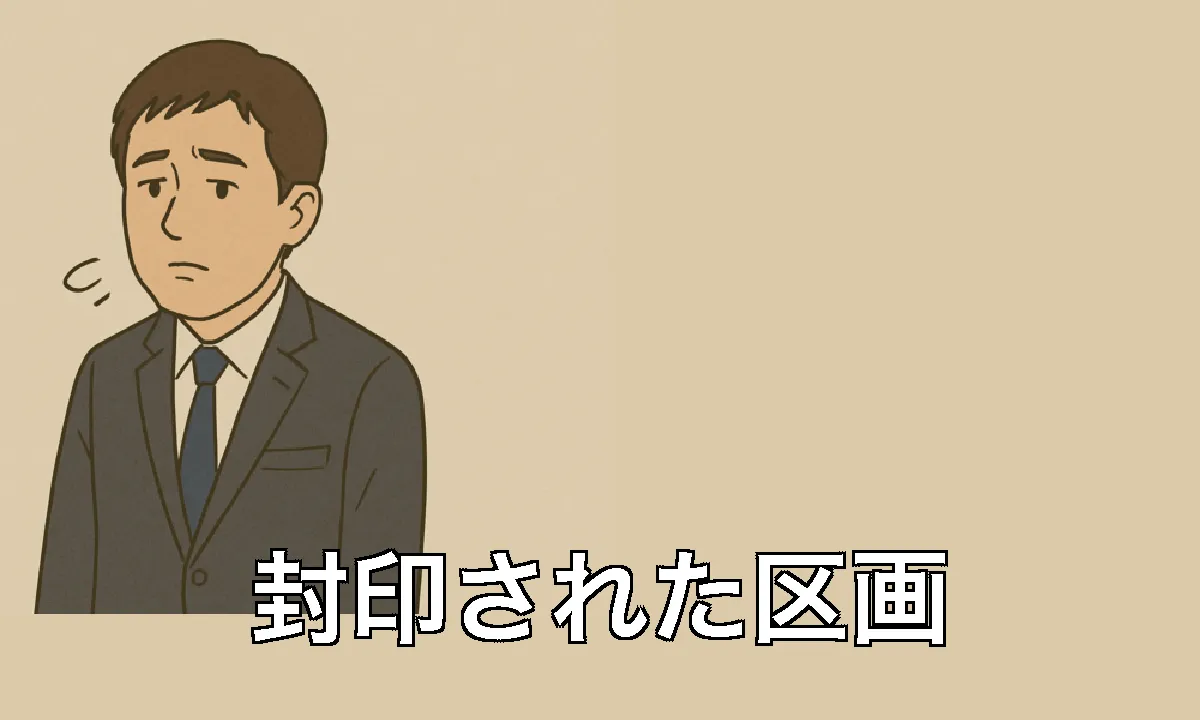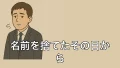封印された区画
梅雨明け間近の蒸し暑い午後。エアコンの効きが悪い事務所で、僕は汗を拭いながら登記簿を眺めていた。
表題部の記載に妙な違和感を覚えたのは、偶然ではなかった。
依頼人の言葉が脳裏に焼き付いていた。「ここの土地、昔と面積が違う気がするんです」
怪しい登記簿の記載
地番も合っているし、所有者も間違いない。けれど、地積が変わっていた。
書類上は正しい。だが直感が「違う」と告げていた。
机の上に広げた地積測量図と照合すると、一筆地だけ異様に整形されていた。
サトウさんの眉間に寄るしわ
「ここの別表一、数字が合いません」そう言ってサトウさんが画面を指差す。
地目は宅地、地積はおよそ100坪。でも現地写真を見る限り、もっと広い。
彼女の眉間のしわが、それがただ事じゃない証拠だった。
依頼人は地元の古株地主
昭和から続く地主の家系。その長男が今回の依頼人だ。
「隣の土地、もともとうちのだったはずなんですよ。昔の帳簿にはそう書いてある」
彼の語る過去の記憶と、現在の登記が食い違っているのだ。
地積測量図に潜む違和感
ファイルを引っ張り出し、僕は平成初期の測量図を確認した。
そこには破線で囲まれた、どこにも登記されていない「空白の区画」があった。
「やれやれ、、、また土地か」僕の脳裏に、過去の境界トラブルがよみがえる。
表題部と別表一のずれ
表題部の記載は最新だが、別表一の面積が旧データと一致していない。
そもそも別表一の役割は共有者の持分の明示。だが今回は単有なのに別表がある。
つまり何かを“隠すために”あえて残したとしか思えない。
消された一筆の謎
旧登記簿を洗うと、かつて確かに存在した地番が、ある時期を境に抹消されていた。
相続か合筆か、あるいはなりすましの可能性も捨てきれない。
これはただの記載ミスではなく、意図的な消去だ。
シンドウ、書類の山に埋もれる
事件性はない。だが不自然だ。僕は昼飯も忘れて書類を読み込んだ。
「シンドウさん、食べないと死にますよ」サトウさんの冷たい声が、妙に優しく聞こえた。
でも今は何かに気付けそうで、席を立つ気になれなかった。
昭和の登記と平成の手続
古い登記は手書きの台帳時代のもの。合筆・分筆が手作業で行われていた。
どうやら、その時代に一筆が意図的に消され、別の人間の名義で登記されたらしい。
誰かが、封印したのだ。区画と、過去と、罪を。
サザエさん方式の住所表記
旧住所と現住所の表記がぐちゃぐちゃになっており、登記官泣かせな構成。
しかも仮換地の名残まである。まるでサザエさんの家の間取りのように、変則的だった。
これでは正確な所有関係など追えるはずもない。
サトウさんの鮮やかな推理
「名義変更されたの、恐らく被相続人の死後ですね」
サトウさんの指摘で、僕ははっとした。確かに、死亡時期と登記日付が合わない。
「つまり偽造申請の可能性もありますね」彼女は当然のように言った。
現地確認で見つけた境界標
現場へ赴くと、確かに古い境界杭が残っていた。
それは今の登記より明らかに広い範囲を示していた。
杭は語る。「ここは誰かが隠した土地だ」と。
筆界特定申請の落とし穴
筆界特定制度ならば過去の境界を公的に確定できる。
だがそれには全関係者の協力が必要で、相手は既に他界していた。
「制度はあるけど、万能じゃない」やるせない気持ちだけが残った。
通帳と印鑑の不自然な動き
依頼人が提供した古い通帳には、登記変更の直前に不自然な出金が記録されていた。
印鑑登録証明の取得日も、相続開始後のものだった。
もう、これで確定だった。誰かが“やった”のだ。
本当の持ち主は誰なのか
結論として、現在の登記名義人は真の所有者ではない。
だが事件としては時効が成立しており、法的措置は困難だった。
それでも依頼人は言った。「知れてよかったです」
判明した区画の過去と真実
僕はすべての経緯を報告書にまとめ、依頼人に渡した。
帰り際、彼は空を見上げていた。「父も、あの区画を大事にしてました」
人は土地に名前を刻むが、時にその名は封印される。