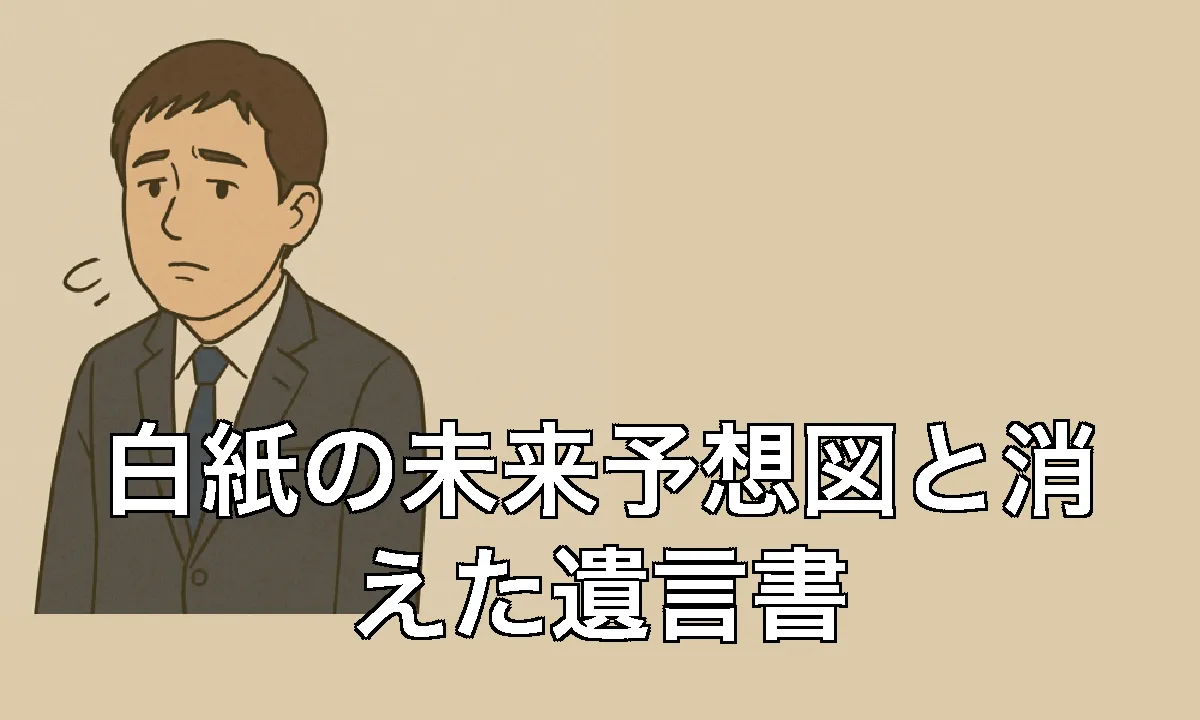朝のコーヒーと届かぬ書類
午前9時。コンビニの100円コーヒーを片手に事務所のドアを開けると、すでにサトウさんはパソコンに向かっていた。タイピングの音が小気味よく響いていて、こちらの入室にも眉一つ動かさない。
「おはようございます」とこちらが言っても返事は目線だけ。そんな朝に限って、今日届くはずの書類が届いていない。やれやれ、、、予感がする。
机の上には茶封筒が一通。宛名も差出人も手書きだった。
サトウさんの冷たい指摘
「それ、朝イチでポストに入ってました。なんだか、変な感じがします」
封を開けると、中には一枚のコピー用紙が入っていた。ただの白紙だ。サトウさんが眉をひそめる。「紙質、妙に分厚いですね」
「白紙の書類って、意味わかんないんだけど」とぶつぶつ言いながら、私は中身を眺めるしかなかった。
封筒に残された一枚の白紙
依頼人の名は田島伸吾、先週亡くなった地元の不動産オーナーの長男だった。登記に関する書類を揃えていた最中に、この封筒が届いたという。
「昨日、親父の書斎を整理してたら、机の奥にこれが挟まってたんです。もしかして、遺言書かと思って……でも、白紙なんですよ」
空っぽの未来予想図。書くべきことをあえて書かなかったのか、それとも何かのメッセージか。
白紙の意味と依頼人の不安
「親父、生前に“全部きれいに書いてある”って言ってたんです。本当に何も書いてなかったら、それっておかしくないですか?」
田島氏は焦燥の色を浮かべながら、テーブルの上に資料を広げた。名義変更、相続、評価証明書。必要書類はすでに一式揃っている。
だが、肝心の遺言が白紙となると、すべてが法定相続へと振り戻されることになる。
予想図はなぜ書かれなかったのか
未来予想図が白紙であるというのは、残す意志がなかったからなのか。あるいは、残せなかった理由があったのか。
サトウさんが一言、「白紙って、何かを隠すには一番手軽な方法です」とつぶやいた。
「あの人、筆圧強かったんですよ」と田島氏がぽつり。私はその瞬間、思いついた。
依頼人が語る亡き父の言葉
「長男だけに任せるな、兄弟で話し合え。口癖だったんです」
つまり、父親はあえて遺言書を白紙のまま残し、子どもたちの“未来予想図”を試そうとしていたのかもしれない。
が、それならなぜあの封筒が封をされた状態で残っていたのか。もっと単純な“隠された意志”があるような気がしてならない。
遺言書の謎と相続登記の準備
私は封筒を再び手に取った。中をライトで照らすと、紙の端にわずかな擦れが見える。コピー用紙ではない。二枚重ねかもしれない。
「サトウさん、カーボン紙持ってきて」
サトウさんが無言で立ち上がり、棚から使いかけの複写紙を出してきた。どこかルパンの次元のような身のこなしだった。
法定相続の混乱
「遺言が無効なら、弟たちは黙ってませんよ。土地だけで三筆、評価もバラバラですし」
私はうなずいた。だが、その“無効”の可能性が揺らぎ始めていた。
白紙には何も書いていない。だが、“書かれていた”可能性はある。つまり、見えないだけで何かが存在していたかもしれないのだ。
財産はどこに消えたのか
田島家の通帳を見せてもらった。父親の死の直前、大きな引き出しがあった。その金の行方は不明。
「現金は全部父のタンスにあるはずでした。でも、タンスは空でした」
白紙の紙と消えた現金。これは偶然なのだろうか。
サザエさんに学ぶ家庭のヒント
「波平さんなら“我が家は家族会議だ”って叫んで終わるところですよね」と私が言うと、サトウさんが微笑した。珍しい。
「でも、その会議が一番揉めるんですよ。とくに土地が絡むと」
おそらく波平でも、この登記の整理は無理だろう。フネさんが泣いてしまうに違いない。
波平タイプの遺言がもたらす混沌
白紙の遺言は、何も決めたくない人の最後の逃げ道なのかもしれない。
だが、その曖昧さが時として大きな争いの火種になる。
「これ、家庭裁判所まで行く流れですかね」私がつぶやくと、サトウさんは首を振った。
未来を予測しないという選択
「予想図を描かないってことは、“あなたたちが描きなさい”ってことだと思います」
あくまでサトウさんの私見だが、なぜか妙に納得がいった。そういう哲学的な父親だったのかもしれない。
だが、それでも我々の仕事は“意思”を明らかにすることだ。
やれやれの午後と逆転の発想
複写紙と白紙を重ね、指でこすっていくと、わずかに文字の跡が浮かび上がった。筆圧が残した、かすかな痕跡。
「これ、スキャンして画像処理にかけましょう」
やれやれ、、、いつもこうなる。簡単に終わるはずの登記が、まるで探偵ごっこのようになる。
司法書士は占い師ではない
法的に有効とするには条件が必要だ。筆跡、日付、署名。全てが揃わなければ、ただの紙切れだ。
しかし、複写の下には確かにあった。「長男に全てを託す」それが遺言の一文だった。
私は田島氏に告げた。「これ、なんとか証明してみせますよ。司法書士ですから」
見えない遺志と見える文字
複写から得た筆跡は、筆跡鑑定士のもとへ送り、数日後「本人の筆跡でほぼ間違いない」と返答があった。
裁判所の判断を仰ぐまでもなく、家族会議が再開された。
そして、誰もが父の遺志に納得した。なぜか不思議と、争いは起きなかった。
複写式の用紙に残された筆圧
かつて父が書こうとし、しかし取り出さなかった一枚の未来予想図。それは白紙ではなく、静かに子どもたちへ届いた。
それを導いたのは、司法書士と塩対応な事務員だった。
まあ、そういう職業なんです。派手じゃないけど、最後にはちゃんと活躍する。
消されたのは未来か意図か
白紙の遺言書は、消されたものではなかった。むしろ、静かに届くことを願って残された贈り物だった。
サトウさんは最後にこう言った。「やっぱり、人間って紙に書くことで何かを託すんですね」
私は黙ってうなずいた。彼女の言葉のほうが、よほど司法書士っぽかった。
終わらぬ争族と一通の手紙
午後の陽射しの中で、田島家の家族たちが並んで座り、遺志を読み上げた。
そのときだけ、空気が和らいだ。白紙は、もう白紙ではなかった。
小さな手紙が一つ、大きな未来を変えたのだった。
筆跡が語る真実
筆圧は嘘をつかない。それは父の声だった。遠回しで、不器用で、でも誰よりも家族思いの。
「やれやれ、、、結局、人ってのは文字でしか真面目になれないのかもな」
私はそんなことを思いながら、机の上の白紙を静かにファイルに綴じた。
司法書士の静かな一手
事件は解決した。登記も整った。誰も褒めてはくれないし、報道にもならない。
でも、これでいい。そういう仕事だ。そういう男だ。
だから今日も、書類の山に囲まれて私は思うのだ。「やれやれ、、、次は何が来るんだか」と。
ラストボールは誰の手に
夕暮れ時、ひとりで野球グローブを手に取った。あの頃のように、最後のボールを誰かに託すような気持ちで。
白紙の未来予想図は、もう真っ白ではない。
サトウさんのタイピング音が止み、「次の案件、入りました」と淡々と声がする。やれやれ、、、またか。