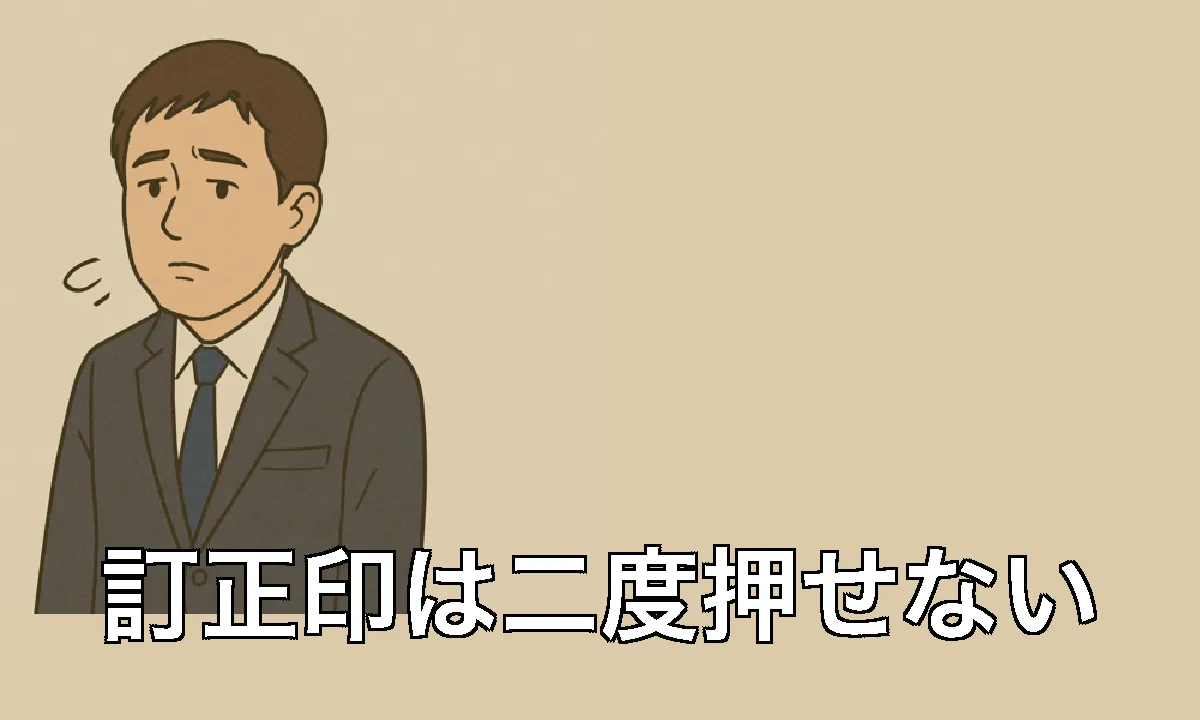朝の依頼人は涙の中にいた
「本当に、どうしてあんなことをしてしまったのか自分でもわからないんです…」と女性は委任状を握りしめ、机の上にポタリと涙を落とした。 その手元には訂正印がいくつも押された委任状があり、紙は湿気で波打っていた。 一見ただの事務的な修正に見えたが、直感的に違和感があった。
訂正印の跡が滲んだ委任状
訂正された箇所は、住所の番地や名前の漢字など、いずれも微細なものだった。 だが、それにしては回数が多い。訂正印が押された場所の配置が妙に不規則だった。 ふと『これは、なにかを隠すための訂正か?』という疑念が湧く。
「間違えたんです すべて」
女性は目を伏せたまま続けた。「夫が亡くなる前に、どうしても財産の一部を甥に譲りたいと…。でも、義父の反対で……」 話すほどに彼女の声は掠れ、矛盾が浮き彫りになっていく。 訂正ではなく、偽装。そんな言葉が頭をかすめた。
サトウさんの冷静な目
「この筆跡、同じに見えて微妙に違いますね」と、隣で事務処理をしていたサトウさんが呟いた。 彼女は眼鏡をくいっと上げ、複数の訂正箇所を並べたコピーを用意している。 「こことここ、字の左払いが逆に流れてるんです。…書いた人、違いますよ」
書類は語る 嘘と矛盾の痕跡
司法書士の仕事は、正しいものに印を与えること。 だが、誰かが印を悪用したら? そしてその訂正印の一つ一つに、意図が隠れていたら? それはただの事務ではなく、立派な“事件”になる。
誰の指示で訂正されたのか
依頼人の説明と、実際の訂正内容が微妙にずれていた。 それを追えば、誰が何を意図して修正を行ったかが見えてくる。 だが本人が「やり直したい」と言っても、すでにそれは完了している登記の話だ。
登記申請は止められない
一度完了した登記は、基本的に修正できない。 やり直しを望む気持ちと、制度の非可逆性は、しばしば依頼人を苦しめる。 「もう戻れないんですか?」という問いに、言葉を詰まらせた。
やり直しの効かない登記完了
登記簿には、訂正された形で記録が残っている。 正当な手続きを踏んでいないならば、無効の申請として訴えるしかない。 だがそれには、明確な証拠が必要だ。
やれやれ、、、またトラブルの予感か
ふと空を見上げる。今日は晴れているくせに、心の中はどしゃ降りだ。 トラブルは毎度のことだが、今回はどこか気が重い。 「サトウさん、昼、カツ丼でも行く?」と聞いてみたら、「糖質制限中です」と秒で斬られた。
過去と今をつなぐ筆跡の謎
筆跡鑑定まではいかないが、微細な癖の違いは確かに存在する。 どうやら訂正された部分には、複数人が関与している形跡があった。 そのすべてに依頼人が関わっているのか、誰かに誘導されただけなのか。
署名欄の微妙な震え
署名欄の最後の一文字、妙に震えていた。 「あのとき、手が震えて…」と彼女は語る。 だが、それが本当に彼女自身のものなのか、それとも偽造なのか。
依頼人の言葉と齟齬
「夫が亡くなる前に署名した」との主張と、訂正の日時が一致しない。 提出された原本と保存されたコピーのタイムスタンプに食い違いがあった。 もしかすると、夫の死後に書かれたものかもしれない。
意外な人物からの電話
その日の夕方、突然かかってきたのは、故人の弟を名乗る男からだった。 「兄貴は、そんな譲渡の書類を書くようなやつじゃなかった。おかしいと思ってたんだ」 抑えきれない怒りが、受話器越しに伝わってきた。
亡くなった夫の弟からの告発
彼の証言で、遺産分割をめぐる争いの影が浮上する。 甥に譲るとされた財産には、長年の確執が関係していたという。 つまり、誰かが勝手に訂正印を使って“意思”をねじ曲げた可能性がある。
「兄はそんな書類 書くはずがない」
弟の言葉には強い確信があった。 「兄貴は、義父を裏切るような人間じゃないんです」 それが事実だとすれば、遺言も訂正も、すべてが虚偽ということになる。
真実は公証役場に眠っていた
調査の結果、公証役場に保存されていた正本と、依頼人が持参した写しに微細な違いがあった。 公証役場にある正本には訂正がなく、署名の字もなめらかだった。 それに対し、依頼人のものは訂正だらけで筆跡も不自然だった。
原本台帳と正本のズレ
原本台帳には一度も訂正の記録がない。 つまり訂正印のある書類は、後に作られた可能性がある。 しかも登記に使われたのは、訂正後の書類だった。
誰が訂正し 誰が承認したのか
この訂正は、公証人も知らないところで行われた。 つまり、非公式かつ不正な改ざんだ。 訂正印という正当性の仮面を被った、印影のトリックだ。
決定的証拠は別の申請書類
過去に提出された別の書類と照合したところ、訂正印が逆さに押されていたことがわかった。 「サトウさん、また見つけたの?」と聞くと、「初歩ですよ」といつもの塩対応。 彼女の指摘で、すべてが動き出す。
謄本に浮かぶ不自然な訂正履歴
訂正履歴が記録された謄本には、同じ訂正印が複数人の名前に使われていた。 同一印影を使い回した形跡があった。 これは、誰かが印を勝手に使った決定的証拠だ。
別人の訂正印を確認
印影照合の結果、印鑑登録と異なる方向で押されたものが複数確認された。 偽造とはいかなくても、意図的な流用である可能性が高い。 依頼人がやったのか、それとも別の誰かが操ったのか。
サトウさんのひと言がすべてを解く
「この印影、逆さですね」 たったその一言で、すべてが氷解した。 訂正印は自分で押したものではなかった。逆さに押すことは通常あり得ない。
やっぱり彼女には敵わない
僕は深く椅子に沈んだ。 ああ、またサトウさんに一本取られた。 やれやれ、、、せめて夕飯はカツ丼で挽回したい。
不正の背景にあったのは
依頼人の背後には、甥とその家族の生活がかかっていた。 「どうしても、この家を守りたかったんです…」 正義と情の狭間で、彼女は揺れていた。
家族の再構築を願う切実な想い
夫を失い、甥を失いたくなかった。 ただ、それが許される手段ではなかっただけ。 法の前に感情は無力だ。
だが法律は感情を待ってくれない
裁判所に訂正の無効を訴える書類を整えることになった。 彼女の責任は免れないが、やり直すチャンスは残されている。 それでも、訂正印は二度押せない。
訂正印は二度押せない
訂正印は、過去を塗り替える道具ではない。 真実をより明確にするためのものだ。 やり直しの気持ちは痛いほどわかるが、法は感情に応えない。
やり直せないこともある
だからこそ、最初の一押しに責任を持たねばならない。 登記も、人生も、そういうものだ。 元野球部としては、初回のミスが試合を左右するのをよく知っている。
でも前を向くことはできる
「また来週、書類持ってきます」と彼女は深く頭を下げた。 「今度は、最初からちゃんとやります」 その一言が、少しだけ救いだった。