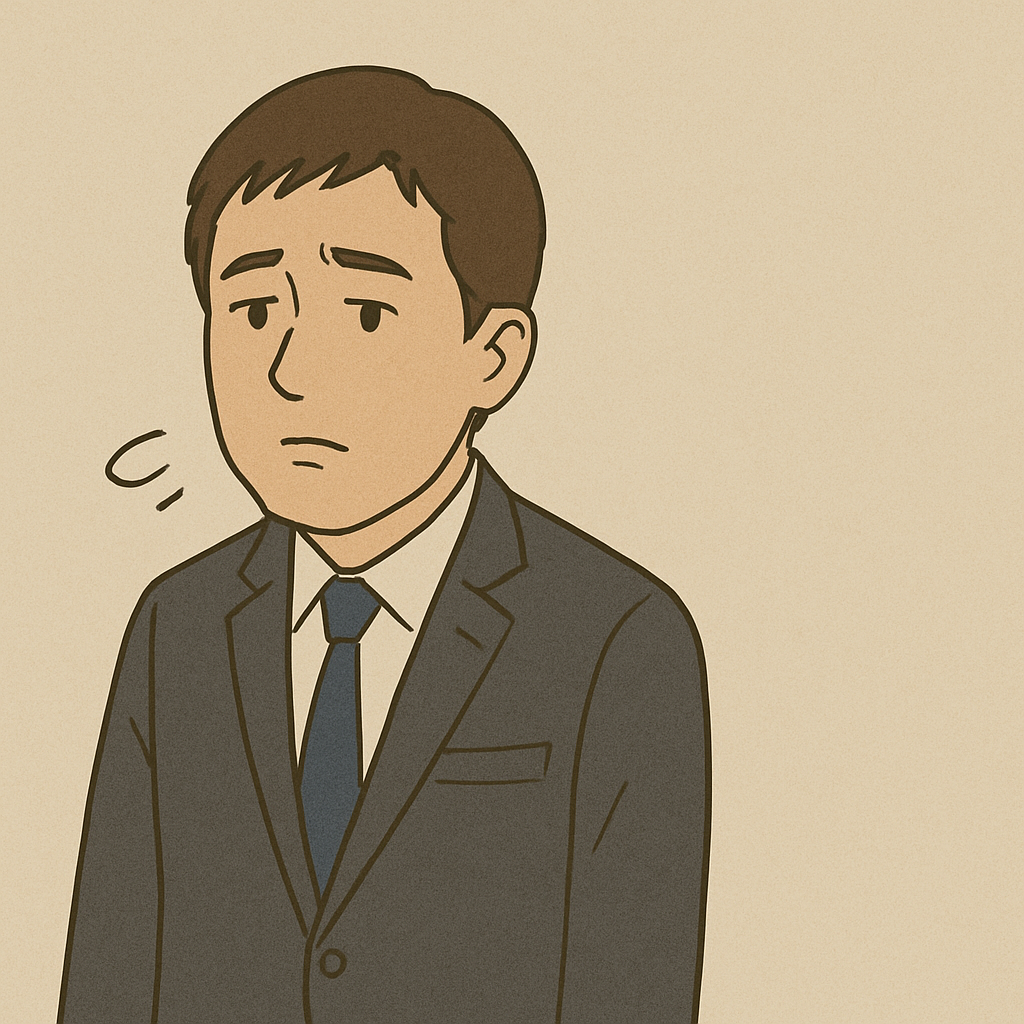静かな朝と一本の電話
地方都市の朝は、都会の喧騒とは無縁で、せわしなくもどこか間延びしている。私の事務所にも、今日も変わらぬルーチンが始まろうとしていた。インスタントのコーヒーをすすりながら、書類の山を眺めていたそのときだった。
事務所の電話が鳴った。受話器を取ったのはサトウさん。無表情でメモを私に差し出しながら、声だけで「相続相談です」とだけ言う。はいはい、どうせ遺産争いか何かだろう。
事務所に届いた不穏な依頼
依頼人は五十代の女性で、兄が亡くなったという。相続登記の依頼のはずだったが、彼女の言うには「父の土地が二筆あるはずなのに、登記簿上は一筆しかない」とのことだった。なんだそれ、と思いながらも、私は登記簿を取り寄せてみることにした。
やれやれ、、、また面倒なパターンか。とりあえず、話だけでもちゃんと聞くか。私の目の下のクマが深くなる音がした気がした。
サトウさんの違和感と直感
「この地番、昔の住所の地番と食い違ってますね」 そう言ってファイルを見つめるサトウさんの目が鋭い。私は一瞬、「こち亀の本田巡査がスイッチ入ったとき」みたいだなと思った。普段は塩だけど、時々妙に頼りになるのが困る。
彼女の指摘に従って調査を進めてみると、確かに昭和の旧地番の記録と現状の登記簿とで、不一致がある。これは単なる登記ミスか? それとも意図的な隠蔽か?
相談者の語る奇妙な相続話
依頼人によれば、父は生前に兄に土地を譲っていたという。だが、譲渡登記がされていない。しかも兄は生前、「父からのもう一筆がまだ未登記だ」と言っていたらしい。それが今回、見つからないというのだ。
本当に二筆あったのか、それとも記憶違いか。だが、亡き兄が自分の子どもたちに「将来は家二軒分の土地がある」と言っていたというのだから話は重い。私はだんだんこの話に引き込まれていった。
名義変更のはずが土地が二つ
仮に兄の言葉が正しければ、現在の登記簿には一筆しかないこと自体がおかしい。旧土地台帳をあたってみると、昭和45年の時点では確かに二筆の地目が記載されていた痕跡があった。
なのに、登記簿では一筆に合筆された記録がない。つまり、どこかで一筆が消えたのだ。これは、事件だ。というより、うっかりでは説明できない何かがある。
古い登記簿に残された手がかり
法務局の倉庫から出てきた、色褪せた謄本のコピー。そこには、手書きの補足記録が残っていた。合筆処理がされたという走り書き。だが、それには正式な処理日付も印もない。
おいおい、昭和の役所仕事ってやつか。私が中学のとき、サザエさんがまだフィルムだった頃だ。まさかその頃のズサンさが、今になって依頼人の人生を狂わせているとは。
昭和の登記情報に潜む落とし穴
問題の土地は、当時町内会の集会所として使われていた時期があったらしい。正式な所有権移転登記がなされず、事実上の利用者変更だけで数十年が経過していた。 所有権はどうなっている? 今誰が使ってる? 曖昧なまま、土地だけが取り残されたような形だ。
私は元野球部だったことを思い出した。送球ミスで誰もいないところにボールが転がっていく――そんな光景が、今この案件に重なる。誰もが見て見ぬふりをしていたのかもしれない。
シンドウの元野球部的発想が光る
ボールの行方を追うように、私は当時の町会長の親族に連絡を取った。意外にも快く話を聞いてくれ、昭和時代の寄付台帳を見せてくれた。そこに、「寄付扱いで町に渡した」旨の記録があった。
これだ。だが寄付されたのに名義変更がされていない。つまり、今でも法的には依頼人の父の所有地なのだ。私は、ようやくボールを掴んだ気分になった。
過去と現在をつなぐ権利の継承
相続登記を進めるため、まずはその“幽霊地”の存在を確定させねばならない。現地調査と現況証明、さらに地元役場の非公式な証言。法的根拠は薄いが、事実関係は確かに存在する。
不動産登記法の条文をめくりながら、私は一つひとつ、積み木のように証拠を積み上げていった。ゴールはまだ遠いが、確かに近づいている。
失踪者と生存者の交差点
さらに調査を進めると、消えたはずの筆の登記名義人が、失踪宣告された人物であることが判明した。つまり法的には死亡扱いだが、実は生きている可能性もある。
昭和の終わりに失踪して以来、誰も彼を見ていない。だが、町の誰かが「最近似た顔を見た」という。サトウさんが、淡々と「これ、やばいやつですね」と言った。
意外な人物が鍵を握っていた
聞き込みの末、現れたのはなんと、依頼人の従兄弟だった。「あの土地?まだあったのか」彼は笑いながら、町に寄付されたと思い込んでいた。だが、彼の父が勝手にそう決めただけだったのだ。
本当にサザエさんだったら、波平が「バカモン!」って言って終わってる話だが、現実はそんなに甘くない。土地はまだ生きていた。そして、それは依頼人の相続財産だった。
真相に迫る静かな対決
法的処理の準備を整えた私は、依頼人と共に再び法務局へ向かった。登記官も首をひねる記録の数々。それでも、証拠と根拠を揃えた私は、静かに説明を重ねていった。
やれやれ、、、説明資料だけでファイルが三冊になった。肩が凝る。だが、この静かな対決を制しなければ、この土地は誰のものにもならない。
やれやれと言いつつも詰める証拠
司法書士の仕事は派手ではない。だが、地道な積み重ねが真実を浮かび上がらせる。その積み上げこそが、依頼人の未来を変えるのだ。
私は登記原因証明情報と添付書類一式を提出し、印鑑を押した。静かだが、確かな決着だった。
司法書士が下した結論
結論として、その土地は依頼人の父の名義で残っていた。そして、今回の相続により彼女が法的な所有者となった。彼女は泣きそうな顔で私に何度も頭を下げた。
私はただ、「仕事ですから」と言って、目をそらした。こんなとき、何と返せばいいのか、今でもわからない。
書類一枚が暴いた人間の欲望
登記簿一枚の裏には、人間の記憶と欲望、曖昧さと信頼のバランスが詰まっている。今回の件で、それを改めて痛感した。
正しさとは何か。形式とは何か。それを扱う者として、私は今日も迷いながら判を押す。
法と感情の間で揺れた判断
法的には正しくても、人の感情は追いつかないことがある。だが、それでも前に進めるよう、我々は支えるのが仕事だ。 私はそう信じている。少なくとも今日までは。
そして日常へ戻る昼下がり
事件は終わり、事務所に戻ると昼休憩の時間だった。私はカップ焼きそばを啜りながら、ぼんやりと遠くを見ていた。
「今日は、ちゃんと活躍しましたね」 サトウさんが珍しく、塩じゃない言い方をした。私は驚いてむせた。
サトウさんの塩対応とほっとした一息
「……え、褒めた?」 「そんなつもりはないですけど」 うん、やっぱりいつも通りだ。私はそう思いながら、もう一口すすると、やけに塩辛かった。
再び静寂を取り戻した事務所
やれやれ、、、またいつもの一日に戻った。ただ、それが悪いことだとも思わなかった。次の依頼が来るまでは、平穏が続けばそれでいい。
私は新しい登記簿を印刷し、静かにファイルへ綴じた。今日も誰かの「証言」が、登記簿に記録された。